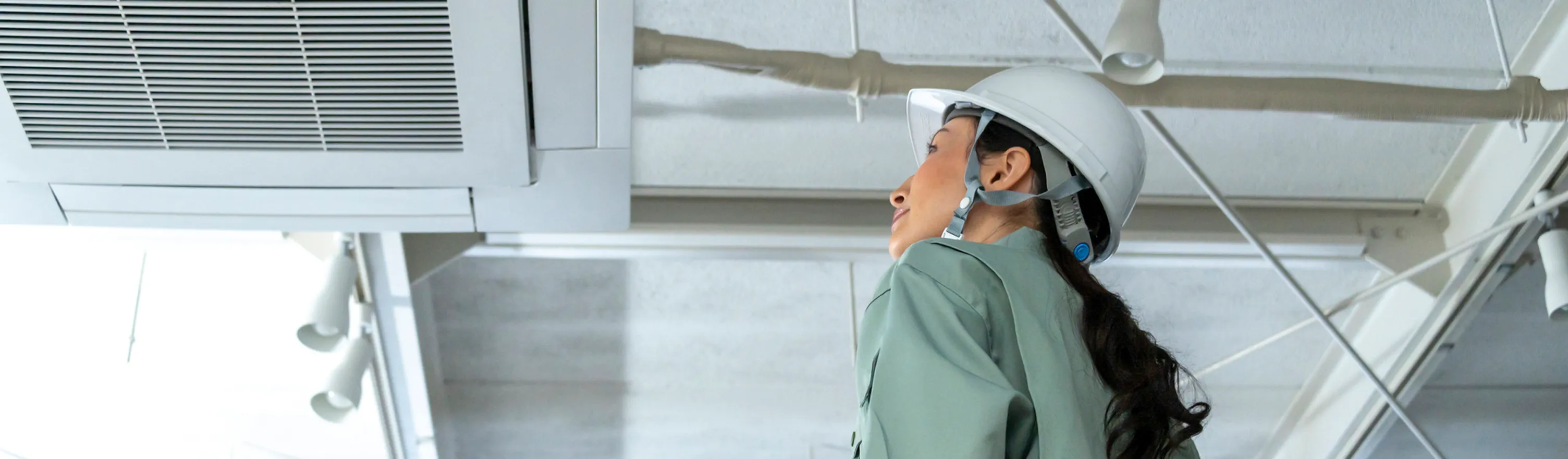
ビルメンテナンス
ビルメンテナンスの課題例
-

専門的な知識や技術が必要
建物を維持・管理していくためには専門知識と技術がなければ多くの労力と時間を費やしてしまいます。老朽化した設備やトラブルを適切な方法で対応しなければ入居者からの信頼も損なう恐れがあります。 -

コストと品質のバランス
多くのビルオーナーにとって、メンテナンスコストの削減は重要な関心事ですが、必要な作業を怠ると建物の劣化を早めたり、安全性や快適性を損なう可能性があり入居者の不満につながることも。建物に適した内容と品質を保てる管理作業が重要となります。 -

ビルの機能や性能を維持・向上
清掃と衛生管理は感染症対策や衛生管理に関する知識や経験がなくして維持管理できません。設備の老朽化や故障への対応もビルの機能や性能の維持・向上には不可欠な課題です。入居者の満足度はビル運営にも大きく影響します。
事業概要
-
 Buildings and offices for rent
Buildings and offices for rent貸ビル・貸事務所
事業の成長に最適なオフィスを提案し、豊富な選択肢と専門的なサポートで理想のオフィス選びを実現します。移転計画から契約交渉、レイアウト工事の設計・施工まで一貫して対応します。 -
 Building Renovation
Building Renovationビルリノベーション
老朽化したビルの単なる修繕はリフォームと呼ばれますが、ある程度の広さを総合的に改修して建物の性能を向上させたり、価値を高めたりすることをリノベーションと呼びます。 -
 Property Management
Property Managementプロパティマネジメント
不動産オーナーやアセットマネージャーに代わって、不動産の管理や運営を行います。不動産の資産価値や収益を最大化することを目的としています。 -
 Building Maintenance
Building Maintenanceビルメンテナンス
建物を維持・管理し、ご利用の方が快適に過ごせる環境を保ちます。ビルメンテナンスがカバーする領域は幅広く、それぞれに専門的な知識・技術が要求されます。 有資格者のみができる業務も少なくありません。 -
 Building Development
Building Developmentビル開発
賃貸ビルは長期安定収益を目指した事業です。当社は賃貸オフィスビルと賃貸マンションの開発で多数の実績があり、オフィスでは80棟超・マンションでは東京建築賞(東京都建築士事務所協会主催)を3回受賞等数々の実績があります。当社はビル開発に伴う、全ての業務を行います。
サービスの特長
-
オフィスビルに特化した
管理実績当社では、貸ビル開発の初期段階からビル運営に必要なビルメンテナンスに関わる計画、提案、業務に携わってきました。私たちは、単にビルを管理するのではなく、その価値を最大化し、利用者に快適な環境を提供することに注力しています。
オフィスビルは、企業の顔であり、従業員の生産性を左右する重要な要素です。私たちは、オフィスビル特有のニーズを深く理解し、最適なソリューションを提供します。私たちのサービスは、日常清掃から専門的な設備管理、セキュリティに至るまで、オフィスビル運営のあらゆる側面を網羅しています。
-
適切な管理サービスと
コスト当社は、豊富なオフィスビルの運営管理実績で培った経験と実績、専門的知識から、高品質なビルメンテナンスの管理サービスを提供します。ビル毎に最適な管理メニューを提案するオーダーメイド型ですので、ニーズに応じたサービスを適切なコストで提供できます。
具体的には、不要な定期作業をより効率的な業務内容でスポット作業に切り替えることによるコスト削減や緊急時のトラブルを当社の専任担当者が迅速で適切な対応をすることにより無駄な専門業者の対応によるコストや時間の経過を削減しオーナー様や入居者に信頼を得られるように心がけます。
-
老朽化・修繕計画・
改修提案今、建物の構造や設備は非常に複雑になり、入居者は見た目や快適さにこだわるようになっている現状を踏まえ、当社が培ってきた豊富な経験と実績、専門的知識から、建物自体や設備の老朽化に最適な管理メニューまたは修繕計画を提案することができます。
放置するとコストが高騰したり余分な作業や発生する恐れがあるため、適切なタイミングを的確な計画で改修提案も含めたご提案により建物の価値を向上させます。
対応業務例
-

テナント管理
テナントからの問い合わせ窓口を一本化し、即時対応で満足度向上。定期的なコミュニケーション施策も実施し、早期の課題発見に努める。
-

長期修繕計画
古くなった設備の更新や省エネ改修を計画的に行い、ランニングコストの削減とビルの競争力向上を両立。
-

リニューアル提案
共用部のデザイン刷新や、執務環境の改善、セキュリティ強化など、物件の魅力を高めるリニューアルプランを提案。リニューアルで空室を付加価値の高い物件に作り変え、賃料アップを狙う。
管理実績
-

幅広い物件のPM実績
累計60棟以上・総面積10万㎡超のプロパティマネジメント実績を誇り、都心の大規模オフィスビルから地域密着型の中小ビルまで、多様な物件の管理を手掛けています。 -

主要3区で
平均稼働率99%超を維持市場分析と戦略的リーシングにより、空室期間の短縮と賃料水準の維持を実現。特に、築年数のあるビルでもリニューアル施策を実施し、主要3区で平均99%を超える高稼働率を維持しています。 -
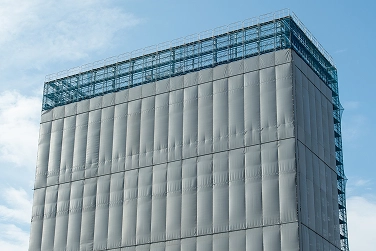
適正な修繕計画による
資産価値の向上長期修繕計画の策定と効率的な工事実施により、ビルの資産価値を維持・向上。修繕コストの最適化と設備の更新により、築30年以上のビルでも賃料水準を維持し、競争力のある資産運用を実現しています。
お客様の声
-

-

自分で契約していた清掃員や専門業者とやりとりする必要がなくなり、時間の余裕もできるし、経費も大幅に削減できました。
-

定期的なメンテナンスと早期の修繕により、建物の老朽化を抑え、資産価値の維持・向上に繋げることができています。
-

何か問題が発生した際も、24時間体制で対応してもらえるため、安心してビルを所有・運営できています。
ご契約までの流れ
-
1

お問い合わせ・ヒアリング
お電話またはWebフォームでご相談内容をお聞かせください。物件概要や現状の課題点などをお伺いいたします。 -
2

現地調査・改善提案
当社スタッフが現地を確認し、建物の状況や周辺市場を分析。その上で、リーシング方針や修繕計画など含めた最適な運営プランをご提示いたします。 -
3

ご契約・運営開始
サービス内容・費用にご納得いただけましたら契約を締結。綿密なスケジュール管理のもとでスムーズにPM業務をスタートし、オーナー様への定期報告を実施いたします。











今までの清掃会社に頼んでいた時よりも、気になっていた場所も含めて清掃や点検が入り、ビルをより清潔で快適な状態に保てるようになりました。