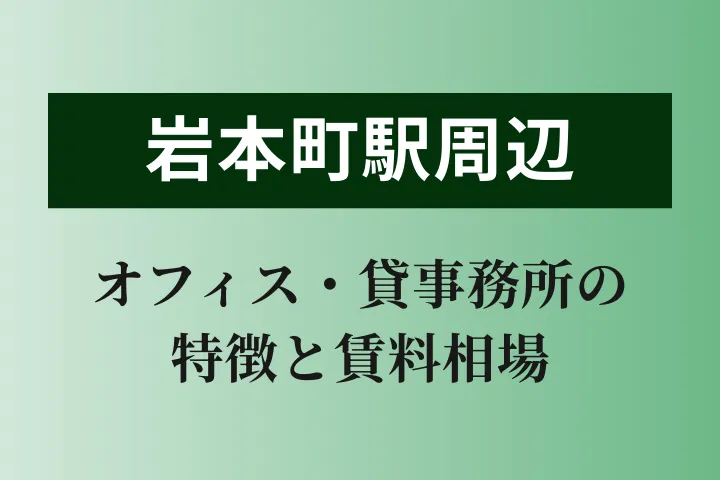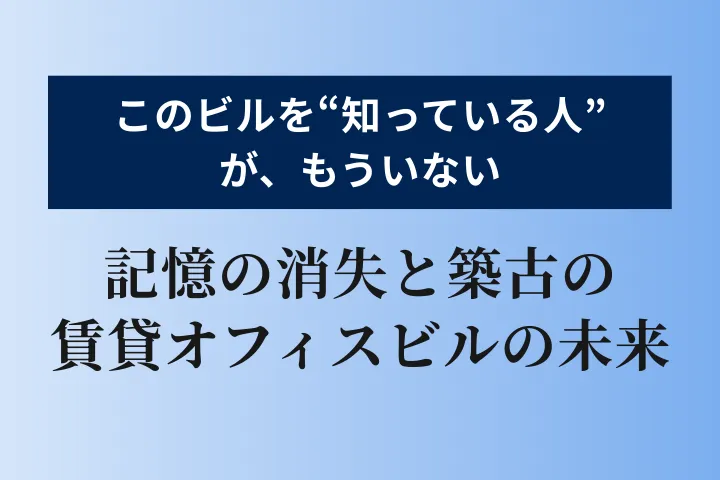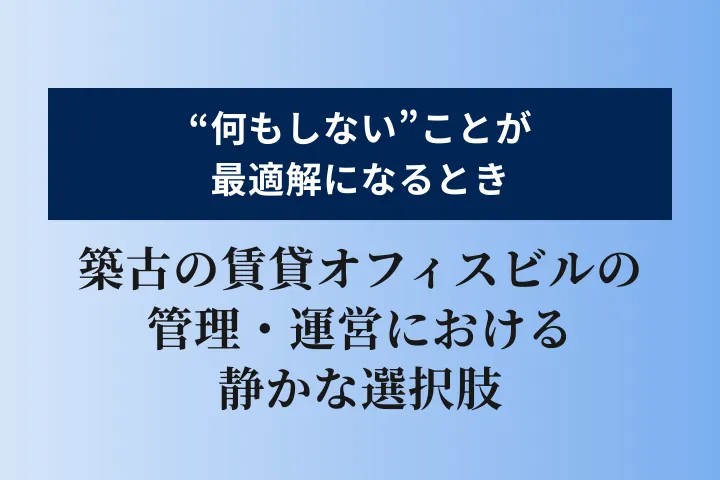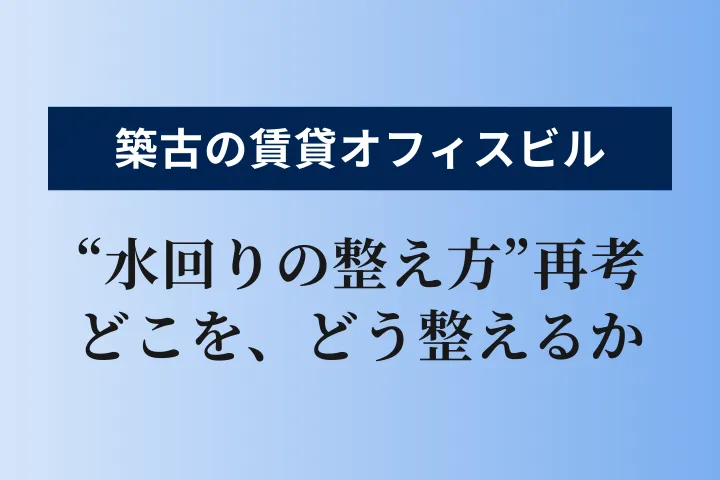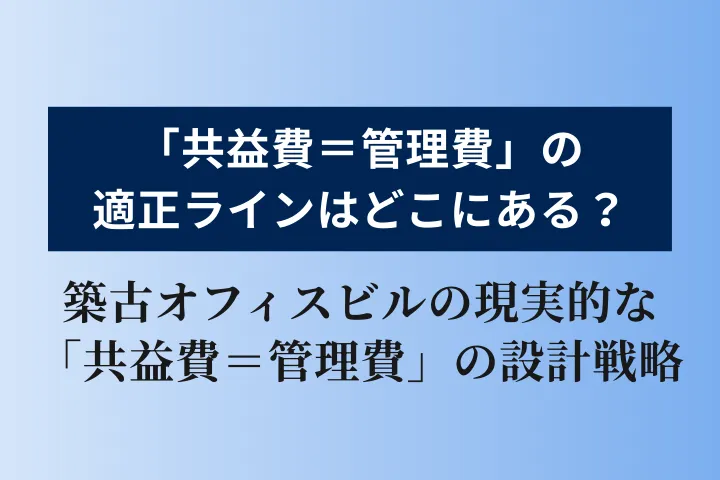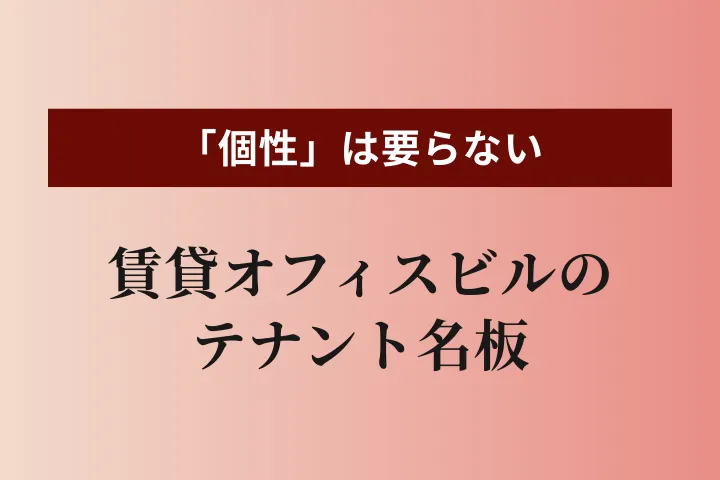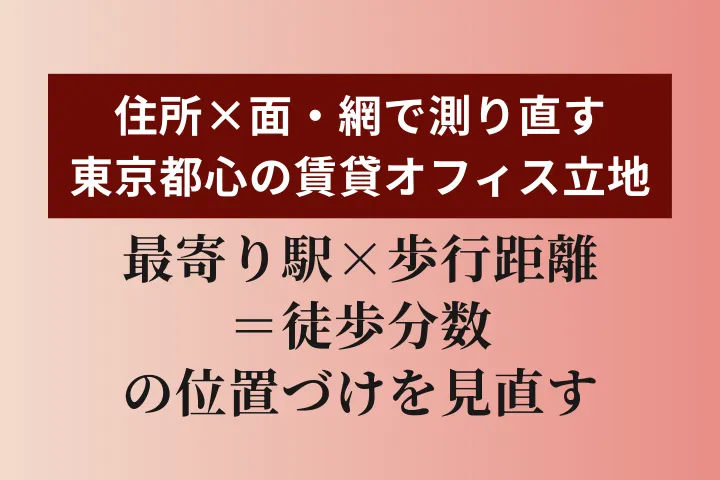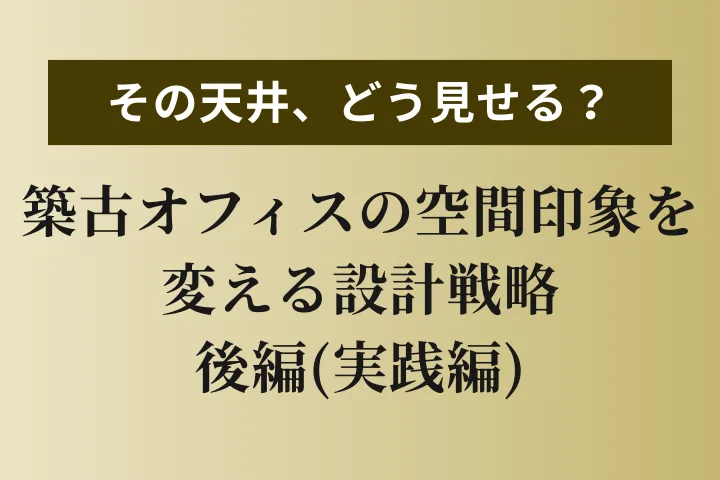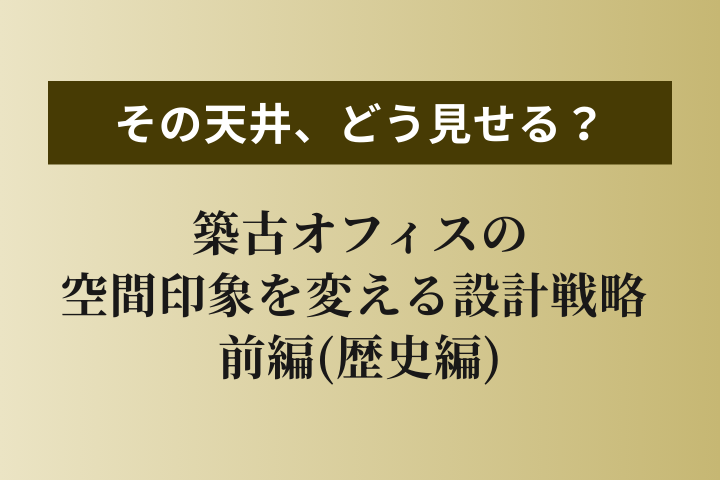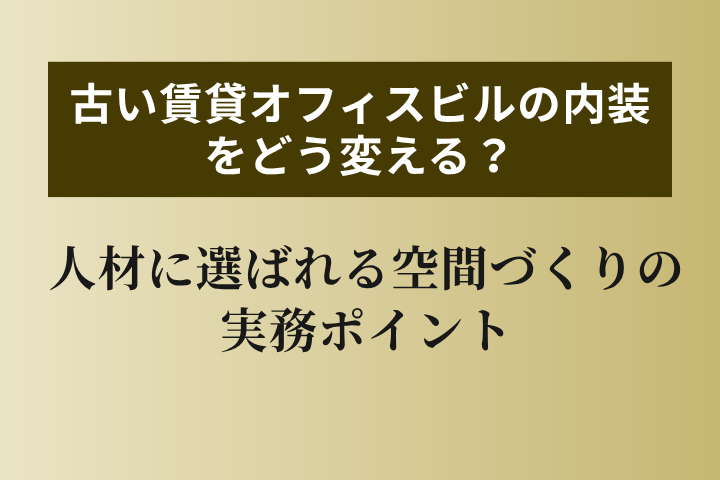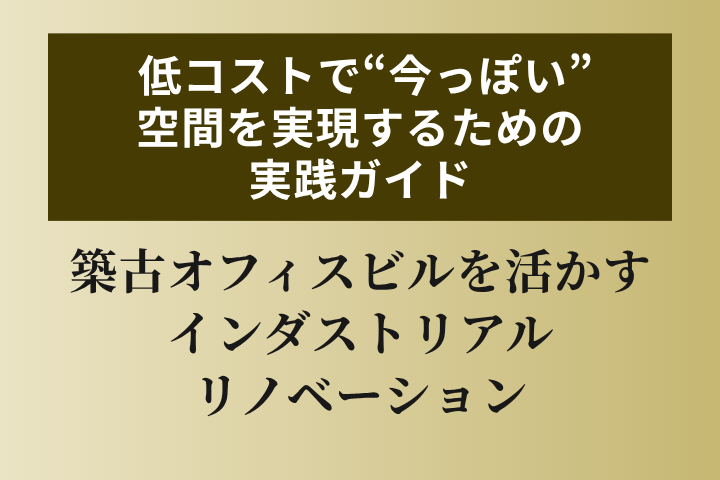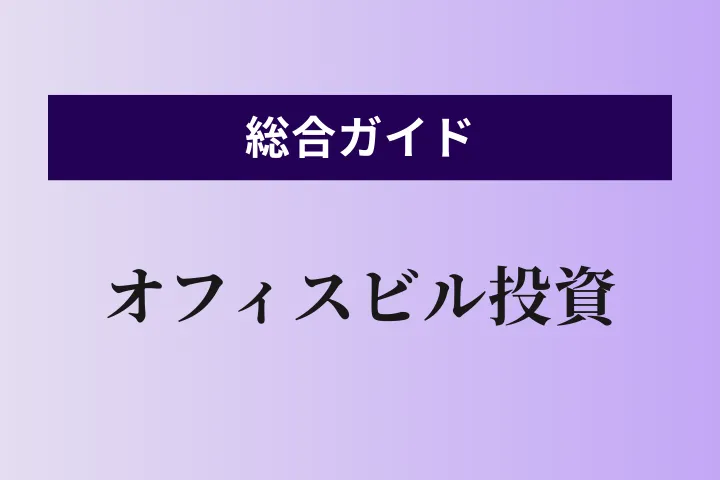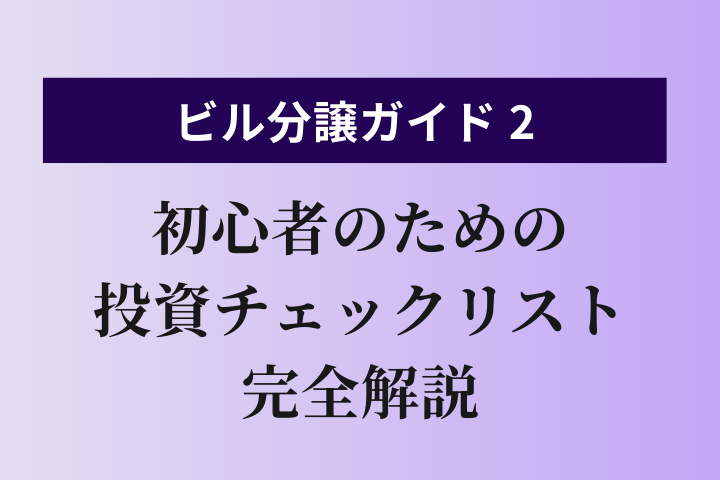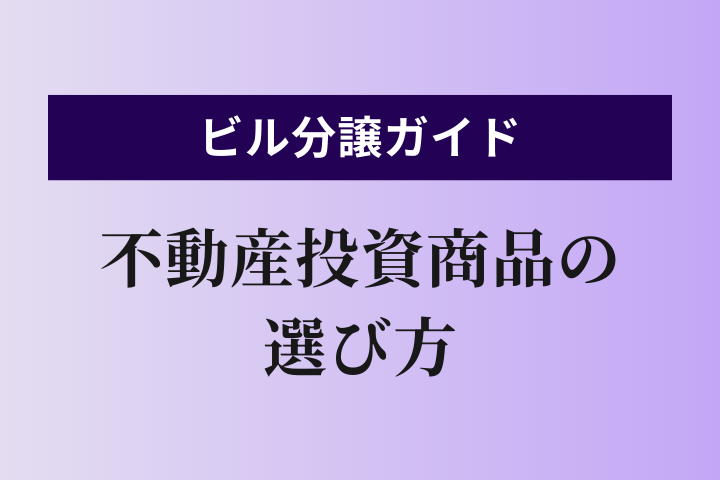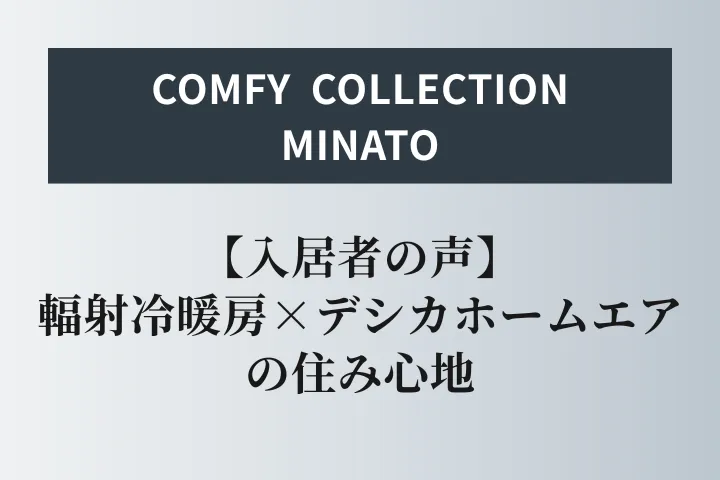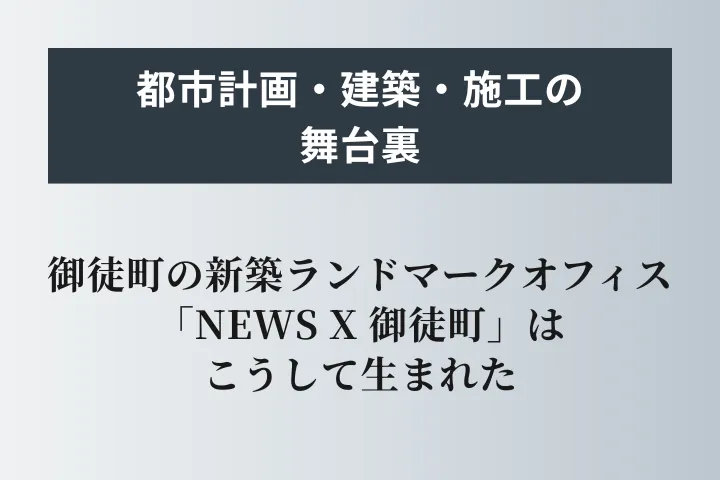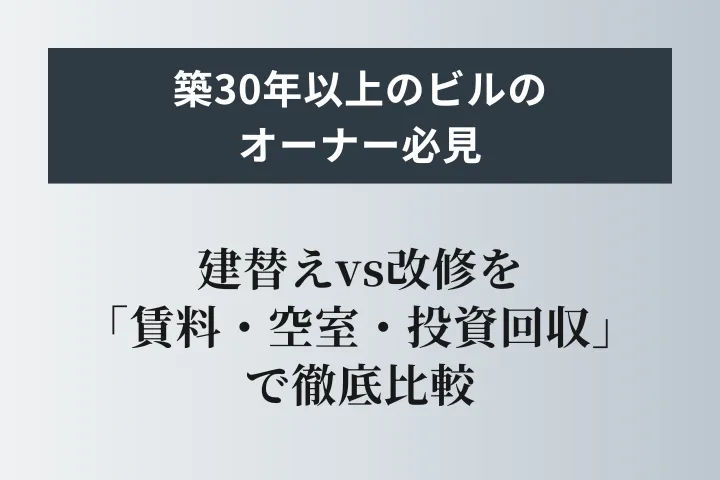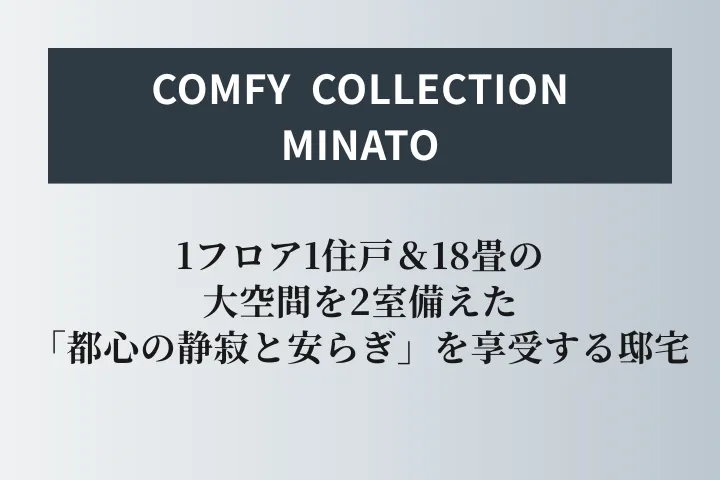-
ビルリノベーション
オフィスのトイレをリフォームしたい!|気になる費用を解説
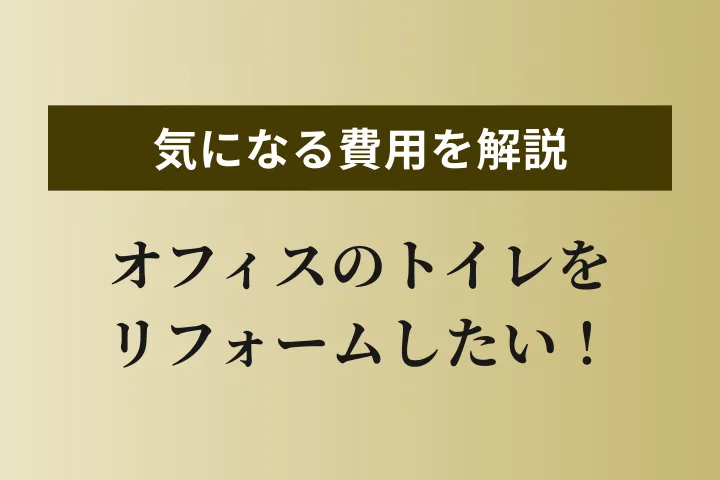 皆さんこんにちは。株式会社スペースライブラリの鶴谷です。この記事はオフィスのトイレをリフォームする際の費用についてまとめたもので、2026年2月24日に改訂しています。少しでも皆様のお役に立てる記事にできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 目次はじめに第1章:オフィスのトイレリフォーム費用の相場第2章:実際のトイレリフォーム事例A第3章:実際のトイレリフォーム事例B第4章:費用に影響を与える主な要因第5章:リフォーム計画を成功させるポイント第6章:費用のまとめとおわりに はじめに 空室の出てきた築古オフィスビルで、入居テナントのためにできることを考えたとき、真っ先に浮かぶのはトイレのリフォームではないでしょうか。トイレは毎日必ず使う場所であり、ビルにとっては入居者満足度やイメージを左右する非常に重要なポイントです。きれいで機能的なトイレは、入居テナントや来訪者にとっても快適に働く環境を作り出します。オフィスのトイレは一般的にテナント側ではなくビル側で用意する共用部の設えであり、トイレが美しく快適であることは、テナントの入居決定に直結します。その一方で、「リフォームをやる」と一口に言っても、どの程度費用がかかるのかをまず知りたいという方が多いのではないでしょうか。費用を簡単に把握できれば、予算的に実行が可能かどうか、あるいはその費用を工面する必要があるのか、早めに判断することができます。費用の相場が分かっていれば、業者との打ち合わせや見積もり検討の際の指標にもなります。本稿では、簡単に費用を把握できる概算値と、実際に行われたオフィスビルのトイレリフォーム事例を参考にして、トイレリフォーム費用の概要を整理していきます。さらに、より詳しいリフォームの工程や、コストを左右する要因、リフォーム後の効果についても触れながら、総合的にトイレリフォーム費用を理解するための情報をお届けします。 第1章:オフィスのトイレリフォーム費用の相場 1-1.トイレリフォームにおける「相場」の捉え方 オフィスの共用トイレをリフォームするのに、費用はいくらかかるのでしょうか。最初にリフォームの概要を掴みたいときに役立つのが、過去の実績や一般的にいわれる「相場」です。しかし、リフォーム案件は建物の状況、設備のグレード、工事範囲、既存設備の老朽度合いなどによって大きく変動します。何もかもゼロから新設する場合と、部分的に入れ替えるだけで済む場合では、当然費用に大きな差が出てきます。そのため、相場はあくまで目安と捉え、実際には現地調査や詳細見積もりで最終的な工事費を確認することが重要です。 1-2.大まかな指標となる2つの考え方 オフィスビルのトイレリフォームに関する費用を大まかに把握する方法として、以下の2つの指標がよく用いられます。①トイレの単位面積当たり単価20~30万円/㎡(66~99万円/坪)トイレの床面積がどれくらいかをベースにして見積もる方法です。床面積に合わせて、床・壁の内装材や配管・給排水工事に必要な費用などを大まかに算出します。オフィスビルであれば、小さく見ても1フロアあたり10㎡~」20㎡程度のトイレスペースがあることが多いですから、その面積に上記の単価を乗じると、大まかな金額が導き出せます。②便器の台数当たりの単価80~120万円/台こちらは便器1台あたりを基準にして費用を算出する方式です。大便器3台・小便器2台で合計5台なら、5台×80~」120万円=400~」600万円ほどが目安になります。この計算では、洗面台の数や内装工事の規模、給排水や電気工事などのセットを含めた金額がざっくりと含まれますが、実際にはグレード(自動洗浄タイプやセンサー付き水栓、ウォシュレット機能など)やレイアウト変更の有無によっても変わります。 第2章:実際のトイレリフォーム事例A ここからは、実際に行われたトイレリフォーム事例を具体的に見ていきましょう。理論だけでなく、実例を知ることで、相場との照らし合わせやイメージがしやすくなります。所在:東京都文京区築年数:33年施工フロア:4・5階1フロア面積:トイレ部分17.0㎡(5.1坪)便器更新:大便器×3、小便器×2洗面台更新:手洗い器×4内装更新:床長尺シート貼替、壁SOP塗装パテ補修の上SOP塗り 2-1.事例Aの費用内訳 上記工事(1フロア)に約450万円(税抜)かかっています。このうち、解体工事費が約20万円、設備工事材料費が約200万円というのが主な内訳です。①トイレの単位面積あたり工事費450万円÷17.0㎡(5.1坪)=26.4万円/㎡(88.2万円/坪)②便器の台数当たりの単価450万円÷5台=90万円/台上記計算から、第1章で挙げた相場(20~」30万円/㎡、80~」120万円/台)の範囲内におおむね収まっていることがわかります。 2-2.工事内容の特徴と留意点 設備工事材料費の占める割合:費用のかなりの部分を設備工事の材料費が占めていることがわかります。古い配管を撤去して新たな給排水設備を設置するなど、見えない部分でのコストが意外とかかる点に注意が必要です。内装の仕上げレベル:壁をSOP塗装しているため、タイル貼りや高級クロスを使った場合よりも安価になっている可能性があります。仕上げの選択により、見た目や耐久性、メンテナンス性、そしてコストが大きく変わります。 第3章:実際のトイレリフォーム事例B 続いて、もう一つの事例を見ていきましょう。所在:東京都文京区築年数:30年施工フロア:5階1フロア面積:トイレ部分18.5㎡(5.6坪)便器更新:大便器×3、小便器×2洗面台更新:手洗い器×4内装更新:床長尺シート貼替、壁SOP塗装の上SOP塗り 3-1.事例Bの費用内訳 上記工事に約510万円(税抜)かかっています。このうち解体工事費が約30万円、設備工事材料費が約265万円でした。①トイレの単位面積あたり工事費510万円÷18.5㎡(5.6坪)=27.5万円/㎡(91.0万円/坪)②便器の台数当たりの単価510万円÷5台=102万円/台こちらの事例も事例Aと同様に、第1章で提示した相場の範囲内であることが確認できます。 3-2.事例Bから見えるポイント 解体費用の差:事例Aより少し解体工事費が高めです。床下や壁内の配管が複雑だった、あるいは既存の内装や下地の状態によって撤去工事の手間が増えた可能性があります。設備コストの増加要因:事例Aと比較して、設備工事材料費もやや高めです。これは材料のグレードや配管系の更新範囲が異なることが想定されます。同じような規模でも、既存設備の老朽度合いや使用する機器のレベルでこれだけ差が出るということがわかります。 第4章:費用に影響を与える主な要因 トイレリフォームは上記のように相場という大枠がありますが、実際は個別の事情で金額が上下します。ここでは、費用に影響を与える主な要因を整理します。 4-1.既存配管の状態 築古ビルの場合、配管がかなり老朽化しているケースもあります。錆びや詰まりが激しいと、配管の総取り替えが必要になり、設備工事費が大幅に増加します。逆に、まだ比較的使用できる状態であれば、一部交換や補強だけで済ませられることもあります。 4-2.給排水設備・トイレ機器のグレード 節水型の便器やウォシュレット機能付き便器、自動洗浄小便器など、最新機能を盛り込むほどコストは上がります。洗面台の素材や水栓のタイプも、一般的なレバー水栓に比べ、センサー式や自動水栓は高価です。内装材もタイル仕上げや高級クロス、あるいは耐水性・耐久性に優れた材料ほど費用がかさみます。 4-3.レイアウト変更の有無 トイレ個室の配置や数を変更したり、バリアフリー対応でブーススペースを拡張したりする場合は、間仕切り壁の撤去や新設、給排水配管のルート変更などの工事が必要となります。特に配管の大幅な変更は費用を押し上げる原因になりがちです。 4-4.工事の範囲 トイレ空間だけでなく、パウダールームや廊下も含めて一体的にリニューアルするかどうかで費用は大きく変わります。また、照明をLEDに変更する、換気設備を追加するなどの電気工事も範囲に含めると、追加費用が発生します。 4-5.施工スケジュールや夜間工事の有無 オフィスビルでは日中の工事が難しく、夜間や休日に工事する場合もあります。夜間工事や連休期間での集中工事では、人工(にんく:人件費)が割増になることもあるため、施工スケジュールの組み方で費用が左右されることがあります。 第5章:リフォーム計画を成功させるポイント トイレリフォームを円滑に進め、コスト面でも納得のいく結果を得るためには、計画段階からのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、実際に工事を発注したり、施工会社とやり取りをする上でのアドバイスをご紹介します。 5-1.現地調査を徹底し、正確な見積もりを得る 相場を把握することは大切ですが、最終的には現地調査をしてもらった上で正式な見積もりを取ることが欠かせません。配管の状態や既存内装の下地、電気設備の容量など、建物ごとの事情を反映してはじめて、正確な金額がわかります。 5-2.優先順位を明確にする 「とにかく最新の機能を全部取り入れたい」「見た目を最高にしたい」など、要望はいろいろと出てくるかもしれませんが、コストとのバランスを考慮した優先順位を決めておくことが大切です。節水効果を狙いたいのかウォシュレット機能を充実させたいのかデザイン重視なのか日常清掃が楽になる仕上げ材を選びたいのか等々、優先度を明確にすると、設備や内装の選定段階で迷いが少なくなり、スムーズに発注できます。 5-3.テナントや利用者の声をヒアリング オフィスビルのトイレは「利用者の満足度」が非常に重要です。工事を決める前に、テナントや従業員から現在のトイレに対する不満や要望をリサーチしておくと良いでしょう。実際に不満が多い箇所は費用をかけてでも改善することで、入居者満足度の向上につながり、空室対策にも大きく寄与します。 5-4.メンテナンス性や清掃性にも配慮する リフォーム後のトイレを長期にわたって快適に保つために、メンテナンスのしやすさや清掃性を重視することが大切です。特に、汚れが付きにくい便器や、ワンタッチで取り外しできるウォシュレット機能など、清掃が簡単になる機能を選んでおくと、日々の維持管理コストを抑えられます。 5-5.バリアフリーやジェンダーレス対応を検討 近年は、バリアフリー対応やユニバーサルデザインを取り入れるケースが増えてきました。車椅子利用者でも使いやすい広めのブース、手すりの設置、段差の解消などは、多様な利用者が訪れるオフィスビルにおいて重要な要素です。また、ジェンダーレスや多目的トイレの検討も、ビルとしてのイメージ向上や利用者の安心感につながります。これらの新しいニーズへの対応は、工事費用を増加させる場合もありますが、将来的な価値を高める点で検討する価値があります。 5-6.施工会社選びは複数社比較で リフォーム費用は施工会社ごとに差があります。少なくとも2~」3社の工事会社から相見積もりを取り、工事内容や条件を比較検討しましょう。価格だけでなく、工事内容の詳細やアフターサービスの有無、施工実績なども考慮すると、より納得できる発注先を選ぶことができます。 第6章:費用のまとめとおわりに 6-1.費用のまとめ 本稿では、オフィスビルのトイレリフォーム費用を相場と実際の事例の両面から概観してきました。事例A・事例Bの費用をみると、下記の相場の数値(第1章で紹介したもの)におおむね納まっていることがわかります。①トイレの単位面積当たりリフォーム単価:20~30万円/㎡(66~99万円/坪)②トイレの便器の台数(小便器+大便器の数)当たりのリフォーム単価:80~120万円/台とはいえ、既存建物の状況やトイレ機器のグレード、解体工事の範囲、内装仕上げの種類などの要素によって、解体工事費・内装工事・設備工事・電気工事・大工工事などの費用は変動します。一概に「〇〇万円で大丈夫」と言い切れないのがリフォームの難しさでもあります。しかし、概算ベースで「大体これくらいになる」という指標を持っておけば、リフォームをやるかどうかの初期判断を下す際に役立ちます。 6-2.今後の進め方 もし、トイレリフォームをやろうかどうか迷っている段階であれば、まずは簡単に床面積や便器数をベースに概算費用を出してみてください。そのうえで、実際に施工会社に現地調査してもらい、詳細見積もりを取ることをおすすめします。また、テナントや従業員の声をよく聞き、どういった改善を望まれているのかを明確にすることも非常に重要です。コストを抑えるための妥協点と、入居者満足度を高めるために譲れない部分をしっかりとすり合わせ、計画に反映させましょう。 6-3.おわりに 本稿では、オフィスビルのトイレのリフォーム費用について、大まかな相場から具体的な事例、その費用に影響を与える要因やリフォーム成功のポイントまでを一通り解説しました。「どれくらい費用がかかるかイメージできない」という悩みをお持ちの方が多いと思いますが、今回ご紹介した相場と事例を目安に、まずはプランを立ててみてください。実際の金額は現場の状況や選ぶ設備で変わりますが、早期の概算把握は意思決定をスムーズにする大きな助けになります。もしやろうかどうしようか迷っていらっしゃったら、ぜひこの費用感を参考にしてみてください。清潔で使いやすいトイレにすることは、入居テナントの満足度やビルの価値向上にもつながります。なにより美しいトイレはテナントの入居決定を後押ししてくれると思います。ぜひ前向きにご検討いただければと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆様のリフォーム計画が成功に導かれることを心より願っております。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ 設計チーム 鶴谷 嘉平 1994年東京大学建築学科を卒業。同大学大学院にて集合住宅の再生に関する研究を行いました。 一級建築士として、集合住宅、オフィス、保育園、結婚式場などの設計に携わってきました。 2024年に当社に入社し、オフィスのリノベーション設計や、開発・設計(オフィス・マンション)を行っています。 2026年2月24日執筆2026年02月24日
皆さんこんにちは。株式会社スペースライブラリの鶴谷です。この記事はオフィスのトイレをリフォームする際の費用についてまとめたもので、2026年2月24日に改訂しています。少しでも皆様のお役に立てる記事にできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 目次はじめに第1章:オフィスのトイレリフォーム費用の相場第2章:実際のトイレリフォーム事例A第3章:実際のトイレリフォーム事例B第4章:費用に影響を与える主な要因第5章:リフォーム計画を成功させるポイント第6章:費用のまとめとおわりに はじめに 空室の出てきた築古オフィスビルで、入居テナントのためにできることを考えたとき、真っ先に浮かぶのはトイレのリフォームではないでしょうか。トイレは毎日必ず使う場所であり、ビルにとっては入居者満足度やイメージを左右する非常に重要なポイントです。きれいで機能的なトイレは、入居テナントや来訪者にとっても快適に働く環境を作り出します。オフィスのトイレは一般的にテナント側ではなくビル側で用意する共用部の設えであり、トイレが美しく快適であることは、テナントの入居決定に直結します。その一方で、「リフォームをやる」と一口に言っても、どの程度費用がかかるのかをまず知りたいという方が多いのではないでしょうか。費用を簡単に把握できれば、予算的に実行が可能かどうか、あるいはその費用を工面する必要があるのか、早めに判断することができます。費用の相場が分かっていれば、業者との打ち合わせや見積もり検討の際の指標にもなります。本稿では、簡単に費用を把握できる概算値と、実際に行われたオフィスビルのトイレリフォーム事例を参考にして、トイレリフォーム費用の概要を整理していきます。さらに、より詳しいリフォームの工程や、コストを左右する要因、リフォーム後の効果についても触れながら、総合的にトイレリフォーム費用を理解するための情報をお届けします。 第1章:オフィスのトイレリフォーム費用の相場 1-1.トイレリフォームにおける「相場」の捉え方 オフィスの共用トイレをリフォームするのに、費用はいくらかかるのでしょうか。最初にリフォームの概要を掴みたいときに役立つのが、過去の実績や一般的にいわれる「相場」です。しかし、リフォーム案件は建物の状況、設備のグレード、工事範囲、既存設備の老朽度合いなどによって大きく変動します。何もかもゼロから新設する場合と、部分的に入れ替えるだけで済む場合では、当然費用に大きな差が出てきます。そのため、相場はあくまで目安と捉え、実際には現地調査や詳細見積もりで最終的な工事費を確認することが重要です。 1-2.大まかな指標となる2つの考え方 オフィスビルのトイレリフォームに関する費用を大まかに把握する方法として、以下の2つの指標がよく用いられます。①トイレの単位面積当たり単価20~30万円/㎡(66~99万円/坪)トイレの床面積がどれくらいかをベースにして見積もる方法です。床面積に合わせて、床・壁の内装材や配管・給排水工事に必要な費用などを大まかに算出します。オフィスビルであれば、小さく見ても1フロアあたり10㎡~」20㎡程度のトイレスペースがあることが多いですから、その面積に上記の単価を乗じると、大まかな金額が導き出せます。②便器の台数当たりの単価80~120万円/台こちらは便器1台あたりを基準にして費用を算出する方式です。大便器3台・小便器2台で合計5台なら、5台×80~」120万円=400~」600万円ほどが目安になります。この計算では、洗面台の数や内装工事の規模、給排水や電気工事などのセットを含めた金額がざっくりと含まれますが、実際にはグレード(自動洗浄タイプやセンサー付き水栓、ウォシュレット機能など)やレイアウト変更の有無によっても変わります。 第2章:実際のトイレリフォーム事例A ここからは、実際に行われたトイレリフォーム事例を具体的に見ていきましょう。理論だけでなく、実例を知ることで、相場との照らし合わせやイメージがしやすくなります。所在:東京都文京区築年数:33年施工フロア:4・5階1フロア面積:トイレ部分17.0㎡(5.1坪)便器更新:大便器×3、小便器×2洗面台更新:手洗い器×4内装更新:床長尺シート貼替、壁SOP塗装パテ補修の上SOP塗り 2-1.事例Aの費用内訳 上記工事(1フロア)に約450万円(税抜)かかっています。このうち、解体工事費が約20万円、設備工事材料費が約200万円というのが主な内訳です。①トイレの単位面積あたり工事費450万円÷17.0㎡(5.1坪)=26.4万円/㎡(88.2万円/坪)②便器の台数当たりの単価450万円÷5台=90万円/台上記計算から、第1章で挙げた相場(20~」30万円/㎡、80~」120万円/台)の範囲内におおむね収まっていることがわかります。 2-2.工事内容の特徴と留意点 設備工事材料費の占める割合:費用のかなりの部分を設備工事の材料費が占めていることがわかります。古い配管を撤去して新たな給排水設備を設置するなど、見えない部分でのコストが意外とかかる点に注意が必要です。内装の仕上げレベル:壁をSOP塗装しているため、タイル貼りや高級クロスを使った場合よりも安価になっている可能性があります。仕上げの選択により、見た目や耐久性、メンテナンス性、そしてコストが大きく変わります。 第3章:実際のトイレリフォーム事例B 続いて、もう一つの事例を見ていきましょう。所在:東京都文京区築年数:30年施工フロア:5階1フロア面積:トイレ部分18.5㎡(5.6坪)便器更新:大便器×3、小便器×2洗面台更新:手洗い器×4内装更新:床長尺シート貼替、壁SOP塗装の上SOP塗り 3-1.事例Bの費用内訳 上記工事に約510万円(税抜)かかっています。このうち解体工事費が約30万円、設備工事材料費が約265万円でした。①トイレの単位面積あたり工事費510万円÷18.5㎡(5.6坪)=27.5万円/㎡(91.0万円/坪)②便器の台数当たりの単価510万円÷5台=102万円/台こちらの事例も事例Aと同様に、第1章で提示した相場の範囲内であることが確認できます。 3-2.事例Bから見えるポイント 解体費用の差:事例Aより少し解体工事費が高めです。床下や壁内の配管が複雑だった、あるいは既存の内装や下地の状態によって撤去工事の手間が増えた可能性があります。設備コストの増加要因:事例Aと比較して、設備工事材料費もやや高めです。これは材料のグレードや配管系の更新範囲が異なることが想定されます。同じような規模でも、既存設備の老朽度合いや使用する機器のレベルでこれだけ差が出るということがわかります。 第4章:費用に影響を与える主な要因 トイレリフォームは上記のように相場という大枠がありますが、実際は個別の事情で金額が上下します。ここでは、費用に影響を与える主な要因を整理します。 4-1.既存配管の状態 築古ビルの場合、配管がかなり老朽化しているケースもあります。錆びや詰まりが激しいと、配管の総取り替えが必要になり、設備工事費が大幅に増加します。逆に、まだ比較的使用できる状態であれば、一部交換や補強だけで済ませられることもあります。 4-2.給排水設備・トイレ機器のグレード 節水型の便器やウォシュレット機能付き便器、自動洗浄小便器など、最新機能を盛り込むほどコストは上がります。洗面台の素材や水栓のタイプも、一般的なレバー水栓に比べ、センサー式や自動水栓は高価です。内装材もタイル仕上げや高級クロス、あるいは耐水性・耐久性に優れた材料ほど費用がかさみます。 4-3.レイアウト変更の有無 トイレ個室の配置や数を変更したり、バリアフリー対応でブーススペースを拡張したりする場合は、間仕切り壁の撤去や新設、給排水配管のルート変更などの工事が必要となります。特に配管の大幅な変更は費用を押し上げる原因になりがちです。 4-4.工事の範囲 トイレ空間だけでなく、パウダールームや廊下も含めて一体的にリニューアルするかどうかで費用は大きく変わります。また、照明をLEDに変更する、換気設備を追加するなどの電気工事も範囲に含めると、追加費用が発生します。 4-5.施工スケジュールや夜間工事の有無 オフィスビルでは日中の工事が難しく、夜間や休日に工事する場合もあります。夜間工事や連休期間での集中工事では、人工(にんく:人件費)が割増になることもあるため、施工スケジュールの組み方で費用が左右されることがあります。 第5章:リフォーム計画を成功させるポイント トイレリフォームを円滑に進め、コスト面でも納得のいく結果を得るためには、計画段階からのポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、実際に工事を発注したり、施工会社とやり取りをする上でのアドバイスをご紹介します。 5-1.現地調査を徹底し、正確な見積もりを得る 相場を把握することは大切ですが、最終的には現地調査をしてもらった上で正式な見積もりを取ることが欠かせません。配管の状態や既存内装の下地、電気設備の容量など、建物ごとの事情を反映してはじめて、正確な金額がわかります。 5-2.優先順位を明確にする 「とにかく最新の機能を全部取り入れたい」「見た目を最高にしたい」など、要望はいろいろと出てくるかもしれませんが、コストとのバランスを考慮した優先順位を決めておくことが大切です。節水効果を狙いたいのかウォシュレット機能を充実させたいのかデザイン重視なのか日常清掃が楽になる仕上げ材を選びたいのか等々、優先度を明確にすると、設備や内装の選定段階で迷いが少なくなり、スムーズに発注できます。 5-3.テナントや利用者の声をヒアリング オフィスビルのトイレは「利用者の満足度」が非常に重要です。工事を決める前に、テナントや従業員から現在のトイレに対する不満や要望をリサーチしておくと良いでしょう。実際に不満が多い箇所は費用をかけてでも改善することで、入居者満足度の向上につながり、空室対策にも大きく寄与します。 5-4.メンテナンス性や清掃性にも配慮する リフォーム後のトイレを長期にわたって快適に保つために、メンテナンスのしやすさや清掃性を重視することが大切です。特に、汚れが付きにくい便器や、ワンタッチで取り外しできるウォシュレット機能など、清掃が簡単になる機能を選んでおくと、日々の維持管理コストを抑えられます。 5-5.バリアフリーやジェンダーレス対応を検討 近年は、バリアフリー対応やユニバーサルデザインを取り入れるケースが増えてきました。車椅子利用者でも使いやすい広めのブース、手すりの設置、段差の解消などは、多様な利用者が訪れるオフィスビルにおいて重要な要素です。また、ジェンダーレスや多目的トイレの検討も、ビルとしてのイメージ向上や利用者の安心感につながります。これらの新しいニーズへの対応は、工事費用を増加させる場合もありますが、将来的な価値を高める点で検討する価値があります。 5-6.施工会社選びは複数社比較で リフォーム費用は施工会社ごとに差があります。少なくとも2~」3社の工事会社から相見積もりを取り、工事内容や条件を比較検討しましょう。価格だけでなく、工事内容の詳細やアフターサービスの有無、施工実績なども考慮すると、より納得できる発注先を選ぶことができます。 第6章:費用のまとめとおわりに 6-1.費用のまとめ 本稿では、オフィスビルのトイレリフォーム費用を相場と実際の事例の両面から概観してきました。事例A・事例Bの費用をみると、下記の相場の数値(第1章で紹介したもの)におおむね納まっていることがわかります。①トイレの単位面積当たりリフォーム単価:20~30万円/㎡(66~99万円/坪)②トイレの便器の台数(小便器+大便器の数)当たりのリフォーム単価:80~120万円/台とはいえ、既存建物の状況やトイレ機器のグレード、解体工事の範囲、内装仕上げの種類などの要素によって、解体工事費・内装工事・設備工事・電気工事・大工工事などの費用は変動します。一概に「〇〇万円で大丈夫」と言い切れないのがリフォームの難しさでもあります。しかし、概算ベースで「大体これくらいになる」という指標を持っておけば、リフォームをやるかどうかの初期判断を下す際に役立ちます。 6-2.今後の進め方 もし、トイレリフォームをやろうかどうか迷っている段階であれば、まずは簡単に床面積や便器数をベースに概算費用を出してみてください。そのうえで、実際に施工会社に現地調査してもらい、詳細見積もりを取ることをおすすめします。また、テナントや従業員の声をよく聞き、どういった改善を望まれているのかを明確にすることも非常に重要です。コストを抑えるための妥協点と、入居者満足度を高めるために譲れない部分をしっかりとすり合わせ、計画に反映させましょう。 6-3.おわりに 本稿では、オフィスビルのトイレのリフォーム費用について、大まかな相場から具体的な事例、その費用に影響を与える要因やリフォーム成功のポイントまでを一通り解説しました。「どれくらい費用がかかるかイメージできない」という悩みをお持ちの方が多いと思いますが、今回ご紹介した相場と事例を目安に、まずはプランを立ててみてください。実際の金額は現場の状況や選ぶ設備で変わりますが、早期の概算把握は意思決定をスムーズにする大きな助けになります。もしやろうかどうしようか迷っていらっしゃったら、ぜひこの費用感を参考にしてみてください。清潔で使いやすいトイレにすることは、入居テナントの満足度やビルの価値向上にもつながります。なにより美しいトイレはテナントの入居決定を後押ししてくれると思います。ぜひ前向きにご検討いただければと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆様のリフォーム計画が成功に導かれることを心より願っております。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ 設計チーム 鶴谷 嘉平 1994年東京大学建築学科を卒業。同大学大学院にて集合住宅の再生に関する研究を行いました。 一級建築士として、集合住宅、オフィス、保育園、結婚式場などの設計に携わってきました。 2024年に当社に入社し、オフィスのリノベーション設計や、開発・設計(オフィス・マンション)を行っています。 2026年2月24日執筆2026年02月24日 -
貸ビル・貸事務所
南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所の特徴と賃料相場|不動産会社が解説
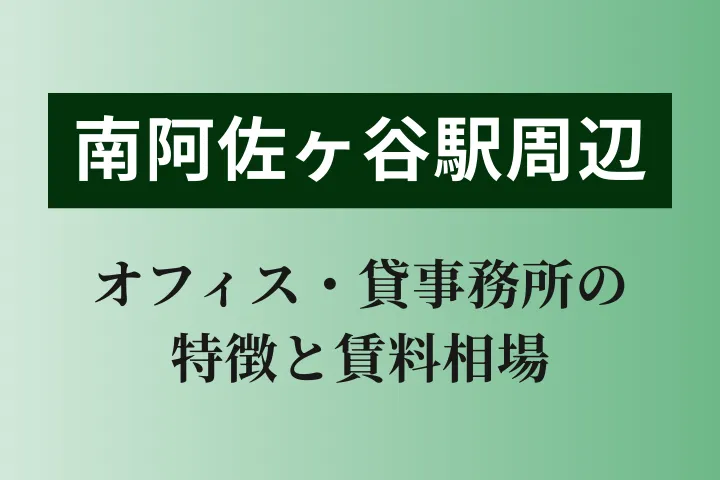 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月20日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次南阿佐ヶ谷駅周辺の特徴とトレンド南阿佐ヶ谷駅周辺の入居企業の傾向南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場南阿佐ヶ谷駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 南阿佐ヶ谷駅周辺の特徴とトレンド 南阿佐ヶ谷駅は、東京メトロ丸ノ内線の単独駅で、杉並区役所の最寄り駅として知られています。新宿駅までは丸ノ内線で約10分前後と、都心主要エリアへのアクセスは比較的良好です。また、徒歩圏内にはJR中央線・総武線が利用できる阿佐ヶ谷駅があり、新宿・東京方面のほか、吉祥寺・立川エリアへの移動にも対応できる立地となっています。駅周辺は、大規模なオフィス街というよりも、区役所を中心とした行政機能と、中小規模ビルが点在するエリアとして形成されてきました。中杉通り、青梅街道沿いや杉並区役所周辺には、事務所利用が可能なビルが一定数集積しており、低層〜中層の建物が街並みの中心です。中杉通り周辺は、並木と低層建物が連続する落ち着いた町並みが形成されており、オフィスエリアでありながら住居エリアと隣接している点も特徴です。騒がしさが抑えられ、来客対応や日常業務を行ううえでも、比較的穏やかな環境が維持されています。オフィス利用者にとっては、駅前から青梅街道にかけて飲食店や金融機関、郵便局などが揃っている点が実務面での利便性につながっています。大規模な再開発は限定的ですが、近年は既存ビルのリニューアルや用途転換により、比較的使い勝手の良い中小規模オフィスが供給される動きが見られます。都心過密エリアとは異なる、落ち着いた業務環境を背景としたエリア特性が維持されています。また、阿佐ヶ谷駅周辺には商店街が広がり、夏には七夕まつりなど地域行事も開催されるなど、過度に商業化されすぎない生活感のある街としての側面も持ち合わせています。業務一辺倒になりすぎない環境を重視する企業にとっては、こうした地域性も評価されるポイントです。 南阿佐ヶ谷駅周辺の入居企業の傾向 南阿佐ヶ谷駅周辺では、従来から士業(税理士・行政書士など)や、地域密着型のサービス業、卸売関連の事務所利用が一定数見られます。杉並区役所に近い立地特性から、行政手続きとの親和性を重視する業種が選ばれてきた経緯があります。近年では、IT関連の小規模事業者や、企画・制作系など比較的少人数で運営される企業の入居も見受けられます。都心部ほどの集積はありませんが、賃料水準を抑えつつ、丸ノ内線とJR中央線の双方を利用できる点が評価されている傾向です。このエリアが選ばれる理由としては、第一に都心部と比較した場合の賃料水準の落ち着きがあります。また、駅周辺は住居エリアと連続した落ち着いた街並みが広がっており、比較的静かで業務に集中しやすい環境が確保されていること、加えて主要エリアへのアクセスが確保されている点が、入居判断の要素として挙げられます。派手なビジネス街ではありませんが、実務重視の法人にとっては検討対象となりやすい立地です。 南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 南阿佐ヶ谷周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約12,000円約16,000円50~100坪約14,000円約18,000円100~200坪--200坪以上-- ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※飛び抜けて安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 南阿佐ヶ谷駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 OSAWAビル住所:杉並区阿佐谷南1丁目8番5号GoogleMapsで見る階/号室:2階坪単価:応相談面 積:73.84坪入居日:2026年3月1日 詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 南阿佐ヶ谷駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、南阿佐ヶ谷駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月20日執筆2026年02月20日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月20日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次南阿佐ヶ谷駅周辺の特徴とトレンド南阿佐ヶ谷駅周辺の入居企業の傾向南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場南阿佐ヶ谷駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 南阿佐ヶ谷駅周辺の特徴とトレンド 南阿佐ヶ谷駅は、東京メトロ丸ノ内線の単独駅で、杉並区役所の最寄り駅として知られています。新宿駅までは丸ノ内線で約10分前後と、都心主要エリアへのアクセスは比較的良好です。また、徒歩圏内にはJR中央線・総武線が利用できる阿佐ヶ谷駅があり、新宿・東京方面のほか、吉祥寺・立川エリアへの移動にも対応できる立地となっています。駅周辺は、大規模なオフィス街というよりも、区役所を中心とした行政機能と、中小規模ビルが点在するエリアとして形成されてきました。中杉通り、青梅街道沿いや杉並区役所周辺には、事務所利用が可能なビルが一定数集積しており、低層〜中層の建物が街並みの中心です。中杉通り周辺は、並木と低層建物が連続する落ち着いた町並みが形成されており、オフィスエリアでありながら住居エリアと隣接している点も特徴です。騒がしさが抑えられ、来客対応や日常業務を行ううえでも、比較的穏やかな環境が維持されています。オフィス利用者にとっては、駅前から青梅街道にかけて飲食店や金融機関、郵便局などが揃っている点が実務面での利便性につながっています。大規模な再開発は限定的ですが、近年は既存ビルのリニューアルや用途転換により、比較的使い勝手の良い中小規模オフィスが供給される動きが見られます。都心過密エリアとは異なる、落ち着いた業務環境を背景としたエリア特性が維持されています。また、阿佐ヶ谷駅周辺には商店街が広がり、夏には七夕まつりなど地域行事も開催されるなど、過度に商業化されすぎない生活感のある街としての側面も持ち合わせています。業務一辺倒になりすぎない環境を重視する企業にとっては、こうした地域性も評価されるポイントです。 南阿佐ヶ谷駅周辺の入居企業の傾向 南阿佐ヶ谷駅周辺では、従来から士業(税理士・行政書士など)や、地域密着型のサービス業、卸売関連の事務所利用が一定数見られます。杉並区役所に近い立地特性から、行政手続きとの親和性を重視する業種が選ばれてきた経緯があります。近年では、IT関連の小規模事業者や、企画・制作系など比較的少人数で運営される企業の入居も見受けられます。都心部ほどの集積はありませんが、賃料水準を抑えつつ、丸ノ内線とJR中央線の双方を利用できる点が評価されている傾向です。このエリアが選ばれる理由としては、第一に都心部と比較した場合の賃料水準の落ち着きがあります。また、駅周辺は住居エリアと連続した落ち着いた街並みが広がっており、比較的静かで業務に集中しやすい環境が確保されていること、加えて主要エリアへのアクセスが確保されている点が、入居判断の要素として挙げられます。派手なビジネス街ではありませんが、実務重視の法人にとっては検討対象となりやすい立地です。 南阿佐ヶ谷駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 南阿佐ヶ谷周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約12,000円約16,000円50~100坪約14,000円約18,000円100~200坪--200坪以上-- ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※飛び抜けて安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 南阿佐ヶ谷駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 OSAWAビル住所:杉並区阿佐谷南1丁目8番5号GoogleMapsで見る階/号室:2階坪単価:応相談面 積:73.84坪入居日:2026年3月1日 詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 南阿佐ヶ谷駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、南阿佐ヶ谷駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月20日執筆2026年02月20日 -
プロパティマネジメント
旧耐震ビルの賃貸経営をあきらめない ――中小規模オフィスオーナーのためのリスク管理と活路
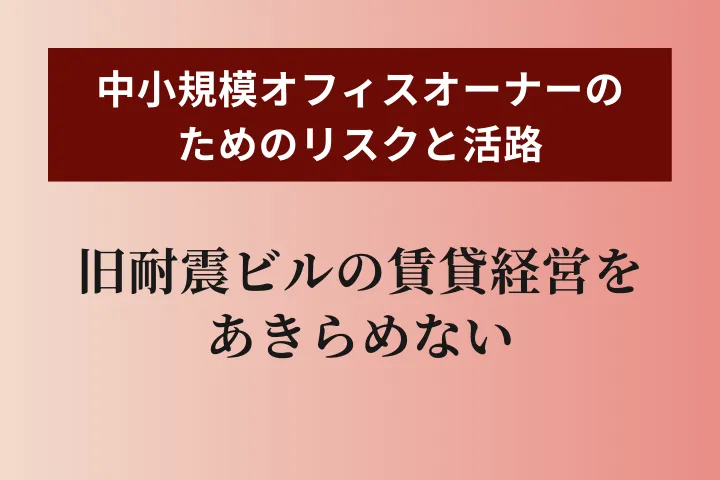 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの飯野です。この記事は「旧耐震ビルの賃貸経営をあきらめない──中小規模オフィスオーナーのためのリスク管理と活路」のタイトルで、2026年2月19に改訂しました。少しでも、皆様のお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次はじめに第1章:旧耐震ビルとは何か第2章:なぜ今「対策」を検討すべきなのか第3章:耐震補強という選択肢の実情第4章:賃貸オフィスビルの建替え/売却という選択肢(出口設計を整理する)第5章:PM/BMを、出口判断の判断材料を揃えるために活用します第6章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営の核心は「リスク管理」第7章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営で有効な「意思決定の型」おわりに はじめに 突然ではありますが、あなたの保有している賃貸オフィスビルは「旧耐震基準」で建てられたものではないでしょうか。1981年以前の耐震基準(いわゆる「旧耐震」)で設計・施工された建物は、日本各地にまだ多く存在しています。「旧耐震ビルのリスクはなんとなく知っている。でも、使えているうちはこのままでいいのではないか?」こう考えるビルオーナーは、実は少なくないのです。すでに建物の減価償却が終わっていて、毎月の賃料収入がほぼ「実入り」となっている状況であれば、わざわざ大きな投資をしてまで建替えや耐震補強を行わなくても、今のところは利益が出ているため、決断を先延ばしにするのも自然な流れなのかもしれません。しかし、耐震基準が古いということは、地震大国である日本において見過ごせない問題と言えましょう。大地震が発生したとき、倒壊や大規模な損傷が生じるリスクが高く、万一の際にはテナントにも大きな被害が及びかねません。近年では、テナント企業が賃貸オフィスビルを選ぶ際、BCP(Business Continuity Plan)の観点から建物の耐震性能を重視する傾向も強まっています。結果的に、旧耐震の賃貸オフィスビルはテナント募集の際の選択肢から外されやすくなっているのです。さらに、あなたのビルの周辺には新耐震基準の下、制震・免震構造を備えた新しいビルが増えています。賃料や立地条件が同程度であれば、「安全かつ設備が備わったビル」を選ぶテナントが大半でしょう。古いビルであるがゆえに空室リスクが高まるうえ、大地震のニュースが流れた直後などは、一時的にでも解約を検討する動きが出るかもしれません。とはいえ、旧耐震ビルに「全面的な耐震補強」を実施するのは、コスト面でも建物形状の面でも簡単ではありません。オフィスフロアの基準面積が100坪以下など比較的コンパクトな建物ほど、耐震壁やブレースの増設が執務スペースを大きく圧迫してしまい、窓を塞いでしまうようなケースも出てきます。テナントからすれば、使い勝手が悪く見栄えも損なわれるため、魅力が下がる懸念があるでしょう。こうした状況下で、多くのビルオーナーが「建替えしかないのか、それとも改修でしのぐべきか」と頭を悩ませています。実際、大規模な改修や建替えには多額の資金調達が必要ですし、仮にそこまで踏み切ったとしても、ビル経営的にペイするかどうかは不透明です。そのため、結局は“現状維持”を選択してしまうケースも少なくありません。しかし、建物の老朽化は待ってはくれません。耐震性の不安だけでなく、設備・配管・内装など、多方面の劣化が進むことで、想定外の修繕費用が急に発生したり、突然のトラブルでテナントからクレームが増えたりするなど、オーナーとしての負担は後々一段と大きくなる恐れがあります。そこで、本コラムでは、そうした問題を抱える旧耐震の中小型賃貸オフィスビルのオーナーを対象に、以下の点を中心に解説していきます。旧耐震ビルが抱えるリスクと、賃貸オフィス市場での評価が下がる背景実際に耐震補強を行う場合に生じる課題と、メリット・デメリットの整理大規模改修・建替え・売却などの意思決定を迫られたときの考え方プロパティマネジメント(PM)やビルメンテナンス(BM)導入の具体的意義とメリット事例紹介を通じた、収益改善や資産価値向上につなげるためのヒントこれから、このコラムでご紹介しようとしているPM/BMは、「オーナーが管理業務の多くを専門家に委託し、不動産経営を最適化するための仕組み」です。単に清掃や警備を外注するビル管理業務(BM)だけでなく、テナント誘致や契約管理、修繕計画立案などを総合的に担うプロパティマネジメント(PM)を活用することで、オーナー自身が把握しきれていない建物の価値を引き出したり、将来のリスクに備えることが可能になります。特に小規模ビルでは、オーナーが自分ひとりで全てを運営管理しているケースが多いため、専門知識や時間的リソースがどうしても不足しがちです。PM/BM導入により、そうした弱点を補い、最終的に建替えや売却を検討する際にも、視野を広げた判断ができるようになります。 本コラムは、建替えや売却を当然として推奨するわけではありません。むしろ、「旧耐震ビルに耐震補強を施す」という一見まっとうに思える選択肢が、本当に得策かどうかを改めて考えてみる必要がある、という問題提起をしたいのです。そして、その検討過程においてこそ、PM/BMの活用が大いに役立つはずであると考えています。もし、このコラムを読んでいるあなたが「うちは旧耐震だけど、まあ大丈夫だろう」と漠然と考えているのであれば、ぜひ最後までお付き合いください。建物の将来について早めに情報を集め、必要に応じた対策をとることで、結果的に余計なコストやリスクを大幅に削減できる可能性があります。なにより、“決断しないまま時が経って、いよいよどうしようもなくなる”という事態だけは避けたいところです。費用面のハードルや工事時期の問題など、悩みは尽きないかもしれませんが、本コラムの内容が少しでもヒントになれば幸いです。それでは、次章からは本題に入りましょう。まずは「旧耐震ビルとは何か」という基本的な定義やリスクを改めて整理し、現状を正確に把握することから始めていきたいと思います。 第1章:旧耐震ビルとは何か 旧耐震ビルとは、1981年以前の耐震基準(いわゆる「旧耐震基準」)で設計・施工された建物のことを指します。日本においては、1950年に制定された建築基準法の改正に伴い、幾度か耐震設計に関する規定が強化されてきました。その転換点となったのが、1981年6月1日に施行された新耐震設計法規です。この新基準以降に建てられた建物を「新耐震」、それより前の基準をもとに建築された建物を「旧耐震」と呼び分けています。 1-1.旧耐震基準と新耐震基準の違い そもそも、なぜ1981年という年が大きな区切りなのでしょうか。それは、1978年に発生した宮城県沖地震での被害を踏まえ、建物が「倒壊しないため」に必要な耐震強度を再検証し、耐震設計の方法が大幅に見直されたためです。新耐震基準では、主に以下のようなポイントが強化されました。設計用地震力の見直し地震発生時に建物に作用すると想定される水平力(地震力)の想定値を見直し、より大きな地震を想定して構造計算を行うようにした。靭性設計の導入建物の構造部材や接合部が、ある程度の変形に耐えうるように設計する考え方。これにより、大地震が起きてもすぐに崩壊せず、人命被害を防ぐことを重視。施工精度・品質管理の強化単に設計段階だけでなく、施工段階のコンクリート強度や鉄筋のかぶり厚さ(鉄筋を覆うコンクリートの厚み)などの品質もより厳しく求めるようにした。一方、旧耐震基準は「中規模地震で倒壊しない程度」というおおまかな基準で、現行の新耐震基準ほどの詳細な検討や品質管理が行われていない場合が多いのです。その結果、旧耐震基準で建てられたビルは「大きな地震が発生すると、倒壊または重大な損傷のリスクが高い」と見なされています。 1-2.旧耐震ビルが抱えるリスク 旧耐震ビルは、単に“古い”というだけでなく、構造的・物理的にリスクをはらんでいます。代表的なものを挙げると、次のとおりです。(1)地震による倒壊・大損傷のリスク耐震強度が不足しているため、大地震の発生時に建物が部分的に崩落したり、大きく傾くおそれが高まります。建物が万一倒壊すると、テナントの事業継続はもちろん、人命に関わる非常事態になり得ます。(2)テナント募集時のネガティブ要因テナント企業の安全意識やBCPが浸透している昨今、旧耐震というだけで敬遠される場面が増えています。特に、社会的信用を重視するテナント(金融機関やIT企業など)は耐震性能を重視する傾向が強いです。結果的に空室が埋まらない、賃料を下げざるを得ない、という悪循環が起きやすいのです。(3)資産価値の下落建物の評価額は、耐震性や築年数、建物グレードなど多角的に評価されます。旧耐震ビルの場合、いくら立地が良くても、耐震リスクや老朽化の懸念で資産価値が低く見積もられることが多々あります。賃貸オフィス市場のトレンドも加味すれば、将来的に売却を検討する際、想定よりもはるかに安い価格が提示される可能性があります。(4)今後の法改正や行政指導リスク地震防災対策や都市計画の観点から、行政が段階的に耐震化の基準を引き上げる方向にあることは周知の事実です。既に、一部の公共施設や大規模建築物には、耐震診断や補強実施の義務化が進んでいます。今後、基準がさらに厳しくなる可能性はゼロではなく、行政からの指導や是正命令が下るリスクも想定されます。 1-3.中小型賃貸オフィスビル特有の状況 賃貸オフィスビルと一言でいっても、大規模なタワービルから数十坪規模の小型ビルまでさまざまです。ここで注目したいのが、オフィスフロアの基準面積100坪以下の中小規模ビルに固有の“制約”です。旧耐震の議論は耐震性能だけに目が行きがちですが、中小規模のビル特有の意思決定を難しくする要因があるので、以下、説明します。(1)建物の構造上、改修工事の物理的な影響が大きく収支が悪化するリスク大規模ビルに比べてスペースの余裕が少なく、耐震補強を施そうとすると執務スペースを侵食しやすいのが現実です。窓を塞ぐ、ブレースが張り出す、動線が崩れる――こうした変化を以て、普通、耐震補強後、賃貸オフィスが貸しづらくなり、収支が悪化するリスクも想定されます。耐震補強の検討にあたっては「構造の正しさ」だけでなく、以下のポイントについても確認・評価します。耐震補強後に貸室がどれだけ減るか(㎡/坪)採光・レイアウト自由度がどれだけ落ちるか工事中の退去誘発リスク(騒音・振動・工期)(2)テナントも小規模・零細だと共倒れになるリスク中小規模の賃貸オフィスには、地元の小規模・零細な企業/個人事務所が入居しがちです。対応余力が乏しく、移転が先延ばしになりがちだったりします。オーナー側から見ると「なんとなく使い続けてもらえる」点は安心とも思えるのですが、問題が先送りされて、共倒れになるリスクには留意しておく必要があります。(3)ビル経営が属人化して、「意思決定」が正しく行われないリスク中小規模の賃貸ビルほど、ビルオーナーが一人で運営判断を背負っているケースも多く見受けられます。結果として、修繕判断が行き当たりバッタリになり、ビル経営の観点に鑑みると、問題が放置され易い状況が起こりがちです。ビルオーナーが自ら、状況を「見える化」して、整理することができないようであれば、PM/BMを使って、運営をオーナー個人から切り離すことが現実解なのかもしれません。 1-4.旧耐震ビル数の現状データ 東京23区における旧耐震オフィスビルの割合東京23区内で賃貸オフィスとして利用されている建物のうち、1981年以前の旧耐震基準で建てられたビルは、おおむね全体の2割前後を占めると推計されています。中小規模ビルほど旧耐震率が高いオフィスビル全体の傾向を、規模別に見てみます。大規模オフィスビル(延床5,000坪以上)に比べて、延床5,000坪未満の中小規模ビルは旧耐震が多く残っている傾向にあります。ザイマックス総研の「東京オフィスピラミッド2025」によると、旧耐震基準のビルの割合が大規模ビルで12%だったのに対し、中小規模ビルでは22%に上っています。都心部で大規模再開発が進んだ結果、比較的大きなビルの建替えや耐震補強は先行して行われてきた一方、中小規模のオフィスビルについては、更新が遅れがちな状況が数字でも見てとれます。耐震化は進んでいるが、「未達が残る領域」もはっきりある東京都が公表している「特定緊急輸送道路沿道建築物」(条例により旧耐震の耐震診断が義務付けられる領域)では、旧耐震建築物のうち改修済等で耐震性を満たす割合は57.3%(令和6年12月末)にとどまり、4割強は未達という状況です。また国交省資料では、耐震診断義務付け対象建築物(全国)について、2024年3月末時点の耐震化率は約72%と整理され、耐震性不十分な建築物が残っていることも示されています。結論:旧耐震は“もう少しで消える在庫”ではなく、当面残る前提で経営判断が必要東京23区でも旧耐震の在庫は、延床300坪以上の範囲に限っても2,000棟規模で残っています。つまり「古いから仕方ない」で流せる話ではなく、募集・改修・管理体制・出口(建替え/売却)を、現実の数字の上で組み直す必要があります。 【参考文献】ザイマックス不動産総合研究所「東京23区オフィスピラミッド2025」 東京都耐震ポータルサイト「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化状況(令和6年12月末時点)」 第2章:なぜ今「対策」を検討すべきなのか 旧耐震の賃貸オフィスビルのオーナーが耐震補強や建替え、売却などについて「いつかは考えなければいけない」と思いつつも、実際に大きなアクションに踏み切れないケースは少なくありません。減価償却が終わっていれば、毎月の賃料収入は、そのまま実入りに見えますし、現状維持の判断に傾くのも自然です。ただし、旧耐震の問題は「危ないかどうか」だけではありません。先送りの本当のコストは、支出額そのものより“選択肢が減ること”です。(運営改善・補強・建替え・売却のどの選択肢も、タイミングを逸してしまうと、後になるほど条件が悪くなる) 2-1.建物寿命と老朽化、そして地震リスク RC造やS造は法定耐用年数を超えても使えますが、築年が進むほど、構造体より先に設備・防水・配管などが劣化しやすくなります。劣化は静かに進むため、「今まで大丈夫だったからこれからも大丈夫」と判断しがちです。しかし一度、大きな故障や漏水が起きると、復旧コストの問題にとどまりません。テナントの業務停止や営業機会の損失につながり、最悪の場合は退去に至り、賃料そのものが消えることがあります。さらに旧耐震の地震リスクは、「地震で壊れたら直す」だけの話ではありません。旧耐震下での対応を「耐震補強工事をする/しない」「地震後の復旧費用をどうする」に限定すると、賃貸経営の判断としてズレます。地震リスクは、建物の損傷・復旧コストだけでなく、テナントの事業継続、従業員の安全、対外説明、そして更新・移転判断にまで波及するからです。 2-2.地震リスクは「起きた後」ではなく、「起きる前」に効いてくる 日本で地震リスクがゼロになることはありません。旧耐震は新耐震より倒壊・大破リスクが高いと見られやすく、仮に倒壊に至らなくても、損傷が出れば継続利用が難しくなり、賃料収入が止まる一方で復旧費用が発生します。ただ、いま考えるべき地震リスクは「発災後の被害」だけではありません。発災後のリスクを前提に、テナント側ではBCPやリスク管理の観点から、入居・更新・移転の判断基準が組み立てられています。旧耐震であることは、次のような形で“いま”効いてきます。入居候補から外される(=空室リスクに直結する)契約更新で慎重になる(=移転検討が始まる) 2-3.行政・金融機関の見方が変わると、動けなくなる 耐震改修促進法や自治体の施策により、建物の用途・規模・立地条件によっては、耐震診断・報告・改修の流れが強まっています。今は対象外でも、対象領域の拡大、運用の厳格化の進捗次第では、オーナーの負担は後から重くなりかねません。また、金融機関は「旧耐震かどうか」だけでなく、修繕計画があるか、資料が揃えてあるか、運営体制が規定化されているかなどを見ます。旧耐震で資料に不備があると、担保評価が下がるだけでなく、借換えや追加投資の局面で条件が悪くなりやすい。結果として「動きたいのに動けない」状態を招きかねません。 2-4.この章の結論:今やるべきは「工事の決断」ではなく「判断材料の整備」 ここまで見てきた通り、旧耐震のリスクは「建物が壊れるかどうか」だけではありません。老朽化や地震は、復旧費用に加えて、テナントの継続利用・更新判断・移転判断に波及し、賃料収入そのものを不安定にします。さらに、行政対応や金融機関の見方が変わると、資金調達や改修の自由度も下がり、動きたいときに動けない状況が起きます。だから旧耐震の対策は、いきなり耐震補強や建替えを決める話ではありません。先送りの本当のコストは、修繕費そのものより“選択肢が減っていくこと”です。今やるべきは、次の情報を整理して、耐震補強・建替え・売却・運営改善を同じ土俵で比較できる状態を作ることです。建物と設備の状態修繕履歴と今後の支出見通しテナント状況と契約条件次章以降で、具体的な選択肢を順に見ていきます。 第3章:耐震補強という選択肢の実情 旧耐震の賃貸オフィスビルにおいて「耐震補強を実施する」というのは、安全性を高めるための最も正攻法のように見えます。耐震性能を上げること自体は合理的です。ただし、賃貸オフィスビルの経営として見たとき、耐震補強は、“やれば勝ち”の施策ではありません。中小規模ビルほど、補強のやり方次第では、かえって、賃貸オフィスビルとしての価値が下落して、既存テナントが退去して空室となり、さらに、空室を埋める際の募集賃料が下落して、賃料収入が低減することになりかねません。この章では、耐震補強が向く/向かないの判断基準を整理します。耐震補強で失敗するパターンはだいたい同じです。オフィスの執務スペースの面積の減少/採光性が損なわれ/工事でテナントの退去が連鎖する/回収の筋が立たない。まずは、ここを外さないための視点を押さえます。 3-1.中小規模ビルでは耐震補強工事の物理的な影響が大きい 中小規模ビルの耐震補強にあたっては、耐震性能だけでなく、面積・採光・レイアウト自由度等の物理的影響についても細心の注意を以て確認する必要があります。図面でチェックすべきポイント執務スペースの面積がどれだけ減少するのか:ブレース・耐震壁・袖壁の張り出しで、実質有効面積が何㎡(何坪)減少するのか確認採光がどこまで損なわれるのか:窓前に耐震壁・ブレースが設置される場合の影響度合い執務スペース内の動線への影響:入口〜執務〜水回りの通行に支障が生じないか執務スペースのレイアウト自由度が確保できるか:会議室・執務・倉庫などの区画が成立するかこれらの点を確認しないまま「耐震補強の可否/性能」だけで議論すると、耐震補強後に“貸し難い賃貸オフィスビル”が出来上がりかねません。特に、中小規模の賃貸オフィスビルでは致命的な状況に陥りかねません。 3-2.工事コストと資金調達の負担 耐震補強の検討にあたって、工事費だけで是非を決めようとする、判断を誤りやすくなります。耐震診断を起点に、設計・工事・テナント対応まで含めた費用総額と、その後の収益への影響もあわせて整理する必要があります。(1)耐震診断・補強設計費も含めた総コスト耐震補強工事の前提として耐震診断・補強設計が必要です。ここだけでも数百万円規模になることがあります。当然のことながら、補強工事費はさらに別にかかって、建物条件次第で振れ幅が大きく、近年のコスト増に鑑みると、相応の負担を覚悟する必要があります。(2)減価償却が終わっている物件ほど、ビルオーナーにとって、追加投資の心理ハードルが上がる旧耐震の賃貸オフィスビルは築年数が経過しているので、会計上の減価償却が既に終了しているケースが少なくありません。賃料収入を“そのまま収益”と捉えてしまうと、ビル・オーナーの心理上、現状維持バイアスがかかり易く、借入をして耐震補強工事に踏み出し難くなります。耐震補強を検討する出発点は、「いまの収益が将来も同じ形で続くとは限らない」という前提を置くことです。現状の収益だけを基準に判断すると、必要な検討や準備が遅れ、結果として選択肢を狭めてしまう可能性があります。(3)公的支援制度は“補助”であって“全額負担の肩代わり”ではない一部の自治体や国土交通省が行っている耐震化の助成制度は、適用要件や上限金額が限定的で、補強費用全体をカバーできるほどの補助は期待しにくい面があります。使えるものは使う、ただし当てにしすぎない。これが現実的な対応です。 3-3.耐震補強工事のテナントへの影響 耐震補強工事は、建物の躯体に手を入れるため、工事の影響が大きくなりやすい工種です。ここでの対応を誤ると、工事費そのもの以上に、テナント退去による空室、賃料収入の低下といった形でビル経営に跳ね返ってくるリスクを想定しておく必要があります。(1)騒音・振動によるテナントの業務への影響耐震補強工事は騒音や振動が発生しやすく、工事期間が数か月に及ぶ場合もあります。入居中テナントの業務への影響が避けられません。(2)テナント退去が連鎖するリスク耐震補強の規模によっては、工事期間中にテナントの退去を要するケースも想定されます。また、工事対象区画が空室になることに加えて、同じビル内の他テナントが工事による業務影響を嫌い、更新を見送る・移転を検討する、といった動きが連鎖する可能性もあります。この点は、耐震補強の是非を左右する重要な論点です。(3)周辺・他テナントとの調整ビル内のテナントが退去しなくても、搬出入・騒音等で周辺に影響が出るので、工事内容やスケジュールについて事前調整が必要になります。調整が長引けば工期が延び、結果としてコスト増につながるおそれもあります。「工事で失う金額」を整理する(工事費以外も含めて捉える)耐震補強の負担は、工事費だけではありません。検討の段階で、少なくとも次の要素も踏まえて整理しておくと、より的確な判断の前提となります。総コスト(経営目線)=工事費(含む、耐震診断・補強設計費)+近隣対策費用△耐震補強工事期間の賃料減△自治体等の補助 3-4.耐震補強のメリット・デメリット(整理した上で、判断に落とす) ここまでの話を踏まえた上で、耐震補強のメリット・デメリットを“経営判断”の観点から整理します。メリット(1)安全性の向上耐震性能が上がれば、地震時の倒壊・大破リスクの低減が期待できます。その結果、テナントの安心材料にもなります。(2)売却・融資での説明力が増える可能性耐震性が高い物件は、売却時や金融機関の担保評価が相対的に高まることが期待できます。今後、災害リスクへの意識が高まると、「安全な建物」であることが資産価値向上に寄与するでしょう。(3)将来的な行政対応の負担を軽くする可能性耐震診断・改修が義務化される流れが強まっていることを前提にすると、早めの耐震補強を実施しておくことで、将来的な是正命令などに対応する負担を減らせます。デメリット(1)初期投資額が嵩む先述のとおり、耐震診断や設計費用、工事費などを合わせると数千万円規模でかかることも少なくありません。十分な資金が確保できない場合、耐震補強工事の実施自体が困難となる場合もあります。(2)耐震補強工事中の退去による空室、収益低減リスク前項の耐震補強工事に関連する費用発生に加えて、耐震補強工事の影響で発生する空室による収益の低減は重要なファクターです。(3)貸室価値が落ちると、投下の回収が厳しくなる耐震補強工事の物理的影響(賃貸面積の減少/採光に支障/レイアウトに支障)により、賃貸オフィスとしても魅力が低減してしまい、耐震補強後、将来に向けて、賃料の引上げが難しくなる可能性も想定されます。 【耐震補強工事の是非に関する判断チェックリスト(耐震補強が向く/向かない)】耐震補強工事の是非に関する判断基準を明示します。A:補強が向く耐震補強しても貸室面積の減少が軽微と判断。採光・動線・レイアウト自由度を確保できる。耐震補強工事中でも一定程度、テナントの維持ができる。耐震補強後、賃貸オフィスとしても魅力を保持できる。B:補強が向かないブレース・耐震壁で貸室面積が顕著に減少/窓の採光が妨げられる退去工事中のテナントの退去の連鎖が想定される耐震補強後、テナント募集して稼働、賃料水準の維持・改善が期待できない近い将来、賃貸オフィスビルの建替え・売却を想定していて、耐震補強に資金と時間をかける意義が薄いこのチェックリストは、専門家の結論を待つ前に、ビルオーナーが判断の軸を持つためのものです。 3-5.耐震補強とは別に「貸しやすさ」を回復させる改修という選択肢 耐震補強は「安全性」の論点ですが、賃貸オフィスビルの経営判断は、それだけで決まりません。仮に耐震補強に費用を投じたとしても、耐震補強の内容や進め方によって貸室価値が低減したり、耐震補強工事を契機にテナント退去が連鎖したりすれば、経営上はマイナスに働く可能性があります。そこで現実的な選択肢として出てくるのが、耐震補強とは切り分けて、“貸しやすさを回復させる改修”を検討するという考え方です。ここで言う改修は、テナントの入居判断に直結する機能面の改善を指します。たとえば、次のような項目です。空調設備の更新(故障リスクの低減と快適性の改善)給排水・防水の更新(漏水リスクの抑制)電気容量・配線まわりを含む電気設備の整理・更新共用部の機能不全の解消(使いにくさ・不具合の是正)耐震補強が結果として貸室価値を下げる見込みが強い場合は、補強仕様を見直すか、あるいは耐震補強とは別に“貸しやすさ回復”の改修を優先したほうが合理的なケースもあります。一方で、貸しやすさを回復させる改修を行っても、空室が埋まらない/募集賃料の低減/大きな修繕や更新が連続して必要になるといった状況が見えている場合は、「改修で運営を続ける」だけでは解決にならない可能性があります。ここまで来ると論点は、改修の是非ではなく、保有を続けるのか、建替えるのか、売却するのかという“資産の出口”の判断に移ります。次章では、耐震補強や運営改善と並べて比較できるように、建替え/売却という選択肢を、メリット・デメリットと判断ポイントに分解して整理します。 第4章:賃貸オフィスビルの建替え/売却という選択肢(出口設計を整理する) 旧耐震の賃貸オフィスビルは、耐震性の不足だけでなく、設備の老朽化や賃貸市場での競争力低下といった課題を抱えています。対策の検討を後回しにするほど、建物の劣化は進み、ビルの安全性、テナントの確保がますます難しくなっていくでしょう。前章で検討してきた、耐震補強や“貸しやすさ回復”の改修は、うまく効けば、賃貸オフィスビルの経営を立て直す手段になりえます。ただし、耐震補強工事の影響が大きすぎる/テナント募集が難しくなる/賃料水準の維持が困難/大きな修繕が連続する見通しといった状況が見えている場合、賃貸オフィスビルの経営上の論点は「どの工事・改修をするのか」ではなく、「建替え」あるいは「売却」の方向性をより真剣に検討するフェーズに入っている可能性が高いのです。ここでは、まず、耐震補強・建替え・売却を、同じ土俵で比較できるように整理します。 4-1.まず比較表で“意思決定の土台”を作る 比較項目耐震補強建替え売却初期費用中〜高(診断・設計・工事)高(解体+建築+設計+諸費用)低〜中(仲介・測量等)賃料収入の停止期間工事影響あり(減収〜空室の可能性)工事期間中(解体〜竣工まで)売却完了で賃料収入はゼロテナント調整の難易度中〜高(工事影響・退去連鎖)高(明渡し・補償・移転調整)中(契約条件と引継ぎ次第)将来の自由度補強内容次第ではあるが、限定されがち高(商品を作り直せる)高(資産入替・撤退が可能)失敗パターン貸室価値低下→空室・賃料下落資金計画破綻/期間長期化/出口が読めない情報不足で買い手が限定されると売価が低下 4-2.建替え(メリットと注意点) 建替えは、旧耐震の賃貸オフィスビルに残る課題を「部分的に直す」のではなく、建物そのものを作り直す選択肢です。耐震性だけでなく、設備・電気容量・レイアウト自由度・共用部の機能など、賃貸オフィスとしての条件をまとめて更新できます。一方で、建替え工事は大規模なので、資金調達の金額が大きくなり、入居中テナントとの明渡し調整も不可避です。ビルの解体、テナントとの明渡し調整を、一旦、始めると、関係者も動き出して、コストも発生するため、途中で方針転換するのが難しくなります。したがって、建替えで解決したい課題と、それに伴って発生する負担を、最初に確認し、明示した上で判断する必要があります。メリット(建替えが効く場面)(1)“商品を作り直せる”という強みがある建て替えることで、現行の耐震基準を満たすのはもちろん、老朽化が進んだ設備(空調・給排水・防水・電気)も一括で更新できます。建替えは「個別修繕の継ぎ足し」では解決しにくい問題をまとめて整理・解決できる可能性があります。(2)テナント募集戦略と賃料設計を“前提から”組み直せる建替えの効果は、竣工後に「どういうテナントを想定するか」を先に定め、その想定に合わせてオフィス賃貸の前提条件を整えられる点にあります。築年数が経過している旧耐震の中小規模の賃貸オフィスビルで、テナントに敬遠されやすい条件は、耐震性能だけではありません。電気容量が足りない、空調が不安定、給排水や防水の不具合の発生が見通しにくく、電気設備の老朽化で停電のリスクが高い――こうした設備由来の事故・停止リスクが、入居判断と更新判断に影響します。建替えでは、設備更新によって事故・停止リスクを下げ、万一の不具合が起きた場合でも影響範囲を限定しやすい構成にできます。あわせて、防災設備や非常用電源の有無、停止時の復旧手順などを含め、従業員の安全と事業継続に関わる前提条件を整理して、募集条件として提示できます。結果として、テナントの懸念点が減り、リーシングの組み立てがしやすくなり、賃料水準の維持・見直しの余地が生まれます。注意点必要資金が大きく、資金計画・資金調達の前提を先に固める必要がある建替えには、建築費だけでなくて、解体費、設計監理費、各種申請費、仮移転対応・近隣補償などが積み上がり、必要資金は想定より膨らみやすいです。さらに、旧耐震の賃貸オフィスビルの場合は、担保評価が伸びにくいケースもあり、資金調達上の制約になりやすい点も考慮しておく必要があります。建替えは、具体的な「工事の話」に入る前に、金融機関と資金調達の話をつけておく必要があります。一般的に、金融機関は、いくら貸せるか、いつ実行するか、返済条件をどうするのかを、次の材料で判断します。総事業費の内訳(解体・設計・建築・諸経費)と資金の出し方(自己資金/借入)資金が必要になる時期(解体〜竣工までの支払予定)と、賃料収入が入らない期間の資金繰り竣工後の賃料収入見込み(想定賃料・稼働率)と運営費、返済計画テナント明渡しの進め方(スケジュール、補償の考え方)と想定リスクこれらが整理されていないと、融資額や実行時期が決まらず、着工までの手続きが長引きかねません。結果として、賃料収入がない期間が延びて、追加費用が発生して、当初の資金計画の前提が崩れ、建て替えプロジェクトの進捗にとって大きなリスク要因となりかねません。また、着工後も、追加工事、行政協議、調整の遅れなどにより、工期と費用が想定の範囲内に納まらない可能性もありえます。したがって、資金計画は「見積りどおりに進む前提」で組むのではなく、予備費と予備期間をあらかじめ織り込んだ設計にしておく必要があります。 4-3.売却(メリットと注意点) 耐震補強・建替えは、資金調達ならびに工事実施を前提にした「続けるための選択肢」です。これに対して、売却は、賃貸オフィスビルを保有し続ける前提をいったんやめて、資産を現金化する選択肢です。耐震補強や設備更新等、「続けるための投資」を抱え込まず、いまの条件で手仕舞いして次の選択に移るための判断になります。旧耐震の築古の中小規模の賃貸オフィスビルにおいては、この選択肢を検討対象に入れておくのは、充分、意味があるものと考えられます。メリット将来コストと運営リスクから解放されます耐震補強、大規模修繕、設備更新、空室の長期化など、築年が進むほど発生しやすい支出と対応が続きます。売却すれば、こうした不確実性を「自分が抱える運営課題」から外せます。金額面だけでなく、判断の回数や調整の手間が減る点も、現実的なメリットです。手元資金を確保し、次の選択肢を可能とします売却によってまとまった手元資金を確保できれば、借入返済、別物件への投資、資産配分の見直し、事業・生活設計への充当など、次の選択肢を具体化できます。賃料収入の維持と「別の形での期待収益」とのバランス判断がポイントです。ハードル資産査定額は「買い手が見込む追加コスト」に左右されます旧耐震の賃貸オフィスビルは、買い手が現状のまま長期運用する前提になりにくく、大規模改修、建て替え等の対応コストを見込んだうえで査定額が算定されます。具体的には、解体費、耐震補強や改修の費用、用途変更・建替えに向けた手続き負担などがポイントになります。そのため、売主がそれらの工事を実施しなくても、これらの見込みコストは売却価格に織り込まれやすいです。さらに、買い手がどの前提で収支を置くかによって、同じ物件でも提示価格に幅が出ます。各種費用や税金負担を控除したネット金額を想定する売却代金だけで判断せず、仲介手数料、譲渡にかかる税金、ローン残債の精算、その他の付随費用まで引いた後の金額を以て想定しておく必要があります。例:手元資金概算 = 売却代金 − 仲介手数料 − 譲渡関連税 − 残債精算 − その他費用 4-4.結論:出口は、比較できる状態を作ってから決めます 建替えと売却は、どちらも大きい判断です。判断の質を左右するのは、同じ土俵で比較できているかです。この章の冒頭、4-1でも示しましたが、以下の判断材料を揃えることが重要です。建物・設備の状態、修繕履歴、テナントの賃貸契約条件、賃料・運営コストの収支を整理します。耐震補強/建替え/売却の選択肢について、初期費用・賃料収入がない(減収)期間・テナント調整を同じ軸で見ます。この比較ができるうちに、次の打ち手に移れる状態にしておきます。先送りで減るのは、修繕費の余裕よりも選択肢の余裕です。次章では、これらの判断材料を揃えて、更新していくために、PM/BMをどう使うかを扱います。 第5章:PM/BMを、出口判断の判断材料を揃えるために活用します 旧耐震の賃貸オフィスビルを巡る意思決定には、耐震補強・建替え・売却などの選択肢があります。どの選択肢にも、投資金額とリスクが伴いますので、ビルオーナーが迷うのは当然です。問題になるのは「迷うこと」そのものではありません。比較の前提となる判断材料が揃わないまま、検討が進まず、時間だけが過ぎていくことです。結論を出すには、まず、「比較の土台」を作る必要があります。耐震補強/建替え/売却を並べるのであれば、少なくとも次の情報が、同じ整理軸で揃っていることが前提になります。建物・設備の現況(不具合・劣化の状況、故障傾向、法定点検の実施状況など)テナントとの賃貸借契約の条件(解約条項、原状回復義務の範囲、工事制限、特約など)収支と将来支出(賃料、運営コスト、修繕・更新の見込み、賃料減収の想定期間など)工期とテナント調整(通知、移転の要否、休業補償の論点、工程上の制約など)ただ、この「比較の土台」をオーナー自身で作り切るのは、実務上ハードルが高いかもしれません。必要な情報は、竣工図・点検報告・修繕見積・工事履歴・契約書・収支資料など複数の資料にまたがります。さらに、集めるだけでなく、抜け漏れの確認、情報の粒度・確度の確認、同じ形式への整理といった作業が必要になります。ここで検討に入るのが、PM(プロパティ・マネジメント)とBM(ビル・メンテナンス)という役割の導入です。なお、PM/BMの役割は、ビル管理会社が担う場合もあれば、外部専門家と連携・分担する場合もあります。重要なのは、旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断に必要な材料が、比較できる形で整う体制になっているかどうかです。次節では、PMとBMの違いを整理します。 5-1.PM/BM:機能の違い PM(Property Management)とBM(Building Maintenance)は、どちらも「賃貸オフィスビル管理」に関わりますが、見ている対象が違います。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断に必要なのは、この違いを押さえたうえで、それぞれの役割を活かして活用することです。PMは、賃貸経営の運用を扱います。賃料や募集条件、契約条件、収支、テナント対応、修繕の優先順位づけ、外部業者や関係者の調整など、ビルを事業として回すための業務です。結論を出す場面では、集まってきた情報を整理し、耐震補強/建替え/売却を同じ条件で並べられるように整えます。BMは、建物設備の維持管理を扱います。設備の点検・保守、故障対応、法定点検の実施と管理、衛生・安全面の段取り、工事手配の実務など、建物と設備を止めずに動かすための業務です。結論を出す場面では、現況の把握や劣化の状況、故障傾向など、比較の前提になる「現場の根拠」を出します。この章で扱う旧耐震の賃貸オフィスビルの意思決定では、PM/BMの価値は次の形で整理できます。PM:比較できる形に整える側(判断に使える形式へ整理します)BM:比較の根拠を出す側(現場の状態を把握し、根拠を示します) 5-2.まず整理して揃えるのは「判断用資料」(比較の土台を形にします) PM/BMの役割を踏まえて、実務では「結局、何が揃えば比較できるのか」が曖昧なまま進んでしまうことがあります。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断においては、必要な情報の種類が多く、粒度もばらつきやすいためです。そこで、最初にやるべきことは、比較に必要な判断用資料を先に定義し、同じ形式で整理して揃えることです。出口判断に必要な判断用資料は、最低限、次の5点です。これが揃うと、耐震補強/建替え/売却を同じ土俵に載せられます。(1)建物・設備の現況一覧(根拠の入口)主要設備ごとの状態(劣化・不具合・故障傾向)法定点検・定期点検の実施状況と指摘事項直近の修繕・更新履歴(いつ、何を、どの範囲で)当面の注意点(止まると影響が大きい箇所、優先度の高い不具合)※これは基本的にBMの領域です。「現場の事実」をここで固めます。(2)将来支出の見立て(修繕・更新の候補整理)今後数年で現実に出てきそうな更新・修繕項目概算費用は“点”ではなく“幅”(レンジ)で置く不確定要素(追加調査が必要な箇所、見積条件の前提)※BMの見立てをベースに、PMが収支と接続します。(3)テナントとの賃貸借契約の条件とテナント調整の論点整理解約条項、工事制限、原状回復の扱い、特約休業補償や仮移転が論点になり得る条件の有無通知期間・工事可能時間帯など、工程に効く制約※ここが抜けると、工期や減収期間の比較が成立しません。PM側で整理するのが基本です。(4)3案比較表(耐震補強/建替え/売却)初期費用(概算レンジ)工期と減収期間の見込みテナント調整の難所(どこがボトルネックか)収益・売却の見通し(前提条件つきで整理)前提条件(何を仮定しているか)と、条件が崩れた場合の影響※ここが「比較の本体」です。PMが形式を作り、BMが根拠を供給します。(5)未確定事項リスト(次に何を確かめるか)追加調査が必要な項目追加見積が必要な項目判断に影響する前提のうち、まだ確定していないもの※“分からないこと”を残したまま比較表だけ整えると、結論の再検討が増えます。最後に必ず残します。この5点が揃うと、議論は「情報が足りない」状態から抜け出して、比較の質が上がります。PM/BMを使うかどうかに関わらず、この判断用資料セットを基準にしておくことで、旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断の実務を進捗させることができます。 5-3.PM/BMへの頼み方(判断用資料を基準に委託範囲を決めます) PM/BMを使う場合、最初に決めるべきなのは、「判断用資料」と「責任範囲」です。判断用資料を基準に委託範囲を定義すると、判断材料の整理、とりまとめが進めやすくなります。①判断用資料ごとに担当範囲を割り当てます5-2の判断用資料に沿って、中心となる担当を分けます。BMが中心になる範囲(1)現況一覧(2)将来支出の技術的な見立て(更新・修繕候補と根拠)PMが中心になる範囲(3)テナントとの賃貸借契約の条件とテナント調整の論点(4)3案比較表(5)未確定事項リストの整理と更新管理同一の会社がPM/BMを一体で担う場合でも、判断用資料ごとに「根拠を出す責任」と「比較表に整理する責任」を分けておくと、責任範囲が曖昧になりません。②比較の土台を揃える(検討フェーズ/対象範囲/数字の前提)耐震補強/建替え/売却を比べるときは、各案の数字がどのフェーズの、どの前提条件で、どこまでを対象に出ているかを揃えないと比較になりません。片方が机上の概算、もう片方が詳細調査ベース──この状態で表に並べても、結論がブレます。揃えるのは次の3点です。1)検討フェーズと、数字の根拠レベルを明記するいまが「方向性を絞る一次検討」なのか、「実行可否を判断する段階」なのかを、はっきりさせます。後者なら耐震診断を含む必要調査が前提です。一次検討なら、概算で進めてOKですが、“概算の前提条件”と“未確定の残し方”(どこから先は次段で確定させるか)も合わせてはっきりさせます。例:夜間工事の要否/搬入条件/工事可能時間/追加調査が必要な箇所の扱い…など、概算に直撃する条件は必ず明示します。2)耐震補強が「どこまで影響するのか」を踏まえて検討する耐震補強工事の影響範囲を「構造要素だけ」に限定せず、付随して影響し、検討・調整が必要になる範囲を明示した上で検討します。例:天井・間仕切り・内装・什器/設備更新や機器移設の要否/工事中の使用制限/テナント調整の範囲/賃料の減収期間の見立て。3)比較表の“必須項目”を統一して、判断に使える形にする比較表のそれぞれの選択肢について、費用・工期・賃料の減収(空室/賃料影響)・調整論点(テナント/行政/金融)・将来支出・前提条件・未確定事項を項目として網羅します。未確定事項が残るのはOK。ただしその場合は、次に何を調べれば確定させられるのか(追加調査・見積条件・判断形成の手順)まで付記します。③判断資料の提出の締め切りとスケジュール(比較表を“更新できる運用”にする)前提条件は途中で必ず変わります。だから「比較表の完成版を一気に作る」のではなくて、短いサイクルで提出→判断→更新します。ここで決めるのは提出物と締切と判断ポイント(ゲート)です。 標準的な進め方(目安)第1段階:1週間以内(5)未確定事項リスト一次版を提出└ 不足資料、追加調査の要否、調査の優先順位、次段で確定させる項目を明記ゲートA:一次検討として走れるか/追加調査が先かを決める第2段階:2週間以内(1)(2)(3)の一次版を提出(=比較の土台)└ 前提条件/概算の根拠レベル/影響範囲(波及工事・制約)を揃えるゲートB:3案を同じ土俵で並べる準備ができたかを確認第3段階:3〜4週間以内(4)3案比較表一次版を提出└ 費用・工期・減収・調整論点・将来支出・前提条件・未確定事項をセットでゲートC:方向性を絞る(残す案/捨てる案)第4段階:追加調査・見積反映(+4〜8週間が目安)(4)比較表改訂版を提出└ 第1段階の未確定事項を潰した反映版(必要なら複数回更新)ゲートD:実行可否の判断(やる/やらない/売る)重要な補足(ここが肝)一次検討だけで「絞る」なら、最短3〜4週間でいける(第3段階まで)「やる/やらない」を判断するなら、調査を入れるので+1〜2か月は見ておく(第4段階)つまり、ここでは「順番」の話じゃなくて、“比較表を継続的に更新していく前提で締切と判断点を置く”って話。 5-4.判断用資料が揃っても、ビルオーナーの「判断の閾値」が必要です。 5-2の判断用資料が揃うと、耐震補強/建替え/売却は同じ土俵で比較できるようになります。ただし、比較表があっても結論は自動的に出ません。最後に必要なのは、オーナー側の判断の閾値です。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断で、閾値になりやすいのは次の3つです。投資の上限額(いくらまで出すか)耐震補強・建替えの工事費・設備更新・改修費用等を含めて、投下できる金額上限を決めます。この上限値の設定がないと、どの案も「もう少し追加資金を投下すれば良くなる」で終わって、最終判断が下せません。資金繰りの限界(何ヶ月・最大いくらまで耐えるか)比較表に出てくる「賃料収入の減収額・減収期間・追加支出額」の結果を見て、①賃料収入の減収が続いてよい最大額・月数、②その期間での追加支出の許容を設定します。投資金額だけでなくて、キャッシュフローを見ておいて、どこまでの持ち出しに耐えられるかの許容額を設定しておく必要があります。テナント対応リスクの許容(どのレベルの個別協議まで受けるか)テナント調整の進捗は、重要なポイントです。個別協議(減額・補償・合意書・退去協議など)の方針によっては、協議期間、補償・減額の金額に幅が出ます。具体の交渉実務は、PM等の専門家のサポートを受けるべきですが、協議の方針については、最終的にビルオーナーが判断する必要があります。PM/BMができるのは、比較表の項目を埋めて、それぞれの選択肢がこの判断の閾値を超えるかどうかを見える化することです。逆に言えば、判断の閾値が決まっていないと、判断用資料が揃っても結論には辿り着けません。 第6章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営の核心は「リスク管理」 これまでで整理した通り、耐震補強/建替え/売却の選択肢は、判断材料が揃っても、最後にはビルオーナーの判断が必要です。ただし、その前に押さえるべき前提があります。旧耐震の賃貸オフィスビルでは、経営の基本姿勢が定まっていないと、判断の軸が定まらず、いくら判断材料を並べても結論が出ません。この章では、旧耐震の賃貸オフィスビル経営を「リスク管理」として成立させるための基本姿勢を整理します。 6-1.旧耐震の賃貸オフィスビルの意思決定は、運営と責任の整理から始まる 旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断は、耐震補強/建替え/売却のどれを選ぶにしても、「誰が何を整理して、誰が何を判断するのか」の分担で決まります。PM/BMは、比較し、判断を下すのに必要な情報を揃え、論点を整理し、選択肢を同じ土俵に載せる役割を担います。一方で、どのリスクをどこまで引き受けるのか、どこで線を引くのかについては、ビルオーナーの判断が必要です。意思決定を成立させるために、PM/BMに委ねる領域と、オーナーが引受ける判断を、明確にします。借主との調整が、一番、不確定要素があって、期間・金額の振れ幅への影響が大きいので、その点にフォーカスして、それぞれの分担を整理します。PM/BMが担う領域(材料を判断に使える形に整える)借主への影響を、条件別に整理する(在館工事/部分退去/段階退去など)借主の同意が必要になる論点を洗い出し、協議の論点・想定期間・条件・補償/精算額の幅を整理する費用が上振れしやすいポイントを押さえ、レンジと前提条件を示す(追加工事・追加調査・施工条件の制約など)以上を、耐震補強/建替え/売却の各案で、比較できる形にまとめるオーナーが担う判断(許容範囲を決める)判断上、重視するリスクを決める(安全性/収益/資金繰り/出口など)借主対応として、どこまでの調整を前提に置くかを決める(時間・条件変更・追加負担の許容)その前提の下、耐震補強/建替え/売却の選択肢を決める借主がいる以上、耐震補強/建替え工事や売却の判断は借主の営業に影響します。合意の取り方次第で工期・賃料の減収期間/幅・補償の見通しが変わり、収支も変わります。だから、材料の整理はPM/BMに任せながらも、最後に「どこまで背負う/覚悟するのか」を決める判断はオーナーが下します。 6-2.旧耐震の賃貸オフィスビルの経営における「リスク管理」 賃貸オフィスビルの経営におけるリスク管理とは、一般的に、不確実要素を棚卸しし、影響(安全・法務・収支・工期・出口)を評価し、対応方針を選び、前提更新に合わせて見直すことです。国際的にも、リスクを「特定・分析・評価・対応(treatment)し、監視とコミュニケーションを回す」フローの下、整理されます。旧耐震の賃貸オフィスビルの経営において、実務上、ボトルネックになりやすいリスクについて、以下、上げておきます。法令・制度対応リスク耐震改修促進法の枠組みでは、一定の建築物に耐震診断が義務付けられ、結果の報告・公表まで含めて制度化されています。さらに、建築基準法の「定期報告制度」は、使用開始後も適法状態を維持するための定期調査・検査・報告を所有者に求めています(建築物、防火設備、昇降機など)。東京だと防火対象物点検報告制度(消防法)も、一定の対象で点検・報告が義務になります。)安全・賠償責任リスク地震発生時、建物が損壊し損害が出たときに「建物の安全性」「維持管理の相当性」が争点になり、所有者側の責任が問題化し得る、という意味でのリスクです(いわゆる土地工作物責任の射程など)。契約・テナント対応リスク賃貸借は「使用・収益させる」契約なので、工事や不具合で使用が制限されると、賃料減額や修繕をめぐる運用が現実の論点になります。改正民法では賃貸借のルールが整理され、修繕や原状回復等の考え方も明文化されて、「借主の立場の尊重」の傾向が見てとれます。借主の使用が妨げられると、契約上の論点(賃料・補償・合意書・解除)に直結して、収支と工期に影響が及びます。工事・更新リスク耐震補強、建替え等、老朽化対応工事は、見積りの時点で“確定”しない部分が残りやすい(追加調査、追加工事、施工条件、夜間・搬入制約など)。この上振れは、金額だけじゃなく工程・テナント調整にも波及します。収益・資金繰りリスク「投資総額」も重要ですが、キャッシュフロー(キャッシュアウトのタイミング・追加・長期化)で資金繰りが行き詰るリスクは想定しておくべきです。売却時の価格リスク売却価格・条件を協議するにあたって、デューデリで指摘される論点(耐震、法定点検の履歴、是正、テナント条件等)によって、買い手の幅を狭めると、最終的な売却価格に影響することがあります。耐震診断が公表対象になる場合、さらに情報の整理が必要です。最後に。PM/BMの役割は、それぞれのリスクについて、論点・前提条件・影響(工期/収支/合意難易度)に分解して、比較表に載る形へ整えること。ビルオーナーが、どのリスクを優先して取りに行くか/抑えに行くか、の選択について判断します。 6-3.出口判断は「収益比較」ではなく、リスクを踏まえた許容度の設定で決まる 旧耐震の賃貸オフィスビルで出口(耐震補強/建替え/売却)を判断するとき、議論が迷走しやすい原因は、リスク管理の観点(何をリスクと見なすか/どこまで見込むか/誰が負うか/許容できない線はどこか)を踏まえずに、表面的な計算で収入と支出を設定して、優劣を付けようとすることにあります。それでは、リスク管理の考え方に沿って出口判断を組み立てようとするにあたって、以下の4つのステップに分解できます。①リスクを「特定」するまず、旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断に影響するリスクを、法令・制度対応、安全・賠償責任、契約・テナント対応、工事・更新、収益・資金繰り、売却価格等に整理します。ここで重要なのは、細目を増やすことではなく、「どのリスクが、この物件では支配的なのか」を見える形にすることです。②リスクを「評価」する(影響の出方を揃える)次に、各リスクが出口判断にどう影響するかを、同じ物差しで揃えます。具体的には、影響を工期・賃料収益への影響(減収)・追加支出(持ち出し)・実行難易度・不確実性(幅)に落とします。この段階では、数字は、単一の見込み値というのではなく、変動幅を踏まえたレンジとして扱います。レンジの幅について、未確定事項があるからなのか、リスク要因の性質に根差したものであるのかにつちえも整理します。③リスクへの「対応方針」を決める(選択肢を作る)評価までできたら、リスクへの向き合い方を決めます。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断は、だいたい次の3タイプに分類できます。リスク低減型:安全性・適法性・設備リスクを優先して低減させて、運営の不確実性を小さくしようとする(耐震補強・更新寄り)リスク回避型:長期の不確実性を抱えず、外部化しようとする(売却寄り)リスク転換型:一度大きく動かして、以後のリスク発生の構造を作り替え、制御しようとする(建替え寄り)どのタイプが優れているのかではなく、この物件とこのビルオーナーが、どのリスクを許容して、どのリスクを回避するのかという選択になります。④「見直し前提」で運用する(出口判断を一回で終わらせない)出口判断は、一度、方針を決めたら、それで終わりではありません。追加調査や見積、制度・市場環境の変化で前提は更新されます。だから判断材料は「更新できる形」で維持します。このようなかたちで運用していくと、途中で前提条件、外部環境が変わったとしても、判断を更新して、対応することが可能となります。 6-4.出口判断のタイミングは選べない 旧耐震の賃貸オフィスビルでは、出口判断(耐震補強/建替え/売却)を、“当初の想定通りの時期”まで持ち越せるとは限りません。実際には、以下の事情・要因を以て判断の前倒しが迫られることもあります。設備故障が続き、設備更新が避けられなくなる故障対応が「都度修理」からすぐに「設備更新」が必要な状態に移行すると、将来支出の前提が変わってきます。空室が長期化し、募集賃料を下げてもテナントが決まりにくくなる賃料の収益面だけでなく、改修・耐震補強・建替え・売却、それぞれの選択肢の見え方にも影響します。行政・金融・売却候補先から、耐震性を踏まえた法制への適合性について確認・説明を求められる調査・点検・是正の要否が、意思決定の前提になります。相続・共有者の異動・借入の期限などの事情により、意思決定が迫られる“いつか判断する”という先送りが成り立たない状況になります。ここで重要なのは、判断の結論を早急に下そうとすることではありません。前提条件が変わったときに、耐震補強/建替え/売却の選択肢の比較の判断をやり直せる状態にしておくことです。やることは次の4点です。①判断の前提条件の内、変わる要因を押さえておく補助制度、工事費の水準、売買市場の見え方、稼働状況(空室・賃料)など、前提を動かす要因に絞って把握します。②修繕・更新の記録(一覧+根拠資料)を整備「いつ・どこを・何で・いくらで直したか」を一覧にし、点検報告書・工事報告書・図面・保証書も紐づけておきます。これらが整備されていると、調査・見積・売却査定の立上げの際、“調べ直し”の手間が軽減できます。③判断材料を整理し、揃える作業を継続して進めておくたとえば、追加調査の段取り、見積条件の整理、設備更新の優先順位付け、売却の障害になりやすい論点の洗い出し。これらの作業は、結論を出す作業ではなく、あくまでも「判断材料を整理する作業」です。④意思決定の手続きを決めておく(特に個人・共有)誰が最終的に決めるのか、どこまで委任するのか、いくら以上は誰の同意が必要か。これらの点が曖昧だと、相続・共有者の異動の局面にあたって判断を円滑に下すことが難しくなります。 第7章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営で有効な「意思決定の型」 おわりに 旧耐震の賃貸オフィスビルと向き合う「今」から始める一歩旧耐震の賃貸オフィスビルのオーナーは、多かれ少なかれ同じ感覚を持っています。「家賃は入っている。でも、このままで本当にいいのか」この“引っかかり”は、弱さではありません。旧耐震という前提を踏まえたとき、経営者としての自然な感覚です。耐震補強も、建替えも、売却も、そうそう簡単に決められる話ではありません。費用、工期、テナント調整、資金の手当て、法的な論点など、どの選択肢にも負担と不確実性があります。ただ一つ確かなのは、何も決めないまま時間が過ぎるほど、現実に取り得る選択肢が減っていくということです。設備の更新時期、空室、資金繰り、金利、相続や共有者の事情など、外側の事情・要因が先に動き、オーナーが選びたかった道を狭めていきます。ここで必要なのは、いきなり大きな決断を下そうとすることではありません。結論を出せる状態に近付けることです。その最初の一歩は、小さくても構いません。現状を見える形にする(建物・設備・賃貸条件・市場・資金の整理)判断に必要な材料を、比較できる形で揃える(概算、工期の見通し、テナント調整の難易度、資金の当たり、法的な致命傷の有無など)判断材料が揃った時点で一度判断し、必要なら前提を更新して次に進む(揃える→判断する→更新する、を繰り返せる形にする) オーナーが主役であることは変わりません ただし、主役が一人で舞台を支える必要もありません。判断材料を整える役、選択肢を比較可能にする役、実行の段取りを作る役を揃えていくと、経営者としてのあなたの決断は「いちかばちかの賭け」ではなく「納得できる経営」になります。旧耐震の賃貸オフィスビルの将来に、完璧な正解はありません。工事費も賃料も金利も、テナントの動きも、判断に影響する前提が途中で変動するからです。それでも、判断を先送りにしない方法はあります。何を確認すれば比較できるのか、いつ一度結論を出すのか、前提が変わったらどこを見直すのか――この3点を決めて、材料を揃え、判断して、必要なら更新する。その方法が手元にあれば、どの選択肢を選んだとしても、判断した理由と前提を記録しながら、常に検証可能なビル経営として、次の一歩に進めます。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 飯野 仁 東京大学経済学部を卒業 日本興業銀行(現みずほ銀行)で市場・リスク・資産運用業務に携わり、外資系運用会社2社を経て、プライム上場企業で執行役員。 年金総合研究センター研究員も歴任。証券アナリスト協会検定会員。 2026年2月19日執筆2026年02月19日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの飯野です。この記事は「旧耐震ビルの賃貸経営をあきらめない──中小規模オフィスオーナーのためのリスク管理と活路」のタイトルで、2026年2月19に改訂しました。少しでも、皆様のお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次はじめに第1章:旧耐震ビルとは何か第2章:なぜ今「対策」を検討すべきなのか第3章:耐震補強という選択肢の実情第4章:賃貸オフィスビルの建替え/売却という選択肢(出口設計を整理する)第5章:PM/BMを、出口判断の判断材料を揃えるために活用します第6章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営の核心は「リスク管理」第7章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営で有効な「意思決定の型」おわりに はじめに 突然ではありますが、あなたの保有している賃貸オフィスビルは「旧耐震基準」で建てられたものではないでしょうか。1981年以前の耐震基準(いわゆる「旧耐震」)で設計・施工された建物は、日本各地にまだ多く存在しています。「旧耐震ビルのリスクはなんとなく知っている。でも、使えているうちはこのままでいいのではないか?」こう考えるビルオーナーは、実は少なくないのです。すでに建物の減価償却が終わっていて、毎月の賃料収入がほぼ「実入り」となっている状況であれば、わざわざ大きな投資をしてまで建替えや耐震補強を行わなくても、今のところは利益が出ているため、決断を先延ばしにするのも自然な流れなのかもしれません。しかし、耐震基準が古いということは、地震大国である日本において見過ごせない問題と言えましょう。大地震が発生したとき、倒壊や大規模な損傷が生じるリスクが高く、万一の際にはテナントにも大きな被害が及びかねません。近年では、テナント企業が賃貸オフィスビルを選ぶ際、BCP(Business Continuity Plan)の観点から建物の耐震性能を重視する傾向も強まっています。結果的に、旧耐震の賃貸オフィスビルはテナント募集の際の選択肢から外されやすくなっているのです。さらに、あなたのビルの周辺には新耐震基準の下、制震・免震構造を備えた新しいビルが増えています。賃料や立地条件が同程度であれば、「安全かつ設備が備わったビル」を選ぶテナントが大半でしょう。古いビルであるがゆえに空室リスクが高まるうえ、大地震のニュースが流れた直後などは、一時的にでも解約を検討する動きが出るかもしれません。とはいえ、旧耐震ビルに「全面的な耐震補強」を実施するのは、コスト面でも建物形状の面でも簡単ではありません。オフィスフロアの基準面積が100坪以下など比較的コンパクトな建物ほど、耐震壁やブレースの増設が執務スペースを大きく圧迫してしまい、窓を塞いでしまうようなケースも出てきます。テナントからすれば、使い勝手が悪く見栄えも損なわれるため、魅力が下がる懸念があるでしょう。こうした状況下で、多くのビルオーナーが「建替えしかないのか、それとも改修でしのぐべきか」と頭を悩ませています。実際、大規模な改修や建替えには多額の資金調達が必要ですし、仮にそこまで踏み切ったとしても、ビル経営的にペイするかどうかは不透明です。そのため、結局は“現状維持”を選択してしまうケースも少なくありません。しかし、建物の老朽化は待ってはくれません。耐震性の不安だけでなく、設備・配管・内装など、多方面の劣化が進むことで、想定外の修繕費用が急に発生したり、突然のトラブルでテナントからクレームが増えたりするなど、オーナーとしての負担は後々一段と大きくなる恐れがあります。そこで、本コラムでは、そうした問題を抱える旧耐震の中小型賃貸オフィスビルのオーナーを対象に、以下の点を中心に解説していきます。旧耐震ビルが抱えるリスクと、賃貸オフィス市場での評価が下がる背景実際に耐震補強を行う場合に生じる課題と、メリット・デメリットの整理大規模改修・建替え・売却などの意思決定を迫られたときの考え方プロパティマネジメント(PM)やビルメンテナンス(BM)導入の具体的意義とメリット事例紹介を通じた、収益改善や資産価値向上につなげるためのヒントこれから、このコラムでご紹介しようとしているPM/BMは、「オーナーが管理業務の多くを専門家に委託し、不動産経営を最適化するための仕組み」です。単に清掃や警備を外注するビル管理業務(BM)だけでなく、テナント誘致や契約管理、修繕計画立案などを総合的に担うプロパティマネジメント(PM)を活用することで、オーナー自身が把握しきれていない建物の価値を引き出したり、将来のリスクに備えることが可能になります。特に小規模ビルでは、オーナーが自分ひとりで全てを運営管理しているケースが多いため、専門知識や時間的リソースがどうしても不足しがちです。PM/BM導入により、そうした弱点を補い、最終的に建替えや売却を検討する際にも、視野を広げた判断ができるようになります。 本コラムは、建替えや売却を当然として推奨するわけではありません。むしろ、「旧耐震ビルに耐震補強を施す」という一見まっとうに思える選択肢が、本当に得策かどうかを改めて考えてみる必要がある、という問題提起をしたいのです。そして、その検討過程においてこそ、PM/BMの活用が大いに役立つはずであると考えています。もし、このコラムを読んでいるあなたが「うちは旧耐震だけど、まあ大丈夫だろう」と漠然と考えているのであれば、ぜひ最後までお付き合いください。建物の将来について早めに情報を集め、必要に応じた対策をとることで、結果的に余計なコストやリスクを大幅に削減できる可能性があります。なにより、“決断しないまま時が経って、いよいよどうしようもなくなる”という事態だけは避けたいところです。費用面のハードルや工事時期の問題など、悩みは尽きないかもしれませんが、本コラムの内容が少しでもヒントになれば幸いです。それでは、次章からは本題に入りましょう。まずは「旧耐震ビルとは何か」という基本的な定義やリスクを改めて整理し、現状を正確に把握することから始めていきたいと思います。 第1章:旧耐震ビルとは何か 旧耐震ビルとは、1981年以前の耐震基準(いわゆる「旧耐震基準」)で設計・施工された建物のことを指します。日本においては、1950年に制定された建築基準法の改正に伴い、幾度か耐震設計に関する規定が強化されてきました。その転換点となったのが、1981年6月1日に施行された新耐震設計法規です。この新基準以降に建てられた建物を「新耐震」、それより前の基準をもとに建築された建物を「旧耐震」と呼び分けています。 1-1.旧耐震基準と新耐震基準の違い そもそも、なぜ1981年という年が大きな区切りなのでしょうか。それは、1978年に発生した宮城県沖地震での被害を踏まえ、建物が「倒壊しないため」に必要な耐震強度を再検証し、耐震設計の方法が大幅に見直されたためです。新耐震基準では、主に以下のようなポイントが強化されました。設計用地震力の見直し地震発生時に建物に作用すると想定される水平力(地震力)の想定値を見直し、より大きな地震を想定して構造計算を行うようにした。靭性設計の導入建物の構造部材や接合部が、ある程度の変形に耐えうるように設計する考え方。これにより、大地震が起きてもすぐに崩壊せず、人命被害を防ぐことを重視。施工精度・品質管理の強化単に設計段階だけでなく、施工段階のコンクリート強度や鉄筋のかぶり厚さ(鉄筋を覆うコンクリートの厚み)などの品質もより厳しく求めるようにした。一方、旧耐震基準は「中規模地震で倒壊しない程度」というおおまかな基準で、現行の新耐震基準ほどの詳細な検討や品質管理が行われていない場合が多いのです。その結果、旧耐震基準で建てられたビルは「大きな地震が発生すると、倒壊または重大な損傷のリスクが高い」と見なされています。 1-2.旧耐震ビルが抱えるリスク 旧耐震ビルは、単に“古い”というだけでなく、構造的・物理的にリスクをはらんでいます。代表的なものを挙げると、次のとおりです。(1)地震による倒壊・大損傷のリスク耐震強度が不足しているため、大地震の発生時に建物が部分的に崩落したり、大きく傾くおそれが高まります。建物が万一倒壊すると、テナントの事業継続はもちろん、人命に関わる非常事態になり得ます。(2)テナント募集時のネガティブ要因テナント企業の安全意識やBCPが浸透している昨今、旧耐震というだけで敬遠される場面が増えています。特に、社会的信用を重視するテナント(金融機関やIT企業など)は耐震性能を重視する傾向が強いです。結果的に空室が埋まらない、賃料を下げざるを得ない、という悪循環が起きやすいのです。(3)資産価値の下落建物の評価額は、耐震性や築年数、建物グレードなど多角的に評価されます。旧耐震ビルの場合、いくら立地が良くても、耐震リスクや老朽化の懸念で資産価値が低く見積もられることが多々あります。賃貸オフィス市場のトレンドも加味すれば、将来的に売却を検討する際、想定よりもはるかに安い価格が提示される可能性があります。(4)今後の法改正や行政指導リスク地震防災対策や都市計画の観点から、行政が段階的に耐震化の基準を引き上げる方向にあることは周知の事実です。既に、一部の公共施設や大規模建築物には、耐震診断や補強実施の義務化が進んでいます。今後、基準がさらに厳しくなる可能性はゼロではなく、行政からの指導や是正命令が下るリスクも想定されます。 1-3.中小型賃貸オフィスビル特有の状況 賃貸オフィスビルと一言でいっても、大規模なタワービルから数十坪規模の小型ビルまでさまざまです。ここで注目したいのが、オフィスフロアの基準面積100坪以下の中小規模ビルに固有の“制約”です。旧耐震の議論は耐震性能だけに目が行きがちですが、中小規模のビル特有の意思決定を難しくする要因があるので、以下、説明します。(1)建物の構造上、改修工事の物理的な影響が大きく収支が悪化するリスク大規模ビルに比べてスペースの余裕が少なく、耐震補強を施そうとすると執務スペースを侵食しやすいのが現実です。窓を塞ぐ、ブレースが張り出す、動線が崩れる――こうした変化を以て、普通、耐震補強後、賃貸オフィスが貸しづらくなり、収支が悪化するリスクも想定されます。耐震補強の検討にあたっては「構造の正しさ」だけでなく、以下のポイントについても確認・評価します。耐震補強後に貸室がどれだけ減るか(㎡/坪)採光・レイアウト自由度がどれだけ落ちるか工事中の退去誘発リスク(騒音・振動・工期)(2)テナントも小規模・零細だと共倒れになるリスク中小規模の賃貸オフィスには、地元の小規模・零細な企業/個人事務所が入居しがちです。対応余力が乏しく、移転が先延ばしになりがちだったりします。オーナー側から見ると「なんとなく使い続けてもらえる」点は安心とも思えるのですが、問題が先送りされて、共倒れになるリスクには留意しておく必要があります。(3)ビル経営が属人化して、「意思決定」が正しく行われないリスク中小規模の賃貸ビルほど、ビルオーナーが一人で運営判断を背負っているケースも多く見受けられます。結果として、修繕判断が行き当たりバッタリになり、ビル経営の観点に鑑みると、問題が放置され易い状況が起こりがちです。ビルオーナーが自ら、状況を「見える化」して、整理することができないようであれば、PM/BMを使って、運営をオーナー個人から切り離すことが現実解なのかもしれません。 1-4.旧耐震ビル数の現状データ 東京23区における旧耐震オフィスビルの割合東京23区内で賃貸オフィスとして利用されている建物のうち、1981年以前の旧耐震基準で建てられたビルは、おおむね全体の2割前後を占めると推計されています。中小規模ビルほど旧耐震率が高いオフィスビル全体の傾向を、規模別に見てみます。大規模オフィスビル(延床5,000坪以上)に比べて、延床5,000坪未満の中小規模ビルは旧耐震が多く残っている傾向にあります。ザイマックス総研の「東京オフィスピラミッド2025」によると、旧耐震基準のビルの割合が大規模ビルで12%だったのに対し、中小規模ビルでは22%に上っています。都心部で大規模再開発が進んだ結果、比較的大きなビルの建替えや耐震補強は先行して行われてきた一方、中小規模のオフィスビルについては、更新が遅れがちな状況が数字でも見てとれます。耐震化は進んでいるが、「未達が残る領域」もはっきりある東京都が公表している「特定緊急輸送道路沿道建築物」(条例により旧耐震の耐震診断が義務付けられる領域)では、旧耐震建築物のうち改修済等で耐震性を満たす割合は57.3%(令和6年12月末)にとどまり、4割強は未達という状況です。また国交省資料では、耐震診断義務付け対象建築物(全国)について、2024年3月末時点の耐震化率は約72%と整理され、耐震性不十分な建築物が残っていることも示されています。結論:旧耐震は“もう少しで消える在庫”ではなく、当面残る前提で経営判断が必要東京23区でも旧耐震の在庫は、延床300坪以上の範囲に限っても2,000棟規模で残っています。つまり「古いから仕方ない」で流せる話ではなく、募集・改修・管理体制・出口(建替え/売却)を、現実の数字の上で組み直す必要があります。 【参考文献】ザイマックス不動産総合研究所「東京23区オフィスピラミッド2025」 東京都耐震ポータルサイト「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化状況(令和6年12月末時点)」 第2章:なぜ今「対策」を検討すべきなのか 旧耐震の賃貸オフィスビルのオーナーが耐震補強や建替え、売却などについて「いつかは考えなければいけない」と思いつつも、実際に大きなアクションに踏み切れないケースは少なくありません。減価償却が終わっていれば、毎月の賃料収入は、そのまま実入りに見えますし、現状維持の判断に傾くのも自然です。ただし、旧耐震の問題は「危ないかどうか」だけではありません。先送りの本当のコストは、支出額そのものより“選択肢が減ること”です。(運営改善・補強・建替え・売却のどの選択肢も、タイミングを逸してしまうと、後になるほど条件が悪くなる) 2-1.建物寿命と老朽化、そして地震リスク RC造やS造は法定耐用年数を超えても使えますが、築年が進むほど、構造体より先に設備・防水・配管などが劣化しやすくなります。劣化は静かに進むため、「今まで大丈夫だったからこれからも大丈夫」と判断しがちです。しかし一度、大きな故障や漏水が起きると、復旧コストの問題にとどまりません。テナントの業務停止や営業機会の損失につながり、最悪の場合は退去に至り、賃料そのものが消えることがあります。さらに旧耐震の地震リスクは、「地震で壊れたら直す」だけの話ではありません。旧耐震下での対応を「耐震補強工事をする/しない」「地震後の復旧費用をどうする」に限定すると、賃貸経営の判断としてズレます。地震リスクは、建物の損傷・復旧コストだけでなく、テナントの事業継続、従業員の安全、対外説明、そして更新・移転判断にまで波及するからです。 2-2.地震リスクは「起きた後」ではなく、「起きる前」に効いてくる 日本で地震リスクがゼロになることはありません。旧耐震は新耐震より倒壊・大破リスクが高いと見られやすく、仮に倒壊に至らなくても、損傷が出れば継続利用が難しくなり、賃料収入が止まる一方で復旧費用が発生します。ただ、いま考えるべき地震リスクは「発災後の被害」だけではありません。発災後のリスクを前提に、テナント側ではBCPやリスク管理の観点から、入居・更新・移転の判断基準が組み立てられています。旧耐震であることは、次のような形で“いま”効いてきます。入居候補から外される(=空室リスクに直結する)契約更新で慎重になる(=移転検討が始まる) 2-3.行政・金融機関の見方が変わると、動けなくなる 耐震改修促進法や自治体の施策により、建物の用途・規模・立地条件によっては、耐震診断・報告・改修の流れが強まっています。今は対象外でも、対象領域の拡大、運用の厳格化の進捗次第では、オーナーの負担は後から重くなりかねません。また、金融機関は「旧耐震かどうか」だけでなく、修繕計画があるか、資料が揃えてあるか、運営体制が規定化されているかなどを見ます。旧耐震で資料に不備があると、担保評価が下がるだけでなく、借換えや追加投資の局面で条件が悪くなりやすい。結果として「動きたいのに動けない」状態を招きかねません。 2-4.この章の結論:今やるべきは「工事の決断」ではなく「判断材料の整備」 ここまで見てきた通り、旧耐震のリスクは「建物が壊れるかどうか」だけではありません。老朽化や地震は、復旧費用に加えて、テナントの継続利用・更新判断・移転判断に波及し、賃料収入そのものを不安定にします。さらに、行政対応や金融機関の見方が変わると、資金調達や改修の自由度も下がり、動きたいときに動けない状況が起きます。だから旧耐震の対策は、いきなり耐震補強や建替えを決める話ではありません。先送りの本当のコストは、修繕費そのものより“選択肢が減っていくこと”です。今やるべきは、次の情報を整理して、耐震補強・建替え・売却・運営改善を同じ土俵で比較できる状態を作ることです。建物と設備の状態修繕履歴と今後の支出見通しテナント状況と契約条件次章以降で、具体的な選択肢を順に見ていきます。 第3章:耐震補強という選択肢の実情 旧耐震の賃貸オフィスビルにおいて「耐震補強を実施する」というのは、安全性を高めるための最も正攻法のように見えます。耐震性能を上げること自体は合理的です。ただし、賃貸オフィスビルの経営として見たとき、耐震補強は、“やれば勝ち”の施策ではありません。中小規模ビルほど、補強のやり方次第では、かえって、賃貸オフィスビルとしての価値が下落して、既存テナントが退去して空室となり、さらに、空室を埋める際の募集賃料が下落して、賃料収入が低減することになりかねません。この章では、耐震補強が向く/向かないの判断基準を整理します。耐震補強で失敗するパターンはだいたい同じです。オフィスの執務スペースの面積の減少/採光性が損なわれ/工事でテナントの退去が連鎖する/回収の筋が立たない。まずは、ここを外さないための視点を押さえます。 3-1.中小規模ビルでは耐震補強工事の物理的な影響が大きい 中小規模ビルの耐震補強にあたっては、耐震性能だけでなく、面積・採光・レイアウト自由度等の物理的影響についても細心の注意を以て確認する必要があります。図面でチェックすべきポイント執務スペースの面積がどれだけ減少するのか:ブレース・耐震壁・袖壁の張り出しで、実質有効面積が何㎡(何坪)減少するのか確認採光がどこまで損なわれるのか:窓前に耐震壁・ブレースが設置される場合の影響度合い執務スペース内の動線への影響:入口〜執務〜水回りの通行に支障が生じないか執務スペースのレイアウト自由度が確保できるか:会議室・執務・倉庫などの区画が成立するかこれらの点を確認しないまま「耐震補強の可否/性能」だけで議論すると、耐震補強後に“貸し難い賃貸オフィスビル”が出来上がりかねません。特に、中小規模の賃貸オフィスビルでは致命的な状況に陥りかねません。 3-2.工事コストと資金調達の負担 耐震補強の検討にあたって、工事費だけで是非を決めようとする、判断を誤りやすくなります。耐震診断を起点に、設計・工事・テナント対応まで含めた費用総額と、その後の収益への影響もあわせて整理する必要があります。(1)耐震診断・補強設計費も含めた総コスト耐震補強工事の前提として耐震診断・補強設計が必要です。ここだけでも数百万円規模になることがあります。当然のことながら、補強工事費はさらに別にかかって、建物条件次第で振れ幅が大きく、近年のコスト増に鑑みると、相応の負担を覚悟する必要があります。(2)減価償却が終わっている物件ほど、ビルオーナーにとって、追加投資の心理ハードルが上がる旧耐震の賃貸オフィスビルは築年数が経過しているので、会計上の減価償却が既に終了しているケースが少なくありません。賃料収入を“そのまま収益”と捉えてしまうと、ビル・オーナーの心理上、現状維持バイアスがかかり易く、借入をして耐震補強工事に踏み出し難くなります。耐震補強を検討する出発点は、「いまの収益が将来も同じ形で続くとは限らない」という前提を置くことです。現状の収益だけを基準に判断すると、必要な検討や準備が遅れ、結果として選択肢を狭めてしまう可能性があります。(3)公的支援制度は“補助”であって“全額負担の肩代わり”ではない一部の自治体や国土交通省が行っている耐震化の助成制度は、適用要件や上限金額が限定的で、補強費用全体をカバーできるほどの補助は期待しにくい面があります。使えるものは使う、ただし当てにしすぎない。これが現実的な対応です。 3-3.耐震補強工事のテナントへの影響 耐震補強工事は、建物の躯体に手を入れるため、工事の影響が大きくなりやすい工種です。ここでの対応を誤ると、工事費そのもの以上に、テナント退去による空室、賃料収入の低下といった形でビル経営に跳ね返ってくるリスクを想定しておく必要があります。(1)騒音・振動によるテナントの業務への影響耐震補強工事は騒音や振動が発生しやすく、工事期間が数か月に及ぶ場合もあります。入居中テナントの業務への影響が避けられません。(2)テナント退去が連鎖するリスク耐震補強の規模によっては、工事期間中にテナントの退去を要するケースも想定されます。また、工事対象区画が空室になることに加えて、同じビル内の他テナントが工事による業務影響を嫌い、更新を見送る・移転を検討する、といった動きが連鎖する可能性もあります。この点は、耐震補強の是非を左右する重要な論点です。(3)周辺・他テナントとの調整ビル内のテナントが退去しなくても、搬出入・騒音等で周辺に影響が出るので、工事内容やスケジュールについて事前調整が必要になります。調整が長引けば工期が延び、結果としてコスト増につながるおそれもあります。「工事で失う金額」を整理する(工事費以外も含めて捉える)耐震補強の負担は、工事費だけではありません。検討の段階で、少なくとも次の要素も踏まえて整理しておくと、より的確な判断の前提となります。総コスト(経営目線)=工事費(含む、耐震診断・補強設計費)+近隣対策費用△耐震補強工事期間の賃料減△自治体等の補助 3-4.耐震補強のメリット・デメリット(整理した上で、判断に落とす) ここまでの話を踏まえた上で、耐震補強のメリット・デメリットを“経営判断”の観点から整理します。メリット(1)安全性の向上耐震性能が上がれば、地震時の倒壊・大破リスクの低減が期待できます。その結果、テナントの安心材料にもなります。(2)売却・融資での説明力が増える可能性耐震性が高い物件は、売却時や金融機関の担保評価が相対的に高まることが期待できます。今後、災害リスクへの意識が高まると、「安全な建物」であることが資産価値向上に寄与するでしょう。(3)将来的な行政対応の負担を軽くする可能性耐震診断・改修が義務化される流れが強まっていることを前提にすると、早めの耐震補強を実施しておくことで、将来的な是正命令などに対応する負担を減らせます。デメリット(1)初期投資額が嵩む先述のとおり、耐震診断や設計費用、工事費などを合わせると数千万円規模でかかることも少なくありません。十分な資金が確保できない場合、耐震補強工事の実施自体が困難となる場合もあります。(2)耐震補強工事中の退去による空室、収益低減リスク前項の耐震補強工事に関連する費用発生に加えて、耐震補強工事の影響で発生する空室による収益の低減は重要なファクターです。(3)貸室価値が落ちると、投下の回収が厳しくなる耐震補強工事の物理的影響(賃貸面積の減少/採光に支障/レイアウトに支障)により、賃貸オフィスとしても魅力が低減してしまい、耐震補強後、将来に向けて、賃料の引上げが難しくなる可能性も想定されます。 【耐震補強工事の是非に関する判断チェックリスト(耐震補強が向く/向かない)】耐震補強工事の是非に関する判断基準を明示します。A:補強が向く耐震補強しても貸室面積の減少が軽微と判断。採光・動線・レイアウト自由度を確保できる。耐震補強工事中でも一定程度、テナントの維持ができる。耐震補強後、賃貸オフィスとしても魅力を保持できる。B:補強が向かないブレース・耐震壁で貸室面積が顕著に減少/窓の採光が妨げられる退去工事中のテナントの退去の連鎖が想定される耐震補強後、テナント募集して稼働、賃料水準の維持・改善が期待できない近い将来、賃貸オフィスビルの建替え・売却を想定していて、耐震補強に資金と時間をかける意義が薄いこのチェックリストは、専門家の結論を待つ前に、ビルオーナーが判断の軸を持つためのものです。 3-5.耐震補強とは別に「貸しやすさ」を回復させる改修という選択肢 耐震補強は「安全性」の論点ですが、賃貸オフィスビルの経営判断は、それだけで決まりません。仮に耐震補強に費用を投じたとしても、耐震補強の内容や進め方によって貸室価値が低減したり、耐震補強工事を契機にテナント退去が連鎖したりすれば、経営上はマイナスに働く可能性があります。そこで現実的な選択肢として出てくるのが、耐震補強とは切り分けて、“貸しやすさを回復させる改修”を検討するという考え方です。ここで言う改修は、テナントの入居判断に直結する機能面の改善を指します。たとえば、次のような項目です。空調設備の更新(故障リスクの低減と快適性の改善)給排水・防水の更新(漏水リスクの抑制)電気容量・配線まわりを含む電気設備の整理・更新共用部の機能不全の解消(使いにくさ・不具合の是正)耐震補強が結果として貸室価値を下げる見込みが強い場合は、補強仕様を見直すか、あるいは耐震補強とは別に“貸しやすさ回復”の改修を優先したほうが合理的なケースもあります。一方で、貸しやすさを回復させる改修を行っても、空室が埋まらない/募集賃料の低減/大きな修繕や更新が連続して必要になるといった状況が見えている場合は、「改修で運営を続ける」だけでは解決にならない可能性があります。ここまで来ると論点は、改修の是非ではなく、保有を続けるのか、建替えるのか、売却するのかという“資産の出口”の判断に移ります。次章では、耐震補強や運営改善と並べて比較できるように、建替え/売却という選択肢を、メリット・デメリットと判断ポイントに分解して整理します。 第4章:賃貸オフィスビルの建替え/売却という選択肢(出口設計を整理する) 旧耐震の賃貸オフィスビルは、耐震性の不足だけでなく、設備の老朽化や賃貸市場での競争力低下といった課題を抱えています。対策の検討を後回しにするほど、建物の劣化は進み、ビルの安全性、テナントの確保がますます難しくなっていくでしょう。前章で検討してきた、耐震補強や“貸しやすさ回復”の改修は、うまく効けば、賃貸オフィスビルの経営を立て直す手段になりえます。ただし、耐震補強工事の影響が大きすぎる/テナント募集が難しくなる/賃料水準の維持が困難/大きな修繕が連続する見通しといった状況が見えている場合、賃貸オフィスビルの経営上の論点は「どの工事・改修をするのか」ではなく、「建替え」あるいは「売却」の方向性をより真剣に検討するフェーズに入っている可能性が高いのです。ここでは、まず、耐震補強・建替え・売却を、同じ土俵で比較できるように整理します。 4-1.まず比較表で“意思決定の土台”を作る 比較項目耐震補強建替え売却初期費用中〜高(診断・設計・工事)高(解体+建築+設計+諸費用)低〜中(仲介・測量等)賃料収入の停止期間工事影響あり(減収〜空室の可能性)工事期間中(解体〜竣工まで)売却完了で賃料収入はゼロテナント調整の難易度中〜高(工事影響・退去連鎖)高(明渡し・補償・移転調整)中(契約条件と引継ぎ次第)将来の自由度補強内容次第ではあるが、限定されがち高(商品を作り直せる)高(資産入替・撤退が可能)失敗パターン貸室価値低下→空室・賃料下落資金計画破綻/期間長期化/出口が読めない情報不足で買い手が限定されると売価が低下 4-2.建替え(メリットと注意点) 建替えは、旧耐震の賃貸オフィスビルに残る課題を「部分的に直す」のではなく、建物そのものを作り直す選択肢です。耐震性だけでなく、設備・電気容量・レイアウト自由度・共用部の機能など、賃貸オフィスとしての条件をまとめて更新できます。一方で、建替え工事は大規模なので、資金調達の金額が大きくなり、入居中テナントとの明渡し調整も不可避です。ビルの解体、テナントとの明渡し調整を、一旦、始めると、関係者も動き出して、コストも発生するため、途中で方針転換するのが難しくなります。したがって、建替えで解決したい課題と、それに伴って発生する負担を、最初に確認し、明示した上で判断する必要があります。メリット(建替えが効く場面)(1)“商品を作り直せる”という強みがある建て替えることで、現行の耐震基準を満たすのはもちろん、老朽化が進んだ設備(空調・給排水・防水・電気)も一括で更新できます。建替えは「個別修繕の継ぎ足し」では解決しにくい問題をまとめて整理・解決できる可能性があります。(2)テナント募集戦略と賃料設計を“前提から”組み直せる建替えの効果は、竣工後に「どういうテナントを想定するか」を先に定め、その想定に合わせてオフィス賃貸の前提条件を整えられる点にあります。築年数が経過している旧耐震の中小規模の賃貸オフィスビルで、テナントに敬遠されやすい条件は、耐震性能だけではありません。電気容量が足りない、空調が不安定、給排水や防水の不具合の発生が見通しにくく、電気設備の老朽化で停電のリスクが高い――こうした設備由来の事故・停止リスクが、入居判断と更新判断に影響します。建替えでは、設備更新によって事故・停止リスクを下げ、万一の不具合が起きた場合でも影響範囲を限定しやすい構成にできます。あわせて、防災設備や非常用電源の有無、停止時の復旧手順などを含め、従業員の安全と事業継続に関わる前提条件を整理して、募集条件として提示できます。結果として、テナントの懸念点が減り、リーシングの組み立てがしやすくなり、賃料水準の維持・見直しの余地が生まれます。注意点必要資金が大きく、資金計画・資金調達の前提を先に固める必要がある建替えには、建築費だけでなくて、解体費、設計監理費、各種申請費、仮移転対応・近隣補償などが積み上がり、必要資金は想定より膨らみやすいです。さらに、旧耐震の賃貸オフィスビルの場合は、担保評価が伸びにくいケースもあり、資金調達上の制約になりやすい点も考慮しておく必要があります。建替えは、具体的な「工事の話」に入る前に、金融機関と資金調達の話をつけておく必要があります。一般的に、金融機関は、いくら貸せるか、いつ実行するか、返済条件をどうするのかを、次の材料で判断します。総事業費の内訳(解体・設計・建築・諸経費)と資金の出し方(自己資金/借入)資金が必要になる時期(解体〜竣工までの支払予定)と、賃料収入が入らない期間の資金繰り竣工後の賃料収入見込み(想定賃料・稼働率)と運営費、返済計画テナント明渡しの進め方(スケジュール、補償の考え方)と想定リスクこれらが整理されていないと、融資額や実行時期が決まらず、着工までの手続きが長引きかねません。結果として、賃料収入がない期間が延びて、追加費用が発生して、当初の資金計画の前提が崩れ、建て替えプロジェクトの進捗にとって大きなリスク要因となりかねません。また、着工後も、追加工事、行政協議、調整の遅れなどにより、工期と費用が想定の範囲内に納まらない可能性もありえます。したがって、資金計画は「見積りどおりに進む前提」で組むのではなく、予備費と予備期間をあらかじめ織り込んだ設計にしておく必要があります。 4-3.売却(メリットと注意点) 耐震補強・建替えは、資金調達ならびに工事実施を前提にした「続けるための選択肢」です。これに対して、売却は、賃貸オフィスビルを保有し続ける前提をいったんやめて、資産を現金化する選択肢です。耐震補強や設備更新等、「続けるための投資」を抱え込まず、いまの条件で手仕舞いして次の選択に移るための判断になります。旧耐震の築古の中小規模の賃貸オフィスビルにおいては、この選択肢を検討対象に入れておくのは、充分、意味があるものと考えられます。メリット将来コストと運営リスクから解放されます耐震補強、大規模修繕、設備更新、空室の長期化など、築年が進むほど発生しやすい支出と対応が続きます。売却すれば、こうした不確実性を「自分が抱える運営課題」から外せます。金額面だけでなく、判断の回数や調整の手間が減る点も、現実的なメリットです。手元資金を確保し、次の選択肢を可能とします売却によってまとまった手元資金を確保できれば、借入返済、別物件への投資、資産配分の見直し、事業・生活設計への充当など、次の選択肢を具体化できます。賃料収入の維持と「別の形での期待収益」とのバランス判断がポイントです。ハードル資産査定額は「買い手が見込む追加コスト」に左右されます旧耐震の賃貸オフィスビルは、買い手が現状のまま長期運用する前提になりにくく、大規模改修、建て替え等の対応コストを見込んだうえで査定額が算定されます。具体的には、解体費、耐震補強や改修の費用、用途変更・建替えに向けた手続き負担などがポイントになります。そのため、売主がそれらの工事を実施しなくても、これらの見込みコストは売却価格に織り込まれやすいです。さらに、買い手がどの前提で収支を置くかによって、同じ物件でも提示価格に幅が出ます。各種費用や税金負担を控除したネット金額を想定する売却代金だけで判断せず、仲介手数料、譲渡にかかる税金、ローン残債の精算、その他の付随費用まで引いた後の金額を以て想定しておく必要があります。例:手元資金概算 = 売却代金 − 仲介手数料 − 譲渡関連税 − 残債精算 − その他費用 4-4.結論:出口は、比較できる状態を作ってから決めます 建替えと売却は、どちらも大きい判断です。判断の質を左右するのは、同じ土俵で比較できているかです。この章の冒頭、4-1でも示しましたが、以下の判断材料を揃えることが重要です。建物・設備の状態、修繕履歴、テナントの賃貸契約条件、賃料・運営コストの収支を整理します。耐震補強/建替え/売却の選択肢について、初期費用・賃料収入がない(減収)期間・テナント調整を同じ軸で見ます。この比較ができるうちに、次の打ち手に移れる状態にしておきます。先送りで減るのは、修繕費の余裕よりも選択肢の余裕です。次章では、これらの判断材料を揃えて、更新していくために、PM/BMをどう使うかを扱います。 第5章:PM/BMを、出口判断の判断材料を揃えるために活用します 旧耐震の賃貸オフィスビルを巡る意思決定には、耐震補強・建替え・売却などの選択肢があります。どの選択肢にも、投資金額とリスクが伴いますので、ビルオーナーが迷うのは当然です。問題になるのは「迷うこと」そのものではありません。比較の前提となる判断材料が揃わないまま、検討が進まず、時間だけが過ぎていくことです。結論を出すには、まず、「比較の土台」を作る必要があります。耐震補強/建替え/売却を並べるのであれば、少なくとも次の情報が、同じ整理軸で揃っていることが前提になります。建物・設備の現況(不具合・劣化の状況、故障傾向、法定点検の実施状況など)テナントとの賃貸借契約の条件(解約条項、原状回復義務の範囲、工事制限、特約など)収支と将来支出(賃料、運営コスト、修繕・更新の見込み、賃料減収の想定期間など)工期とテナント調整(通知、移転の要否、休業補償の論点、工程上の制約など)ただ、この「比較の土台」をオーナー自身で作り切るのは、実務上ハードルが高いかもしれません。必要な情報は、竣工図・点検報告・修繕見積・工事履歴・契約書・収支資料など複数の資料にまたがります。さらに、集めるだけでなく、抜け漏れの確認、情報の粒度・確度の確認、同じ形式への整理といった作業が必要になります。ここで検討に入るのが、PM(プロパティ・マネジメント)とBM(ビル・メンテナンス)という役割の導入です。なお、PM/BMの役割は、ビル管理会社が担う場合もあれば、外部専門家と連携・分担する場合もあります。重要なのは、旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断に必要な材料が、比較できる形で整う体制になっているかどうかです。次節では、PMとBMの違いを整理します。 5-1.PM/BM:機能の違い PM(Property Management)とBM(Building Maintenance)は、どちらも「賃貸オフィスビル管理」に関わりますが、見ている対象が違います。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断に必要なのは、この違いを押さえたうえで、それぞれの役割を活かして活用することです。PMは、賃貸経営の運用を扱います。賃料や募集条件、契約条件、収支、テナント対応、修繕の優先順位づけ、外部業者や関係者の調整など、ビルを事業として回すための業務です。結論を出す場面では、集まってきた情報を整理し、耐震補強/建替え/売却を同じ条件で並べられるように整えます。BMは、建物設備の維持管理を扱います。設備の点検・保守、故障対応、法定点検の実施と管理、衛生・安全面の段取り、工事手配の実務など、建物と設備を止めずに動かすための業務です。結論を出す場面では、現況の把握や劣化の状況、故障傾向など、比較の前提になる「現場の根拠」を出します。この章で扱う旧耐震の賃貸オフィスビルの意思決定では、PM/BMの価値は次の形で整理できます。PM:比較できる形に整える側(判断に使える形式へ整理します)BM:比較の根拠を出す側(現場の状態を把握し、根拠を示します) 5-2.まず整理して揃えるのは「判断用資料」(比較の土台を形にします) PM/BMの役割を踏まえて、実務では「結局、何が揃えば比較できるのか」が曖昧なまま進んでしまうことがあります。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断においては、必要な情報の種類が多く、粒度もばらつきやすいためです。そこで、最初にやるべきことは、比較に必要な判断用資料を先に定義し、同じ形式で整理して揃えることです。出口判断に必要な判断用資料は、最低限、次の5点です。これが揃うと、耐震補強/建替え/売却を同じ土俵に載せられます。(1)建物・設備の現況一覧(根拠の入口)主要設備ごとの状態(劣化・不具合・故障傾向)法定点検・定期点検の実施状況と指摘事項直近の修繕・更新履歴(いつ、何を、どの範囲で)当面の注意点(止まると影響が大きい箇所、優先度の高い不具合)※これは基本的にBMの領域です。「現場の事実」をここで固めます。(2)将来支出の見立て(修繕・更新の候補整理)今後数年で現実に出てきそうな更新・修繕項目概算費用は“点”ではなく“幅”(レンジ)で置く不確定要素(追加調査が必要な箇所、見積条件の前提)※BMの見立てをベースに、PMが収支と接続します。(3)テナントとの賃貸借契約の条件とテナント調整の論点整理解約条項、工事制限、原状回復の扱い、特約休業補償や仮移転が論点になり得る条件の有無通知期間・工事可能時間帯など、工程に効く制約※ここが抜けると、工期や減収期間の比較が成立しません。PM側で整理するのが基本です。(4)3案比較表(耐震補強/建替え/売却)初期費用(概算レンジ)工期と減収期間の見込みテナント調整の難所(どこがボトルネックか)収益・売却の見通し(前提条件つきで整理)前提条件(何を仮定しているか)と、条件が崩れた場合の影響※ここが「比較の本体」です。PMが形式を作り、BMが根拠を供給します。(5)未確定事項リスト(次に何を確かめるか)追加調査が必要な項目追加見積が必要な項目判断に影響する前提のうち、まだ確定していないもの※“分からないこと”を残したまま比較表だけ整えると、結論の再検討が増えます。最後に必ず残します。この5点が揃うと、議論は「情報が足りない」状態から抜け出して、比較の質が上がります。PM/BMを使うかどうかに関わらず、この判断用資料セットを基準にしておくことで、旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断の実務を進捗させることができます。 5-3.PM/BMへの頼み方(判断用資料を基準に委託範囲を決めます) PM/BMを使う場合、最初に決めるべきなのは、「判断用資料」と「責任範囲」です。判断用資料を基準に委託範囲を定義すると、判断材料の整理、とりまとめが進めやすくなります。①判断用資料ごとに担当範囲を割り当てます5-2の判断用資料に沿って、中心となる担当を分けます。BMが中心になる範囲(1)現況一覧(2)将来支出の技術的な見立て(更新・修繕候補と根拠)PMが中心になる範囲(3)テナントとの賃貸借契約の条件とテナント調整の論点(4)3案比較表(5)未確定事項リストの整理と更新管理同一の会社がPM/BMを一体で担う場合でも、判断用資料ごとに「根拠を出す責任」と「比較表に整理する責任」を分けておくと、責任範囲が曖昧になりません。②比較の土台を揃える(検討フェーズ/対象範囲/数字の前提)耐震補強/建替え/売却を比べるときは、各案の数字がどのフェーズの、どの前提条件で、どこまでを対象に出ているかを揃えないと比較になりません。片方が机上の概算、もう片方が詳細調査ベース──この状態で表に並べても、結論がブレます。揃えるのは次の3点です。1)検討フェーズと、数字の根拠レベルを明記するいまが「方向性を絞る一次検討」なのか、「実行可否を判断する段階」なのかを、はっきりさせます。後者なら耐震診断を含む必要調査が前提です。一次検討なら、概算で進めてOKですが、“概算の前提条件”と“未確定の残し方”(どこから先は次段で確定させるか)も合わせてはっきりさせます。例:夜間工事の要否/搬入条件/工事可能時間/追加調査が必要な箇所の扱い…など、概算に直撃する条件は必ず明示します。2)耐震補強が「どこまで影響するのか」を踏まえて検討する耐震補強工事の影響範囲を「構造要素だけ」に限定せず、付随して影響し、検討・調整が必要になる範囲を明示した上で検討します。例:天井・間仕切り・内装・什器/設備更新や機器移設の要否/工事中の使用制限/テナント調整の範囲/賃料の減収期間の見立て。3)比較表の“必須項目”を統一して、判断に使える形にする比較表のそれぞれの選択肢について、費用・工期・賃料の減収(空室/賃料影響)・調整論点(テナント/行政/金融)・将来支出・前提条件・未確定事項を項目として網羅します。未確定事項が残るのはOK。ただしその場合は、次に何を調べれば確定させられるのか(追加調査・見積条件・判断形成の手順)まで付記します。③判断資料の提出の締め切りとスケジュール(比較表を“更新できる運用”にする)前提条件は途中で必ず変わります。だから「比較表の完成版を一気に作る」のではなくて、短いサイクルで提出→判断→更新します。ここで決めるのは提出物と締切と判断ポイント(ゲート)です。 標準的な進め方(目安)第1段階:1週間以内(5)未確定事項リスト一次版を提出└ 不足資料、追加調査の要否、調査の優先順位、次段で確定させる項目を明記ゲートA:一次検討として走れるか/追加調査が先かを決める第2段階:2週間以内(1)(2)(3)の一次版を提出(=比較の土台)└ 前提条件/概算の根拠レベル/影響範囲(波及工事・制約)を揃えるゲートB:3案を同じ土俵で並べる準備ができたかを確認第3段階:3〜4週間以内(4)3案比較表一次版を提出└ 費用・工期・減収・調整論点・将来支出・前提条件・未確定事項をセットでゲートC:方向性を絞る(残す案/捨てる案)第4段階:追加調査・見積反映(+4〜8週間が目安)(4)比較表改訂版を提出└ 第1段階の未確定事項を潰した反映版(必要なら複数回更新)ゲートD:実行可否の判断(やる/やらない/売る)重要な補足(ここが肝)一次検討だけで「絞る」なら、最短3〜4週間でいける(第3段階まで)「やる/やらない」を判断するなら、調査を入れるので+1〜2か月は見ておく(第4段階)つまり、ここでは「順番」の話じゃなくて、“比較表を継続的に更新していく前提で締切と判断点を置く”って話。 5-4.判断用資料が揃っても、ビルオーナーの「判断の閾値」が必要です。 5-2の判断用資料が揃うと、耐震補強/建替え/売却は同じ土俵で比較できるようになります。ただし、比較表があっても結論は自動的に出ません。最後に必要なのは、オーナー側の判断の閾値です。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断で、閾値になりやすいのは次の3つです。投資の上限額(いくらまで出すか)耐震補強・建替えの工事費・設備更新・改修費用等を含めて、投下できる金額上限を決めます。この上限値の設定がないと、どの案も「もう少し追加資金を投下すれば良くなる」で終わって、最終判断が下せません。資金繰りの限界(何ヶ月・最大いくらまで耐えるか)比較表に出てくる「賃料収入の減収額・減収期間・追加支出額」の結果を見て、①賃料収入の減収が続いてよい最大額・月数、②その期間での追加支出の許容を設定します。投資金額だけでなくて、キャッシュフローを見ておいて、どこまでの持ち出しに耐えられるかの許容額を設定しておく必要があります。テナント対応リスクの許容(どのレベルの個別協議まで受けるか)テナント調整の進捗は、重要なポイントです。個別協議(減額・補償・合意書・退去協議など)の方針によっては、協議期間、補償・減額の金額に幅が出ます。具体の交渉実務は、PM等の専門家のサポートを受けるべきですが、協議の方針については、最終的にビルオーナーが判断する必要があります。PM/BMができるのは、比較表の項目を埋めて、それぞれの選択肢がこの判断の閾値を超えるかどうかを見える化することです。逆に言えば、判断の閾値が決まっていないと、判断用資料が揃っても結論には辿り着けません。 第6章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営の核心は「リスク管理」 これまでで整理した通り、耐震補強/建替え/売却の選択肢は、判断材料が揃っても、最後にはビルオーナーの判断が必要です。ただし、その前に押さえるべき前提があります。旧耐震の賃貸オフィスビルでは、経営の基本姿勢が定まっていないと、判断の軸が定まらず、いくら判断材料を並べても結論が出ません。この章では、旧耐震の賃貸オフィスビル経営を「リスク管理」として成立させるための基本姿勢を整理します。 6-1.旧耐震の賃貸オフィスビルの意思決定は、運営と責任の整理から始まる 旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断は、耐震補強/建替え/売却のどれを選ぶにしても、「誰が何を整理して、誰が何を判断するのか」の分担で決まります。PM/BMは、比較し、判断を下すのに必要な情報を揃え、論点を整理し、選択肢を同じ土俵に載せる役割を担います。一方で、どのリスクをどこまで引き受けるのか、どこで線を引くのかについては、ビルオーナーの判断が必要です。意思決定を成立させるために、PM/BMに委ねる領域と、オーナーが引受ける判断を、明確にします。借主との調整が、一番、不確定要素があって、期間・金額の振れ幅への影響が大きいので、その点にフォーカスして、それぞれの分担を整理します。PM/BMが担う領域(材料を判断に使える形に整える)借主への影響を、条件別に整理する(在館工事/部分退去/段階退去など)借主の同意が必要になる論点を洗い出し、協議の論点・想定期間・条件・補償/精算額の幅を整理する費用が上振れしやすいポイントを押さえ、レンジと前提条件を示す(追加工事・追加調査・施工条件の制約など)以上を、耐震補強/建替え/売却の各案で、比較できる形にまとめるオーナーが担う判断(許容範囲を決める)判断上、重視するリスクを決める(安全性/収益/資金繰り/出口など)借主対応として、どこまでの調整を前提に置くかを決める(時間・条件変更・追加負担の許容)その前提の下、耐震補強/建替え/売却の選択肢を決める借主がいる以上、耐震補強/建替え工事や売却の判断は借主の営業に影響します。合意の取り方次第で工期・賃料の減収期間/幅・補償の見通しが変わり、収支も変わります。だから、材料の整理はPM/BMに任せながらも、最後に「どこまで背負う/覚悟するのか」を決める判断はオーナーが下します。 6-2.旧耐震の賃貸オフィスビルの経営における「リスク管理」 賃貸オフィスビルの経営におけるリスク管理とは、一般的に、不確実要素を棚卸しし、影響(安全・法務・収支・工期・出口)を評価し、対応方針を選び、前提更新に合わせて見直すことです。国際的にも、リスクを「特定・分析・評価・対応(treatment)し、監視とコミュニケーションを回す」フローの下、整理されます。旧耐震の賃貸オフィスビルの経営において、実務上、ボトルネックになりやすいリスクについて、以下、上げておきます。法令・制度対応リスク耐震改修促進法の枠組みでは、一定の建築物に耐震診断が義務付けられ、結果の報告・公表まで含めて制度化されています。さらに、建築基準法の「定期報告制度」は、使用開始後も適法状態を維持するための定期調査・検査・報告を所有者に求めています(建築物、防火設備、昇降機など)。東京だと防火対象物点検報告制度(消防法)も、一定の対象で点検・報告が義務になります。)安全・賠償責任リスク地震発生時、建物が損壊し損害が出たときに「建物の安全性」「維持管理の相当性」が争点になり、所有者側の責任が問題化し得る、という意味でのリスクです(いわゆる土地工作物責任の射程など)。契約・テナント対応リスク賃貸借は「使用・収益させる」契約なので、工事や不具合で使用が制限されると、賃料減額や修繕をめぐる運用が現実の論点になります。改正民法では賃貸借のルールが整理され、修繕や原状回復等の考え方も明文化されて、「借主の立場の尊重」の傾向が見てとれます。借主の使用が妨げられると、契約上の論点(賃料・補償・合意書・解除)に直結して、収支と工期に影響が及びます。工事・更新リスク耐震補強、建替え等、老朽化対応工事は、見積りの時点で“確定”しない部分が残りやすい(追加調査、追加工事、施工条件、夜間・搬入制約など)。この上振れは、金額だけじゃなく工程・テナント調整にも波及します。収益・資金繰りリスク「投資総額」も重要ですが、キャッシュフロー(キャッシュアウトのタイミング・追加・長期化)で資金繰りが行き詰るリスクは想定しておくべきです。売却時の価格リスク売却価格・条件を協議するにあたって、デューデリで指摘される論点(耐震、法定点検の履歴、是正、テナント条件等)によって、買い手の幅を狭めると、最終的な売却価格に影響することがあります。耐震診断が公表対象になる場合、さらに情報の整理が必要です。最後に。PM/BMの役割は、それぞれのリスクについて、論点・前提条件・影響(工期/収支/合意難易度)に分解して、比較表に載る形へ整えること。ビルオーナーが、どのリスクを優先して取りに行くか/抑えに行くか、の選択について判断します。 6-3.出口判断は「収益比較」ではなく、リスクを踏まえた許容度の設定で決まる 旧耐震の賃貸オフィスビルで出口(耐震補強/建替え/売却)を判断するとき、議論が迷走しやすい原因は、リスク管理の観点(何をリスクと見なすか/どこまで見込むか/誰が負うか/許容できない線はどこか)を踏まえずに、表面的な計算で収入と支出を設定して、優劣を付けようとすることにあります。それでは、リスク管理の考え方に沿って出口判断を組み立てようとするにあたって、以下の4つのステップに分解できます。①リスクを「特定」するまず、旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断に影響するリスクを、法令・制度対応、安全・賠償責任、契約・テナント対応、工事・更新、収益・資金繰り、売却価格等に整理します。ここで重要なのは、細目を増やすことではなく、「どのリスクが、この物件では支配的なのか」を見える形にすることです。②リスクを「評価」する(影響の出方を揃える)次に、各リスクが出口判断にどう影響するかを、同じ物差しで揃えます。具体的には、影響を工期・賃料収益への影響(減収)・追加支出(持ち出し)・実行難易度・不確実性(幅)に落とします。この段階では、数字は、単一の見込み値というのではなく、変動幅を踏まえたレンジとして扱います。レンジの幅について、未確定事項があるからなのか、リスク要因の性質に根差したものであるのかにつちえも整理します。③リスクへの「対応方針」を決める(選択肢を作る)評価までできたら、リスクへの向き合い方を決めます。旧耐震の賃貸オフィスビルの出口判断は、だいたい次の3タイプに分類できます。リスク低減型:安全性・適法性・設備リスクを優先して低減させて、運営の不確実性を小さくしようとする(耐震補強・更新寄り)リスク回避型:長期の不確実性を抱えず、外部化しようとする(売却寄り)リスク転換型:一度大きく動かして、以後のリスク発生の構造を作り替え、制御しようとする(建替え寄り)どのタイプが優れているのかではなく、この物件とこのビルオーナーが、どのリスクを許容して、どのリスクを回避するのかという選択になります。④「見直し前提」で運用する(出口判断を一回で終わらせない)出口判断は、一度、方針を決めたら、それで終わりではありません。追加調査や見積、制度・市場環境の変化で前提は更新されます。だから判断材料は「更新できる形」で維持します。このようなかたちで運用していくと、途中で前提条件、外部環境が変わったとしても、判断を更新して、対応することが可能となります。 6-4.出口判断のタイミングは選べない 旧耐震の賃貸オフィスビルでは、出口判断(耐震補強/建替え/売却)を、“当初の想定通りの時期”まで持ち越せるとは限りません。実際には、以下の事情・要因を以て判断の前倒しが迫られることもあります。設備故障が続き、設備更新が避けられなくなる故障対応が「都度修理」からすぐに「設備更新」が必要な状態に移行すると、将来支出の前提が変わってきます。空室が長期化し、募集賃料を下げてもテナントが決まりにくくなる賃料の収益面だけでなく、改修・耐震補強・建替え・売却、それぞれの選択肢の見え方にも影響します。行政・金融・売却候補先から、耐震性を踏まえた法制への適合性について確認・説明を求められる調査・点検・是正の要否が、意思決定の前提になります。相続・共有者の異動・借入の期限などの事情により、意思決定が迫られる“いつか判断する”という先送りが成り立たない状況になります。ここで重要なのは、判断の結論を早急に下そうとすることではありません。前提条件が変わったときに、耐震補強/建替え/売却の選択肢の比較の判断をやり直せる状態にしておくことです。やることは次の4点です。①判断の前提条件の内、変わる要因を押さえておく補助制度、工事費の水準、売買市場の見え方、稼働状況(空室・賃料)など、前提を動かす要因に絞って把握します。②修繕・更新の記録(一覧+根拠資料)を整備「いつ・どこを・何で・いくらで直したか」を一覧にし、点検報告書・工事報告書・図面・保証書も紐づけておきます。これらが整備されていると、調査・見積・売却査定の立上げの際、“調べ直し”の手間が軽減できます。③判断材料を整理し、揃える作業を継続して進めておくたとえば、追加調査の段取り、見積条件の整理、設備更新の優先順位付け、売却の障害になりやすい論点の洗い出し。これらの作業は、結論を出す作業ではなく、あくまでも「判断材料を整理する作業」です。④意思決定の手続きを決めておく(特に個人・共有)誰が最終的に決めるのか、どこまで委任するのか、いくら以上は誰の同意が必要か。これらの点が曖昧だと、相続・共有者の異動の局面にあたって判断を円滑に下すことが難しくなります。 第7章:旧耐震の賃貸オフィスビル経営で有効な「意思決定の型」 おわりに 旧耐震の賃貸オフィスビルと向き合う「今」から始める一歩旧耐震の賃貸オフィスビルのオーナーは、多かれ少なかれ同じ感覚を持っています。「家賃は入っている。でも、このままで本当にいいのか」この“引っかかり”は、弱さではありません。旧耐震という前提を踏まえたとき、経営者としての自然な感覚です。耐震補強も、建替えも、売却も、そうそう簡単に決められる話ではありません。費用、工期、テナント調整、資金の手当て、法的な論点など、どの選択肢にも負担と不確実性があります。ただ一つ確かなのは、何も決めないまま時間が過ぎるほど、現実に取り得る選択肢が減っていくということです。設備の更新時期、空室、資金繰り、金利、相続や共有者の事情など、外側の事情・要因が先に動き、オーナーが選びたかった道を狭めていきます。ここで必要なのは、いきなり大きな決断を下そうとすることではありません。結論を出せる状態に近付けることです。その最初の一歩は、小さくても構いません。現状を見える形にする(建物・設備・賃貸条件・市場・資金の整理)判断に必要な材料を、比較できる形で揃える(概算、工期の見通し、テナント調整の難易度、資金の当たり、法的な致命傷の有無など)判断材料が揃った時点で一度判断し、必要なら前提を更新して次に進む(揃える→判断する→更新する、を繰り返せる形にする) オーナーが主役であることは変わりません ただし、主役が一人で舞台を支える必要もありません。判断材料を整える役、選択肢を比較可能にする役、実行の段取りを作る役を揃えていくと、経営者としてのあなたの決断は「いちかばちかの賭け」ではなく「納得できる経営」になります。旧耐震の賃貸オフィスビルの将来に、完璧な正解はありません。工事費も賃料も金利も、テナントの動きも、判断に影響する前提が途中で変動するからです。それでも、判断を先送りにしない方法はあります。何を確認すれば比較できるのか、いつ一度結論を出すのか、前提が変わったらどこを見直すのか――この3点を決めて、材料を揃え、判断して、必要なら更新する。その方法が手元にあれば、どの選択肢を選んだとしても、判断した理由と前提を記録しながら、常に検証可能なビル経営として、次の一歩に進めます。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 飯野 仁 東京大学経済学部を卒業 日本興業銀行(現みずほ銀行)で市場・リスク・資産運用業務に携わり、外資系運用会社2社を経て、プライム上場企業で執行役員。 年金総合研究センター研究員も歴任。証券アナリスト協会検定会員。 2026年2月19日執筆2026年02月19日 -
貸ビル・貸事務所
四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所の特徴と賃料相場|不動産会社が解説
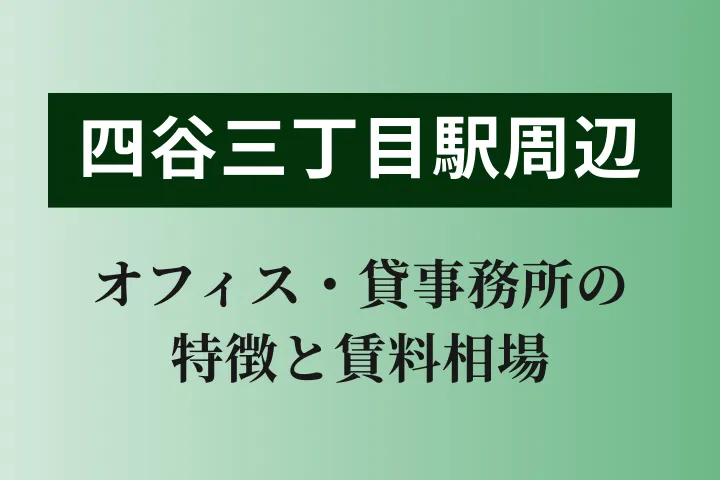 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月18日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次四谷三丁目駅周辺の特徴とトレンド四谷三丁目駅周辺の入居企業の傾向四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場四谷三丁目駅周辺の街並みと周辺環境 四谷三丁目駅周辺の特徴とトレンド 四谷三丁目駅は、東京メトロ丸ノ内線が乗り入れる駅で、新宿駅・東京駅方面の双方へアクセスしやすい立地にあります。丸ノ内線を利用することで、新宿駅へは約5分、赤坂見附・大手町方面へもダイレクトに移動でき、都心主要業務エリアとの物理的距離が近く、移動時間の面でも負担が小さい点が特徴です。徒歩圏内には、JR中央線・総武線および東京メトロ南北線・丸ノ内線が利用できる「四ツ谷」駅、東京メトロ丸ノ内線の「新宿御苑前」駅、都営新宿線の「曙橋」駅などがあり、目的地に応じて複数路線を使い分けられる交通利便性を備えています。四谷三丁目周辺は、戦後から中小規模の事務所ビルが段階的に建設され、出版社、印刷関連、医療・学術系団体、士業事務所などが集積してきたエリアです。新宿通り沿いを中心に、ワンフロア30〜100坪程度のオフィスビルが点在しており、大規模再開発エリアとは異なる、比較的落ち着いた業務環境が形成されています。周辺には飲食店やコンビニエンスストア、金融機関、郵便局など、日常的なオフィス利用に必要な施設が揃っており、特に新宿通り沿いはランチ需要を支える飲食店が多い点も特徴です。派手な商業集積はありませんが、業務に集中しやすい環境として評価される傾向があります。近年は大規模な再開発こそ限定的ですが、既存ビルのリニューアルや設備更新が進み、耐震補強や共用部改修を行った中小規模オフィスが徐々に増えています。新宿区内でありながら比較的安定した街並みが維持されている点は、当エリアならではの特徴といえます。 四谷三丁目駅周辺の入居企業の傾向 四谷三丁目駅周辺では、従来から士業(法律・会計・税務関連)、医療・学術系団体、出版社や印刷・制作関連企業などが多く見られます。新宿や四ツ谷に近接しつつ、繁華性が抑えられている点が、こうした業種に適した環境とされています。近年は、IT関連の小規模事業者やコンサルティング会社、スタートアップのサテライトオフィスとしての利用も徐々に増加しています。特に20〜50坪程度の区画では、「新宿アドレスを避けつつ、交通利便性を確保したい」といったニーズから検討されるケースが見受けられます。このエリアが選ばれる理由としては、以下の点が挙げられます。賃料水準:新宿駅至近エリアと比較すると、同規模・同築年帯で賃料が抑えられる傾向があります。交通利便性:丸ノ内線に加え、徒歩圏で複数路線が利用可能な点は、来客対応や通勤面で評価されています。街の雰囲気:過度な商業色がなく、業務用途に適した落ち着いた環境である点が、長期利用を前提とする企業に好まれています。 四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 四谷三丁目周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約13,000円約20,000円50~100坪約15,000円約21,000円100~200坪約15,000円約23,000円200坪以上-- 四谷三丁目駅周辺の街並みと周辺環境 四谷三丁目駅周辺の街並みを象徴する要素の一つが、写真に写る四谷消防署と四谷三丁目交差点周辺の景観です。新宿通りと外苑東通りが交差するこの地点は、当エリアの交通・人流の結節点であり、周辺環境を理解するうえでの基準点となっています。写真からも分かる通り、周辺には中高層の業務系・公共系建築物が立ち並び、低層の雑居ビルが密集する繁華街とは異なる、整った街路景観が形成されています。建物の用途はオフィスや公共施設が中心で、外観も比較的落ち着いた色調・デザインのものが多く、業務エリアとしての性格が明確です。また、交差点周辺は歩道幅が確保され、視認性の高い建物が点在しているため、来訪者にとっても場所の把握がしやすい環境といえます。取引先や来客を迎える機会が多い企業にとっては、説明しやすい立地要素の一つとなっています。新宿通り沿いには、オフィスビルの低層階に飲食店やサービス店舗が入居しており、業務エリアとしての機能性と日常利便性が両立しています。一方で、通りから少し離れたエリアでは住宅や小規模ビルが混在し、全体として過度な喧騒は抑えられています。このように四谷三丁目駅周辺は、主要幹線道路に面した業務拠点性と、落ち着いた街並みのバランスが取れたエリアです。派手な再開発や大型商業施設に依存せず、既存の都市基盤の中で安定したオフィス街として機能している点が、当エリアの街並みの大きな特徴といえます。 ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 四谷三丁目駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、四谷三丁目駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月18日執筆2026年02月18日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月18日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次四谷三丁目駅周辺の特徴とトレンド四谷三丁目駅周辺の入居企業の傾向四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場四谷三丁目駅周辺の街並みと周辺環境 四谷三丁目駅周辺の特徴とトレンド 四谷三丁目駅は、東京メトロ丸ノ内線が乗り入れる駅で、新宿駅・東京駅方面の双方へアクセスしやすい立地にあります。丸ノ内線を利用することで、新宿駅へは約5分、赤坂見附・大手町方面へもダイレクトに移動でき、都心主要業務エリアとの物理的距離が近く、移動時間の面でも負担が小さい点が特徴です。徒歩圏内には、JR中央線・総武線および東京メトロ南北線・丸ノ内線が利用できる「四ツ谷」駅、東京メトロ丸ノ内線の「新宿御苑前」駅、都営新宿線の「曙橋」駅などがあり、目的地に応じて複数路線を使い分けられる交通利便性を備えています。四谷三丁目周辺は、戦後から中小規模の事務所ビルが段階的に建設され、出版社、印刷関連、医療・学術系団体、士業事務所などが集積してきたエリアです。新宿通り沿いを中心に、ワンフロア30〜100坪程度のオフィスビルが点在しており、大規模再開発エリアとは異なる、比較的落ち着いた業務環境が形成されています。周辺には飲食店やコンビニエンスストア、金融機関、郵便局など、日常的なオフィス利用に必要な施設が揃っており、特に新宿通り沿いはランチ需要を支える飲食店が多い点も特徴です。派手な商業集積はありませんが、業務に集中しやすい環境として評価される傾向があります。近年は大規模な再開発こそ限定的ですが、既存ビルのリニューアルや設備更新が進み、耐震補強や共用部改修を行った中小規模オフィスが徐々に増えています。新宿区内でありながら比較的安定した街並みが維持されている点は、当エリアならではの特徴といえます。 四谷三丁目駅周辺の入居企業の傾向 四谷三丁目駅周辺では、従来から士業(法律・会計・税務関連)、医療・学術系団体、出版社や印刷・制作関連企業などが多く見られます。新宿や四ツ谷に近接しつつ、繁華性が抑えられている点が、こうした業種に適した環境とされています。近年は、IT関連の小規模事業者やコンサルティング会社、スタートアップのサテライトオフィスとしての利用も徐々に増加しています。特に20〜50坪程度の区画では、「新宿アドレスを避けつつ、交通利便性を確保したい」といったニーズから検討されるケースが見受けられます。このエリアが選ばれる理由としては、以下の点が挙げられます。賃料水準:新宿駅至近エリアと比較すると、同規模・同築年帯で賃料が抑えられる傾向があります。交通利便性:丸ノ内線に加え、徒歩圏で複数路線が利用可能な点は、来客対応や通勤面で評価されています。街の雰囲気:過度な商業色がなく、業務用途に適した落ち着いた環境である点が、長期利用を前提とする企業に好まれています。 四谷三丁目駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 四谷三丁目周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約13,000円約20,000円50~100坪約15,000円約21,000円100~200坪約15,000円約23,000円200坪以上-- 四谷三丁目駅周辺の街並みと周辺環境 四谷三丁目駅周辺の街並みを象徴する要素の一つが、写真に写る四谷消防署と四谷三丁目交差点周辺の景観です。新宿通りと外苑東通りが交差するこの地点は、当エリアの交通・人流の結節点であり、周辺環境を理解するうえでの基準点となっています。写真からも分かる通り、周辺には中高層の業務系・公共系建築物が立ち並び、低層の雑居ビルが密集する繁華街とは異なる、整った街路景観が形成されています。建物の用途はオフィスや公共施設が中心で、外観も比較的落ち着いた色調・デザインのものが多く、業務エリアとしての性格が明確です。また、交差点周辺は歩道幅が確保され、視認性の高い建物が点在しているため、来訪者にとっても場所の把握がしやすい環境といえます。取引先や来客を迎える機会が多い企業にとっては、説明しやすい立地要素の一つとなっています。新宿通り沿いには、オフィスビルの低層階に飲食店やサービス店舗が入居しており、業務エリアとしての機能性と日常利便性が両立しています。一方で、通りから少し離れたエリアでは住宅や小規模ビルが混在し、全体として過度な喧騒は抑えられています。このように四谷三丁目駅周辺は、主要幹線道路に面した業務拠点性と、落ち着いた街並みのバランスが取れたエリアです。派手な再開発や大型商業施設に依存せず、既存の都市基盤の中で安定したオフィス街として機能している点が、当エリアの街並みの大きな特徴といえます。 ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 四谷三丁目駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、四谷三丁目駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月18日執筆2026年02月18日 -
プロパティマネジメント
築古・小規模の賃貸オフィスビルの苦戦と再生へのヒント
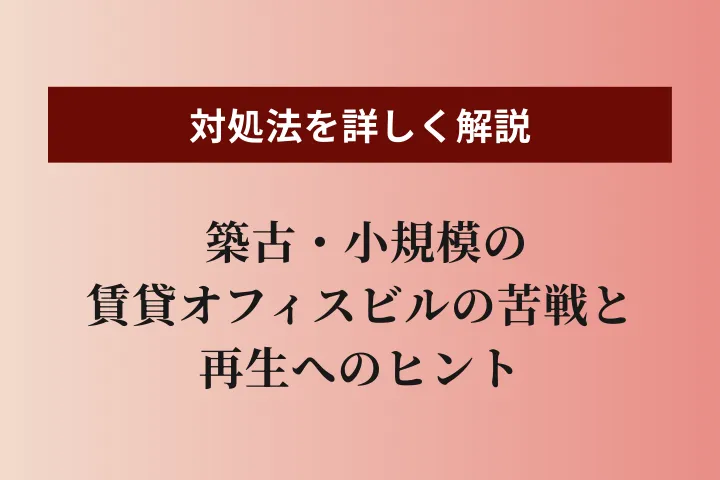 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの飯野です。この記事は「築古の賃貸オフィスビルの苦戦と再生へのヒント」を解説したもので、2026年2月17日に改訂しています。少しでも、皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次はじめに:築古賃貸オフィスビル市場の現状と課題(築古・小規模の賃貸オフィスビルが市場で不利になりやすい背景)第1章:資金を大きく投入せずに築古・小規模の賃貸オフィスビルを再生する方法第2章:満室稼働を実現する具体策おわりに:築古・小規模の賃貸オフィスビル再生は戦略的に、そして継続的に はじめに:築古賃貸オフィスビル市場の現状と課題(築古・小規模の賃貸オフィスビルが市場で不利になりやすい背景) 日本のオフィスビル市場では、1980年代のバブル期に大量供給されたビル群が築30年を超え、ストックの高齢化が進んでいます。東京都心部では賃貸オフィスビルの平均築年数が約33年に達し、中小規模ビルの約9割がバブル期竣工という状況です。こうした築古ビルは設備や内装の老朽化が進み、何も手を打たなければ競争力を失っていきます。さらに近年、在宅勤務と出社を組み合わせたハイブリッドワークが広がるなど、「オフィスは社内コミュニケーションやコラボレーションの場である」という認識が高まっています。その結果、昔ながらの画一的なオフィス空間しか提供できない築古の賃貸オフィスビルは、テナントに選ばれにくくなっているのが実情です。このような環境下で、築古の賃貸オフィスビルオーナーは苦戦を強いられています。かつては「駅近・新築・大規模」(俗に「近・新・大」)という3条件を満たすオフィスほど競争力が高いとされました。従来は築年数が浅いほど空室率も低く安定していましたが、大規模ビルの開発が相次いでいることもあり、築浅ビルでも空室が目立ちはじめ、築年の古いビルとの差が縮小したとの指摘もあります。しかしそれは「築古ビルでも安泰」という意味ではなく、単にテナントの選別眼が厳しくなり、築浅ビルですら条件が悪ければ敬遠されるようになったということです。実際、「単に場所を貸すだけではテナントはついてこない時代」が既に始まっていると指摘されています。とくに課題が表面化しやすいのが、築古の中でも小規模の賃貸オフィスビルです。大規模ビルのように設備投資や大規模改装で一気に見栄えを変え、設備ハードのスペックを底上げする体力がなく、テナントにとっても「このビル、何かあったとき対応できるの?」という不安を持たれやすいので、築古・小規模であること自体が、内見や比較検討の段階で、減点要素として働きやすいのです。だからこそ、派手な改装や全面的な設備更新を先行させるのはそもそも無理なので、築古・小規模の賃貸オフィスビルの再生は、小規模の施策を積み上げて“選ばれる状態”を作る戦略のほうが、再現性が高いと言えます。言い換えるならば、勝ち筋は、「改装」より先に、小規模の修繕と運用によって不安の芽を潰すことにあります。止まる・漏れる・効かない・暗い・汚いといった基本的不安が残ったまま見た目だけを整えても、テナントからの評価の改善は見込めません。小規模でも的確に修繕し、ビル管理の反応速度や運用の確実さを示せるビルのほうが、結果としてテナントから選ばれやすくなるはずです。多くの築古・小規模の賃貸オフィスビルでは、テナント誘致のために賃料を下げざるを得ない場面が増えています。しかし、賃料値下げによる空室解消は一時しのぎに過ぎず、長期的には資産価値の低下に直結するリスクがあります。本コラムでは、賃料を安易に下げずに満室稼働を実現するための戦略と具体策について、事例やデータを交えながら論理的に考察します。築古・小規模の賃貸オフィスビル再生のヒントを探り、ビルオーナーが直面する課題にどのように対処すべきかを明らかにしていきたいと思います。 第1章:資金を大きく投入せずに築古・小規模の賃貸オフィスビルを再生する方法 築古・小規模の賃貸オフィスビルオーナーにとって、建物や設備の老朽化に伴う改修コストは頭の痛い問題です。立地や規模によっては、過度な投資を回収できないリスクも高く、経営の意思決定が難しくなることも多々あります。しかし、予算が限られているからといって、何もせずに放置してしまえば、築古・小規模ビルはさらに価値を下げ、空室率の悪化や賃料下落が進む一方です。ここでは、限られた資金でも実行可能な、建物の魅力アップとランニングコスト削減を両立する具体的な手法を解説していきます。 1-0.築古・小規模の賃貸オフィスビル再生では「修繕」と「更新」と「改装」を混同しない 築古・小規模の賃貸オフィスビルは、最小コストで最大の効果を狙うには「小さく直して、早く回す」が基本になります。ただ、このとき現場で、「修繕」「設備更新」「改装(リニューアル)」が混同されると、話がややこしくなりかねません。混同されて、目的・効果が取り違えられて、優先順位が決まらないと、小規模に効果的に進めることが難しくなりかねません。だから最初に、この3つの用語を切り分けて整理します。修繕:不安の芽を潰します。壊れた/劣化した部分を元の機能に戻すこと(漏水、腐食、異音、チラつき、排水詰まり、建具不良など)。築古・小規模ビルではまずこの対応の漏れをなくすことが“信用”を作ります。テナントが不安を感じるのは、「不具合が放置されないか」「止まったときに復旧できるか」です。設備更新:このコラムでは主な検討対象とはしていませんが、修繕対応では対応し切れない場合、次のステップとして検討が必要なケースも想定しておく必要があります。文字通り、設備の入替です。不具合が解消され、性能の向上も見込まれます(高効率空調、LED化、エレベーターの制御盤更新など)。いずれにしても、修繕で潰すべき不具合(漏水・臭気・排水不良・空調のムラ)について充分な検証をしないまま、設備更新に踏み込むと、結果的にまだ使えるのに買い替えるのはモッタイナイということになりかねません。改装(リニューアル):見た目や使い勝手を刷新して印象を上げます(エントランス、共用部、トイレ内装など)。うまくやれば効果的ですが、修繕対応が甘いまま改装しても、見た目だけで、不安材料は残っているということになりかねません。築古・小規模の賃貸オフィスビルで効果的な対応は、「大きく変える」ことではなく、「小さく直して、早く回す」ことです。まず優先すべきは、漏水跡、異音、チラつき、臭気、排水不良、建具の不具合といった、テナントの不安の芽を小規模の修繕で確実に潰すことです。この点がクリアされない限り、その他でどのような改善策を打ってもテナントの評価にはつながりません。改装・リニューアルを実施する場合、エントランスやトイレなど、少ない範囲で印象が変わる場所に絞り、小規模で手を打つのが現実的です。派手さより、修繕と運用の反応速度で「このビルは手当てされている」と伝わる状態を作る。これが、最小コストで最大の効果を狙う対応の基本方針になります。 1-1.設備関連の支出抑制の鍵は、継続的な保守と適切な小規模修繕対応 設備を大規模修繕したり、すべて更新するには膨大な費用がかかりますが、既存設備を丁寧に保守しつつ、適切で小規模の修繕対応を実施することで、設備自体の長寿命化を図り、大幅な修繕費用・更新投資等の設備関連の支出を先送りすることが期待できます。特に、空調設備のフィルターや熱交換器の定期的な清掃、給排水設備の定期洗浄や点検を行い、適切なタイミングで保守部品を交換することで、設備の稼働効率を高め、故障リスクを軽減することができます。事例①港区の築30年ビルの空調修繕・保守対策港区にある築30年超のオフィスビルでは、老朽化した空調設備が頻繁に故障し、夏場のトラブルが続出。そこで、フィルターの定期交換や空調ダクトの清掃を徹底したところ、年間の修理費が40%削減され、冷暖房の効率が向上しました。これにより、テナントの満足度も向上し、契約更新率が改善しました。 1-2.ポイントを絞った小規模改装(リニューアル) 建物全体の大規模リノベーションは費用負担が重いため、ポイントを絞った小規模改装(リニューアル)を行うことで、効率的にビルの印象を改善できる場合もあります。特に、エントランスや共用部など第一印象を左右する場所に、照明改善や壁・床の美装化などを適切に施せば、ビルの魅力は大幅に向上することも期待できます。事例②千代田区のオフィスビルの共用部改装千代田区の築35年のオフィスビルでは、エントランスと廊下のリニューアルを実施。床材を明るいタイルに変更し、照明をLEDに切り替えた結果、「清潔感が増し、古さを感じさせない」という声が増加。結果として新規テナント獲得率が向上しました。 1-3.小規模でも効果的な設備導入・運用改善 低予算で付加価値を提供するには、IoTを活用したスマートビル化がおすすめです。後付け型のスマートロックや照明・空調の自動制御システムを導入することで、テナントにとっての利便性や快適性を高められます。これらの設備は比較的低コストで導入でき、かつ設備管理の効率化にもつながるため、運営面でもメリットが期待できます。また、近年、テナントの関心が高まっている省エネに着目した施策も有効です、限られた資金内でも築古・小規模の賃貸オフィスビルの競争力を回復し、収益性の向上を目指すことが可能となります。 事例③渋谷区の中規模ビルでのIoT導入渋谷区にある築32年のビルでは、スマートロックシステムを導入し、テナントがスマホアプリで入退館管理を行えるようにしました。これによりセキュリティが向上し、新規入居希望者へのアピールポイントとなりました。 事例④中央区の省エネ関連小規模設備導入・運用改善事例中央区の築33年のオフィスビルでは、空調設備の適正運用とLED照明導入により、電力コストを年間15%削減。これにより、共益費の削減にもつながり、結果としてテナントの退去抑制に成功しました。 これらの実例からも分かるように、築古・小規模の賃貸オフィスビルの再生には、単なるコスト削減ではなく、設備の適正運用や小規模修繕による魅力向上が重要です。限られた予算内でも、適切な戦略を講じることで、築古ビルの資産価値を維持・向上させることが可能です。成功事例から浮かび上がるキーワードは、「付加価値」「ターゲット戦略」「運営力」です。建物のハード(物理的な質)を高めることに加え、どのテナント層にどんな価値を提供するかを明確に描き、それに沿った小規模修繕・運用改善を行うことが満室への近道となっています。 一方で、すべての築古・小規模の賃貸オフィスビル再生プロジェクトが成功するわけではないことにも注意が必要です。改装(リニューアル)に多額の費用を投じて内装を一新し、「これで賃料アップだ」と意気込んでも、肝心の入居者が集まらなければ投資回収は困難です。例えばデザイン優先で改装したものの、立地とのマッチングを十分に検証しないまま進めたので、高めに設定した賃料に見合うテナントが見つからなかったケースや、テナントのニーズを読み違えて設備投資が空回りした例も報告されています。また、築古・小規模の賃貸オフィスビル特有の課題(耐震性や法規制上の制約など)を無視して表面的な改装(リニューアル)に終始した結果、「見た目は綺麗でも安心して入居できない」と敬遠されてしまう失敗もあります。こうした事例から学ぶべきは、市場ニーズや物件の本質的課題を見極めずに闇雲に改装したとしても成果は出ないという点です。再生策を講じる際には、しっかりとした戦略とニーズ分析に基づいて計画を立てることが不可欠でしょう。 以下では、築古オフィスビルを満室稼働させるための具体的な対策をいくつかの観点から掘り下げます。成功事例のエッセンスと失敗例の教訓を踏まえつつ、費用対効果を意識した実践的な手法を紹介していきます。 第2章:満室稼働を実現する具体策 2-1.「不安」の芽を潰す適切な小規模修繕 築古の小規模ビルで空室が長引くとき、原因は「賃料」より「不安」のことが多いです。具体的には、漏水跡、共用部のガタつき、トイレの不具合、照明のムラ、空調の効きムラ、異音――このあたりが残っていると、内見の瞬間に評価が落ちます。だからまず、やるべきは、いきなり、設備更新、リノベーションに踏み切ることではなく、小規模修繕で“減点ポイント”を消すことです。小規模修繕は、費用の上振れを抑えながら、内見評価を底上げできます。築古・小規模の賃貸オフィスビル再生の第一歩は、建物の基本性能と印象を底上げするハード面の改善です。限られた予算内でも工夫次第で効果的な小規模修繕は可能です。ポイントは「コストパフォーマンスの高い箇所から優先的に手を付ける」ことです。基本設備の基盤整備:古いビルでは空調や電気設備の老朽化により室内環境が劣化していることが少なくありません。空調設備の調整やフィルター清掃、必要に応じたメンテナンスを行い、適切な温度・空気質を維持しましょう。設備(とくに空調)の性能向上はテナント満足度を高め、ビル競争力の向上につながります。内装・共用部の改装で印象をリフレッシュ(小規模な設備導入とも組合わせ):ビル内外の見た目の改善も検討課題です。第一印象を左右するエントランスやロビーは、比較的低コストな小規模な改装(リニューアル)で大きな効果が期待できます。壁や天井の塗装を明るい色調に塗り替える、床材やカーペットを新調する、照明をLED化して明るさと省エネを両立する、といった改装は定番ながら有効です。特に照明のLED化は初期費用こそかかるものの、電気代削減効果をもって数年程度で初期支出を回収できるケースも多く、長寿命化により修繕・保守頻度も減らせます。また、水回り(トイレや給湯室)の清潔感は入居検討者が重視するポイントです。古いトイレ設備を最新の節水型に交換したり、和式トイレしかない場合は洋式化したり、内装を明るく改装するだけでも印象は格段に向上します。男女別トイレの設置が難しい小規模ビルでも、小規模ながら改装(リニューアル)して、清掃を行き届かせることで「清潔で安心」なイメージを与えられます。小規模改装で費用対効果を最大化:すべてを一度に直す予算がない場合は、ポイントを絞った部分リニューアルで段階的に価値向上を図りましょう。たとえば「エントランスホールのみ先行小規模改装」「空室となっているフロアをモデルルーム化」など、支出額に対してテナント受けする効果が高い部分から着手します。費用を抑える工夫としては、既存の什器や間仕切りを活用・再配置する、レイアウト変更を伴わない模様替え中心の工事にする、安価でもデザイン性の高い建材を取り入れる、といった方法があります。また、「古さ」を逆手に取る発想も有効です。内装のレトロな雰囲気をあえて残し、ヴィンテージ風オフィスとして売り出した例もあります。天井の躯体をあらわしにしてインダストリアルデザイン風に仕上げたり、昭和レトロな外観を活かして味わいのあるクリエイティブオフィスとしてPRすることで、画一的な新築ビルにはない個性を求めるテナントを引き付けられる場合もあります。このように、低予算でも「安全性の底上げ」と「印象の刷新」を両立する小規模修繕・小規模改装を組合わせて進めることで、築古・小規模の賃貸オフィスビルのマイナスイメージを払拭し競争力を高めることができます。小さな改良の積み重ねがテナント満足度を向上させ、結果として高稼働率・賃料維持につながるのです。 2-2.テナントニーズを捉えた運営工夫と差別化戦略 ハード面の改善と並んで重要なのが、ソフト面での戦略、すなわちテナントのニーズに合った運営とサービスの提供です。ただ空間を貸すだけでは選ばれない時代だからこそ、ビル独自の付加価値を打ち出し差別化を図る必要があります。ここではテナント・ターゲットの見直しと賃貸条件・サービス面での工夫について具体策を考えてみましょう。テナントのターゲット層の再設定:築古・小規模の賃貸オフィスビルが従来想定していたテナント像(例えば近隣の中小企業向け事務所利用など)に固執していては、市場の変化に取り残される恐れがあります。成功事例にあったように、発想を転換して新たな需要層を開拓することが鍵です。昨今増えているスタートアップ企業、ITベンチャー、地方や海外から進出してくる企業など、数十年前には想定しなかったターゲットも台頭しています。彼らは大企業ほどオフィスに高い予算は割けないものの、働きやすい環境やクリエイティブな雰囲気を求めています。また、小規模でもセキュアで快適なオフィスを必要とする専門士業(士業事務所)や、リモートワーク普及で郊外勤務を希望する従業員向けのサテライトオフィス需要なども見逃せません。自ビルの立地や規模に照らし、「このビルならでは」のターゲット層を定め、その層に響く改装・サービスを考えましょう。例えば駅から距離があるビルでも駐車場があれば車移動が主なテナントを狙う、都心でエリアイメージが良くない場所ならあえてクリエイター向けに内装を個性的にしてみる、といった戦略が考えられます。ターゲットを明確に絞ることで、その層に特化した売り込みが可能になって、満室への道が見えてきます。ビルブランディングと情報発信:築古・小規模の賃貸オフィスビルを再生する際には、そのビルのコンセプトや強みを明確に打ち出すことも大切です。ただ安いというだけではなく、「○○な人たちが集まるビル」「△△な働き方ができるオフィス」といった物語性を持たせるのです。ビルのブランドを育てていく姿勢はテナントにも伝わります。具体的には、ビルの名前をリブランディングしてみるのも一案です。築年数が古いままの名前より、コンセプトに合ったネーミングやロゴを作成して刷新すれば、新規顧客の目にも留まりやすくなります。改装(リニューアル)のタイミングに合わせて内覧会イベントを開催し、当社のオウンド・メディア・サイトで紹介記事を掲載するなど、積極的な情報発信を以て「生まれ変わったビル」をアピールしましょう。最近ではリノベーション専門の不動産メディアや、テナントリーシング支援のプラットフォームもありますので、そうしたチャネルを活用して露出を増やすのも有効です。オフィス探しをしている企業だけでなく、不動産仲介業者に対しても物件のセールス・ポイントを明確に伝え、認知度を高めておくことで紹介件数アップが期待できます。テナントとのコミュニケーション向上:ソフト面の充実として忘れてはならないのが、既存テナントとの関係構築です。現在入居中のテナントの満足度を上げることは、退去防止と口コミ効果につながります。小規模ビルでは管理人が常駐しない場合も多いですが、その場合でもビル管理会社が定期的に巡回した際に、こまめにチェックして、設備不具合の対応を早める、共用部の清掃頻度を上げる、といった地道な施策がテナントの愛着を育み、長期入居や知人企業の紹介といった形で報いてくれるでしょう。「このビルの管理は信頼できる」という評判が立ち、多少古いビルでも安心して入居できるとの評価につながります。結果として空室が出ても別のテナントで埋まりやすくなり、安定稼働・賃料維持に寄与するのです。 2-3.省エネ小規模修繕・エネルギー管理の強化による付加価値創出 近年、企業の環境意識の高まりやエネルギー価格の上昇を背景に、オフィスビルの省エネルギー性能は重要な競争力の一つとなっています。ビルの省エネ性能を高めることは光熱費の削減による運営コスト低減だけでなく、「環境に配慮したオフィス」という付加価値を生み、テナント企業のイメージ向上にもつながります。ここでは、築古・小規模の賃貸オフィスビルでも実践できる省エネ・エネルギー管理強化策を考えてみましょう。照明・空調の省エネ化:オフィスビルで電力消費の大きな割合を占める照明と空調の高効率化は、省エネの要です。照明は前述の通りLED照明への更新が効果的で、消費電力を約半分程度に削減できるケースもあります。人感センサーを設置して人がいない時には自動で消灯するシステムを導入すれば、無駄な点灯を防げます。空調については、旧式の個別空調機(パッケージエアコン等)で効率が悪いものはインバーター式の省エネ型に交換する、さらに、支出額は嵩みますが、熱源機器やポンプ類の高効率型への更新や制御システムの最適化を行うことで、かなりの省エネが期待できます。また、テナントが退去したフロアなど未使用区画の空調を停止・間引き運転できるようゾーニング制御を取り入れるなど、きめ細かなエネルギー管理を行うことも重要です。ビルのエネルギー使用量を見える化する、スマートメーターやエネルギー管理システム(BEMS)を導入すれば、テナントごとの使用量を把握して省エネ意識を高めたり、ピーク電力を抑制したりといったデータに基づく運用改善が可能になります。省エネ小規模修繕の結果、CO2排出量削減や電気料金削減といった具体的数値が出れば、それ自体をビルのセールス・ポイントとして訴求できます。▪断熱性能の向上と快適性アップ:築古・小規模の賃貸オフィスビルでは、窓サッシや外壁の断熱性能が低く、外気の影響を受けやすいため空調負荷が大きくなりがちです。可能であれば窓ガラスを複層ガラスに交換したり、窓枠に後付で断熱内窓を設置することで断熱性を高められます。簡易な対策としては窓ガラスに遮熱フィルムを貼るだけでも冷房負荷を減らす効果があります。夏場の直射日光が強い開口部には外部に可動ルーバーや日よけ(オーニング)を設置し日射を遮る工夫も有効です。逆に冬場の熱損失を防ぐため、出入口に風除室やエアカーテンを設けることも検討できます。こうした断熱対応は、テナントの光熱費負担軽減につながるだけでなく、室内の温度ムラが減り快適性が向上する副次効果もあります。室温の安定したオフィスは従業員の生産性や健康にもプラスに働くため、テナント企業にとってもメリットが大きいポイントです。 2-4.スマートビル化・付加価値サービスの導入による競争力強化 テナントの要望が高度化する中、築古・小規模の賃貸オフィスビルでも、テクノロジーの力を借りて付加価値サービスを提供することが求められています。いわゆる「スマートビル」的な機能は何も最新鋭のビルだけのものではありません。近年は後付け可能なIoTソリューションやサービスプラットフォームが数多く登場しており、築古・小規模の賃貸オフィスビルでも比較的容易に導入できるようになっています。ここでは、テクノロジー活用によるサービス向上策と付加価値創出の方法を見ていきます。IoTによるビル管理の効率化と快適性向上:まず挙げられるのが、ビル管理業務へのIoT導入です。センサーやネットワークを活用して設備の稼働状況や各種環境データを収集・制御することで、旧来型のビルでも最新ビルと遜色ない管理レベルを実現できます。たとえば、水漏れセンサーや設備異常検知センサーを設置しておけば、故障やトラブルの兆候を早期に把握し対処できます。エレベーターやポンプなどの主要設備にもIoT監視を付ければ、異常時に迅速な修繕・保守対応が可能となり、サービス停止時間の短縮や事故防止による信頼性向上につながります。さらにセキュリティ面でも、顔認証やICカードによる入退館管理システムを後付け導入する例が増えています。非接触で解錠できるスマートロックやスマートセンサーライト、防犯カメラのネット連携などにより、小規模ビルでも安全・安心なスマートセキュリティ環境を整備できます。古いビルでも後付け技術でそうした環境が実現できるなら、テナントの安心感は格段に増すでしょう。テクノロジー導入の費用対効果:スマート・システムや付加価値サービスを導入する際には、その費用対効果も考慮しましょう。幸いなことに、クラウドサービスやIoT機器の普及で初期投資ゼロ~小額で始められるサービスも多くなっています。例えば入退館管理システムは、クラウド型サービスを月額課金で利用すれば高価な専用機器を買う必要がありません。スマートロックも1台数万円程度からあり、工事も簡単です。また、テナント向けのスマホアプリを提供し、ビルの設備予約(会議室予約や空調延長申請など)を便利に行えるようにするサービスもあります。自社ビル専用アプリを開発するのは費用がかかりますが、既存のプラットフォームを使えば比較的安価です。重要なのは、テナント目線で「このビルに入ると便利」と思える仕組みを一つでも増やすことです。最新ビルでは当たり前の仕組みも、築古・小規模の賃貸オフィスビルで導入すれば大きな差別化になります。それがオーナーにとっても省力化・効率化につながるものであれば一石二鳥です。例えばオンライン上でテナントからの問い合わせや工事申請を受け付ける仕組みを導入すれば、対応履歴も残り管理もしやすくなります。小規模ビルゆえに人的サービスでカバーしていたことをIT化することで、逆にきめ細かなサービス提供が可能になる分野もあるでしょう。このように、スマート技術とサービスの導入は、築古ビルに現代的な付加価値をもたらし競争力を高める有効な手段です。テクノロジーは日進月歩で進化しており、今後も新たなソリューションが生まれるでしょう。オーナーとしては常に情報収集を怠らず、自ビルにフィットしそうなサービスがあれば積極的に試してみる姿勢が大切です。大掛かりな設備投資をしなくても導入できるサービスは数多くありますので、「築古だから…」「小規模だから…」と尻込みせずチャレンジすることで、テナント満足度と稼働率アップにつなげていきましょう。 おわりに:築古・小規模の賃貸オフィスビル再生は戦略的に、そして継続的に このコラムを通じて、築古・小規模の賃貸オフィスビルが直面する苦戦の背景と、再生への具体的ヒントを述べてきました。重要なのは、単に賃料を下げる安易な道に逃げるのではなく、戦略を持ってビルの価値を高める取り組みを行うことです。幸いにも、多くの成功事例が示すように、工夫次第で築古・小規模の賃貸オフィスビルは見違えるように蘇り、テナントにとって魅力的な存在になり得ます。老朽化が進むオフィス・ストックが大量にあるということは、裏を返せば変革の余地がそれだけ大きいということです。オーナーにとってはチャレンジであると同時に、大きなチャンスとも言えるでしょう。再生策を講じる際には、まず自ビルの強み・弱み、市場環境やターゲットのニーズをしっかり分析することが出発点です。その上で、本コラムで述べたようなハード・ソフト両面の手立てを組み合わせ、自社の事情に合ったロードマップを描いてください。すべてを一度に実現する必要はありません。小さな改善を積み重ね、それをテナント募集のアピール材料として発信し、徐々に稼働率と収益性を高めていくことが現実的です。一度、満室を達成しても油断は禁物で、市場動向やテナント要望は刻々と変化します。定期的にビルの状況を見直し、新たな競合ビルの動きや技術トレンドをチェックして、常にアップデートを図る姿勢が求められます。「単なる古い・小規模なビル」だった物件が、小規模修繕・改装(リニューアル)やサービス強化の組み合わせによって「選ばれるオフィス」に進化したとき、適正賃料で高い稼働を維持し、資産価値も向上する好循環が生まれます。築古・小規模の賃貸オフィスビルが持つポテンシャルを引き出し、テナントにとってもオーナーにとってもWin-Winとなる再生を実現するために、本コラムのヒントがお役に立てば幸いです。築古・小規模の賃貸オフィスビル再生の成功例が増えれば、賃貸オフィス・マーケット全体の活性化にもつながります。老朽化ストックが多い日本の賃貸オフィス市場において、一つひとつのビルが再生への一歩を踏み出すことで、新築偏重ではない持続可能な発展が期待できるでしょう。ぜひ、専門家の知見や周囲の協力も得ながら、ビジネスライクかつ柔軟な発想で築古・小規模の賃貸オフィスビルの再生にチャレンジしてみてください。満室稼働のその先に、ビル・オーナーとテナント双方の明るい未来が拓けるはずです。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 飯野 仁 東京大学経済学部を卒業 日本興業銀行(現みずほ銀行)で市場・リスク・資産運用業務に携わり、外資系運用会社2社を経て、プライム上場企業で執行役員。 年金総合研究センター研究員も歴任。証券アナリスト協会検定会員。 2026年2月17日執筆2026年02月17日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの飯野です。この記事は「築古の賃貸オフィスビルの苦戦と再生へのヒント」を解説したもので、2026年2月17日に改訂しています。少しでも、皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次はじめに:築古賃貸オフィスビル市場の現状と課題(築古・小規模の賃貸オフィスビルが市場で不利になりやすい背景)第1章:資金を大きく投入せずに築古・小規模の賃貸オフィスビルを再生する方法第2章:満室稼働を実現する具体策おわりに:築古・小規模の賃貸オフィスビル再生は戦略的に、そして継続的に はじめに:築古賃貸オフィスビル市場の現状と課題(築古・小規模の賃貸オフィスビルが市場で不利になりやすい背景) 日本のオフィスビル市場では、1980年代のバブル期に大量供給されたビル群が築30年を超え、ストックの高齢化が進んでいます。東京都心部では賃貸オフィスビルの平均築年数が約33年に達し、中小規模ビルの約9割がバブル期竣工という状況です。こうした築古ビルは設備や内装の老朽化が進み、何も手を打たなければ競争力を失っていきます。さらに近年、在宅勤務と出社を組み合わせたハイブリッドワークが広がるなど、「オフィスは社内コミュニケーションやコラボレーションの場である」という認識が高まっています。その結果、昔ながらの画一的なオフィス空間しか提供できない築古の賃貸オフィスビルは、テナントに選ばれにくくなっているのが実情です。このような環境下で、築古の賃貸オフィスビルオーナーは苦戦を強いられています。かつては「駅近・新築・大規模」(俗に「近・新・大」)という3条件を満たすオフィスほど競争力が高いとされました。従来は築年数が浅いほど空室率も低く安定していましたが、大規模ビルの開発が相次いでいることもあり、築浅ビルでも空室が目立ちはじめ、築年の古いビルとの差が縮小したとの指摘もあります。しかしそれは「築古ビルでも安泰」という意味ではなく、単にテナントの選別眼が厳しくなり、築浅ビルですら条件が悪ければ敬遠されるようになったということです。実際、「単に場所を貸すだけではテナントはついてこない時代」が既に始まっていると指摘されています。とくに課題が表面化しやすいのが、築古の中でも小規模の賃貸オフィスビルです。大規模ビルのように設備投資や大規模改装で一気に見栄えを変え、設備ハードのスペックを底上げする体力がなく、テナントにとっても「このビル、何かあったとき対応できるの?」という不安を持たれやすいので、築古・小規模であること自体が、内見や比較検討の段階で、減点要素として働きやすいのです。だからこそ、派手な改装や全面的な設備更新を先行させるのはそもそも無理なので、築古・小規模の賃貸オフィスビルの再生は、小規模の施策を積み上げて“選ばれる状態”を作る戦略のほうが、再現性が高いと言えます。言い換えるならば、勝ち筋は、「改装」より先に、小規模の修繕と運用によって不安の芽を潰すことにあります。止まる・漏れる・効かない・暗い・汚いといった基本的不安が残ったまま見た目だけを整えても、テナントからの評価の改善は見込めません。小規模でも的確に修繕し、ビル管理の反応速度や運用の確実さを示せるビルのほうが、結果としてテナントから選ばれやすくなるはずです。多くの築古・小規模の賃貸オフィスビルでは、テナント誘致のために賃料を下げざるを得ない場面が増えています。しかし、賃料値下げによる空室解消は一時しのぎに過ぎず、長期的には資産価値の低下に直結するリスクがあります。本コラムでは、賃料を安易に下げずに満室稼働を実現するための戦略と具体策について、事例やデータを交えながら論理的に考察します。築古・小規模の賃貸オフィスビル再生のヒントを探り、ビルオーナーが直面する課題にどのように対処すべきかを明らかにしていきたいと思います。 第1章:資金を大きく投入せずに築古・小規模の賃貸オフィスビルを再生する方法 築古・小規模の賃貸オフィスビルオーナーにとって、建物や設備の老朽化に伴う改修コストは頭の痛い問題です。立地や規模によっては、過度な投資を回収できないリスクも高く、経営の意思決定が難しくなることも多々あります。しかし、予算が限られているからといって、何もせずに放置してしまえば、築古・小規模ビルはさらに価値を下げ、空室率の悪化や賃料下落が進む一方です。ここでは、限られた資金でも実行可能な、建物の魅力アップとランニングコスト削減を両立する具体的な手法を解説していきます。 1-0.築古・小規模の賃貸オフィスビル再生では「修繕」と「更新」と「改装」を混同しない 築古・小規模の賃貸オフィスビルは、最小コストで最大の効果を狙うには「小さく直して、早く回す」が基本になります。ただ、このとき現場で、「修繕」「設備更新」「改装(リニューアル)」が混同されると、話がややこしくなりかねません。混同されて、目的・効果が取り違えられて、優先順位が決まらないと、小規模に効果的に進めることが難しくなりかねません。だから最初に、この3つの用語を切り分けて整理します。修繕:不安の芽を潰します。壊れた/劣化した部分を元の機能に戻すこと(漏水、腐食、異音、チラつき、排水詰まり、建具不良など)。築古・小規模ビルではまずこの対応の漏れをなくすことが“信用”を作ります。テナントが不安を感じるのは、「不具合が放置されないか」「止まったときに復旧できるか」です。設備更新:このコラムでは主な検討対象とはしていませんが、修繕対応では対応し切れない場合、次のステップとして検討が必要なケースも想定しておく必要があります。文字通り、設備の入替です。不具合が解消され、性能の向上も見込まれます(高効率空調、LED化、エレベーターの制御盤更新など)。いずれにしても、修繕で潰すべき不具合(漏水・臭気・排水不良・空調のムラ)について充分な検証をしないまま、設備更新に踏み込むと、結果的にまだ使えるのに買い替えるのはモッタイナイということになりかねません。改装(リニューアル):見た目や使い勝手を刷新して印象を上げます(エントランス、共用部、トイレ内装など)。うまくやれば効果的ですが、修繕対応が甘いまま改装しても、見た目だけで、不安材料は残っているということになりかねません。築古・小規模の賃貸オフィスビルで効果的な対応は、「大きく変える」ことではなく、「小さく直して、早く回す」ことです。まず優先すべきは、漏水跡、異音、チラつき、臭気、排水不良、建具の不具合といった、テナントの不安の芽を小規模の修繕で確実に潰すことです。この点がクリアされない限り、その他でどのような改善策を打ってもテナントの評価にはつながりません。改装・リニューアルを実施する場合、エントランスやトイレなど、少ない範囲で印象が変わる場所に絞り、小規模で手を打つのが現実的です。派手さより、修繕と運用の反応速度で「このビルは手当てされている」と伝わる状態を作る。これが、最小コストで最大の効果を狙う対応の基本方針になります。 1-1.設備関連の支出抑制の鍵は、継続的な保守と適切な小規模修繕対応 設備を大規模修繕したり、すべて更新するには膨大な費用がかかりますが、既存設備を丁寧に保守しつつ、適切で小規模の修繕対応を実施することで、設備自体の長寿命化を図り、大幅な修繕費用・更新投資等の設備関連の支出を先送りすることが期待できます。特に、空調設備のフィルターや熱交換器の定期的な清掃、給排水設備の定期洗浄や点検を行い、適切なタイミングで保守部品を交換することで、設備の稼働効率を高め、故障リスクを軽減することができます。事例①港区の築30年ビルの空調修繕・保守対策港区にある築30年超のオフィスビルでは、老朽化した空調設備が頻繁に故障し、夏場のトラブルが続出。そこで、フィルターの定期交換や空調ダクトの清掃を徹底したところ、年間の修理費が40%削減され、冷暖房の効率が向上しました。これにより、テナントの満足度も向上し、契約更新率が改善しました。 1-2.ポイントを絞った小規模改装(リニューアル) 建物全体の大規模リノベーションは費用負担が重いため、ポイントを絞った小規模改装(リニューアル)を行うことで、効率的にビルの印象を改善できる場合もあります。特に、エントランスや共用部など第一印象を左右する場所に、照明改善や壁・床の美装化などを適切に施せば、ビルの魅力は大幅に向上することも期待できます。事例②千代田区のオフィスビルの共用部改装千代田区の築35年のオフィスビルでは、エントランスと廊下のリニューアルを実施。床材を明るいタイルに変更し、照明をLEDに切り替えた結果、「清潔感が増し、古さを感じさせない」という声が増加。結果として新規テナント獲得率が向上しました。 1-3.小規模でも効果的な設備導入・運用改善 低予算で付加価値を提供するには、IoTを活用したスマートビル化がおすすめです。後付け型のスマートロックや照明・空調の自動制御システムを導入することで、テナントにとっての利便性や快適性を高められます。これらの設備は比較的低コストで導入でき、かつ設備管理の効率化にもつながるため、運営面でもメリットが期待できます。また、近年、テナントの関心が高まっている省エネに着目した施策も有効です、限られた資金内でも築古・小規模の賃貸オフィスビルの競争力を回復し、収益性の向上を目指すことが可能となります。 事例③渋谷区の中規模ビルでのIoT導入渋谷区にある築32年のビルでは、スマートロックシステムを導入し、テナントがスマホアプリで入退館管理を行えるようにしました。これによりセキュリティが向上し、新規入居希望者へのアピールポイントとなりました。 事例④中央区の省エネ関連小規模設備導入・運用改善事例中央区の築33年のオフィスビルでは、空調設備の適正運用とLED照明導入により、電力コストを年間15%削減。これにより、共益費の削減にもつながり、結果としてテナントの退去抑制に成功しました。 これらの実例からも分かるように、築古・小規模の賃貸オフィスビルの再生には、単なるコスト削減ではなく、設備の適正運用や小規模修繕による魅力向上が重要です。限られた予算内でも、適切な戦略を講じることで、築古ビルの資産価値を維持・向上させることが可能です。成功事例から浮かび上がるキーワードは、「付加価値」「ターゲット戦略」「運営力」です。建物のハード(物理的な質)を高めることに加え、どのテナント層にどんな価値を提供するかを明確に描き、それに沿った小規模修繕・運用改善を行うことが満室への近道となっています。 一方で、すべての築古・小規模の賃貸オフィスビル再生プロジェクトが成功するわけではないことにも注意が必要です。改装(リニューアル)に多額の費用を投じて内装を一新し、「これで賃料アップだ」と意気込んでも、肝心の入居者が集まらなければ投資回収は困難です。例えばデザイン優先で改装したものの、立地とのマッチングを十分に検証しないまま進めたので、高めに設定した賃料に見合うテナントが見つからなかったケースや、テナントのニーズを読み違えて設備投資が空回りした例も報告されています。また、築古・小規模の賃貸オフィスビル特有の課題(耐震性や法規制上の制約など)を無視して表面的な改装(リニューアル)に終始した結果、「見た目は綺麗でも安心して入居できない」と敬遠されてしまう失敗もあります。こうした事例から学ぶべきは、市場ニーズや物件の本質的課題を見極めずに闇雲に改装したとしても成果は出ないという点です。再生策を講じる際には、しっかりとした戦略とニーズ分析に基づいて計画を立てることが不可欠でしょう。 以下では、築古オフィスビルを満室稼働させるための具体的な対策をいくつかの観点から掘り下げます。成功事例のエッセンスと失敗例の教訓を踏まえつつ、費用対効果を意識した実践的な手法を紹介していきます。 第2章:満室稼働を実現する具体策 2-1.「不安」の芽を潰す適切な小規模修繕 築古の小規模ビルで空室が長引くとき、原因は「賃料」より「不安」のことが多いです。具体的には、漏水跡、共用部のガタつき、トイレの不具合、照明のムラ、空調の効きムラ、異音――このあたりが残っていると、内見の瞬間に評価が落ちます。だからまず、やるべきは、いきなり、設備更新、リノベーションに踏み切ることではなく、小規模修繕で“減点ポイント”を消すことです。小規模修繕は、費用の上振れを抑えながら、内見評価を底上げできます。築古・小規模の賃貸オフィスビル再生の第一歩は、建物の基本性能と印象を底上げするハード面の改善です。限られた予算内でも工夫次第で効果的な小規模修繕は可能です。ポイントは「コストパフォーマンスの高い箇所から優先的に手を付ける」ことです。基本設備の基盤整備:古いビルでは空調や電気設備の老朽化により室内環境が劣化していることが少なくありません。空調設備の調整やフィルター清掃、必要に応じたメンテナンスを行い、適切な温度・空気質を維持しましょう。設備(とくに空調)の性能向上はテナント満足度を高め、ビル競争力の向上につながります。内装・共用部の改装で印象をリフレッシュ(小規模な設備導入とも組合わせ):ビル内外の見た目の改善も検討課題です。第一印象を左右するエントランスやロビーは、比較的低コストな小規模な改装(リニューアル)で大きな効果が期待できます。壁や天井の塗装を明るい色調に塗り替える、床材やカーペットを新調する、照明をLED化して明るさと省エネを両立する、といった改装は定番ながら有効です。特に照明のLED化は初期費用こそかかるものの、電気代削減効果をもって数年程度で初期支出を回収できるケースも多く、長寿命化により修繕・保守頻度も減らせます。また、水回り(トイレや給湯室)の清潔感は入居検討者が重視するポイントです。古いトイレ設備を最新の節水型に交換したり、和式トイレしかない場合は洋式化したり、内装を明るく改装するだけでも印象は格段に向上します。男女別トイレの設置が難しい小規模ビルでも、小規模ながら改装(リニューアル)して、清掃を行き届かせることで「清潔で安心」なイメージを与えられます。小規模改装で費用対効果を最大化:すべてを一度に直す予算がない場合は、ポイントを絞った部分リニューアルで段階的に価値向上を図りましょう。たとえば「エントランスホールのみ先行小規模改装」「空室となっているフロアをモデルルーム化」など、支出額に対してテナント受けする効果が高い部分から着手します。費用を抑える工夫としては、既存の什器や間仕切りを活用・再配置する、レイアウト変更を伴わない模様替え中心の工事にする、安価でもデザイン性の高い建材を取り入れる、といった方法があります。また、「古さ」を逆手に取る発想も有効です。内装のレトロな雰囲気をあえて残し、ヴィンテージ風オフィスとして売り出した例もあります。天井の躯体をあらわしにしてインダストリアルデザイン風に仕上げたり、昭和レトロな外観を活かして味わいのあるクリエイティブオフィスとしてPRすることで、画一的な新築ビルにはない個性を求めるテナントを引き付けられる場合もあります。このように、低予算でも「安全性の底上げ」と「印象の刷新」を両立する小規模修繕・小規模改装を組合わせて進めることで、築古・小規模の賃貸オフィスビルのマイナスイメージを払拭し競争力を高めることができます。小さな改良の積み重ねがテナント満足度を向上させ、結果として高稼働率・賃料維持につながるのです。 2-2.テナントニーズを捉えた運営工夫と差別化戦略 ハード面の改善と並んで重要なのが、ソフト面での戦略、すなわちテナントのニーズに合った運営とサービスの提供です。ただ空間を貸すだけでは選ばれない時代だからこそ、ビル独自の付加価値を打ち出し差別化を図る必要があります。ここではテナント・ターゲットの見直しと賃貸条件・サービス面での工夫について具体策を考えてみましょう。テナントのターゲット層の再設定:築古・小規模の賃貸オフィスビルが従来想定していたテナント像(例えば近隣の中小企業向け事務所利用など)に固執していては、市場の変化に取り残される恐れがあります。成功事例にあったように、発想を転換して新たな需要層を開拓することが鍵です。昨今増えているスタートアップ企業、ITベンチャー、地方や海外から進出してくる企業など、数十年前には想定しなかったターゲットも台頭しています。彼らは大企業ほどオフィスに高い予算は割けないものの、働きやすい環境やクリエイティブな雰囲気を求めています。また、小規模でもセキュアで快適なオフィスを必要とする専門士業(士業事務所)や、リモートワーク普及で郊外勤務を希望する従業員向けのサテライトオフィス需要なども見逃せません。自ビルの立地や規模に照らし、「このビルならでは」のターゲット層を定め、その層に響く改装・サービスを考えましょう。例えば駅から距離があるビルでも駐車場があれば車移動が主なテナントを狙う、都心でエリアイメージが良くない場所ならあえてクリエイター向けに内装を個性的にしてみる、といった戦略が考えられます。ターゲットを明確に絞ることで、その層に特化した売り込みが可能になって、満室への道が見えてきます。ビルブランディングと情報発信:築古・小規模の賃貸オフィスビルを再生する際には、そのビルのコンセプトや強みを明確に打ち出すことも大切です。ただ安いというだけではなく、「○○な人たちが集まるビル」「△△な働き方ができるオフィス」といった物語性を持たせるのです。ビルのブランドを育てていく姿勢はテナントにも伝わります。具体的には、ビルの名前をリブランディングしてみるのも一案です。築年数が古いままの名前より、コンセプトに合ったネーミングやロゴを作成して刷新すれば、新規顧客の目にも留まりやすくなります。改装(リニューアル)のタイミングに合わせて内覧会イベントを開催し、当社のオウンド・メディア・サイトで紹介記事を掲載するなど、積極的な情報発信を以て「生まれ変わったビル」をアピールしましょう。最近ではリノベーション専門の不動産メディアや、テナントリーシング支援のプラットフォームもありますので、そうしたチャネルを活用して露出を増やすのも有効です。オフィス探しをしている企業だけでなく、不動産仲介業者に対しても物件のセールス・ポイントを明確に伝え、認知度を高めておくことで紹介件数アップが期待できます。テナントとのコミュニケーション向上:ソフト面の充実として忘れてはならないのが、既存テナントとの関係構築です。現在入居中のテナントの満足度を上げることは、退去防止と口コミ効果につながります。小規模ビルでは管理人が常駐しない場合も多いですが、その場合でもビル管理会社が定期的に巡回した際に、こまめにチェックして、設備不具合の対応を早める、共用部の清掃頻度を上げる、といった地道な施策がテナントの愛着を育み、長期入居や知人企業の紹介といった形で報いてくれるでしょう。「このビルの管理は信頼できる」という評判が立ち、多少古いビルでも安心して入居できるとの評価につながります。結果として空室が出ても別のテナントで埋まりやすくなり、安定稼働・賃料維持に寄与するのです。 2-3.省エネ小規模修繕・エネルギー管理の強化による付加価値創出 近年、企業の環境意識の高まりやエネルギー価格の上昇を背景に、オフィスビルの省エネルギー性能は重要な競争力の一つとなっています。ビルの省エネ性能を高めることは光熱費の削減による運営コスト低減だけでなく、「環境に配慮したオフィス」という付加価値を生み、テナント企業のイメージ向上にもつながります。ここでは、築古・小規模の賃貸オフィスビルでも実践できる省エネ・エネルギー管理強化策を考えてみましょう。照明・空調の省エネ化:オフィスビルで電力消費の大きな割合を占める照明と空調の高効率化は、省エネの要です。照明は前述の通りLED照明への更新が効果的で、消費電力を約半分程度に削減できるケースもあります。人感センサーを設置して人がいない時には自動で消灯するシステムを導入すれば、無駄な点灯を防げます。空調については、旧式の個別空調機(パッケージエアコン等)で効率が悪いものはインバーター式の省エネ型に交換する、さらに、支出額は嵩みますが、熱源機器やポンプ類の高効率型への更新や制御システムの最適化を行うことで、かなりの省エネが期待できます。また、テナントが退去したフロアなど未使用区画の空調を停止・間引き運転できるようゾーニング制御を取り入れるなど、きめ細かなエネルギー管理を行うことも重要です。ビルのエネルギー使用量を見える化する、スマートメーターやエネルギー管理システム(BEMS)を導入すれば、テナントごとの使用量を把握して省エネ意識を高めたり、ピーク電力を抑制したりといったデータに基づく運用改善が可能になります。省エネ小規模修繕の結果、CO2排出量削減や電気料金削減といった具体的数値が出れば、それ自体をビルのセールス・ポイントとして訴求できます。▪断熱性能の向上と快適性アップ:築古・小規模の賃貸オフィスビルでは、窓サッシや外壁の断熱性能が低く、外気の影響を受けやすいため空調負荷が大きくなりがちです。可能であれば窓ガラスを複層ガラスに交換したり、窓枠に後付で断熱内窓を設置することで断熱性を高められます。簡易な対策としては窓ガラスに遮熱フィルムを貼るだけでも冷房負荷を減らす効果があります。夏場の直射日光が強い開口部には外部に可動ルーバーや日よけ(オーニング)を設置し日射を遮る工夫も有効です。逆に冬場の熱損失を防ぐため、出入口に風除室やエアカーテンを設けることも検討できます。こうした断熱対応は、テナントの光熱費負担軽減につながるだけでなく、室内の温度ムラが減り快適性が向上する副次効果もあります。室温の安定したオフィスは従業員の生産性や健康にもプラスに働くため、テナント企業にとってもメリットが大きいポイントです。 2-4.スマートビル化・付加価値サービスの導入による競争力強化 テナントの要望が高度化する中、築古・小規模の賃貸オフィスビルでも、テクノロジーの力を借りて付加価値サービスを提供することが求められています。いわゆる「スマートビル」的な機能は何も最新鋭のビルだけのものではありません。近年は後付け可能なIoTソリューションやサービスプラットフォームが数多く登場しており、築古・小規模の賃貸オフィスビルでも比較的容易に導入できるようになっています。ここでは、テクノロジー活用によるサービス向上策と付加価値創出の方法を見ていきます。IoTによるビル管理の効率化と快適性向上:まず挙げられるのが、ビル管理業務へのIoT導入です。センサーやネットワークを活用して設備の稼働状況や各種環境データを収集・制御することで、旧来型のビルでも最新ビルと遜色ない管理レベルを実現できます。たとえば、水漏れセンサーや設備異常検知センサーを設置しておけば、故障やトラブルの兆候を早期に把握し対処できます。エレベーターやポンプなどの主要設備にもIoT監視を付ければ、異常時に迅速な修繕・保守対応が可能となり、サービス停止時間の短縮や事故防止による信頼性向上につながります。さらにセキュリティ面でも、顔認証やICカードによる入退館管理システムを後付け導入する例が増えています。非接触で解錠できるスマートロックやスマートセンサーライト、防犯カメラのネット連携などにより、小規模ビルでも安全・安心なスマートセキュリティ環境を整備できます。古いビルでも後付け技術でそうした環境が実現できるなら、テナントの安心感は格段に増すでしょう。テクノロジー導入の費用対効果:スマート・システムや付加価値サービスを導入する際には、その費用対効果も考慮しましょう。幸いなことに、クラウドサービスやIoT機器の普及で初期投資ゼロ~小額で始められるサービスも多くなっています。例えば入退館管理システムは、クラウド型サービスを月額課金で利用すれば高価な専用機器を買う必要がありません。スマートロックも1台数万円程度からあり、工事も簡単です。また、テナント向けのスマホアプリを提供し、ビルの設備予約(会議室予約や空調延長申請など)を便利に行えるようにするサービスもあります。自社ビル専用アプリを開発するのは費用がかかりますが、既存のプラットフォームを使えば比較的安価です。重要なのは、テナント目線で「このビルに入ると便利」と思える仕組みを一つでも増やすことです。最新ビルでは当たり前の仕組みも、築古・小規模の賃貸オフィスビルで導入すれば大きな差別化になります。それがオーナーにとっても省力化・効率化につながるものであれば一石二鳥です。例えばオンライン上でテナントからの問い合わせや工事申請を受け付ける仕組みを導入すれば、対応履歴も残り管理もしやすくなります。小規模ビルゆえに人的サービスでカバーしていたことをIT化することで、逆にきめ細かなサービス提供が可能になる分野もあるでしょう。このように、スマート技術とサービスの導入は、築古ビルに現代的な付加価値をもたらし競争力を高める有効な手段です。テクノロジーは日進月歩で進化しており、今後も新たなソリューションが生まれるでしょう。オーナーとしては常に情報収集を怠らず、自ビルにフィットしそうなサービスがあれば積極的に試してみる姿勢が大切です。大掛かりな設備投資をしなくても導入できるサービスは数多くありますので、「築古だから…」「小規模だから…」と尻込みせずチャレンジすることで、テナント満足度と稼働率アップにつなげていきましょう。 おわりに:築古・小規模の賃貸オフィスビル再生は戦略的に、そして継続的に このコラムを通じて、築古・小規模の賃貸オフィスビルが直面する苦戦の背景と、再生への具体的ヒントを述べてきました。重要なのは、単に賃料を下げる安易な道に逃げるのではなく、戦略を持ってビルの価値を高める取り組みを行うことです。幸いにも、多くの成功事例が示すように、工夫次第で築古・小規模の賃貸オフィスビルは見違えるように蘇り、テナントにとって魅力的な存在になり得ます。老朽化が進むオフィス・ストックが大量にあるということは、裏を返せば変革の余地がそれだけ大きいということです。オーナーにとってはチャレンジであると同時に、大きなチャンスとも言えるでしょう。再生策を講じる際には、まず自ビルの強み・弱み、市場環境やターゲットのニーズをしっかり分析することが出発点です。その上で、本コラムで述べたようなハード・ソフト両面の手立てを組み合わせ、自社の事情に合ったロードマップを描いてください。すべてを一度に実現する必要はありません。小さな改善を積み重ね、それをテナント募集のアピール材料として発信し、徐々に稼働率と収益性を高めていくことが現実的です。一度、満室を達成しても油断は禁物で、市場動向やテナント要望は刻々と変化します。定期的にビルの状況を見直し、新たな競合ビルの動きや技術トレンドをチェックして、常にアップデートを図る姿勢が求められます。「単なる古い・小規模なビル」だった物件が、小規模修繕・改装(リニューアル)やサービス強化の組み合わせによって「選ばれるオフィス」に進化したとき、適正賃料で高い稼働を維持し、資産価値も向上する好循環が生まれます。築古・小規模の賃貸オフィスビルが持つポテンシャルを引き出し、テナントにとってもオーナーにとってもWin-Winとなる再生を実現するために、本コラムのヒントがお役に立てば幸いです。築古・小規模の賃貸オフィスビル再生の成功例が増えれば、賃貸オフィス・マーケット全体の活性化にもつながります。老朽化ストックが多い日本の賃貸オフィス市場において、一つひとつのビルが再生への一歩を踏み出すことで、新築偏重ではない持続可能な発展が期待できるでしょう。ぜひ、専門家の知見や周囲の協力も得ながら、ビジネスライクかつ柔軟な発想で築古・小規模の賃貸オフィスビルの再生にチャレンジしてみてください。満室稼働のその先に、ビル・オーナーとテナント双方の明るい未来が拓けるはずです。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 飯野 仁 東京大学経済学部を卒業 日本興業銀行(現みずほ銀行)で市場・リスク・資産運用業務に携わり、外資系運用会社2社を経て、プライム上場企業で執行役員。 年金総合研究センター研究員も歴任。証券アナリスト協会検定会員。 2026年2月17日執筆2026年02月17日 -
貸ビル・貸事務所
高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所の特徴と賃料相場|不動産会社が解説
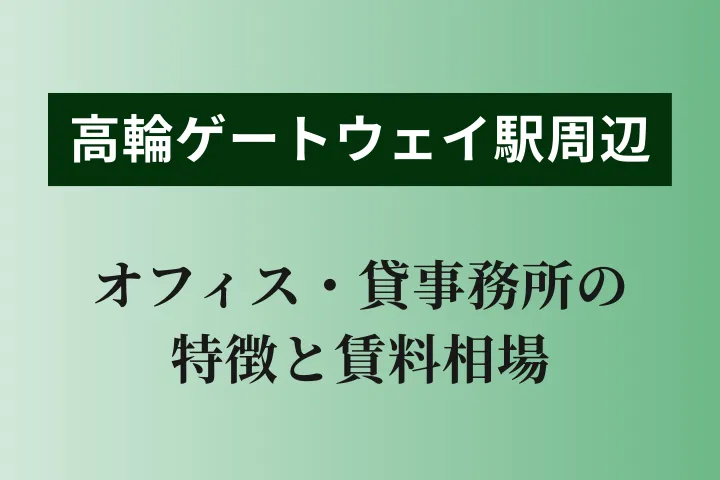 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月16日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次高輪ゲートウェイ駅周辺の特徴とトレンド高輪ゲートウェイ駅周辺の入居企業の傾向高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場高輪ゲートウェイ駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 高輪ゲートウェイ駅周辺の特徴とトレンド 輪ゲートウェイ駅は、JR山手線・京浜東北線が利用可能な駅として2020年に開業しました。品川駅と田町駅の間に位置し、高輪ゲートウェイ駅から品川駅へは徒歩でのアクセスも可能です。また、泉岳寺駅(都営浅草線・京急本線)も徒歩圏内にあり、都内主要エリアに加えて羽田空港方面へのアクセスにも優れた立地です。東京駅・新橋駅へは山手線で直通、品川駅を経由することで新幹線利用もしやすく、首都圏内外の移動を前提とする企業にとって交通利便性の高いエリアといえます。駅周辺は、従来は大規模なオフィス街というよりも、品川駅周辺の業務エリアと高輪・芝浦エリアの中間的な位置付けでした。しかし近年は、品川駅北側を中心に、JR東日本主導による「高輪ゲートウェイシティ」構想に基づく大規模再開発が進行しており、高輪ゲートウェイ駅前では、最新仕様のオフィスビルや商業施設、業務支援機能を備えた複合施設の整備が段階的に進められています。これにより、エリア全体としては、国際性や先進性を意識した「新たなビジネス拠点」としての性格が、徐々に形成されつつある段階にあります。周辺環境としては、現時点では品川駅側にかけて飲食店や金融機関、コンビニエンスストアなどが集積しており、オフィスワーカーの日常利用に大きな支障はありません。一方で、高輪ゲートウェイ駅単体では商業集積がまだ限定的であるため、実務上は品川駅周辺と一体で捉えて検討する企業が多い印象です。今後は、再開発の進展に伴い、業務・商業・交流機能を併せ持つ街へと段階的に成熟していくことが期待されています。 高輪ゲートウェイ駅周辺の入居企業の傾向 高輪ゲートウェイ駅周辺では、従来から品川エリアに拠点を構えてきた大手企業の関連部門や、支店・プロジェクトオフィスといった用途での利用が一定数見られます。業種としては、製造業の本社・技術部門、商社、物流関連、IT・通信系企業などの利用が見られます。近年は、再開発エリア内の新築・大型オフィスを中心に、研究開発機能を重視する企業や、複数拠点を持つ企業のサテライトオフィス需要も見られるようになっています。また、スタートアップや新規事業部門が入居するケースもあり、従来の品川エリアに比べると、やや実証実験型・先進志向のコンセプトを打ち出した街づくりが進められている点が特徴です。このエリアが選ばれる理由としては、品川駅至近という交通利便性の高さ再開発に伴う新築・高機能オフィスの供給都心主要エリアと湾岸エリアの中間に位置する立地バランスといった点が挙げられます。一方で、賃料水準は周辺エリアと比較して高めに推移しており、企業規模や利用目的を明確にした上で検討されるケースが多いのが実情です。 高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 高輪ゲートウェイ周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約11,000円-50~100坪約14,000円-100~200坪約16,000円-200坪以上-- ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※再開発エリア内のビル、飛び抜けて[涼藤1.1]安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 高輪ゲートウェイ駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 T323プレイスビル住所:港区高輪3丁目2番3号GoogleMapsで見る階/号室:401号室坪単価:応相談面 積:41.69坪入居日:即日 詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 高輪ゲートウェイ駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、高輪ゲートウェイ駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月16日執筆2026年02月16日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月16日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次高輪ゲートウェイ駅周辺の特徴とトレンド高輪ゲートウェイ駅周辺の入居企業の傾向高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場高輪ゲートウェイ駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 高輪ゲートウェイ駅周辺の特徴とトレンド 輪ゲートウェイ駅は、JR山手線・京浜東北線が利用可能な駅として2020年に開業しました。品川駅と田町駅の間に位置し、高輪ゲートウェイ駅から品川駅へは徒歩でのアクセスも可能です。また、泉岳寺駅(都営浅草線・京急本線)も徒歩圏内にあり、都内主要エリアに加えて羽田空港方面へのアクセスにも優れた立地です。東京駅・新橋駅へは山手線で直通、品川駅を経由することで新幹線利用もしやすく、首都圏内外の移動を前提とする企業にとって交通利便性の高いエリアといえます。駅周辺は、従来は大規模なオフィス街というよりも、品川駅周辺の業務エリアと高輪・芝浦エリアの中間的な位置付けでした。しかし近年は、品川駅北側を中心に、JR東日本主導による「高輪ゲートウェイシティ」構想に基づく大規模再開発が進行しており、高輪ゲートウェイ駅前では、最新仕様のオフィスビルや商業施設、業務支援機能を備えた複合施設の整備が段階的に進められています。これにより、エリア全体としては、国際性や先進性を意識した「新たなビジネス拠点」としての性格が、徐々に形成されつつある段階にあります。周辺環境としては、現時点では品川駅側にかけて飲食店や金融機関、コンビニエンスストアなどが集積しており、オフィスワーカーの日常利用に大きな支障はありません。一方で、高輪ゲートウェイ駅単体では商業集積がまだ限定的であるため、実務上は品川駅周辺と一体で捉えて検討する企業が多い印象です。今後は、再開発の進展に伴い、業務・商業・交流機能を併せ持つ街へと段階的に成熟していくことが期待されています。 高輪ゲートウェイ駅周辺の入居企業の傾向 高輪ゲートウェイ駅周辺では、従来から品川エリアに拠点を構えてきた大手企業の関連部門や、支店・プロジェクトオフィスといった用途での利用が一定数見られます。業種としては、製造業の本社・技術部門、商社、物流関連、IT・通信系企業などの利用が見られます。近年は、再開発エリア内の新築・大型オフィスを中心に、研究開発機能を重視する企業や、複数拠点を持つ企業のサテライトオフィス需要も見られるようになっています。また、スタートアップや新規事業部門が入居するケースもあり、従来の品川エリアに比べると、やや実証実験型・先進志向のコンセプトを打ち出した街づくりが進められている点が特徴です。このエリアが選ばれる理由としては、品川駅至近という交通利便性の高さ再開発に伴う新築・高機能オフィスの供給都心主要エリアと湾岸エリアの中間に位置する立地バランスといった点が挙げられます。一方で、賃料水準は周辺エリアと比較して高めに推移しており、企業規模や利用目的を明確にした上で検討されるケースが多いのが実情です。 高輪ゲートウェイ駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 高輪ゲートウェイ周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約11,000円-50~100坪約14,000円-100~200坪約16,000円-200坪以上-- ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※再開発エリア内のビル、飛び抜けて[涼藤1.1]安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 高輪ゲートウェイ駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 T323プレイスビル住所:港区高輪3丁目2番3号GoogleMapsで見る階/号室:401号室坪単価:応相談面 積:41.69坪入居日:即日 詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 高輪ゲートウェイ駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、高輪ゲートウェイ駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月16日執筆2026年02月16日 -
貸ビル・貸事務所
錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所の特徴と賃料相場|不動産会社が解説
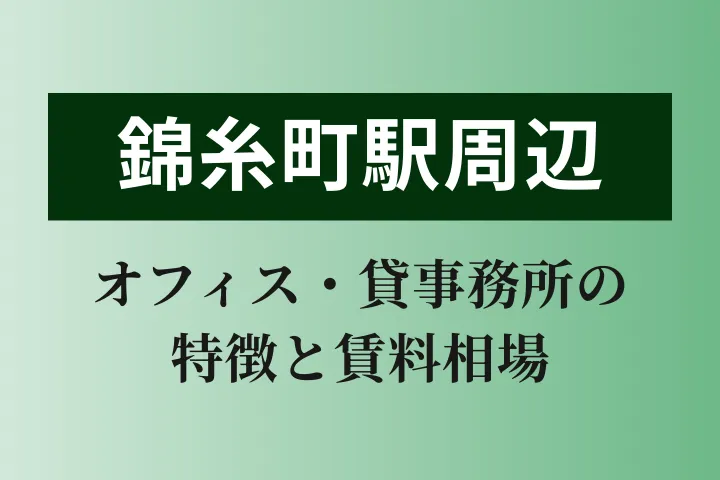 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月13日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次錦糸町駅周辺の特徴とトレンド錦糸町駅周辺の入居企業の傾向錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場錦糸町駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 錦糸町駅周辺の特徴とトレンド 錦糸町駅は、JR総武線(快速・各駅停車)と東京メトロ半蔵門線が乗り入れるターミナル性のある駅です。JR総武快速線を利用すれば東京駅へ約8分、半蔵門線では大手町・渋谷方面へ直通でアクセスでき、都心主要エリアとの接続性に優れています。徒歩圏内で複数路線を利用できる駅はありませんが、駅自体の交通利便性が高く、城東エリアの業務拠点として一定の評価を得ています。駅南口から北口にかけては、古くから商業と業務機能が混在して発展してきたエリアで、中小規模のオフィスビルや雑居ビルが連続的に集積しています。大規模なオフィス街というよりは、1フロア20~100坪前後の貸事務所が多く、企業規模に応じた柔軟な物件選定がしやすい点が特徴です。周辺環境としては、銀行・信用金庫、郵便局などの金融機関が駅周辺に揃っており、法人利用に必要なインフラは一通り整っています。また、飲食店の選択肢が非常に多く、ランチ・打ち合わせ・来客対応のいずれにも対応しやすい点は、オフィス利用者にとって実務面での利便性につながっています。近年は、駅周辺での再開発や大型商業施設のリニューアルにより、街全体の回遊性やイメージが徐々に更新されています。都心副都心と比べると落ち着いた業務環境を保ちつつ、利便性を維持している点が、引き続き評価されているエリアといえます。 錦糸町駅周辺の入居企業の傾向 錦糸町駅周辺には、従来から卸売業、製造業の営業拠点、建設・設備関連企業、各種士業事務所などが多く入居しています。特に、城東・千葉方面に取引先や現場を持つ企業にとっては、地理的なバランスの良さが選定理由となるケースが見られます。近年では、IT関連の受託開発会社、Web制作、コールセンター機能を持つ企業など、比較的フットワークを重視する業種の入居も増加傾向にあります。都心主要エリアほどの賃料負担を避けつつ、採用や通勤の利便性を確保したい企業にとって、検討対象に入りやすい立地といえます。このエリアが選ばれる背景としては、第一に都心直結の交通利便性、第二に23区内としては比較的抑えられた賃料水準、第三に商業地としての賑わいと実務的な街の雰囲気が挙げられます。過度にビジネス色が強すぎない点を評価する企業も一定数存在します。 錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 錦糸町周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約10,000円約18,000円50~100坪約15,000円約20,000円100~200坪約16,000円約20,000円200坪以上-- ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※飛び抜けて安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 錦糸町駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 協新ビルジング住所:墨田区江東橋4丁目24番5号 GoogleMapsで見る階/号室:402号室坪単価:応相談面 積:23.95坪入居日:2026年3月6日詳細はこちら MYSビル住所:墨田区両国4丁目8番10号GoogleMapsで見る階/号室:302号室坪単価:応相談面 積:26.60坪入居日:2026年5月1日詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 錦糸町駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、錦糸町駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月13日執筆2026年02月13日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月13日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次錦糸町駅周辺の特徴とトレンド錦糸町駅周辺の入居企業の傾向錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場錦糸町駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 錦糸町駅周辺の特徴とトレンド 錦糸町駅は、JR総武線(快速・各駅停車)と東京メトロ半蔵門線が乗り入れるターミナル性のある駅です。JR総武快速線を利用すれば東京駅へ約8分、半蔵門線では大手町・渋谷方面へ直通でアクセスでき、都心主要エリアとの接続性に優れています。徒歩圏内で複数路線を利用できる駅はありませんが、駅自体の交通利便性が高く、城東エリアの業務拠点として一定の評価を得ています。駅南口から北口にかけては、古くから商業と業務機能が混在して発展してきたエリアで、中小規模のオフィスビルや雑居ビルが連続的に集積しています。大規模なオフィス街というよりは、1フロア20~100坪前後の貸事務所が多く、企業規模に応じた柔軟な物件選定がしやすい点が特徴です。周辺環境としては、銀行・信用金庫、郵便局などの金融機関が駅周辺に揃っており、法人利用に必要なインフラは一通り整っています。また、飲食店の選択肢が非常に多く、ランチ・打ち合わせ・来客対応のいずれにも対応しやすい点は、オフィス利用者にとって実務面での利便性につながっています。近年は、駅周辺での再開発や大型商業施設のリニューアルにより、街全体の回遊性やイメージが徐々に更新されています。都心副都心と比べると落ち着いた業務環境を保ちつつ、利便性を維持している点が、引き続き評価されているエリアといえます。 錦糸町駅周辺の入居企業の傾向 錦糸町駅周辺には、従来から卸売業、製造業の営業拠点、建設・設備関連企業、各種士業事務所などが多く入居しています。特に、城東・千葉方面に取引先や現場を持つ企業にとっては、地理的なバランスの良さが選定理由となるケースが見られます。近年では、IT関連の受託開発会社、Web制作、コールセンター機能を持つ企業など、比較的フットワークを重視する業種の入居も増加傾向にあります。都心主要エリアほどの賃料負担を避けつつ、採用や通勤の利便性を確保したい企業にとって、検討対象に入りやすい立地といえます。このエリアが選ばれる背景としては、第一に都心直結の交通利便性、第二に23区内としては比較的抑えられた賃料水準、第三に商業地としての賑わいと実務的な街の雰囲気が挙げられます。過度にビジネス色が強すぎない点を評価する企業も一定数存在します。 錦糸町駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 錦糸町周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約10,000円約18,000円50~100坪約15,000円約20,000円100~200坪約16,000円約20,000円200坪以上-- ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※飛び抜けて安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 錦糸町駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 協新ビルジング住所:墨田区江東橋4丁目24番5号 GoogleMapsで見る階/号室:402号室坪単価:応相談面 積:23.95坪入居日:2026年3月6日詳細はこちら MYSビル住所:墨田区両国4丁目8番10号GoogleMapsで見る階/号室:302号室坪単価:応相談面 積:26.60坪入居日:2026年5月1日詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 錦糸町駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、錦糸町駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月13日執筆2026年02月13日 -
貸ビル・貸事務所
三田駅周辺のオフィス・貸事務所の特徴と賃料相場|不動産会社が解説
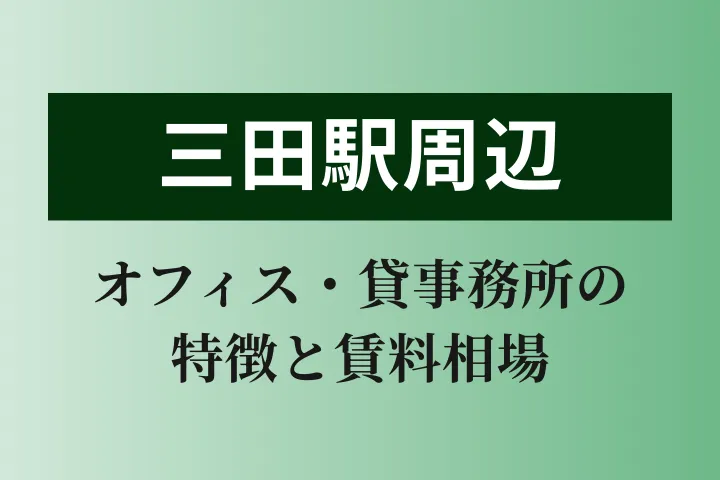 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は三田駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月12日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次三田駅周辺の特徴とトレンド三田駅周辺の入居企業の傾向三田駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場三田駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 三田駅周辺の特徴とトレンド 三田駅は、都営浅草線・都営三田線の2路線が乗り入れる交通拠点です。加えて、徒歩圏内にはJR山手線・京浜東北線が利用可能な田町駅が位置しており、複数路線を使い分けられる利便性の高いエリアといえます。品川・東京・新橋といった都心主要エリアへのアクセスが良好で、都内外からの通勤動線を確保しやすい立地です。三田・田町エリアは、古くから企業の本社機能や支店、関連会社が集積してきた業務エリアとしての歴史があります。特に第一京浜(国道15号)や桜田通り沿いを中心に、中規模から大規模のオフィスビルが立ち並び、計画的に形成されたオフィス街という性格が強い地域です。周辺には銀行支店や郵便局、会議利用が可能な施設が点在しており、日常的な業務を行ううえでの利便性は整っています。また、飲食店もランチ需要を意識した店舗が多い一方で、仕事帰りに立ち寄れる飲食店も多くあり、ビジネスパーソンにとって使い勝手の良い環境が形成されています。近年では、JR田町駅を中心に再開発が進行し、周辺エリア全体としてオフィス機能の更新が進んでいます。三田駅周辺は、再開発エリアに隣接しつつも比較的落ち着いた街並みを維持しており、「都心近接かつ安定感のある業務エリア」として位置付けられています。 三田駅周辺の入居企業の傾向 三田駅周辺では、従来から製造業の本社・支店、商社、卸売業、各種士業事務所などが多く見られます。特に、長年同エリアで事業を継続している大企業が一定数存在し、入居期間が比較的長い傾向がある点は特徴の一つです。近年では、IT関連企業やコンサルティング会社、外資系企業の日本拠点なども徐々に増加しています。六本木・赤坂・大手町といった主要ビジネスエリアへのアクセス性を評価しつつ、賃料水準を抑えたい企業にとって検討対象となりやすい立地といえます。このエリアが選ばれる理由としては、以下の点が挙げられます。複数路線が利用可能で、都心主要エリアへの移動がしやすい交通利便性港区内では比較的落ち着いた賃料水準業務エリアとしての成熟度が高く、周辺環境の安定感があること華やかさや新規性を重視するエリアというよりは、実務を重視する企業に適した街の雰囲気が支持されている印象です。 三田駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 三田周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約12,000円約20,000円50~100坪約15,000円約22,000円100~200坪約18,000円約24,000円200坪以上約25,000円約35,000円 ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※飛び抜けて安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 三田駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 FBR三田ビル住所:港区三田4丁目1番27号GoogleMapsで見る階/号室:9階坪単価:応相談面 積:103.82坪入居日:2026年12月3日詳細はこちら T323プレイスビル住所:港区高輪3丁目2番3号GoogleMapsで見る階/号室:401号室坪単価:応相談面 積:41.69坪入居日:即日詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 三田駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、三田駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月12日執筆2026年02月12日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの藤岡です。この記事は三田駅周辺のオフィス・貸事務所賃料相場についてまとめたもので、2026年2月12日に執筆しています。少しでも皆さんのお役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次三田駅周辺の特徴とトレンド三田駅周辺の入居企業の傾向三田駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場三田駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 三田駅周辺の特徴とトレンド 三田駅は、都営浅草線・都営三田線の2路線が乗り入れる交通拠点です。加えて、徒歩圏内にはJR山手線・京浜東北線が利用可能な田町駅が位置しており、複数路線を使い分けられる利便性の高いエリアといえます。品川・東京・新橋といった都心主要エリアへのアクセスが良好で、都内外からの通勤動線を確保しやすい立地です。三田・田町エリアは、古くから企業の本社機能や支店、関連会社が集積してきた業務エリアとしての歴史があります。特に第一京浜(国道15号)や桜田通り沿いを中心に、中規模から大規模のオフィスビルが立ち並び、計画的に形成されたオフィス街という性格が強い地域です。周辺には銀行支店や郵便局、会議利用が可能な施設が点在しており、日常的な業務を行ううえでの利便性は整っています。また、飲食店もランチ需要を意識した店舗が多い一方で、仕事帰りに立ち寄れる飲食店も多くあり、ビジネスパーソンにとって使い勝手の良い環境が形成されています。近年では、JR田町駅を中心に再開発が進行し、周辺エリア全体としてオフィス機能の更新が進んでいます。三田駅周辺は、再開発エリアに隣接しつつも比較的落ち着いた街並みを維持しており、「都心近接かつ安定感のある業務エリア」として位置付けられています。 三田駅周辺の入居企業の傾向 三田駅周辺では、従来から製造業の本社・支店、商社、卸売業、各種士業事務所などが多く見られます。特に、長年同エリアで事業を継続している大企業が一定数存在し、入居期間が比較的長い傾向がある点は特徴の一つです。近年では、IT関連企業やコンサルティング会社、外資系企業の日本拠点なども徐々に増加しています。六本木・赤坂・大手町といった主要ビジネスエリアへのアクセス性を評価しつつ、賃料水準を抑えたい企業にとって検討対象となりやすい立地といえます。このエリアが選ばれる理由としては、以下の点が挙げられます。複数路線が利用可能で、都心主要エリアへの移動がしやすい交通利便性港区内では比較的落ち着いた賃料水準業務エリアとしての成熟度が高く、周辺環境の安定感があること華やかさや新規性を重視するエリアというよりは、実務を重視する企業に適した街の雰囲気が支持されている印象です。 三田駅周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場 三田周辺のオフィス・貸事務所の賃料相場は次の通りです。面積賃料下限賃料上限20~50坪約12,000円約20,000円50~100坪約15,000円約22,000円100~200坪約18,000円約24,000円200坪以上約25,000円約35,000円 ※募集物件のデータが少ない場合は空欄としています。※法人登記できる実際のオフィスのみを対象としており、バーチャルオフィスは含めていません。※調査は当社が把握している物件情報を対象としておりますが、把握していない物件もあることから正確性を担保するものではありません。※賃料はおおよその目安として掲載しております。賃料下限の物件は、築年数が古く設備も古いケースが多い傾向があります。※飛び抜けて安い、あるいは飛びぬけて高いハイグレード物件の情報は省いています。 三田駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所の一例 FBR三田ビル住所:港区三田4丁目1番27号GoogleMapsで見る階/号室:9階坪単価:応相談面 積:103.82坪入居日:2026年12月3日詳細はこちら T323プレイスビル住所:港区高輪3丁目2番3号GoogleMapsで見る階/号室:401号室坪単価:応相談面 積:41.69坪入居日:即日詳細はこちら ご希望条件をお伝えいただければ、当社の担当よりオフィス・貸事務所のご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 物件の無料提案を依頼してみる 三田駅周辺で募集中のオフィス・貸事務所をお探しの企業様、三田駅周辺で安定したビル経営を望まれているビルオーナー様は、こちらよりお気軽にご相談ください。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 藤岡 涼 入社以来20年以上にわたり、東京23区のオフィスビルを中心にプロパティマネジメント・リーシング・建物管理を担当。 年間多数の交渉やトラブル対応経験を活かし、現場目線に立った迅速かつ的確な提案を通じて、オーナー様とテナント様双方の満足度向上に努めています。 2026年2月12日執筆2026年02月12日 -
ビルメンテナンス
不動産管理費とは?方法やコスト削減の秘訣を現役ビルメンが紹介
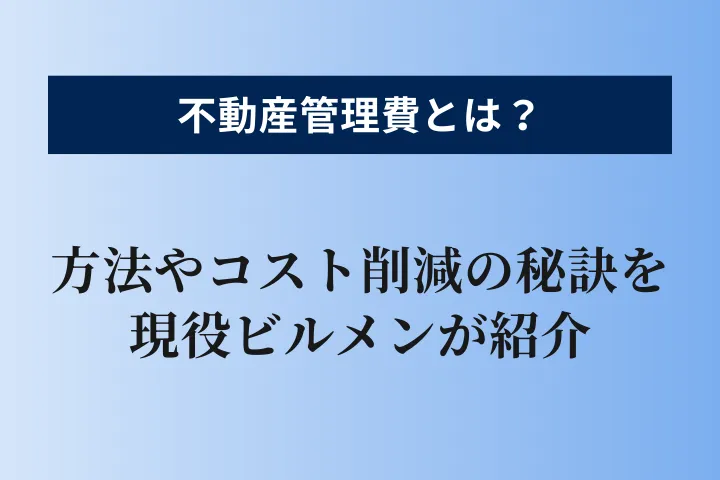 皆さんこんにちは。株式会社スペースライブラリの羽部です。この記事は不動産管理の基礎知識から、管理会社に依頼する際の手順や注意点、コスト削減のポイントなどを詳しくまとめたもので、2026年2月10日に改訂しています。主に不動産オーナーに向けた内容となり、対象の不動産は「賃貸住宅」「オフィス」「商業施設」「物流施設」と幅広く、初めて不動産事業に携わる方でもわかるよう、通常は説明を省略するような部分についても、できる限り丁寧に説明します。特に昨今の物価上昇によるコストアップは不動産管理の分野でも見られますので、そのような状況でどのように対応すべきか、商品サービスの事例などについても言及します。すでに豊富な実務経験をお持ちの方におきましては、冗長に感じられた場合は恐縮でございますが、皆さまのご参考としてご覧いただければ幸いです。 目次第1章:不動産管理費とは?第2章:不動産管理の方法と管理会社の役割第3章:管理会社に委託する場合の手順と注意点第4章:不動産管理費のコスト削減の秘訣第5章:管理仕様を設定する方法第6章:不動産管理会社の品質を把握する方法第7章:ビルメンテナンス会社の例第8章:不動産理論・法律における管理費まとめ:最適な不動産管理で資産価値を守る 第1章:不動産管理費とは? 不動産管理費とは、文字通り「不動産を管理するために必要となる費用・ビルメンテナンス費用」の総称です。具体的には、以下のような業務を遂行する上で発生する費用が含まれます。なお、2項で言及する不動産管理会社の広義の業務内容に含まれる運営管理(PM:プロパティマネジメント)や資産管理(AM:アセットマネジメント)はそれぞれ専門の委託先が存在しており、その費用に関する説明は、それぞれ個別記事にて説明させて頂きます。建物・設備の保守点検費用エレベーターや空調設備、消防設備などの定期点検費用、修繕費用などが該当します。清掃費用共用部・外部・駐車場など、定期的に清掃を行うための費用です。警備費用警備員の配置や、防犯カメラ管理、セキュリティシステムの維持に関する費用です。管理人や事務スタッフの人件費管理人(管理員)の常駐費用や、事務的な手続き(家賃の督促やクレーム対応など)にかかる人件費。事務業務まで外注していれば費用を明確に認識できますが、管理業務を委託する場合でも所有者側で事務業務を負担する場合もあるので、その点を把握するような工夫が必要です。設備更新・修繕積立金経年劣化に応じた設備更新や、大規模改修工事の資金をプールするための積立金が含まれることもあります。区分所有建物と完全所有権建物区分所有建物では管理組合を運営するための事務費用(事務員や理事の報酬・会計処理・印刷・郵送費など)や、集会場・理事会や総会の開催に関わる経費などが含まれることがあります。これらは管理組合の運営方法により費用水準も異なり、建物管理以外の費用を含むので本稿では対象外とします。 【用語の定義】 不動産管理費とは通常、不動産所有者が建物(不動産)を管理するために必要な費用です。これはテナントが負担する管理費や共益費で賄う部分もあれば、建物所有者が負担しても、テナントに転嫁しない部分もあります。同じ用途の建物であっても、テナントが負担する管理費(共益費として負担するものを含む)に法令による定めや一律のルールはないため、不動産による異なる金額水準というだけでなく、そもそもの管理業務内容が異なります。更に賃貸オフィスなどで管理費を含む賃料も見られるため、一般のユーザーや新規の不動産所有者にはわかりづらい印象を持たれるかもしれません。この点について、どのように区分するかは不動産所有者の経営方針となりますので、それらを踏まえた運営方針を検討頂くため、関係する情報を含め説明して参りますが、特に断りない場合は不動産所有者が管理業務を外部に委託する場合の管理費について記述します。 第2章:不動産管理の方法と管理会社の役割 2-1.管理会社に委託するメリット 不動産オーナーが自前ですべての管理業務を行うことは、知識や人材・時間の面で非常に大きな負担となります。管理会社に委託することで、以下のようなメリットがあります。専門的なノウハウ・人材の活用設備の保守点検、清掃や警備など、専門知識や経験が必要な業務をまとめて委託できる。コスト管理の簡略化複数の業者を一社で取りまとめてくれるため、業者への発注や支払いの手間を削減できる。クレーム対応や入居者対応の負荷軽減賃貸住宅であれば入居者からの苦情・問い合わせ、商業施設やオフィスならテナントからの要望対応などを管理会社が担ってくれる。デメリットメリットの裏返しとなりますが、不動産に対する専門的な知見の蓄積や不動産管理を担当する社内人材の確保などが困難となります。また、管理会社次第ではありますが、細かいコスト管理が困難となる、管理会社を切替した場合に運営管理サービス水準が変わる可能性があり、入居者・テナントに対する対応などで混乱を招く懸念があるなど、すみやかに気付けば対応できる部分もありますが、発見できない場合はトラブルに発展するリスクもありますので、これらの部分について随時チェックするなど、定期的な確認・配慮は不可欠です。 2-2.管理会社の主な業務内容 建物管理(BM:ビルメンテナンス)日常清掃・定期清掃、設備点検、修繕対応、警備業務など。運営管理(PM:プロパティマネジメント)賃料回収・送金、テナントリレーション、クレーム対応、契約更新手続きなど。資産管理(AM:アセットマネジメント)建物の長期修繕計画の立案、不動産価値の維持向上施策の提案など、より資産価値にフォーカスした業務。一般的にはBM建物管理業務のみを委託するのが一般的です。但し、オーナーと管理会社の契約範囲によっては、AM業務まで包括的に行うケースもあれば、BMやPMのみを部分的に委託するケースもあります。従前、PM運営管理やAM資産管理は不動産所有者側で行う不動産が多く見られたため、不動産管理会社といえばBMのみを行うことが一般的でしたが、近年、不動産証券化などで運営される不動産が増加する市場環境において、不動産運営は高度化・専門化され、PM、AMなどの業務を含めて委託される不動産が増加しつつあります。但し、PM、AMなどの運営方式は狭義の不動産管理業務の対象外となるため、本稿では概略にとどめ、BMビルメンテナンス業務について説明を行います。 2-3.設備メーカー等によるメンテナンスと独立系メンテナンス会社の違い ビルメンテナンスを設備メーカーに委託するケースが多いのは、設備の専門知識や独自技術が求められ、保守点検や部品交換などをメーカーが一括して請け負いやすいという理由が大きいです。特に下記のような設備についてはメーカー独自の技術・ノウハウまた部品等が必要となる場合が多く、メーカー以外の保守業者が参入しにくい(あるいはそもそも選択肢が少ない)といえます。 ①メーカーに委託することが一般的・標準的な理由専門性・独自技術の高さ設備によっては独自の制御システムやソフトウェアが組み込まれており、メーカー以外が対応するにはノウハウが不足しやすい。メーカーがマニュアルや設計図書を独占的に保持しているケースもある。純正部品の供給・交換が容易メーカーによる純正部品の在庫確保や交換体制が整っているため、迅速かつ適切な修理が期待できる。部品が専用品の場合、メーカー以外の業者では調達が難しく、コストや工期が増加する懸念がある。保証や契約上のメリットメーカー保守契約を結ぶことで、長期保証やサービスパッケージ割引などの優遇がある場合が多い。更新工事やリニューアル時にも、同一メーカーとの付き合いがあるとスムーズに進めやすい。トラブル対応・緊急時のサポート体制遠隔監視システムや24時間対応コールセンターなど、メーカー独自のサポート体制が確立されていることが多い。大規模トラブル時にはメーカーのエンジニアが速やかに現地対応できるネットワークがある。特に故障部材の手配はメーカー以外だと時間がかかる場合もあります。権利関係・安全面の理由建築基準法や消防法などに関連する設備(特にエレベーター、エスカレーターなど)は法定点検が義務付けられており、メーカーに保守を委託することで安全基準を満たすための手続きや書類作成がスムーズになる。ソフトウェアや制御システムに関する知的財産権の都合で、メーカー以外が介入すると契約違反や保証対象外となるケースがある。 ②メーカー以外の選択肢が少ない建物設備の例エレベーター・エスカレーターエレベーター(三菱電機、日立、東芝、オーチスなど)やエスカレーターも同様。法定点検・法令基準を満たすための確かな技術力が必要。制御装置・センサー部分がメーカー独自仕様で、外部業者が手を入れにくい。部品交換はメーカー調達が基本となるため、他業者が対応するとコスト面・納期面で不利になりやすい。大規模空調システム・パッケージエアコン(ビル用マルチエアコンなど)ダイキン、日立、東芝、三菱電機などが製造するビル用空調システム。各社が独自の制御プログラムや配管方式、冷媒制御などを採用しており、故障診断もメーカー専用ソフトを使用することが多い。修理には純正部品・特定知識が不可欠で、メーカー系サービス会社を経由しないと入手できる部品もある。中央監視システム・ビル管理システム(BAS:Building Automation System)ビル全体の空調・照明・セキュリティ・防災などを一元的に制御するシステム(オムロン、ヤマト、アズビル、Johnson Controlsなど)。システム全体がソフトウェアと連携しており、メーカー独自のプロトコル(通信規格)を用いることが多い。外部からのカスタマイズや改修が難しく、メーカーに専用ツールやライセンスがある場合が多い。特殊設備(無停電電源装置(UPS)、大型ボイラー、非常用発電機など)特殊メーカー製の大型UPSや非常用発電機など。特殊部品や法定検査を伴い、メーカーかメーカー代理店での点検がほぼ必須。不具合時の原因究明や修理にも高度な専門知識・部品が必要になる。その他(高性能セキュリティ機器、特殊扉など)たとえば、自動ドア(高性能センサー付き)、特注の防火シャッター、防音・防振設備なども、メーカー以外が対応しづらい場合が多い。 ③独立系メンテナンス会社に委託する場合の注意点部品調達ノウハウや専門資格を持った技術者の有無保証や緊急時の対応近年は一部メーカー製品について外部業者が対応可能なケースも増えているため、コストやサービス品質を比較検討する際は、代替手段がないかどうかを確認することも重要です。 2-4.管理会社の料金体系 一般的なBM管理業務を主体とする上場企業の日本管財(現:日本管財グループ/ホールディングス体制)の2023年度3月期決算短信の損益計算書によると売上高700億円に対する役務提供売上原価554億円とあり、売上の79%が人件費です。すなわち、管理会社の売上は人的サービスが規定しており、委託業務の料金はその業務に必要な人件費で定まる、ということを示しています。昨今、不動産管理業界でもDX化の導入を進めていますが、数値的な部分では不動産管理業務は人的サービス商品となります。個々の業務に必要な人的サービスは常に一定でなく、変動があるため、価格の見積は発注者からはわかりづらい部分もあります。管理会社は標準的な業務量や費用テーブルを構築し、それをもとに料金設定をしてあり、料金を算定する場合、当該業務に必要な時間×当該業務に必要なスタッフの時間単価×一定乗率で算出しています。当該業務に必要な時間は仕様で定めることができます。スタッフの時間単価は仕事の質に比例します。一定乗率は会社の定めなので個々の会社ごとに異なります。発注に際しては、料金÷業務時間により時間単価×一定乗率が求められますので、この部分を比較すれば業務品質の目安の評価が可能と思われます。 第3章:管理会社に委託する場合の手順と注意点 ここでは、不動産オーナーが初めて管理業務を委託する流れを、できるだけわかりやすく解説します。本章はあくまで全体の手順を掴んで頂くための説明なので、詳細な手順について後段で説明します。 3-1.委託範囲の明確化 まずは「どこまで管理会社に任せたいのか」を明確にしましょう。以下のように大きく分けて考えると整理しやすいです。BM(ビルメンテナンス)業務のみ委託:清掃や設備保守点検、警備などPM(プロパティマネジメント)業務も含めて委託:BMに加え、家賃回収やテナント対応など運営管理も任せるAM(アセットマネジメント)まで包括委託:BM・PMに加え、不動産価値向上策の立案・実行まで含む 3-2.複数社への見積もり依頼 管理会社はそれぞれ得意分野やコスト構造が異なります。必ず複数社に声をかけ、業務範囲・管理費・実績・対応力などを比較しましょう。管理仕様:適切な管理仕様を指定できるようであれば仕様を定めた形で見積依頼を行うが、仕様について不明な部分があれば管理会社の提案を受ける形とすることも可能業務範囲:規定した仕様で具体的にどこまでやってもらえるのか、数量的な目安を確認することで比較が可能となります見積もりの内訳:清掃費、設備点検費、警備費、人件費など、それぞれの業務ごとに金額が明確か管理実績:対象とする不動産タイプ(賃貸住宅、オフィス、商業施設、物流施設など)の管理実績はどの程度か緊急対応:24時間365日体制で対応可能か、または対応の方法を持っているか 3-3.管理仕様を決める 管理会社を選定したら、実際にどのような仕様で管理してもらうのかを詰めていきます。以下概略を述べますが、詳細は後述の第5章を参照して下さい。清掃回数・実施場所例)エントランスは毎日、駐車場は週1回、廊下は週2回など個別に頻度を設定する場合と、作業時間を決めて日単位・週単位・月単位・年単位などで何をするかを明確にするなど様々なバリエーションと工夫がある設備点検の頻度法定点検だけでなく、予防保守をどこまで行うか報告・連絡の頻度毎月レポートなのか、四半期ごとなのか、必要に応じてリアルタイムで連絡するのか、報告手順として資料の送付のみか、対面での説明はあるか、など具体的な報告方法について予め確認する必要がある夜間・休日の対応警報発生時やクレームの連絡が来たときのフローを事前に決めるこのように仕様を明確にすることで、管理会社とオーナーの間で認識のズレが生じるリスクを減らし、トラブルを防止できます。 3-4.契約締結と運用スタート 管理内容や費用・報告体制などを取り決めたうえで正式に契約を交わします。運用が始まってからも、定期的にコミュニケーションをとり、必要な修正や要望を逐次伝えることが大切です。 第4章:不動産管理費のコスト削減の秘訣 次に、管理費をできるだけ抑えながら、建物の品質を維持するためのポイントをご紹介します。本来は管理仕様の工夫がコスト削減の基本ですが、管理仕様の設定はコスト以外に賃貸不動産としての競争力にも影響があるので、まずは大枠で管理コスト削減について説明し、管理仕様についてはその後に別途説明する構成とします。 4-1.適切な管理仕様の見直し 清掃や警備など、サービスを必要以上に過剰設定していないか見直しましょう。たとえば賃貸住宅では、エントランスやゴミ置き場など入居者の生活に直結する場所は重点的に清掃し、それ以外の共用廊下はやや回数を減らすなど、必要十分なレベルに調整することでコストを削減できます。管理仕様と費用は直接関係するので、最低限の仕様で管理を委託した方が良いと考えることもできます。短期的なコスト削減ではそのような方策もあり得ますが、入居者の満足度や建物の予防保全などの観点を含めて管理仕様をどの水準とするかは極めて高度な知識と経験が必要な項目です。この記事でも具体的な部分について例として言及しますが、唯一無二の適切な管理仕様があるわけでなく、実際には不動産ごとに状況に応じて管理仕様を設定し、見直して行くことがビル運営管理の業務そのものなので、その手順について後述します。具体的商品サービス例清掃ロボット清掃ロボット導入により、清掃コストを抑えつつ品質を維持する商品です。清掃現場のノウハウを活かし、省人化・品質維持・コスト削減を同時に狙う、商業施設での導入事例があります。共用廊下・エントランス・バックヤードなど定型作業清掃頻度や人員配置の“見直し”とセットで実施します。 4-2.設備の予防保守 定期点検・予防保守を怠ると、結果的に大きな修繕費用が必要になる可能性が高いです。設備が故障してから交換・修理する「事後保全」より、計画的な点検・メンテナンスで不具合を未然に防ぐ方が、トータルコストを抑えられます。 4-3.複数業務の一括発注 清掃会社、設備管理会社、警備会社などを個別に契約すると契約窓口が増えるだけでなく、全体コストも高くなりがちです。管理会社に一括でまとめて委託するとスケールメリットが期待でき、コスト削減につながるケースが多いです。具体的商品サービス例遠隔監視・受付無人化・FM提案で人件費・警備費を削減するALSOK「受付案内システム」(無人受付・遠隔対応の活用)があります。これは無人受付、遠隔・駆けつけ対応、ファシリティマネジメント等を「コスト削減」目的で整理して提供。小規模ビルの受付・夜間対応の省人化、“24時間365日体制の一次受け”を外部化して現場負荷を下げる、緊急対応の標準手順(連絡・駆けつけ・報告)を外部サービスで対応などの効果が期待できます。 4-4.エネルギーコストの見直し 照明のLED化や空調・給排水設備の省エネ化、適切な稼働時間管理など、エネルギーコストの削減は長期的に大きな効果をもたらします。管理会社と相談し、電力・水道使用量やエネルギーモニタリングの方法を導入するのも効果的です。具体的商品サービス例BEMSという仕組みの導入事例があり、電力の見える化と自動制御でエネルギー費を削減する仕組みであり、次の目的や効果を挙げることができます。効果①空調・照明・デマンドのピークカット(基本料金の抑制)効果②テナントへの「見せる化」で節電行動を促す効果③現場常駐の“勘の運転”を減らし、運転ルールを標準化BEMSの具体的な商品は次のとおりです。商品例①アズビル「BEMS」~建物設備のエネルギーマネジメント支援として、運用コスト削減や設備安定稼働を掲げるサービス。商品例②NTTファシリティーズ「FITBEMS」~電力使用状況の「見える化」「見せる化」+自動制御で省エネ・節電を支援するクラウド型BEMS。商品例③丸紅ネットワークソリューションズ「BEMSサービス」~センサー計測+制御+見える化で、契約電力や電気料金の削減効果を目指す。ほか、エネルギー設備の一括運用で運用・調達の最適化商品として、商品例④TGES(東京ガス・TGES)「オンサイトエネルギーサービス」~エネルギー調達まで含めた方式(ESP方式等)であり、エネルギー関連の運用をまとめて任せることで効率化を実現、などもあります。※以下の内容は一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的アドバイスを提供するものではありません。実際に疑義がある場合には、弁護士など専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。 4-5.管理会社による受注調整の可能性 ①受注調整(談合)とは受注調整(談合)とは、複数の企業が競争入札や見積もり合わせの際に、「どこが受注するか」「いくらで受注するか」などを事前に取り決めるなど、競争原理を妨げる行為を指します。これは日本の独占禁止法で禁じられている行為(不当な取引制限)です。②不動産管理業界での談合リスク不動産管理業務には、清掃・設備保守・警備など複数の業者が関わります。管理会社がこれらの業者を取りまとめる形で一括受注・下請け手配をするケースも多く、業務が集中すると「あの管理会社に頼めばある程度相場が決まっている」といった形で実質的に競争が働きにくくなる環境が生まれることがあります。ただし、大手管理会社同士が直接価格を操作し合うような形での談合は表面化しにくく、あくまでも各分野の専門業者との連携の中で調整が起こるケースが想定されます。いずれにせよ、競争原理を阻害する“カルテル”や“談合”は違法であり、発覚すれば公正取引委員会(公取委)から是正を求められたり処分を受けることになります。③発注側が取れる対策複数社からの相見積もり(競合入札)見積もりの透明性・妥当性の確認情報共有や公取委への相談発注方式の工夫契約内容の定期的な評価と改善④まとめ違反行為を完全に防ぐことは難しいものの、発注者としては複数の会社からの見積もりを取り、契約内容をしっかりチェックし、必要に応じて専門家に相談するなどの対策を講じることで、談合リスクを軽減できます。競争環境を整えながら、信頼できる管理会社・工事会社と適切な関係を築いていくことが、結果的に健全なコストと質の両立につながるでしょう。 4-6.まとめと管理費の相場 管理費の相場は一概に説明し切れるものではありません。仕様として作業時間が妥当である場合、2-3で説明したとおり、時間単価の水準を目安とすればそれぞれの業務の相場について数字で把握することは可能なので、その数字が他の水準を逸脱しているようなら確認が必要な場合もあるかもしれません。但し、昨今の傾向として、人件費を含む物価の高騰により管理費も増加傾向にあります。従いまして、同じ管理仕様で切替をした場合のコスト削減は難しい可能性があります。もしくは、管理仕様を向上して不動産の競争力を高めようとしても人手不足で対応が難しい可能性もあります。更に人的なコストや人材確保については、地域により状況が異なるため、あくまで可能性がある、という表現に留めるのが妥当だと思います。そのような状況ということもあり、現在の管理費について、本稿のような全般的な内容のなかで現在の相場を説明するのは誤解を招くおそれがあるので、避けたいと思います。従いまして、いくつかの管理会社に相談し、希望するサービスを提供して頂けそうな管理会社から見積を取得し、それらの見積を比較することが肝要です。 第5章:管理仕様を設定する方法 以下では、「管理仕様を設定する方法」の具体的な手順を中心に解説していきます。前章で説明したとおり、管理費のコストを適切にするための方策として、価格競争にコスト削減は有効に機能しない可能性もあります。不動産のタイプやテナントの種類、建物の構造・設備状況などは千差万別であり、唯一絶対の管理仕様は存在しません。最適な仕様は、建物の特性やオーナーの運営方針、入居者(テナント)ニーズなどによって変動します。したがって、不動産ごとに現状と目標を把握し、管理仕様を段階的かつ継続的に策定・見直ししていくことが求められます。管理仕様の適切な設定が管理コストの合理化や建物競争力の維持改善となるものなので、ある意味で不動産運営における重要ポイントとなります。 5-1.前提条件の整理 まずは、管理仕様を決める際の前提となる情報を整理します。ここで情報が不十分だと、適切な仕様を立案できません。物件の基本情報建物の種類(賃貸住宅、オフィス、商業施設、物流施設など)建築年・階数・延床面積・構造・設備状況(空調、エレベーター、給排水設備、防犯カメラなど)法定点検や行政上の届け出の有無(建築基準法、消防法、労働安全衛生法などの必須点検項目)オーナーの運営方針・目標物件をどのように活用し、どの程度の利益や稼働率をめざすのか資産価値の向上を重視するのか、または早期売却・転貸などの戦略があるのかブランディングやイメージアップ(高級感など)を重視するのか入居者(テナント)の特性・ニーズ賃貸住宅ならファミリー、単身者、高齢者向けなどオフィスなら士業系、IT系、コールセンターなど商業施設なら店舗の業種・営業時間・集客力など物流施設なら荷物の取り扱い量、24時間稼働の有無など現状の課題や希望既にクレームが頻発しているのか、不具合が発生している設備はあるか管理コストをどの程度削減したいのか(短期・長期目標)現状の管理仕様に不足を感じている点は何か 5-2.必要な管理項目の洗い出し 次に、具体的にどのような項目を管理する必要があるのかをリストアップします。建物の種類・規模・設備によって異なりますが、大枠として以下のようなカテゴリに分けると整理しやすいです。清掃日常清掃(共用部のほこり・ごみ回収、玄関・エントランス、トイレなど)定期清掃(フロア洗浄、ガラス清掃、外壁洗浄など)設備保守・点検法定点検(消防設備、エレベーター、空調設備など)予防保守(建物・設備の経年劣化を踏まえた定期点検など)警備・セキュリティ防犯カメラの管理・録画データの保管警備員の常駐や巡回の有無夜間緊急対応(警報発報時の現地対応など)管理人・受付業務常駐管理人の有無(賃貸住宅)受付スタッフの配置(オフィスビルや商業施設)PM(プロパティマネジメント)業務賃料回収、テナント対応、クレーム処理契約更新、退去時の原状回復管理などAM(アセットマネジメント)業務資産価値向上策の検討、長期修繕計画の策定リノベーション提案、リーシング戦略立案など必要な管理項目を一通り洗い出したら、物件の特性とオーナーの方針に照らし合わせて取捨選択を行います。 5-3.重要度と優先順位の評価 管理項目がリストアップできたら、各項目の「重要度」と「優先順位」を評価します。以下のような指標を用いると整理しやすいでしょう。法定必須項目かどうか建物や設備の劣化リスク・入居者への影響度コストと効果(費用対効果)入居者満足度やブランドイメージへの影響このステップでは、1つひとつの項目に対して「なぜ必要なのか」を明確にして、優先度の高いものから確実に管理仕様に組み込むことが大切です。 5-4.管理仕様の具体化とコスト試算 優先度を決定したら、いつ・どの頻度で・どのような内容で実施するかを具体化していきます。その際に、同時にコストの見積もりも行い、仕様と費用のバランスを調整していきます。管理頻度の設定日常清掃:テナント使用状況を鑑みる必要があります。毎日or週○回or月○回定期清掃:日常清掃では対応できない部分や機器類を使用して行う清掃があります。毎月〇回or年〇回設備点検:月次・年次・法定点検のタイミングに合わせる警備・緊急対応:24時間体制か、夜間のみ遠隔監視か管理方法の検討専門業者に外注するか、管理会社による一括手配か巡回や常駐のスタイル、設備点検の報告書作成の有無などコスト試算各項目ごとに必要な人件費・資材費・外注費などを積算管理仕様の高・中・低の3パターンなど、複数のシナリオを比較検討する短期・長期での費用対効果の考察短期的にはコスト削減になるが、長期的に修繕リスクやクレーム対応コストが増える可能性がないかテナントの満足度維持や更新率の向上が見込まれるか仕様変更に伴う価格見直しの検討仕様変更で管理水準の向上を行った場合、それによるテナント負担額の増加ができないかを検討する収入増額のためには、管理仕様単独の変化だけでなく、物件の価値全体を評価して妥当な賃貸条件の見直しも必要となる場合がある 増額を行う場合は一度にすべての増分を転嫁するのでなく、段階的に行うことでテナントの理解を得るように努めることも検討するこの時点で、「もっと安く抑えたいから清掃回数を減らす」「リスク回避のために予防保守を厚くする」といった調整を繰り返し、オーナーのニーズと費用との折り合いをつける一方でテナント満足度も把握しながら仕様見直しを進めます。 5-5.試験運用とフィードバック 策定した管理仕様をすぐにフル稼働させるのではなく、場合によっては試験運用(トライアル)を実施すると、現場のリアルな状況が把握しやすくなります。短期的なテスト導入例)清掃回数を月内で数パターンに分けて実施し、入居者の反応や作業負荷を比較する例)警備体制を常駐から夜間遠隔監視に切り替えてみてトラブル件数を調べるフィードバックの収集入居者やテナントからのクレーム・要望、スタッフからの作業報告を分析クレーム発生頻度や作業負荷が適正かどうかを確認柔軟な仕様修正試験運用で見えた課題を踏まえ、再度仕様を微調整するこのサイクルを繰り返すことで、実態に合った仕様が固まっていく 5-6.本格運用と継続的な見直し 試験運用を経て一定の仕様が固まったら本格運用に移行します。ただし、建物や入居者の状況は時間とともに変化するため、運用開始後も定期的な見直しを行うことが極めて重要です。定期レポート・ミーティング管理会社や業務委託先からの報告書を毎月または四半期で受け取り、清掃品質や設備点検結果、クレーム状況を把握必要に応じて改善要望を伝える入居者アンケート半年や1年ごとに簡易的な満足度調査を実施清掃・警備・設備などに対する評価や要望をヒアリング設備の更新計画との連動長期修繕計画を踏まえて、更新時期が迫っている設備に対する点検強化やリニューアル工事の計画を立案老朽化が進んでいる場合は保守コストが増加しやすいため、管理仕様の組み直しが必要になることも外部環境の変化競合物件の登場、地価や賃料相場の変動法規制の変更(省エネ基準や建築基準法など)需要の高まりによるテナント層の変化(物流施設ならEC需要増加など)収益の変化収入と費用の両面でどのような変化があるかを把握するそれぞれの変化の原因を把握し、トータルの事業としての収益性の変化を把握し、収益改善に向けた検討を重ねるこうした変化に対応しながら、定期的に管理仕様をアップデートするのがビル運営管理の本質です。 5-7.まとめ:状況に合わせた管理仕様の「設定→運用→見直し」が肝 唯一無二の完璧な管理仕様は存在しない物件の状況やオーナーの方針、入居者ニーズによって求められる水準は異なる。法定必須項目やリスク管理は最低限必ず守るコスト削減を最優先すると、長期的な修繕コスト増や入居者離れにつながるリスクがある。短期的なコストカットと長期的な価値維持のバランス清掃や警備を極限まで削減すれば経費は下がるが、結果的にブランドイメージやクレーム対応コストに悪影響を及ぼす可能性がある。試験運用と定期的な見直し一度決めた仕様がベストとは限らない。PDCAサイクルを回し、必要に応じて仕様を修正していく。作業時間と料金は比例身も蓋もない結論に聞こえるかもしれませんが、現在の不動産管理業界の環境では、質の高い管理業務を行うには一定の作業時間は必要であり、その範囲で可能な業務効率化により作業時間も抑制することがコスト削減方法として王道と思われます。ビル運営管理の重要なポイントは、「状況に応じた最適解を継続的に探りながら運営する」というプロセスそのものです。今回ご紹介したステップを踏まえて、ぜひ自分の物件に合った管理仕様を策定し、オーナー・入居者双方が満足できる運営を実現してみてください。 第6章:不動産管理会社の品質を把握する方法 管理業務の品質を確認し、必要に応じて改善要望を伝えるためには、以下のようなポイントを押さえると良いでしょう。 6-1.定期報告書のチェック 月次や四半期で提出される報告書をしっかりと確認し、疑問点があれば管理会社に質問しましょう。清掃実績:清掃箇所や回数、問題点の報告はあるか修繕・点検報告:設備の使用状況、故障の有無や今後の計画はどうなっているかテナント(入居者)対応履歴:クレームや問い合わせの内容と対応結果 6-2.現地確認・立ち会い 定期的に現地を訪問して、以下の点を直接チェックすることも重要です。清掃状態:ごみやほこりが残っていないか、壁や床はきれいに保たれているか設備の稼働状況:エレベーターや空調などの不具合がないか警備体制:防犯カメラが正常に作動しているか、警備員の巡回状況は適切か 6-3.入居者・テナントからの評価 入居者やテナントがいる場合は、定期的にアンケートをとり、管理会社の対応について意見を収集するのも効果的です。クレームや要望が多い場合、管理体制に問題があるかもしれません。 6-4.管理費の内訳の透明性 管理費の明細をしっかり確認し、どの業務にいくらかかっているのかを把握しましょう。不透明な部分が多い場合は、管理会社に説明を求め、納得のいくまで相談することが大切です。 6-5.まとめ 管理業務に関して管理会社に説明を求めた場合の回答内容や説明が適切で納得できる内容であれば、入居者やテナントに対する対応も同様と想定することも可能です。但し、不動産所有者は管理会社の発注主という立場であるため必ずしも異なり、管理会社の窓口が異なる場合もあります。そのような状況を鑑み、管理会社の品質について様々な観点から評価することが望まれ、もし課題を発見したら、管理会社とともに改善に取り組むことも不動産所有者の役割といえます。 第7章:ビルメンテナンス会社の例 本章ではタイプ別にビルメンテナンス会社の例をご紹介します。あくまでビルメンテナンス会社を探す際にどのような特徴があるのかを理解するうえでの一助となることを目的としており、特定の企業の広報を目的とするものではないため、実際の選定についてはご自身で調査されますようお願いいたします。日本のビルメンテナンス業界では、企業ごとに「得意とする物件タイプ」や「強みとする業務分野」が異なります。以下では、施設タイプ別・業務タイプ別にいくつかの主要ビルメンテナンス会社や建物管理会社を例示し、その特徴を簡単に紹介します。あくまで代表例であり、実際には多くの企業が複合的に業務を行っていますので、ご参考程度にご覧ください。 7-1.施設タイプ別 (1)オフィスビル三井不動産ファシリティーズ特徴:三井不動産グループのビルメンテナンス会社。大規模オフィスビルや大規模商業施設の運営管理に強みを持ち、設備管理、ファシリティマネジメントまで幅広く対応。東京ビルサービス株式会社特徴:東京建物グループ。オフィスビルなどのPM・BM(ビルマネジメント)を中心に展開。(2)賃貸住宅(レジデンス・アパートメント)大東建物管理株式会社特徴:大東建託グループの管理会社。賃貸アパート・マンションの一括借上(サブリース)を含めた管理を行い、入居者対応、設備保守、清掃などを総合的に請け負う。主な対象物件:賃貸アパート・マンション。大和リビング特徴:大和ハウスグループの管理会社。賃貸アパート・マンションの管理を行い、入居者対応、設備保守、清掃などを総合的に請け負う。主な対象物件:賃貸アパート・マンション。(3)分譲マンション(区分所有)東急コミュニティー株式会社特徴:東急不動産HD傘下の管理会社。分譲マンションの管理組合運営サポート、清掃・設備点検、長期修繕計画の策定など総合的に対応。主な対象物件:首都圏を中心とした分譲マンション。大京アステージ株式会社特徴:大京グループのマンション管理会社。「ライオンズマンション」シリーズを中心に、管理組合運営サポート、点検・清掃業務、長期修繕計画のコンサルなどを得意とする。主な対象物件:分譲マンション(全国展開)。(4)商業施設(ショッピングセンター・大型商業ビル)イオンディライト株式会社特徴:イオングループの総合ビル管理会社。ショッピングセンター(SC)の清掃・設備管理をはじめ、駐車場運営、セキュリティ、受付案内などワンストップで提供。主な対象物件:イオンモールをはじめとする大規模商業施設。JR東日本ビルテック株式会社特徴:JR東日本グループのビル管理会社。駅ビルや商業施設、オフィスビルの総合管理に強みを持つ。鉄道関連の特殊設備管理にも対応。主な対象物件:駅ビル、商業施設、複合型大規模ビル。(5)物流施設・倉庫星光ビル管理特徴:総合管理会社主な対象物件:倉庫物流施設管理を行う(6)駐車場タイムズ24株式会社(パーク24グループ)特徴:コインパーキングや駐車場運営を主体とした会社。設備保守から料金徴収システムの管理、警備サービスなどを統合的に行う。主な対象物件:駐車場(有人・無人含む)、立体駐車装置。株式会社アズーム主な対象物件:駐車場管理(7)ホテル共立メンテナンス特徴:ドーミーインを展開給食事業なども行う。主な対象物件:ビジネスホテル、リゾートホテル。APAホテルズ&リゾーツ(APAグループ)特徴:APAが自社でホテルの開発・運営を行うケースが多いが、ビルメンテナンスに関してはグループ会社や提携先で設備保守や清掃を担当する。主な対象物件:ビジネスホテル、シティホテル。 7-2.業務タイプ別に強みを持つビルメンテナンス会社の例 (1)清掃業務(ビルクリーニング)東洋テック株式会社特徴:関西を中心に清掃業務や警備業務を得意とする会社。ビル清掃、ガラス清掃、高所作業などの専門技術を有し、警備と合わせて総合管理を行うことも可能。太平ビルサービス株式会社特徴:清掃・設備管理を中心に、全国に拠点を持つ。特に清掃領域ではオフィス・病院・学校など多様な施設対応の実績が豊富。(2)設備保守(電気・空調・給排水・消防など)ビル設備系メーカー系サービス会社例:三菱電機ビルテクノサービス、日立ビルシステム、東芝エレベータ、ダイキンHVACソリューションなど特徴:自社製品(エレベーター、空調設備など)に関する保守点検を中心に、ビルメンテナンス全般に拡大対応している。純正部品・メーカー技術者によるメンテナンスを強みとする。アズビル株式会社(旧:山武)特徴:ビルオートメーションシステム(BAS)など、中央監視・制御設備の保守を得意とし、空調制御・エネルギーマネジメントなど付加価値の高いサービスを提供。(3)修繕工事鹿島建物総合管理株式会社(鹿島グループ)特徴:大手ゼネコン鹿島建設グループ。オフィスビルやマンション等の定期修繕・改修工事の提案・実施を行う。建築知識・施工体制が強み。長谷工コミュニティ(長谷工グループ)特徴:マンション管理と大規模修繕工事で高いシェアを持つ。長谷工コーポレーションの建築ノウハウを生かし、老朽化対策や耐震補強など総合的に対応。(4)ビル運営(テナント管理・運営企画・PM業務)CBRE株式会社特徴:外資系不動産サービス会社。グローバル基準のPM(プロパティマネジメント)、アセットマネジメント、リーシング戦略など幅広いサービスを提供。対象業務:オフィス・商業施設の運営管理、テナント付け、契約交渉・レポーティングなど。 7-3.まとめ 施設タイプ別の得意分野オフィスビル:大手デベロッパー系管理会社賃貸住宅:大東建物管理、レオパレス・パートナーズなど賃貸管理大手分譲マンション:東急コミュニティー、大京アステージなどマンション管理専業大手商業施設:イオンディライト、JR東日本ビルテックなど、SCや駅ビルに強い会社駐車場:タイムズ24など駐車場運営に強い企業ホテル:APAなどホテル運営受託会社業務タイプ別の得意分野清掃:太平ビルサービス、東洋テックなど清掃専門部隊が充実設備保守:三菱電機ビルテクノサービス、日立ビルシステム、アズビルなどメーカー系修繕工事:鹿島建物総合管理、長谷工コミュニティなど建設・ゼネコン系ビル運営(PM業務):外資系不動産サービス企業(CBREなど)、大手デベロッパーグループこのように、ビルメンテナンス会社を選定する際は「対象となる建物の種類や用途」と「必要とする業務の種類・範囲」を明確にし、それに応じて専門性を持つ会社を比較検討することが重要です。大手のグループ会社やゼネコン系、メーカー系、外資系など背景が異なる企業が多いため、コスト・対応スピード・サービス品質など各社の特徴を総合的に踏まえて判断します。 第8章:不動産理論・法律における管理費 以下の内容は、日本における不動産鑑定評価基準や関連する実務の一般的な考え方に基づいてまとめた情報です。個別の案件や契約内容によって扱いが異なる場合があるため、詳細な判断が必要な場合は不動産鑑定士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。冒頭で説明したように管理費の用語は一義的な意味で使われるとは限らないので総括的な知識を持ち、具体的な管理費の議論においてどのような意味合いで使っているのかを把握できるよう補足しています。不動産所有者が管理会社や入居者とのコミュニケーションにおいて、管理費という用語で齟齬が生じないように配慮しています。 8-1.不動産鑑定理論における管理費の位置づけ ①管理費は「オーナーが負担する費用」として捉えられる不動産鑑定評価(特に収益還元法)の考え方では、対象不動産から期待される純収益(Net Operating Income:NOI)を把握するために、賃料収入などの総収益から運営費(管理費や修繕費、固定資産税など)を差し引くという手順を取ります。このとき挙げられる「管理費」は、建物全体の維持管理にかかる費用共用部分の清掃や設備保守・警備などに必要な費用管理会社へ支払う管理委託手数料その他、建物を適正に維持するための一般的な費用といった項目が含まれます。【実務上の扱い】不動産鑑定評価では、賃貸事業を行うオーナー側が負担するべき管理費(=運営側の費用)を前提とします。テナント(入居者)に転嫁できる管理費(共益費)部分があれば、それはオーナーにとって実質的に「収益」になるため、「オーナー負担分」と「テナント負担分」に分けて整理を行うことが多いです。②テナントが負担する「管理費」や「共益費」の扱い一方で、実務の賃貸契約においては、テナントが負担する管理費や共益費が別途設定される場合があります。例えばオフィスやマンションの賃貸借契約書を見ると、「賃料:○○円」「管理費(または共益費):○○円」という形で明記されている入居者は毎月、賃料と管理費(共益費)を合わせて支払うといったケースです。【鑑定評価上の考え方】この「管理費(共益費)」をテナント側が全額負担する契約形態であれば、理論上オーナーが負担する管理費はその分だけ軽減され、オーナーの実質的な収益(NOI)が増加することになります。不動産鑑定の場面では、「テナント負担の管理費相当分を含めた実質的な収入」を把握しつつ、オーナーが直接負担しなければならない管理関連費用(共用部の光熱費や保守費など)がどこまで発生するのかを精査して、最終的な純収益を算出します。 8-2.賃貸不動産における管理費・共益費の法的性質 ①賃貸借契約と管理費の取り扱い日本の民法(債権法)や借地借家法などを見ると、「賃貸借契約でいう賃料」として定義されるのは一般的に使用収益の対価です。一方、管理費や共益費という名称自体は法律上で独立した定義があるわけではありません。賃料:目的物の使用収益に対して支払う対価。管理費・共益費:本来は、共用部の維持管理にかかる費用を入居者が按分して支払う趣旨(と契約で定められることが多い)。しかし、法律上は「賃料の一部」とみなされる場合もあるため、必ずしも賃料と別の法的性質を持つとは限らない。【実務では「賃料+管理費(共益費)」と呼んでも、法的にはひとまとめになりがち】賃貸借契約書の記載次第ですが、裁判例や実務上、「賃料以外の名目で定期的に支払われる金員も含めて、実質的には賃料として扱う」と解される場合があります。例えば、滞納時の賃料回収や契約解除の要件などで「名目が何であれ、入居者が毎月支払う金額は賃料性を有する」と整理されることが少なくありません。②管理費(共益費)は何らかの特別な法律に基づくものか?日本の法律で「管理費」を独立して定義しているものはないといえます。区分所有法でいう「管理費」はマンション管理組合に関する費用(区分所有建物の管理費)を指す場合もありますが、これは区分所有者の負担分であり、賃貸借契約での「管理費」とは別の文脈。一般的な賃貸物件における「管理費」や「共益費」は、あくまで当事者の合意(契約書の定め)により賃料と別枠で設定している金額にすぎません。【管理費の法的性質】賃貸借契約に基づき、当事者同士の合意で定期的に支払われる金員名目上「管理費」や「共益費」と呼ばれていても、法的には「賃料の一部」とみなされる場合がある。 8-3.不動産鑑定における管理費水準の判断 ①市場実態との比較不動産鑑定評価において、管理費の水準が高いか低いかを判断する際は、類似物件の事例(共益費相場など)と照合したり、賃料水準とのバランスを見ながら判断することが多いです。近隣や同種の物件で管理費・共益費がどれくらい設定されているかオーナー側が負担する管理費(運営費)は、規模や管理内容に照らして妥当な金額か②管理費を調整することで賃料総額とバランスをとるまた、テナントが負担する管理費が高めに設定されている場合、逆に賃料がやや低く設定されているなど、いわゆる「賃料+管理費」の総額を見て競合物件と比較する手法もよく行われます。賃料と管理費(共益費)は通算して検討し、「月額トータルでいくら支払うか」がテナントにとっての実質負担不動産鑑定では、実質的な稼働総収益(賃料+共益費収入)を加味しつつ、オーナー負担分の管理費支出を控除する形で純収益を推定③結論:鑑定評価では「市場水準」「賃貸条件の実態」「オーナー実質負担」を確認鑑定士は「賃料+管理費の合計額がマーケットの需給状況と比べて妥当かどうか」を見極めつつ、オーナーが最終的に負担する管理費用の妥当性も併せて調査・算定します。これにより、収益還元法のベースとなる純収益(NOI)をなるべく正確に把握し、最終的な試算価格に反映させるのが一般的なアプローチです。 8-4.取適法(旧:下請法)に関する確認 2026年1月より取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)にて下請法で規定されたルールが強化されていますが、本稿では便宜上、作成時点で一般に浸透している『下請法』という呼称も併記します。不動産管理業務の委託は、「役務提供委託」に該当し得るため、不動産所有者が親事業者、管理会社が下請事業者となり、取適法が適用される可能性があります。例えば下請法が適用される場合、(1)支払いサイトの制限(2)発注書面の交付義務(3)不当な減額・追加業務押し付けの禁止などを遵守しなければなりませんでした。特に、旧下請法の運用上、手形等の支払条件(サイト)が60日を超える取引慣行について是正が求められるため、支払方法(手形・電子記録債権等)と支払期日の設計には注意が必要です。実際の適用可否は、「資本金規模の対比」「業務委託が親事業者の“事業の一部”に当たるかどうか」などの要素で判断されます。不動産オーナーが大規模法人で、不動産管理会社がそれよりも小規模な法人であるなど要件を満たす場合は、契約スキーム・支払い条件・契約書類の整備について取適法違反とならないよう注意が必要です。 8-5.理論的な管理費についてのまとめ 不動産鑑定評価における「管理費」は、建物の運営維持にかかる費用として、オーナー側の支出項目に位置づけられる。テナントが負担する管理費・共益費は、法律上独立した概念があるわけではなく、賃貸借契約で当事者間が合意した金額にすぎません。場合によっては実質「賃料の一部」として扱われる場合もある。鑑定評価では、管理費の水準を判断する際に、近隣や類似物件との比較や、賃料+管理費総額とのバランスをチェックする。法的には管理費という言葉自体に特別な定義はなく、あくまで当事者間合意の結果。滞納・契約解除などの局面では、管理費と賃料を分離できずに同じ「賃貸借契約上の金員」とみなされる場合がある。最終的に、「管理費はどう位置づけられるか」は契約や鑑定評価上の考え方に左右されますが、実務的には「テナントが負担する分(共益費)」と「オーナーが負担する分(運営費)」に区分し、収益と費用を正しく整理することが重要です。一方、法律上は「賃貸借契約による賃料等の支払い」という大枠の中で扱われ、名目がどうであれ実質的に賃料性を有する場合が多い点に留意が必要です。そこで、実務的には賃貸事業において、テナントから徴収する賃料、管理費、共益費などは賃貸収入(=賃料)とし、不動産運営管理に必要な管理外注費や管理に必要な経費は賃貸管理原価(=管理費)と用語を区分すると整理できると思われます。 まとめ:最適な不動産管理で資産価値を守る 不動産管理費は、建物や設備を適切に維持するために必要なコストです。一見すると負担に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえて管理会社を選び、適切な仕様を設定し、予防保守や一括発注などを駆使することで、費用対効果を高めることが可能です。管理会社に委託するメリット:専門知識の活用、コスト管理や不動産事業の効率化、クレーム対応の負担軽減など委託時の手順:業務範囲・仕様の明確化、複数社への見積もり依頼、仕様のすり合わせ、契約・運用開始コスト削減の秘訣:必要十分な管理仕様、必要に応じた見直し、予防保守の徹底、一括発注の活用、省エネ対策品質チェック:定期報告書や現地確認、入居者アンケートの活用、費用内訳の透明化不動産運営管理の相談先:実績のある不動産管理会社は長年の知識・経験をもとに不動産運営で大きな課題が生じた場合に専門的な知見を踏まえたアドバイスを求めることもできます。物件を管理しているため、外部専門家としてだけでなく、不動産運営のパートナーとして活用しましょう。上記を踏まえ、賃貸住宅やオフィス、商業施設、物流施設などの特性に合わせて、無理のない管理計画を立てることが大切です。最終的には、建物の品質維持や資産価値の向上につながる管理を目指し、管理会社との信頼関係を築いていきましょう。不動産管理は奥が深い分野ですが、きちんと理解して取り組むことで大切な不動産を長く・安全に運営することができます。初めての方でもこの記事を参考に、最適な管理体制を整えてみてください。もし、不動産管理についてご質問等あればお気軽にご連絡下さい。お待ちしています。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ代表取締役 羽部 浩志 1991年東京大学経済学部卒業 ビルディング不動産株式会社入社後、不動産仲介営業に携わる 1999年サブリース株式会社に転籍し、プロパティマネジメント業務に携わる 2022年サブリース株式会社代表取締役就任(現職) ライフワークはすぐれた空間作り 2026年2月10日執筆2026年02月10日
皆さんこんにちは。株式会社スペースライブラリの羽部です。この記事は不動産管理の基礎知識から、管理会社に依頼する際の手順や注意点、コスト削減のポイントなどを詳しくまとめたもので、2026年2月10日に改訂しています。主に不動産オーナーに向けた内容となり、対象の不動産は「賃貸住宅」「オフィス」「商業施設」「物流施設」と幅広く、初めて不動産事業に携わる方でもわかるよう、通常は説明を省略するような部分についても、できる限り丁寧に説明します。特に昨今の物価上昇によるコストアップは不動産管理の分野でも見られますので、そのような状況でどのように対応すべきか、商品サービスの事例などについても言及します。すでに豊富な実務経験をお持ちの方におきましては、冗長に感じられた場合は恐縮でございますが、皆さまのご参考としてご覧いただければ幸いです。 目次第1章:不動産管理費とは?第2章:不動産管理の方法と管理会社の役割第3章:管理会社に委託する場合の手順と注意点第4章:不動産管理費のコスト削減の秘訣第5章:管理仕様を設定する方法第6章:不動産管理会社の品質を把握する方法第7章:ビルメンテナンス会社の例第8章:不動産理論・法律における管理費まとめ:最適な不動産管理で資産価値を守る 第1章:不動産管理費とは? 不動産管理費とは、文字通り「不動産を管理するために必要となる費用・ビルメンテナンス費用」の総称です。具体的には、以下のような業務を遂行する上で発生する費用が含まれます。なお、2項で言及する不動産管理会社の広義の業務内容に含まれる運営管理(PM:プロパティマネジメント)や資産管理(AM:アセットマネジメント)はそれぞれ専門の委託先が存在しており、その費用に関する説明は、それぞれ個別記事にて説明させて頂きます。建物・設備の保守点検費用エレベーターや空調設備、消防設備などの定期点検費用、修繕費用などが該当します。清掃費用共用部・外部・駐車場など、定期的に清掃を行うための費用です。警備費用警備員の配置や、防犯カメラ管理、セキュリティシステムの維持に関する費用です。管理人や事務スタッフの人件費管理人(管理員)の常駐費用や、事務的な手続き(家賃の督促やクレーム対応など)にかかる人件費。事務業務まで外注していれば費用を明確に認識できますが、管理業務を委託する場合でも所有者側で事務業務を負担する場合もあるので、その点を把握するような工夫が必要です。設備更新・修繕積立金経年劣化に応じた設備更新や、大規模改修工事の資金をプールするための積立金が含まれることもあります。区分所有建物と完全所有権建物区分所有建物では管理組合を運営するための事務費用(事務員や理事の報酬・会計処理・印刷・郵送費など)や、集会場・理事会や総会の開催に関わる経費などが含まれることがあります。これらは管理組合の運営方法により費用水準も異なり、建物管理以外の費用を含むので本稿では対象外とします。 【用語の定義】 不動産管理費とは通常、不動産所有者が建物(不動産)を管理するために必要な費用です。これはテナントが負担する管理費や共益費で賄う部分もあれば、建物所有者が負担しても、テナントに転嫁しない部分もあります。同じ用途の建物であっても、テナントが負担する管理費(共益費として負担するものを含む)に法令による定めや一律のルールはないため、不動産による異なる金額水準というだけでなく、そもそもの管理業務内容が異なります。更に賃貸オフィスなどで管理費を含む賃料も見られるため、一般のユーザーや新規の不動産所有者にはわかりづらい印象を持たれるかもしれません。この点について、どのように区分するかは不動産所有者の経営方針となりますので、それらを踏まえた運営方針を検討頂くため、関係する情報を含め説明して参りますが、特に断りない場合は不動産所有者が管理業務を外部に委託する場合の管理費について記述します。 第2章:不動産管理の方法と管理会社の役割 2-1.管理会社に委託するメリット 不動産オーナーが自前ですべての管理業務を行うことは、知識や人材・時間の面で非常に大きな負担となります。管理会社に委託することで、以下のようなメリットがあります。専門的なノウハウ・人材の活用設備の保守点検、清掃や警備など、専門知識や経験が必要な業務をまとめて委託できる。コスト管理の簡略化複数の業者を一社で取りまとめてくれるため、業者への発注や支払いの手間を削減できる。クレーム対応や入居者対応の負荷軽減賃貸住宅であれば入居者からの苦情・問い合わせ、商業施設やオフィスならテナントからの要望対応などを管理会社が担ってくれる。デメリットメリットの裏返しとなりますが、不動産に対する専門的な知見の蓄積や不動産管理を担当する社内人材の確保などが困難となります。また、管理会社次第ではありますが、細かいコスト管理が困難となる、管理会社を切替した場合に運営管理サービス水準が変わる可能性があり、入居者・テナントに対する対応などで混乱を招く懸念があるなど、すみやかに気付けば対応できる部分もありますが、発見できない場合はトラブルに発展するリスクもありますので、これらの部分について随時チェックするなど、定期的な確認・配慮は不可欠です。 2-2.管理会社の主な業務内容 建物管理(BM:ビルメンテナンス)日常清掃・定期清掃、設備点検、修繕対応、警備業務など。運営管理(PM:プロパティマネジメント)賃料回収・送金、テナントリレーション、クレーム対応、契約更新手続きなど。資産管理(AM:アセットマネジメント)建物の長期修繕計画の立案、不動産価値の維持向上施策の提案など、より資産価値にフォーカスした業務。一般的にはBM建物管理業務のみを委託するのが一般的です。但し、オーナーと管理会社の契約範囲によっては、AM業務まで包括的に行うケースもあれば、BMやPMのみを部分的に委託するケースもあります。従前、PM運営管理やAM資産管理は不動産所有者側で行う不動産が多く見られたため、不動産管理会社といえばBMのみを行うことが一般的でしたが、近年、不動産証券化などで運営される不動産が増加する市場環境において、不動産運営は高度化・専門化され、PM、AMなどの業務を含めて委託される不動産が増加しつつあります。但し、PM、AMなどの運営方式は狭義の不動産管理業務の対象外となるため、本稿では概略にとどめ、BMビルメンテナンス業務について説明を行います。 2-3.設備メーカー等によるメンテナンスと独立系メンテナンス会社の違い ビルメンテナンスを設備メーカーに委託するケースが多いのは、設備の専門知識や独自技術が求められ、保守点検や部品交換などをメーカーが一括して請け負いやすいという理由が大きいです。特に下記のような設備についてはメーカー独自の技術・ノウハウまた部品等が必要となる場合が多く、メーカー以外の保守業者が参入しにくい(あるいはそもそも選択肢が少ない)といえます。 ①メーカーに委託することが一般的・標準的な理由専門性・独自技術の高さ設備によっては独自の制御システムやソフトウェアが組み込まれており、メーカー以外が対応するにはノウハウが不足しやすい。メーカーがマニュアルや設計図書を独占的に保持しているケースもある。純正部品の供給・交換が容易メーカーによる純正部品の在庫確保や交換体制が整っているため、迅速かつ適切な修理が期待できる。部品が専用品の場合、メーカー以外の業者では調達が難しく、コストや工期が増加する懸念がある。保証や契約上のメリットメーカー保守契約を結ぶことで、長期保証やサービスパッケージ割引などの優遇がある場合が多い。更新工事やリニューアル時にも、同一メーカーとの付き合いがあるとスムーズに進めやすい。トラブル対応・緊急時のサポート体制遠隔監視システムや24時間対応コールセンターなど、メーカー独自のサポート体制が確立されていることが多い。大規模トラブル時にはメーカーのエンジニアが速やかに現地対応できるネットワークがある。特に故障部材の手配はメーカー以外だと時間がかかる場合もあります。権利関係・安全面の理由建築基準法や消防法などに関連する設備(特にエレベーター、エスカレーターなど)は法定点検が義務付けられており、メーカーに保守を委託することで安全基準を満たすための手続きや書類作成がスムーズになる。ソフトウェアや制御システムに関する知的財産権の都合で、メーカー以外が介入すると契約違反や保証対象外となるケースがある。 ②メーカー以外の選択肢が少ない建物設備の例エレベーター・エスカレーターエレベーター(三菱電機、日立、東芝、オーチスなど)やエスカレーターも同様。法定点検・法令基準を満たすための確かな技術力が必要。制御装置・センサー部分がメーカー独自仕様で、外部業者が手を入れにくい。部品交換はメーカー調達が基本となるため、他業者が対応するとコスト面・納期面で不利になりやすい。大規模空調システム・パッケージエアコン(ビル用マルチエアコンなど)ダイキン、日立、東芝、三菱電機などが製造するビル用空調システム。各社が独自の制御プログラムや配管方式、冷媒制御などを採用しており、故障診断もメーカー専用ソフトを使用することが多い。修理には純正部品・特定知識が不可欠で、メーカー系サービス会社を経由しないと入手できる部品もある。中央監視システム・ビル管理システム(BAS:Building Automation System)ビル全体の空調・照明・セキュリティ・防災などを一元的に制御するシステム(オムロン、ヤマト、アズビル、Johnson Controlsなど)。システム全体がソフトウェアと連携しており、メーカー独自のプロトコル(通信規格)を用いることが多い。外部からのカスタマイズや改修が難しく、メーカーに専用ツールやライセンスがある場合が多い。特殊設備(無停電電源装置(UPS)、大型ボイラー、非常用発電機など)特殊メーカー製の大型UPSや非常用発電機など。特殊部品や法定検査を伴い、メーカーかメーカー代理店での点検がほぼ必須。不具合時の原因究明や修理にも高度な専門知識・部品が必要になる。その他(高性能セキュリティ機器、特殊扉など)たとえば、自動ドア(高性能センサー付き)、特注の防火シャッター、防音・防振設備なども、メーカー以外が対応しづらい場合が多い。 ③独立系メンテナンス会社に委託する場合の注意点部品調達ノウハウや専門資格を持った技術者の有無保証や緊急時の対応近年は一部メーカー製品について外部業者が対応可能なケースも増えているため、コストやサービス品質を比較検討する際は、代替手段がないかどうかを確認することも重要です。 2-4.管理会社の料金体系 一般的なBM管理業務を主体とする上場企業の日本管財(現:日本管財グループ/ホールディングス体制)の2023年度3月期決算短信の損益計算書によると売上高700億円に対する役務提供売上原価554億円とあり、売上の79%が人件費です。すなわち、管理会社の売上は人的サービスが規定しており、委託業務の料金はその業務に必要な人件費で定まる、ということを示しています。昨今、不動産管理業界でもDX化の導入を進めていますが、数値的な部分では不動産管理業務は人的サービス商品となります。個々の業務に必要な人的サービスは常に一定でなく、変動があるため、価格の見積は発注者からはわかりづらい部分もあります。管理会社は標準的な業務量や費用テーブルを構築し、それをもとに料金設定をしてあり、料金を算定する場合、当該業務に必要な時間×当該業務に必要なスタッフの時間単価×一定乗率で算出しています。当該業務に必要な時間は仕様で定めることができます。スタッフの時間単価は仕事の質に比例します。一定乗率は会社の定めなので個々の会社ごとに異なります。発注に際しては、料金÷業務時間により時間単価×一定乗率が求められますので、この部分を比較すれば業務品質の目安の評価が可能と思われます。 第3章:管理会社に委託する場合の手順と注意点 ここでは、不動産オーナーが初めて管理業務を委託する流れを、できるだけわかりやすく解説します。本章はあくまで全体の手順を掴んで頂くための説明なので、詳細な手順について後段で説明します。 3-1.委託範囲の明確化 まずは「どこまで管理会社に任せたいのか」を明確にしましょう。以下のように大きく分けて考えると整理しやすいです。BM(ビルメンテナンス)業務のみ委託:清掃や設備保守点検、警備などPM(プロパティマネジメント)業務も含めて委託:BMに加え、家賃回収やテナント対応など運営管理も任せるAM(アセットマネジメント)まで包括委託:BM・PMに加え、不動産価値向上策の立案・実行まで含む 3-2.複数社への見積もり依頼 管理会社はそれぞれ得意分野やコスト構造が異なります。必ず複数社に声をかけ、業務範囲・管理費・実績・対応力などを比較しましょう。管理仕様:適切な管理仕様を指定できるようであれば仕様を定めた形で見積依頼を行うが、仕様について不明な部分があれば管理会社の提案を受ける形とすることも可能業務範囲:規定した仕様で具体的にどこまでやってもらえるのか、数量的な目安を確認することで比較が可能となります見積もりの内訳:清掃費、設備点検費、警備費、人件費など、それぞれの業務ごとに金額が明確か管理実績:対象とする不動産タイプ(賃貸住宅、オフィス、商業施設、物流施設など)の管理実績はどの程度か緊急対応:24時間365日体制で対応可能か、または対応の方法を持っているか 3-3.管理仕様を決める 管理会社を選定したら、実際にどのような仕様で管理してもらうのかを詰めていきます。以下概略を述べますが、詳細は後述の第5章を参照して下さい。清掃回数・実施場所例)エントランスは毎日、駐車場は週1回、廊下は週2回など個別に頻度を設定する場合と、作業時間を決めて日単位・週単位・月単位・年単位などで何をするかを明確にするなど様々なバリエーションと工夫がある設備点検の頻度法定点検だけでなく、予防保守をどこまで行うか報告・連絡の頻度毎月レポートなのか、四半期ごとなのか、必要に応じてリアルタイムで連絡するのか、報告手順として資料の送付のみか、対面での説明はあるか、など具体的な報告方法について予め確認する必要がある夜間・休日の対応警報発生時やクレームの連絡が来たときのフローを事前に決めるこのように仕様を明確にすることで、管理会社とオーナーの間で認識のズレが生じるリスクを減らし、トラブルを防止できます。 3-4.契約締結と運用スタート 管理内容や費用・報告体制などを取り決めたうえで正式に契約を交わします。運用が始まってからも、定期的にコミュニケーションをとり、必要な修正や要望を逐次伝えることが大切です。 第4章:不動産管理費のコスト削減の秘訣 次に、管理費をできるだけ抑えながら、建物の品質を維持するためのポイントをご紹介します。本来は管理仕様の工夫がコスト削減の基本ですが、管理仕様の設定はコスト以外に賃貸不動産としての競争力にも影響があるので、まずは大枠で管理コスト削減について説明し、管理仕様についてはその後に別途説明する構成とします。 4-1.適切な管理仕様の見直し 清掃や警備など、サービスを必要以上に過剰設定していないか見直しましょう。たとえば賃貸住宅では、エントランスやゴミ置き場など入居者の生活に直結する場所は重点的に清掃し、それ以外の共用廊下はやや回数を減らすなど、必要十分なレベルに調整することでコストを削減できます。管理仕様と費用は直接関係するので、最低限の仕様で管理を委託した方が良いと考えることもできます。短期的なコスト削減ではそのような方策もあり得ますが、入居者の満足度や建物の予防保全などの観点を含めて管理仕様をどの水準とするかは極めて高度な知識と経験が必要な項目です。この記事でも具体的な部分について例として言及しますが、唯一無二の適切な管理仕様があるわけでなく、実際には不動産ごとに状況に応じて管理仕様を設定し、見直して行くことがビル運営管理の業務そのものなので、その手順について後述します。具体的商品サービス例清掃ロボット清掃ロボット導入により、清掃コストを抑えつつ品質を維持する商品です。清掃現場のノウハウを活かし、省人化・品質維持・コスト削減を同時に狙う、商業施設での導入事例があります。共用廊下・エントランス・バックヤードなど定型作業清掃頻度や人員配置の“見直し”とセットで実施します。 4-2.設備の予防保守 定期点検・予防保守を怠ると、結果的に大きな修繕費用が必要になる可能性が高いです。設備が故障してから交換・修理する「事後保全」より、計画的な点検・メンテナンスで不具合を未然に防ぐ方が、トータルコストを抑えられます。 4-3.複数業務の一括発注 清掃会社、設備管理会社、警備会社などを個別に契約すると契約窓口が増えるだけでなく、全体コストも高くなりがちです。管理会社に一括でまとめて委託するとスケールメリットが期待でき、コスト削減につながるケースが多いです。具体的商品サービス例遠隔監視・受付無人化・FM提案で人件費・警備費を削減するALSOK「受付案内システム」(無人受付・遠隔対応の活用)があります。これは無人受付、遠隔・駆けつけ対応、ファシリティマネジメント等を「コスト削減」目的で整理して提供。小規模ビルの受付・夜間対応の省人化、“24時間365日体制の一次受け”を外部化して現場負荷を下げる、緊急対応の標準手順(連絡・駆けつけ・報告)を外部サービスで対応などの効果が期待できます。 4-4.エネルギーコストの見直し 照明のLED化や空調・給排水設備の省エネ化、適切な稼働時間管理など、エネルギーコストの削減は長期的に大きな効果をもたらします。管理会社と相談し、電力・水道使用量やエネルギーモニタリングの方法を導入するのも効果的です。具体的商品サービス例BEMSという仕組みの導入事例があり、電力の見える化と自動制御でエネルギー費を削減する仕組みであり、次の目的や効果を挙げることができます。効果①空調・照明・デマンドのピークカット(基本料金の抑制)効果②テナントへの「見せる化」で節電行動を促す効果③現場常駐の“勘の運転”を減らし、運転ルールを標準化BEMSの具体的な商品は次のとおりです。商品例①アズビル「BEMS」~建物設備のエネルギーマネジメント支援として、運用コスト削減や設備安定稼働を掲げるサービス。商品例②NTTファシリティーズ「FITBEMS」~電力使用状況の「見える化」「見せる化」+自動制御で省エネ・節電を支援するクラウド型BEMS。商品例③丸紅ネットワークソリューションズ「BEMSサービス」~センサー計測+制御+見える化で、契約電力や電気料金の削減効果を目指す。ほか、エネルギー設備の一括運用で運用・調達の最適化商品として、商品例④TGES(東京ガス・TGES)「オンサイトエネルギーサービス」~エネルギー調達まで含めた方式(ESP方式等)であり、エネルギー関連の運用をまとめて任せることで効率化を実現、などもあります。※以下の内容は一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的アドバイスを提供するものではありません。実際に疑義がある場合には、弁護士など専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。 4-5.管理会社による受注調整の可能性 ①受注調整(談合)とは受注調整(談合)とは、複数の企業が競争入札や見積もり合わせの際に、「どこが受注するか」「いくらで受注するか」などを事前に取り決めるなど、競争原理を妨げる行為を指します。これは日本の独占禁止法で禁じられている行為(不当な取引制限)です。②不動産管理業界での談合リスク不動産管理業務には、清掃・設備保守・警備など複数の業者が関わります。管理会社がこれらの業者を取りまとめる形で一括受注・下請け手配をするケースも多く、業務が集中すると「あの管理会社に頼めばある程度相場が決まっている」といった形で実質的に競争が働きにくくなる環境が生まれることがあります。ただし、大手管理会社同士が直接価格を操作し合うような形での談合は表面化しにくく、あくまでも各分野の専門業者との連携の中で調整が起こるケースが想定されます。いずれにせよ、競争原理を阻害する“カルテル”や“談合”は違法であり、発覚すれば公正取引委員会(公取委)から是正を求められたり処分を受けることになります。③発注側が取れる対策複数社からの相見積もり(競合入札)見積もりの透明性・妥当性の確認情報共有や公取委への相談発注方式の工夫契約内容の定期的な評価と改善④まとめ違反行為を完全に防ぐことは難しいものの、発注者としては複数の会社からの見積もりを取り、契約内容をしっかりチェックし、必要に応じて専門家に相談するなどの対策を講じることで、談合リスクを軽減できます。競争環境を整えながら、信頼できる管理会社・工事会社と適切な関係を築いていくことが、結果的に健全なコストと質の両立につながるでしょう。 4-6.まとめと管理費の相場 管理費の相場は一概に説明し切れるものではありません。仕様として作業時間が妥当である場合、2-3で説明したとおり、時間単価の水準を目安とすればそれぞれの業務の相場について数字で把握することは可能なので、その数字が他の水準を逸脱しているようなら確認が必要な場合もあるかもしれません。但し、昨今の傾向として、人件費を含む物価の高騰により管理費も増加傾向にあります。従いまして、同じ管理仕様で切替をした場合のコスト削減は難しい可能性があります。もしくは、管理仕様を向上して不動産の競争力を高めようとしても人手不足で対応が難しい可能性もあります。更に人的なコストや人材確保については、地域により状況が異なるため、あくまで可能性がある、という表現に留めるのが妥当だと思います。そのような状況ということもあり、現在の管理費について、本稿のような全般的な内容のなかで現在の相場を説明するのは誤解を招くおそれがあるので、避けたいと思います。従いまして、いくつかの管理会社に相談し、希望するサービスを提供して頂けそうな管理会社から見積を取得し、それらの見積を比較することが肝要です。 第5章:管理仕様を設定する方法 以下では、「管理仕様を設定する方法」の具体的な手順を中心に解説していきます。前章で説明したとおり、管理費のコストを適切にするための方策として、価格競争にコスト削減は有効に機能しない可能性もあります。不動産のタイプやテナントの種類、建物の構造・設備状況などは千差万別であり、唯一絶対の管理仕様は存在しません。最適な仕様は、建物の特性やオーナーの運営方針、入居者(テナント)ニーズなどによって変動します。したがって、不動産ごとに現状と目標を把握し、管理仕様を段階的かつ継続的に策定・見直ししていくことが求められます。管理仕様の適切な設定が管理コストの合理化や建物競争力の維持改善となるものなので、ある意味で不動産運営における重要ポイントとなります。 5-1.前提条件の整理 まずは、管理仕様を決める際の前提となる情報を整理します。ここで情報が不十分だと、適切な仕様を立案できません。物件の基本情報建物の種類(賃貸住宅、オフィス、商業施設、物流施設など)建築年・階数・延床面積・構造・設備状況(空調、エレベーター、給排水設備、防犯カメラなど)法定点検や行政上の届け出の有無(建築基準法、消防法、労働安全衛生法などの必須点検項目)オーナーの運営方針・目標物件をどのように活用し、どの程度の利益や稼働率をめざすのか資産価値の向上を重視するのか、または早期売却・転貸などの戦略があるのかブランディングやイメージアップ(高級感など)を重視するのか入居者(テナント)の特性・ニーズ賃貸住宅ならファミリー、単身者、高齢者向けなどオフィスなら士業系、IT系、コールセンターなど商業施設なら店舗の業種・営業時間・集客力など物流施設なら荷物の取り扱い量、24時間稼働の有無など現状の課題や希望既にクレームが頻発しているのか、不具合が発生している設備はあるか管理コストをどの程度削減したいのか(短期・長期目標)現状の管理仕様に不足を感じている点は何か 5-2.必要な管理項目の洗い出し 次に、具体的にどのような項目を管理する必要があるのかをリストアップします。建物の種類・規模・設備によって異なりますが、大枠として以下のようなカテゴリに分けると整理しやすいです。清掃日常清掃(共用部のほこり・ごみ回収、玄関・エントランス、トイレなど)定期清掃(フロア洗浄、ガラス清掃、外壁洗浄など)設備保守・点検法定点検(消防設備、エレベーター、空調設備など)予防保守(建物・設備の経年劣化を踏まえた定期点検など)警備・セキュリティ防犯カメラの管理・録画データの保管警備員の常駐や巡回の有無夜間緊急対応(警報発報時の現地対応など)管理人・受付業務常駐管理人の有無(賃貸住宅)受付スタッフの配置(オフィスビルや商業施設)PM(プロパティマネジメント)業務賃料回収、テナント対応、クレーム処理契約更新、退去時の原状回復管理などAM(アセットマネジメント)業務資産価値向上策の検討、長期修繕計画の策定リノベーション提案、リーシング戦略立案など必要な管理項目を一通り洗い出したら、物件の特性とオーナーの方針に照らし合わせて取捨選択を行います。 5-3.重要度と優先順位の評価 管理項目がリストアップできたら、各項目の「重要度」と「優先順位」を評価します。以下のような指標を用いると整理しやすいでしょう。法定必須項目かどうか建物や設備の劣化リスク・入居者への影響度コストと効果(費用対効果)入居者満足度やブランドイメージへの影響このステップでは、1つひとつの項目に対して「なぜ必要なのか」を明確にして、優先度の高いものから確実に管理仕様に組み込むことが大切です。 5-4.管理仕様の具体化とコスト試算 優先度を決定したら、いつ・どの頻度で・どのような内容で実施するかを具体化していきます。その際に、同時にコストの見積もりも行い、仕様と費用のバランスを調整していきます。管理頻度の設定日常清掃:テナント使用状況を鑑みる必要があります。毎日or週○回or月○回定期清掃:日常清掃では対応できない部分や機器類を使用して行う清掃があります。毎月〇回or年〇回設備点検:月次・年次・法定点検のタイミングに合わせる警備・緊急対応:24時間体制か、夜間のみ遠隔監視か管理方法の検討専門業者に外注するか、管理会社による一括手配か巡回や常駐のスタイル、設備点検の報告書作成の有無などコスト試算各項目ごとに必要な人件費・資材費・外注費などを積算管理仕様の高・中・低の3パターンなど、複数のシナリオを比較検討する短期・長期での費用対効果の考察短期的にはコスト削減になるが、長期的に修繕リスクやクレーム対応コストが増える可能性がないかテナントの満足度維持や更新率の向上が見込まれるか仕様変更に伴う価格見直しの検討仕様変更で管理水準の向上を行った場合、それによるテナント負担額の増加ができないかを検討する収入増額のためには、管理仕様単独の変化だけでなく、物件の価値全体を評価して妥当な賃貸条件の見直しも必要となる場合がある 増額を行う場合は一度にすべての増分を転嫁するのでなく、段階的に行うことでテナントの理解を得るように努めることも検討するこの時点で、「もっと安く抑えたいから清掃回数を減らす」「リスク回避のために予防保守を厚くする」といった調整を繰り返し、オーナーのニーズと費用との折り合いをつける一方でテナント満足度も把握しながら仕様見直しを進めます。 5-5.試験運用とフィードバック 策定した管理仕様をすぐにフル稼働させるのではなく、場合によっては試験運用(トライアル)を実施すると、現場のリアルな状況が把握しやすくなります。短期的なテスト導入例)清掃回数を月内で数パターンに分けて実施し、入居者の反応や作業負荷を比較する例)警備体制を常駐から夜間遠隔監視に切り替えてみてトラブル件数を調べるフィードバックの収集入居者やテナントからのクレーム・要望、スタッフからの作業報告を分析クレーム発生頻度や作業負荷が適正かどうかを確認柔軟な仕様修正試験運用で見えた課題を踏まえ、再度仕様を微調整するこのサイクルを繰り返すことで、実態に合った仕様が固まっていく 5-6.本格運用と継続的な見直し 試験運用を経て一定の仕様が固まったら本格運用に移行します。ただし、建物や入居者の状況は時間とともに変化するため、運用開始後も定期的な見直しを行うことが極めて重要です。定期レポート・ミーティング管理会社や業務委託先からの報告書を毎月または四半期で受け取り、清掃品質や設備点検結果、クレーム状況を把握必要に応じて改善要望を伝える入居者アンケート半年や1年ごとに簡易的な満足度調査を実施清掃・警備・設備などに対する評価や要望をヒアリング設備の更新計画との連動長期修繕計画を踏まえて、更新時期が迫っている設備に対する点検強化やリニューアル工事の計画を立案老朽化が進んでいる場合は保守コストが増加しやすいため、管理仕様の組み直しが必要になることも外部環境の変化競合物件の登場、地価や賃料相場の変動法規制の変更(省エネ基準や建築基準法など)需要の高まりによるテナント層の変化(物流施設ならEC需要増加など)収益の変化収入と費用の両面でどのような変化があるかを把握するそれぞれの変化の原因を把握し、トータルの事業としての収益性の変化を把握し、収益改善に向けた検討を重ねるこうした変化に対応しながら、定期的に管理仕様をアップデートするのがビル運営管理の本質です。 5-7.まとめ:状況に合わせた管理仕様の「設定→運用→見直し」が肝 唯一無二の完璧な管理仕様は存在しない物件の状況やオーナーの方針、入居者ニーズによって求められる水準は異なる。法定必須項目やリスク管理は最低限必ず守るコスト削減を最優先すると、長期的な修繕コスト増や入居者離れにつながるリスクがある。短期的なコストカットと長期的な価値維持のバランス清掃や警備を極限まで削減すれば経費は下がるが、結果的にブランドイメージやクレーム対応コストに悪影響を及ぼす可能性がある。試験運用と定期的な見直し一度決めた仕様がベストとは限らない。PDCAサイクルを回し、必要に応じて仕様を修正していく。作業時間と料金は比例身も蓋もない結論に聞こえるかもしれませんが、現在の不動産管理業界の環境では、質の高い管理業務を行うには一定の作業時間は必要であり、その範囲で可能な業務効率化により作業時間も抑制することがコスト削減方法として王道と思われます。ビル運営管理の重要なポイントは、「状況に応じた最適解を継続的に探りながら運営する」というプロセスそのものです。今回ご紹介したステップを踏まえて、ぜひ自分の物件に合った管理仕様を策定し、オーナー・入居者双方が満足できる運営を実現してみてください。 第6章:不動産管理会社の品質を把握する方法 管理業務の品質を確認し、必要に応じて改善要望を伝えるためには、以下のようなポイントを押さえると良いでしょう。 6-1.定期報告書のチェック 月次や四半期で提出される報告書をしっかりと確認し、疑問点があれば管理会社に質問しましょう。清掃実績:清掃箇所や回数、問題点の報告はあるか修繕・点検報告:設備の使用状況、故障の有無や今後の計画はどうなっているかテナント(入居者)対応履歴:クレームや問い合わせの内容と対応結果 6-2.現地確認・立ち会い 定期的に現地を訪問して、以下の点を直接チェックすることも重要です。清掃状態:ごみやほこりが残っていないか、壁や床はきれいに保たれているか設備の稼働状況:エレベーターや空調などの不具合がないか警備体制:防犯カメラが正常に作動しているか、警備員の巡回状況は適切か 6-3.入居者・テナントからの評価 入居者やテナントがいる場合は、定期的にアンケートをとり、管理会社の対応について意見を収集するのも効果的です。クレームや要望が多い場合、管理体制に問題があるかもしれません。 6-4.管理費の内訳の透明性 管理費の明細をしっかり確認し、どの業務にいくらかかっているのかを把握しましょう。不透明な部分が多い場合は、管理会社に説明を求め、納得のいくまで相談することが大切です。 6-5.まとめ 管理業務に関して管理会社に説明を求めた場合の回答内容や説明が適切で納得できる内容であれば、入居者やテナントに対する対応も同様と想定することも可能です。但し、不動産所有者は管理会社の発注主という立場であるため必ずしも異なり、管理会社の窓口が異なる場合もあります。そのような状況を鑑み、管理会社の品質について様々な観点から評価することが望まれ、もし課題を発見したら、管理会社とともに改善に取り組むことも不動産所有者の役割といえます。 第7章:ビルメンテナンス会社の例 本章ではタイプ別にビルメンテナンス会社の例をご紹介します。あくまでビルメンテナンス会社を探す際にどのような特徴があるのかを理解するうえでの一助となることを目的としており、特定の企業の広報を目的とするものではないため、実際の選定についてはご自身で調査されますようお願いいたします。日本のビルメンテナンス業界では、企業ごとに「得意とする物件タイプ」や「強みとする業務分野」が異なります。以下では、施設タイプ別・業務タイプ別にいくつかの主要ビルメンテナンス会社や建物管理会社を例示し、その特徴を簡単に紹介します。あくまで代表例であり、実際には多くの企業が複合的に業務を行っていますので、ご参考程度にご覧ください。 7-1.施設タイプ別 (1)オフィスビル三井不動産ファシリティーズ特徴:三井不動産グループのビルメンテナンス会社。大規模オフィスビルや大規模商業施設の運営管理に強みを持ち、設備管理、ファシリティマネジメントまで幅広く対応。東京ビルサービス株式会社特徴:東京建物グループ。オフィスビルなどのPM・BM(ビルマネジメント)を中心に展開。(2)賃貸住宅(レジデンス・アパートメント)大東建物管理株式会社特徴:大東建託グループの管理会社。賃貸アパート・マンションの一括借上(サブリース)を含めた管理を行い、入居者対応、設備保守、清掃などを総合的に請け負う。主な対象物件:賃貸アパート・マンション。大和リビング特徴:大和ハウスグループの管理会社。賃貸アパート・マンションの管理を行い、入居者対応、設備保守、清掃などを総合的に請け負う。主な対象物件:賃貸アパート・マンション。(3)分譲マンション(区分所有)東急コミュニティー株式会社特徴:東急不動産HD傘下の管理会社。分譲マンションの管理組合運営サポート、清掃・設備点検、長期修繕計画の策定など総合的に対応。主な対象物件:首都圏を中心とした分譲マンション。大京アステージ株式会社特徴:大京グループのマンション管理会社。「ライオンズマンション」シリーズを中心に、管理組合運営サポート、点検・清掃業務、長期修繕計画のコンサルなどを得意とする。主な対象物件:分譲マンション(全国展開)。(4)商業施設(ショッピングセンター・大型商業ビル)イオンディライト株式会社特徴:イオングループの総合ビル管理会社。ショッピングセンター(SC)の清掃・設備管理をはじめ、駐車場運営、セキュリティ、受付案内などワンストップで提供。主な対象物件:イオンモールをはじめとする大規模商業施設。JR東日本ビルテック株式会社特徴:JR東日本グループのビル管理会社。駅ビルや商業施設、オフィスビルの総合管理に強みを持つ。鉄道関連の特殊設備管理にも対応。主な対象物件:駅ビル、商業施設、複合型大規模ビル。(5)物流施設・倉庫星光ビル管理特徴:総合管理会社主な対象物件:倉庫物流施設管理を行う(6)駐車場タイムズ24株式会社(パーク24グループ)特徴:コインパーキングや駐車場運営を主体とした会社。設備保守から料金徴収システムの管理、警備サービスなどを統合的に行う。主な対象物件:駐車場(有人・無人含む)、立体駐車装置。株式会社アズーム主な対象物件:駐車場管理(7)ホテル共立メンテナンス特徴:ドーミーインを展開給食事業なども行う。主な対象物件:ビジネスホテル、リゾートホテル。APAホテルズ&リゾーツ(APAグループ)特徴:APAが自社でホテルの開発・運営を行うケースが多いが、ビルメンテナンスに関してはグループ会社や提携先で設備保守や清掃を担当する。主な対象物件:ビジネスホテル、シティホテル。 7-2.業務タイプ別に強みを持つビルメンテナンス会社の例 (1)清掃業務(ビルクリーニング)東洋テック株式会社特徴:関西を中心に清掃業務や警備業務を得意とする会社。ビル清掃、ガラス清掃、高所作業などの専門技術を有し、警備と合わせて総合管理を行うことも可能。太平ビルサービス株式会社特徴:清掃・設備管理を中心に、全国に拠点を持つ。特に清掃領域ではオフィス・病院・学校など多様な施設対応の実績が豊富。(2)設備保守(電気・空調・給排水・消防など)ビル設備系メーカー系サービス会社例:三菱電機ビルテクノサービス、日立ビルシステム、東芝エレベータ、ダイキンHVACソリューションなど特徴:自社製品(エレベーター、空調設備など)に関する保守点検を中心に、ビルメンテナンス全般に拡大対応している。純正部品・メーカー技術者によるメンテナンスを強みとする。アズビル株式会社(旧:山武)特徴:ビルオートメーションシステム(BAS)など、中央監視・制御設備の保守を得意とし、空調制御・エネルギーマネジメントなど付加価値の高いサービスを提供。(3)修繕工事鹿島建物総合管理株式会社(鹿島グループ)特徴:大手ゼネコン鹿島建設グループ。オフィスビルやマンション等の定期修繕・改修工事の提案・実施を行う。建築知識・施工体制が強み。長谷工コミュニティ(長谷工グループ)特徴:マンション管理と大規模修繕工事で高いシェアを持つ。長谷工コーポレーションの建築ノウハウを生かし、老朽化対策や耐震補強など総合的に対応。(4)ビル運営(テナント管理・運営企画・PM業務)CBRE株式会社特徴:外資系不動産サービス会社。グローバル基準のPM(プロパティマネジメント)、アセットマネジメント、リーシング戦略など幅広いサービスを提供。対象業務:オフィス・商業施設の運営管理、テナント付け、契約交渉・レポーティングなど。 7-3.まとめ 施設タイプ別の得意分野オフィスビル:大手デベロッパー系管理会社賃貸住宅:大東建物管理、レオパレス・パートナーズなど賃貸管理大手分譲マンション:東急コミュニティー、大京アステージなどマンション管理専業大手商業施設:イオンディライト、JR東日本ビルテックなど、SCや駅ビルに強い会社駐車場:タイムズ24など駐車場運営に強い企業ホテル:APAなどホテル運営受託会社業務タイプ別の得意分野清掃:太平ビルサービス、東洋テックなど清掃専門部隊が充実設備保守:三菱電機ビルテクノサービス、日立ビルシステム、アズビルなどメーカー系修繕工事:鹿島建物総合管理、長谷工コミュニティなど建設・ゼネコン系ビル運営(PM業務):外資系不動産サービス企業(CBREなど)、大手デベロッパーグループこのように、ビルメンテナンス会社を選定する際は「対象となる建物の種類や用途」と「必要とする業務の種類・範囲」を明確にし、それに応じて専門性を持つ会社を比較検討することが重要です。大手のグループ会社やゼネコン系、メーカー系、外資系など背景が異なる企業が多いため、コスト・対応スピード・サービス品質など各社の特徴を総合的に踏まえて判断します。 第8章:不動産理論・法律における管理費 以下の内容は、日本における不動産鑑定評価基準や関連する実務の一般的な考え方に基づいてまとめた情報です。個別の案件や契約内容によって扱いが異なる場合があるため、詳細な判断が必要な場合は不動産鑑定士や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。冒頭で説明したように管理費の用語は一義的な意味で使われるとは限らないので総括的な知識を持ち、具体的な管理費の議論においてどのような意味合いで使っているのかを把握できるよう補足しています。不動産所有者が管理会社や入居者とのコミュニケーションにおいて、管理費という用語で齟齬が生じないように配慮しています。 8-1.不動産鑑定理論における管理費の位置づけ ①管理費は「オーナーが負担する費用」として捉えられる不動産鑑定評価(特に収益還元法)の考え方では、対象不動産から期待される純収益(Net Operating Income:NOI)を把握するために、賃料収入などの総収益から運営費(管理費や修繕費、固定資産税など)を差し引くという手順を取ります。このとき挙げられる「管理費」は、建物全体の維持管理にかかる費用共用部分の清掃や設備保守・警備などに必要な費用管理会社へ支払う管理委託手数料その他、建物を適正に維持するための一般的な費用といった項目が含まれます。【実務上の扱い】不動産鑑定評価では、賃貸事業を行うオーナー側が負担するべき管理費(=運営側の費用)を前提とします。テナント(入居者)に転嫁できる管理費(共益費)部分があれば、それはオーナーにとって実質的に「収益」になるため、「オーナー負担分」と「テナント負担分」に分けて整理を行うことが多いです。②テナントが負担する「管理費」や「共益費」の扱い一方で、実務の賃貸契約においては、テナントが負担する管理費や共益費が別途設定される場合があります。例えばオフィスやマンションの賃貸借契約書を見ると、「賃料:○○円」「管理費(または共益費):○○円」という形で明記されている入居者は毎月、賃料と管理費(共益費)を合わせて支払うといったケースです。【鑑定評価上の考え方】この「管理費(共益費)」をテナント側が全額負担する契約形態であれば、理論上オーナーが負担する管理費はその分だけ軽減され、オーナーの実質的な収益(NOI)が増加することになります。不動産鑑定の場面では、「テナント負担の管理費相当分を含めた実質的な収入」を把握しつつ、オーナーが直接負担しなければならない管理関連費用(共用部の光熱費や保守費など)がどこまで発生するのかを精査して、最終的な純収益を算出します。 8-2.賃貸不動産における管理費・共益費の法的性質 ①賃貸借契約と管理費の取り扱い日本の民法(債権法)や借地借家法などを見ると、「賃貸借契約でいう賃料」として定義されるのは一般的に使用収益の対価です。一方、管理費や共益費という名称自体は法律上で独立した定義があるわけではありません。賃料:目的物の使用収益に対して支払う対価。管理費・共益費:本来は、共用部の維持管理にかかる費用を入居者が按分して支払う趣旨(と契約で定められることが多い)。しかし、法律上は「賃料の一部」とみなされる場合もあるため、必ずしも賃料と別の法的性質を持つとは限らない。【実務では「賃料+管理費(共益費)」と呼んでも、法的にはひとまとめになりがち】賃貸借契約書の記載次第ですが、裁判例や実務上、「賃料以外の名目で定期的に支払われる金員も含めて、実質的には賃料として扱う」と解される場合があります。例えば、滞納時の賃料回収や契約解除の要件などで「名目が何であれ、入居者が毎月支払う金額は賃料性を有する」と整理されることが少なくありません。②管理費(共益費)は何らかの特別な法律に基づくものか?日本の法律で「管理費」を独立して定義しているものはないといえます。区分所有法でいう「管理費」はマンション管理組合に関する費用(区分所有建物の管理費)を指す場合もありますが、これは区分所有者の負担分であり、賃貸借契約での「管理費」とは別の文脈。一般的な賃貸物件における「管理費」や「共益費」は、あくまで当事者の合意(契約書の定め)により賃料と別枠で設定している金額にすぎません。【管理費の法的性質】賃貸借契約に基づき、当事者同士の合意で定期的に支払われる金員名目上「管理費」や「共益費」と呼ばれていても、法的には「賃料の一部」とみなされる場合がある。 8-3.不動産鑑定における管理費水準の判断 ①市場実態との比較不動産鑑定評価において、管理費の水準が高いか低いかを判断する際は、類似物件の事例(共益費相場など)と照合したり、賃料水準とのバランスを見ながら判断することが多いです。近隣や同種の物件で管理費・共益費がどれくらい設定されているかオーナー側が負担する管理費(運営費)は、規模や管理内容に照らして妥当な金額か②管理費を調整することで賃料総額とバランスをとるまた、テナントが負担する管理費が高めに設定されている場合、逆に賃料がやや低く設定されているなど、いわゆる「賃料+管理費」の総額を見て競合物件と比較する手法もよく行われます。賃料と管理費(共益費)は通算して検討し、「月額トータルでいくら支払うか」がテナントにとっての実質負担不動産鑑定では、実質的な稼働総収益(賃料+共益費収入)を加味しつつ、オーナー負担分の管理費支出を控除する形で純収益を推定③結論:鑑定評価では「市場水準」「賃貸条件の実態」「オーナー実質負担」を確認鑑定士は「賃料+管理費の合計額がマーケットの需給状況と比べて妥当かどうか」を見極めつつ、オーナーが最終的に負担する管理費用の妥当性も併せて調査・算定します。これにより、収益還元法のベースとなる純収益(NOI)をなるべく正確に把握し、最終的な試算価格に反映させるのが一般的なアプローチです。 8-4.取適法(旧:下請法)に関する確認 2026年1月より取適法(正式名称:中小受託取引適正化法)にて下請法で規定されたルールが強化されていますが、本稿では便宜上、作成時点で一般に浸透している『下請法』という呼称も併記します。不動産管理業務の委託は、「役務提供委託」に該当し得るため、不動産所有者が親事業者、管理会社が下請事業者となり、取適法が適用される可能性があります。例えば下請法が適用される場合、(1)支払いサイトの制限(2)発注書面の交付義務(3)不当な減額・追加業務押し付けの禁止などを遵守しなければなりませんでした。特に、旧下請法の運用上、手形等の支払条件(サイト)が60日を超える取引慣行について是正が求められるため、支払方法(手形・電子記録債権等)と支払期日の設計には注意が必要です。実際の適用可否は、「資本金規模の対比」「業務委託が親事業者の“事業の一部”に当たるかどうか」などの要素で判断されます。不動産オーナーが大規模法人で、不動産管理会社がそれよりも小規模な法人であるなど要件を満たす場合は、契約スキーム・支払い条件・契約書類の整備について取適法違反とならないよう注意が必要です。 8-5.理論的な管理費についてのまとめ 不動産鑑定評価における「管理費」は、建物の運営維持にかかる費用として、オーナー側の支出項目に位置づけられる。テナントが負担する管理費・共益費は、法律上独立した概念があるわけではなく、賃貸借契約で当事者間が合意した金額にすぎません。場合によっては実質「賃料の一部」として扱われる場合もある。鑑定評価では、管理費の水準を判断する際に、近隣や類似物件との比較や、賃料+管理費総額とのバランスをチェックする。法的には管理費という言葉自体に特別な定義はなく、あくまで当事者間合意の結果。滞納・契約解除などの局面では、管理費と賃料を分離できずに同じ「賃貸借契約上の金員」とみなされる場合がある。最終的に、「管理費はどう位置づけられるか」は契約や鑑定評価上の考え方に左右されますが、実務的には「テナントが負担する分(共益費)」と「オーナーが負担する分(運営費)」に区分し、収益と費用を正しく整理することが重要です。一方、法律上は「賃貸借契約による賃料等の支払い」という大枠の中で扱われ、名目がどうであれ実質的に賃料性を有する場合が多い点に留意が必要です。そこで、実務的には賃貸事業において、テナントから徴収する賃料、管理費、共益費などは賃貸収入(=賃料)とし、不動産運営管理に必要な管理外注費や管理に必要な経費は賃貸管理原価(=管理費)と用語を区分すると整理できると思われます。 まとめ:最適な不動産管理で資産価値を守る 不動産管理費は、建物や設備を適切に維持するために必要なコストです。一見すると負担に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえて管理会社を選び、適切な仕様を設定し、予防保守や一括発注などを駆使することで、費用対効果を高めることが可能です。管理会社に委託するメリット:専門知識の活用、コスト管理や不動産事業の効率化、クレーム対応の負担軽減など委託時の手順:業務範囲・仕様の明確化、複数社への見積もり依頼、仕様のすり合わせ、契約・運用開始コスト削減の秘訣:必要十分な管理仕様、必要に応じた見直し、予防保守の徹底、一括発注の活用、省エネ対策品質チェック:定期報告書や現地確認、入居者アンケートの活用、費用内訳の透明化不動産運営管理の相談先:実績のある不動産管理会社は長年の知識・経験をもとに不動産運営で大きな課題が生じた場合に専門的な知見を踏まえたアドバイスを求めることもできます。物件を管理しているため、外部専門家としてだけでなく、不動産運営のパートナーとして活用しましょう。上記を踏まえ、賃貸住宅やオフィス、商業施設、物流施設などの特性に合わせて、無理のない管理計画を立てることが大切です。最終的には、建物の品質維持や資産価値の向上につながる管理を目指し、管理会社との信頼関係を築いていきましょう。不動産管理は奥が深い分野ですが、きちんと理解して取り組むことで大切な不動産を長く・安全に運営することができます。初めての方でもこの記事を参考に、最適な管理体制を整えてみてください。もし、不動産管理についてご質問等あればお気軽にご連絡下さい。お待ちしています。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ代表取締役 羽部 浩志 1991年東京大学経済学部卒業 ビルディング不動産株式会社入社後、不動産仲介営業に携わる 1999年サブリース株式会社に転籍し、プロパティマネジメント業務に携わる 2022年サブリース株式会社代表取締役就任(現職) ライフワークはすぐれた空間作り 2026年2月10日執筆2026年02月10日 -
プロパティマネジメント
「そこにあるから借りているだけ」というのは、ホントなの? ── テナント企業は賃貸オフィスのことを、どこまで真面目に考えているのか
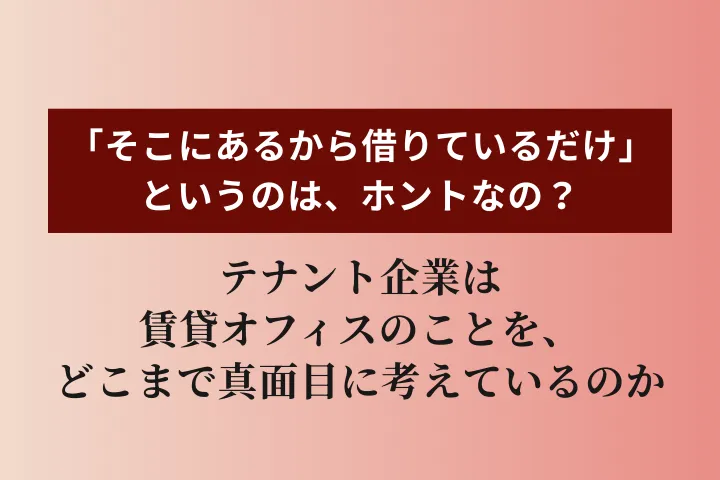 皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの飯野です。この記事は「そこにあるから借りているだけ」というのは、ホントなの?──テナント企業は賃貸オフィスのことを、どこまで真面目に考えているのか」というタイトルで、2026年2月9日に執筆しています。少しでも、皆様に新たな気づきをもたらして、お役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次序章:「そこにあるから借りてるだけ」なの?第1章:賃貸オフィスに関連する社内の意思決定は、なぜ“隙間”に落ちるのか第2章:テナント企業は、賃貸オフィスのどこで“マイナスになっている”のか第3章:賃貸オフィスの賃料を「ただの場所代」と見做す視線の根っこ第4章:賃貸オフィスをインフラとして扱うテナント企業と、雑務として扱うテナント企業の差第5章:貸主側が持てる視点:テナント側の運用に問題があることを前提に対処する終章:「そこにあるから借りてるだけ」を、言葉どおり受け取らない 序章:「そこにあるから借りてるだけ」なの? 賃貸オフィスビルの運営に携わっていると、ふと、不思議な感覚に襲われることがあります。テナント企業にとって、賃貸オフィスは「なくては困る」インフラです。明日から突然、その賃貸オフィスが使えなくなれば、営業も、バックオフィス事務も、採用も、会議も、ほとんどの業務が立ち行かなくなる。いわば、事業の基盤を支えている場所と言えます。けれども、賃貸オフィスの現場で耳にする言葉や、社内の意思決定のされ方を見ていると、どうも、その“インフラ”としての重要性と、テナントの社内での扱われ方のあいだに、微妙なギャップがあるようにも感じられます。「たまたま、そこに空いている物件があったから」「予算の範囲で、いちばん条件が良かったから」「社員から文句が出ていないので、今のところ大丈夫」どれも、現場でよく聞かれるフレーズです。もちろん、オフィス移転のたびに、経営方針を踏まえて、経営の哲学にまで立ち返った議論をしてほしい/しなくてはいけない、というつもりはありません。ただ、「なくては困るインフラ」にしては、あまりに“その場しのぎ”の言葉が並んでいるな、という違和感は拭えないのです。たとえば、製造業の会社において、工場のことであればどうでしょうか。どのエリアに建てるのか。どのくらいの投資をして、どのような製造ラインを組んで、どのように人と設備を配置するのか。その工場を、10年後、20年後にどのように使っていくのか。こうした問いは、経営のど真ん中で議論されるはずです。工場は、製造業の会社にとって、ビジネス上の競争力に直結するインフラだからです。そこに「たまたま空いていたから」「予算的にちょうど良かったから」で決めて良いことなど、あり得ません。しかし、賃貸オフィスになると、話は一気に軽くなっているように見受けられます。さすがに、オフィスの立地については、経営会議で一定の議論が行われるかもしれません。けれど、そのあとの賃貸条件の検討や、日々の運営、更新や解約の判断といった“インフラとしての運用”の部分は、多くの会社で「総務の仕事」として、一段下のレイヤーに落とされているのではないでしょうか。賃貸オフィスはテナント企業にとって、「止まったら困るインフラ」であるにもかかわらず、社内の位置づけとしては“雑務の延長線上”に置かれやすい。そのギャップが、現場でのコミュニケーションや交渉、ビル管理会社との関係性に、じわじわと影響を与えています。オフィスは「そこにあるから借りているだけ」なのか。それとも、本来は工場や物流拠点と同じように、もっと真面目に向き合うべきインフラなのか。このコラムでは、賃貸オフィスビルのビル管理会社という立場から、テナント企業が賃貸オフィスをどのように扱っているのか、その結果、どんな不都合が生まれる可能性があるのか、そして、その前提を踏まえたうえで、貸主側(ビル・オーナー・ビル管理会社側)はどこまで付き合い、どこで線を引くべきなのか――そんなことを、整理してみたいと思います。 第1章:賃貸オフィスに関連する社内の意思決定は、なぜ“隙間”に落ちるのか 序章で触れたとおり、賃貸オフィスは「止まったら困るインフラ」です。それなのに、実務の世界をのぞいてみると、その扱われ方はどう見ても“インフラ級”ではない。このギャップの正体を、まずは社内の意思決定プロセスから分解してみます。 1-1.賃貸オフィスの話には、本来いろんな部署が絡むはずなのに 賃貸オフィスについて、本当は誰が何を考えるべきなのか。ざっくり分解すると、こんな感じになります。経営陣事業ポートフォリオと拠点戦略中長期の人員計画・働き方の方向性固定費としての賃料水準・投資配分事業部門(現場)実際の働き方(来社頻度・会議のスタイル・来客の多さ)必要な席数・会議室数・倉庫スペース拠点ごとの役割分担(開発拠点なのか、営業拠点なのかなど)人事・労務採用・定着に効くロケーションやオフィス環境の水準ハイブリッドワークなど就業制度との整合性安全衛生・従業員のコンディション管理財務・経理キャッシュフローと賃料負担のバランス原価・販管費としての位置づけ長期の賃貸借契約がもつリスク総務・ファシリティビル側との窓口・日々の運用レイアウト変更・増員対応・修繕の取り回し契約更新や原状回復、移転プロジェクトの実務こうして並べてみると、賃貸オフィスの話って、本来は会社のほぼ全部門にまたがる「ど真ん中のテーマ」なんですよね。工場ほど露骨ではないにせよ、経営、事業、人、カネ、現場運用――全部が絡んでくる。……なんですが、現実の会社を見ていると、この全員がちゃんと集まって、腰を据えてオフィスを議論しているケースは、そこまで多くないのでは、ないのでしょうか。 1-2.プロジェクトのときだけ“総力戦”、ふだんは“総務預かり” 賃貸オフィスの話が社内で大きく扱われるタイミングは、だいたい決まっています。賃貸契約の更新が近づいて、「このビル、出るか・残るか」を決めるとき事業拡大や統合で、「増床・移転が必要だ」となったとき働き方改革やコロナ後対応で、「オフィスのあり方を見直そう」となったときこういう「一大イベント」のときには、経営陣も事業部門も人事も巻き込んで、プロジェクト・チームが立ち上がる。そこでは確かに、かなり真面目な議論が行われます。ただ、問題はその後です。移転・増床のプロジェクトが終わった瞬間、チームは解散されるその後の運営・細かな条件調整・更新の検討は、総務・ファシリティが単独で担う形に戻る「とりあえず今の条件からあまりブラさない範囲で更新しておいてください」というざっくりした指示だけ降りてくる結果として、オフィスに関する日々の意思決定は、どうしても「上でざっくり方向性を決める→具体的な判断は総務が現場で処理する」という構図に収まりがちです。ここで問題にしているのは、賃貸オフィス関連業務の扱いが結果的に“隙間業務”に落ちてしまう会社の仕組みであって、「総務がオフィスを真剣に考えていないから」というわけではありません。会社組織の業務分担とリソース配分の設計によって、賃貸オフィスの検討が会社組織の“隙間の仕事”に押し込まれてしまっているという点です。総務の仕事の現場を見てみると、株主総会・取締役会の準備社内規程・押印・契約書管理郵便・電話・来客対応備品・印章・社有車・携帯・PCの管理社内イベントや福利厚生の取り回し……といった、会社の裏側全般を抱えながら、その延長で「賃貸オフィスも見る」ことを求められているというようにも見受けられます。そこに突然、賃貸オフィス関連で、「年間◯億円レベルの固定費」を左右する賃貸条件の交渉10年スパンで効いてくるオフィスのレイアウトや仕様の判断ビル・オーナー、ビル管理会社との長期的な関係構築などが業務分掌のリストに追加されてのってくるわけなので、「雑に扱っている」というより、物理的・能力的に“抱えきれていない”って状況になってしまうんですよね。 1-3.「賃貸オフィスだけのことを考える人」が、社内にいない もう一つ、大きな会社の構造的な問題があるのではって思っています。それは、ほとんどの会社には「オフィスのことだけを、専門的に考えるポジション」が必ずしも置かれていない、という点です。IR担当は、投資家とどうコミュニケーションを取るか、で評価される人事担当は、採用・定着・評価制度などで評価される経営企画は、事業戦略・中期計画の実現度で評価されるじゃあ、「このオフィスが、事業と人にとってベストな状態かどうか」という点で評価されている人は、社内にいるか?と言われると、正直かなり怪しい。総務にしても、「トラブルなく回っているか」「コストが膨らんでいないか」「社員から大きな不満が出ていないか」といった、“マイナスを出さないこと”で評価されるケースが多い。プラスをどこまで取りに行くか、という視点でオフィスを設計する役割は、そもそも誰にも割り当てられていない。つまり、工場:「生産性」という、めちゃくちゃわかりやすいKPIがある物流拠点:配送リードタイムや在庫回転率など、測れる指標があるオフィス:生産性はチームや人によってバラバラ売上との因果関係も測りづらい「ここをこう変えたら〇%業績が上がる」とは言いきれないこうなってくると、賃貸オフィスの話は、どうしても「誰のKPIでもないから、誰も本気でその問題のオーナーシップを取りにいかない」という状態に陥りがちです。 1-4.重要だけど緊急じゃないものは、だいたい後回しになる さらに追い打ちをかけているのが、「緊急度と重要度」の問題です。いますぐ困るわけではないけど、じわじわ効いてくるコストいますぐクレームになるわけではないけど、じわじわ効いてくる使いにくさいますぐ採用難になるわけではないけど、じわじわ効いてくる立地や設備の見劣りオフィスに関する課題は、ほとんどが「重要だけど緊急じゃない」ゾーンに入ります。その一方で、会社には法改正対応システムトラブル大口顧客の対応組織再編・人事異動…などなど「重要かつ緊急」なタスクが、毎日のように降ってきます。その結果どうなるか。賃料の適正水準や、契約条件の見直しは「今度ちゃんと検討しよう」で棚上げレイアウトの最適化や、フロア構成の見直しは「増員したら考えよう」で先送り更新のタイミングになって、ようやくバタバタと協議が始まり、結局「現状維持」が一番通しやすい選択肢に見えてしまう貸主側(ビル・オーナー/ビル管理会社の側)から見ると、「このタイミングで、ちゃんと議論&検討のリストにのせて、関係者でテーブルを囲んで話せれば、結果的に、テナント側にもメリットが出るのに」という局面は、正直かなり多いです。でもテナントの会社内では、そういう中長期の調整に時間を割く余裕がない。ここにも、個人のやる気とか能力というより、会社の構造として“後回しになりやすいテーマ”に分類されてしまっているという事情があります。 1-5.「総務のせい」にしても、何も前に進まない ここまで整理してくると、賃貸オフィスの話は、本来ほぼ全社的なテーマでもプロジェクトのときを除けば、総務・ファシリティに集約されがちそもそも「オフィスの最適化」で評価される人が社内にいない重要だけど緊急じゃないので、構造的に後回しになりやすいという、ちょっと意地悪なパズルのような構図が見えてきます。この状態を前にして、「総務がちゃんとやっていないからだ」と結論づけてしまうのは、正直かなり乱暴だし、非生産的です。人も時間も足りないなかで、会社の“裏側全部”を担っている部署に、「オフィス戦略まで完璧に設計しておいてください」は、さすがに荷が重すぎる。むしろ、経営側が「オフィスをどう位置づけるか」をちゃんと決めているか事業側が「自分たちの仕事にとって、どんなオフィスが必要か」を言語化できているかその上で総務が、ビル管理会社との交渉や日々の運用を“実務として回せる状態”になっているかをセットで見ないと、現場の状況は変わっていきません。 第2章:テナント企業は、賃貸オフィスのどこで“マイナスになっている”のか 第1章では、賃貸オフィスに関連する意思決定が、会社の仕組み上、どうしても“隙間”に落ちやすいという話をしました。ここからは、その結果として、テナント企業側にどんな“マイナス”が生じ得るのかを、もう少し具体的に見ていきます。ここで言う「マイナス」は、いきなり、大きな損失が生じるというのではなくて、余計な費用負担もう少し楽に回せたはずの日常的な業務運用が、ジワジワとしんどくなってしまうという状況みたいな、「ジワジワ系のマイナス」がメイン・ストーリーです。複数の賃貸オフィスビルを横断してテナントの動きを見ていると、同じようなパターンが繰り返されているのがわかります。しかもそれは、「誰かがサボっているから」ではなく、テナント企業での社内の意思決定プロセスそのものがそういうマイナスを生みやすい設計になっている、という言い方のほうがしっくりきます。 2-1.賃料だけ見て「まあ妥当」という判断 わかりやすい例として、「賃料単価だけ見て、なんとなく“相場並みだからOK”になっているケース」です。よくある流れは、こんな感じです。立地と賃料は、仲介会社が持ってきた比較表で確認「この条件なら予算内なので大丈夫そう」ということを以て社内で意思決定表面上の立地を踏まえた賃料は“相場並み”でも、賃貸オフィスビルのグレード、床面積、設備、ビル管理の状況が、本当に見合っているのかについての確認、判断は複雑で難しいので、テナント企業自身が必ずしも重視していないポイントで余計な賃料プレミアムを負担しているというケースも珍しくなくて、そのことが見過ごされていたりもします。ここでのポイントは、社内の議論のテーブルに上がるのが、「立地を踏まえた賃料」と「床面積」に限定されがち賃貸契約の諸条件、賃貸オフィスビルのグレード等を細かく読み込んで、メリット、デメリット、将来コストを試算するだけの時間も、ツールも、役割も用意されていないという「テナント企業の社内の意思判断、組織設計の事情」にあります。個々の担当者の能力の問題ではなく、「賃料、床面積、立地」以外の論点が、そもそも議論に乗りにくい社内の意思決定の仕組みになっている、ということ。 2-2.「とりあえず今のまま」でという判断 次に多いのが、賃貸契約の更新局面で、本来なら検討すべきポイントを自分から見なかったことにしてしまうパターンです。判断としては「現状維持」なんだけど、実態は「現状維持しか選べない状態に自分で寄せていく」みたいな進み方になります。典型例はこうです。賃貸契約の更新が近づいても、社内検討がギリギリまで進まない更新時期が見えているのに、社内での議論が始まらない(始める担当も決まらない)。結果、ビル管理会社から「更新どうしますか?ちなみに適正賃料は○○なので、賃料を○○円上げたいです」という連絡が来て初めて、ようやく社内が“目覚める”。ビル管理会社との交渉での「落としどころ探し」だけになる社内で準備がない状態だと、できることが限られます。せいぜい、「とりあえず更新前提で、提示賃料と現状賃料の“真ん中あたり”を目安に交渉する」みたいな、反射的な対応になりやすい。これでは交渉の主導権は握れません。賃料の妥当性チェックが、近隣相場を踏まえて適正賃料を提示している管理会社の資料の妥当性の確認だけ。本来、テナント企業のビジネスにとっての、賃貸オフィスのロケーションの妥当性を踏まえて、賃料をどこまで負担できるのかということを社内で検討して、判断の上で、協議に臨むべきなのですが、そこまでの判断が下されているのでしょうか。本来、協議のテーブルに乗る前に、テナント側で最低限ここまで整っていると話は一気に前に進みます。社内で移転/残留のシナリオ比較がある程度できている「この条件なら残る」「ここまで上がるなら移転も検討せざるを得ない」というライン(判断基準)が、関係者の間で共有されているこの状態で話が始まれば、相場賃料との乖離があるのに「現状維持一点張り」で停滞し続ける、みたいな不毛なプロセスは避けられます。貸主側も、条件の根拠を出しやすいし、テナント側も“どこが争点か”を絞れる。つまり、お互いに時間を溶かさずに済む。でも現実は、そこまでたどり着かないケースがかなり多い。結局、更新期限ギリギリで「とりあえず継続」を前提に賃料の折り合いどころだけを探すこの形に落ちます。この進み方の問題は、単に交渉がお互いにとって非効率的であるだけじゃありません。立地、床面積、人員配置、運用のしやすさ、コスト負担――そういう要素を並べて、費用とメリットの両面から最適化する機会を、テナント自身が放棄している、とも言えます。更新は本来、そこを見直す“数少ない節目”のはずなので。ここでも原因は、個人のやる気の問題ではなく、ほぼ「社内の意思決定プロセスの設計」にあります。賃貸契約の更新検討に必要な時間が、社内スケジュールとして確保されていない「誰が」「どこまで決めるのか」という社内ルールが曖昧この2つが残っている限り、賃貸契約の更新のたびに同じことが起きます。だからこの節で言いたいのは、「賃貸契約の更新で揉める」のが問題なんじゃなくて、揉め方が毎回“準備不足の揉め方”になってしまう構造が問題、という点です。 2-3.人員増とレイアウト変更のたびに、じわじわと運用コストを払わされる テナント企業の組織改編、人員増を踏まえたとオフィス・レイアウト改変・調整の“ズレによるマイナス”も無視できません。よくあるのは、オフィスの移転、組織改編、人員増に対応した増床のタイミングで、レイアウトの基本設計をそこまで詰めないままスタートするそのときは「とりあえず目の前の人数が入ればOK」が最優先になるその後の組織改編、人員増を見越していないので、そのたびに、間に合わせで対応するので、オフィスで業務を進めるにあたって、やりにくさが露呈してくるというパターン。結果として、少し人が増えたり、組織をちょこっといじくるたびに、都度、レイアウト変更している会議室が足りなくなりがち文書保管のスペース等が後から足りなくなり、その調整に手間がかかるみたいな形で、「最初にちゃんと設計しておけば避けられたコスト」が、後からジワジワ出てきます。ここでも共通しているのは、レイアウト設計のときに、事業計画・人員計画とセットで検討されていない「どう増えるか」「どう縮むか」のシナリオを描ける人が、その場にいないという業務プロセス、組織の構造的なポイントです。「個人の担当者の判断が甘かったから」ではなく、オフィス計画と事業計画が別々のテーブルで進んでしまう組織設計になっているから、こうなりやすい、という見方のほうがしっくりきます。 2-4.賃料だけを重視して、賃貸オフィスビルのグレードを下げると、採用・従業員の定着で見えないマイナスが生じやすい もう1つ、数字には乗りにくいけれど無視できないのが、テナントの従業員側の“小さな我慢”の積み上げによるマイナスです。例えば、賃料をケチって、賃貸オフィスビルのグレードを下げると、どうしても、設備、ビル管理に皺寄せがいってしまって、エレベーター、トイレ・給湯室、空調等のキャパ不足、不調が起こりがちです。どれも1つ1つを取り出すと、「致命的な不具合」とまでは言いにくいものです。でも、毎日・毎週・毎月と積み重なっていくと、テナントの従業員、オフィスへの来訪者への印象に、普通にネガティブに効いてきます。例えば、ちょっとした不満が、「この会社で長く働きたいか?」の判断に影響する採用面接で来社した候補者が、辞退しがちお客様が来たときの印象が、営業のスタートラインに反映されるこういった影響は、KPIとして明示され難いのかもしれません。そのため社内ではどうしても「とりあえず現状維持で」で処理されがちです。ただ、複数のオフィス環境を見比べていると、“我慢の総量”が一定ラインを超えたあたりで、従業員の離職のタイミング、採用の手ごたえ、お客様からの「見られ方」に、ジワっと差が出てくるよな……という感覚は、どうしても拭えません。ここも結局、「従業員の小さな不満」を拾って、人事・総務・ビジネスの現場マネージャーの間で情報共有する場がなく、社内コミュニケーション・プロセスの設計不足が問題の背景にあります。 2-5.場当たり対応が、貸主側との関係性をじわじわ削っていく 最後に、少しセンシティブですが、貸主側(ビル・オーナー/ビル管理会社側)との関係性の“マイナス”の話です。例えば、テナントが:賃貸契約の更新の際、合理的な事由を示さずに「賃料は絶対に現状維持」とだけ主張し続ける社内の意思決定プロセスが外から見えず、「誰が何を決めているのか」が、まったくあやふや。こういったことが続くと、貸主側としては、「このテナントとは、中長期の前提を共有し難いな」「何か問題があっても、合理的に協議し検討するのは難しそうだ」と感じざるを得ない部分が出てきます。その結果として、テナントを重要なパートナーとして位置付けるが難しくなってしまい、入替え可能な相手先として扱わざるを得なくなりがちで、“一歩踏み込んだ提案・相談”をすること自体難しくなるという形のマイナスが出てきます。これも、「総務の対応が悪い」と切ってしまうと、ものすごく雑です。実際には、社内の意思決定に必要な時間が確保されていない誰が窓口で、どこまで権限を持つのかが曖昧「賃貸オフィスのことをちゃんと話す場」がそもそも用意されていないといった、テナント企業の会社としてのガバナンス設計・役割設計の問題として立ち上がってきます。 第3章:賃貸オフィスの賃料を「ただの場所代」と見做す視線の根っこ 賃貸オフィスがテナント社内で軽く扱われるのは、「隙間に落ちている」からだけでもありません。もう少し根っこのところに、オフィス賃貸で成り立つ収益不動産=そこにあるだけで賃料を生むものというイメージが、かなり強く影響しているのではないか――私はそこを疑っています。もちろん、収益不動産の仕組みや歴史をここで掘るつもりはありません。ここで押さえたいのは、テナント側の感覚として自然に立ち上がってくる“見え方”です。前提として、テナント側の頭のなかでは、だいたい次のような図式で整理されがちです。オーナーは、収益不動産を保有し、賃料を受け取る側テナントは、事業で稼いだ収益から、賃料という固定費を支払い続ける側事実と言えば事実です。問題は、この図式そのものではなく、この図式がどう受け止められるかです。実務では、交渉や連絡の相手は管理会社になります。するとテナントの目には、オーナーと管理会社がひとまとめに「同じ側」に見えやすい。ここで“見え方”が固定されます。さらに、賃料という支払いは、モノの納品や工事の完了のように、「これと引き換えに払った」と言い切れる対象が見えにくい。よく考えれば、建物・設備の整備、共用部の運用、保守、ルール整備、トラブル対応など、支払いの背景にはいろいろな実務がある。ただ、その内側を詳しく見ない限り、表面上は「箱に居られる権利にお金を払っている」ようにも見えてしまう。つまり賃料は、等価交換として測りにくい。測りにくい以上、比較軸が持ちにくい。比較軸が持てないと、人は納得のための物語を作ります。いちばん手っ取り早い物語が、「相手は持っているだけで入ってくる側」「こちらは稼いで払っている側」という整理です。そしていつの間にか、“払っている側が主導権を持つはずだ”という錯覚に寄っていく(※この「払った側が上」という感覚は、贈与と返礼の関係に近い構造として理解できる、という見方もあります。)この錯覚が定着してしまうと、振る舞いも変わってきます。本来、賃貸オフィスは、責任分界、連絡の経路、判断のタイミング、情報の粒度といった運用仕様を前提に回すインフラです。ところが“主導権の錯覚”が前提になると、そうした仕様の細かい話が細っていき、「結局いくらか」という一点に議論が寄っていく。隙間に落ちる以前に、テナント側に「賃貸オフィスの運用を見ないようにさせる装置」が内在している――私はむしろ、そう考えています。そして、その錯覚があるからこそ、結果として賃貸オフィスが「隙間に落ちている」とも言える。その結果、賃貸オフィスを巡る協議の経過も粗略に扱われやすくなる。「誰が何を言ったか」「どこまで決まっているか」「何が前提条件か」を社内で丁寧に共有しなくなる。ビル管理会社側にも前提が伝わらない。話が再現できない。だから同じ説明を何度も繰り返し、最後に揉める。さらに厄介なのはここから先です。この“主導権の錯覚”が強くなると、嘘や誇張への罪悪感が薄くなることがある。「相手はどうせ取っている側だ」「こちらは払っている側だ」という自己正当化が、雑なコミュニケーションを正当化してしまうからです。人間は、納得しづらい支払いに対して、後から理屈を作るのがうまい。賃料が等価交換として測りにくい以上、この手の“見え方”は、ある意味で自然に発生しがちです。この章の結論はシンプルです。“賃貸オフィスの賃料をただの場所代として扱う視線”が、テナント側との協議や運用を荒らしやすいのです。そしてその荒れは、結局、テナント側のコストとリスクにも跳ね返ってくる。次章では、その荒れ方がテナントごとにどのように分岐するのかを見ていきます。賃貸オフィスをインフラとして扱うテナント企業と、雑務として扱うテナント企業で、何が決定的に違い、どちらが長期でマイナスを積み増していくのか。そこを冷静に分解します。 第4章:賃貸オフィスをインフラとして扱うテナント企業と、雑務として扱うテナント企業の差 第3章では、「賃料が等価交換として測りにくいこと」が、テナント側の見え方を歪め、ビル側との協議や運用を荒らしやすい、その根っこを整理しました。ここからは、その荒れ方がテナント企業によってどう分岐しているのかを見ていきます。結論はシンプルで、差は「意識」ではなく、会社としてのプロセス設計(=運用の仕様)で決まります。 4-1.差は“やる気”や“意識の高さ”じゃない。運用の仕様の有無で決まる 賃貸オフィスは業務の基幹インフラです。止まったら業務が止まります。それなのに、賃貸オフィスだけが、製造工場や物流拠点のように「運用の仕様」が定められていないテナント企業が少なくないように見えます。ここで言っている「運用の仕様」というのは、立派な戦略のことではありません。もっと地味な話です。誰が最終判断するのか(決裁ライン)何を、いつ、どの粒度で共有するのか(情報のルール)例外が起きたとき、どう裁くのか(責任分界)ビル管理会社と、どの頻度で何を確認するのか(運用の型)こうしたポイントを押さえた運用の仕様の「型」があるテナント企業は、賃貸オフィス関連業務が、隙間に落ちにくい蓋然性を備えていると言えるかもしれません。逆に、そのような「型」がない会社は、賃貸オフィス関連業務が、いつまでも“雑務の延長”のまま片手間に処理されることになります。 4-2.運用の仕様が定まっていないテナントで起きている「いつものこと」 テナントごとに賃貸オフィスビル関連業務の運用の仕様はいろいろなカタチがあってもよいと思います。ただし、運用の仕様が定まっていない、または、実質的に機能していない場合、現象としては、だいたい同じような形で「いつものこと」が起きています。場合①スケジュール管理が回っていない担当者が気付いた時点で手遅れになりやすい。もっとも重要な賃貸契約の更新だけでなく、レイアウト変更工事の段取り、ビル側の設備更新工事、定期法定検査等のイベント管理等が後手に回って、結果として、社内外の関係者の業務の効率性を下げてしまいます。場合②社外の関係者に粛々と情報伝達ができない現場の不満、設備の不具合、使い勝手の問題。本来は「何が困っているか」を社内で整理すべきなのに、重要度・緊急度・個人の感想なのか会社としての要請なのか、そこすら整理されないまま外に転送される。ビル管理会社側も、何をどう優先して取り組んだらいいのか判断できなくなります。場合③ビル側とテナント側の協議の経過が残っていない「誰が何を言ったか」「どこまで決まったか」「前提条件は何か」が社内で共有されていない。その結果、テナント側の担当が変わるたびに話が巻き戻る。最後は、「言った・言わない」の水掛け論に帰結して、ビル側とテナント側の関係が荒れていきます。この3つの場合は、単なるテナントの担当者の不手際ではありません。賃貸オフィス関連業務の運用の仕様がないと、必然的に起きてしまう「いつものこと」なのです。 4-3.賃貸オフィスをインフラとして扱っているテナント企業は、何が違うのか 賃貸オフィスをインフラとして扱っているテナント企業は、別に、その会社の従業員の「意識が高い」わけではありません。やっていることはシンプルで、賃貸オフィスをインフラとして扱うための運用の仕様が定められ、社内で機能している、それだけです。賃貸オフィスを含めた業務拠点の位置付けについて、経営側の言葉で定義されている総務・ファシリティが、窓口だけでなく、権限と情報を持っているビル管理会社とのやり取りが、単発の交渉として処理されるのではなく、一連の運用の流れとして認識され、連続的に記録されている条件の変更や例外的な事態が発生したときのテナント側の判断基準が、最低限、共有されているこれだけで、賃貸契約の更新も、設備対応も、クレーム対応も、円滑に処理されて、ビル側との関係性も荒れにくくなります。ビル側と「揉めないテナント」は、だいたいこのような運用の仕様を備えています。 4-4.どっちが長期でマイナスを積み増すか:コストとリスクの話 運用の仕様を定めるか否かについては、それぞれのテナントが決めることです。ただし、長期で見ると差ははっきり出てくるものと思われます。運用の仕様の有無によって影響が出てきそうなポイントを、以下、あげておきます。①交渉・協議の長期化情報が整理されていない。経過が残っていない。決裁ラインが曖昧。だから毎回、説明、協議と合意形成をやり直すことになり、時間が溶ける。②事故処理コストの増加意思決定が遅れ、対応が後追いになる。結果として、余計な費用や無理なスケジュールが発生しやすい。③コストの硬直化競合案件との比較検討ができない。改善についての判断が下せない。すると運用を最適化する機会を失い、賃料負担を含めたコスト構造が硬直化していく。④ビル側との関係性の脆弱化ビル側から合理的に協議ができない相手として見られがち。長期の前提を共有しにくくなり、関係を安定させることが難しくなっていく。 4-5.ここまでの整理:差を生むのは「運用の仕様」、損を生むのは「曖昧さ」 第3章で見た“見え方の錯覚”があると、運用の仕様は細っていきます。そして運用の仕様が細っていくと、賃貸オフィス関連業務は、隙間に落ちる。隙間に落ちると、また錯覚が強まる。ここはループです。だから、第4章の結論はこれです。賃貸オフィスをインフラとして扱っている会社は、運用の仕様を持っている。運用の仕様がなくて、雑務として扱っている会社は、曖昧さのまま走り、マイナスを積み増していく。次章では、ここから貸主側(オーナー/PM/ビル管理会社)が持つべき視点に移ります。テナント側が賃貸オフィス関連業務をどのように扱っているのかを、そのままの「条件」として織り込み、どこまで付き合い、どこで線を引くべきか。実務として整理します。 第5章:貸主側が持てる視点:テナント側の運用に問題があることを前提に対処する 第4章で見たとおり、賃貸オフィスを“事業インフラ”として扱うテナント企業もあれば、総務の雑務として処理しているテナント企業もあります。ここで大事なのは、「テナントを変えよう」としないこと。無理です。変わりません。貸主側(オーナー/PM/管理会社)がやるべきは、テナントの進め方に是非をつけることではありません。「テナント側の運用に問題があって、社内の意思決定が円滑になされずに、起こり得るトラブルの発生」を前提に、貸主側が、どこまで関わり、どこから距離を取り、テナント側との協議や運用が“荒れる/壊れる”確率をどう下げるか。第5章はその話です。 5-1.テナント企業の「社内の仕組み」は書き換えられない まず前提。貸主側は、テナントの会社の仕組みを書き替えることはできません。事業戦略・人員計画・組織設計を踏まえた予算の設定社内意思決定の稟議決裁フロー実質的な決定者が誰かどこまでが担当者権限で、どこからが経営判断かこれらはテナント企業のガバナンス領域です。貸主側がここに踏み込むと、テナント側との関係が壊れてしまいがちですし、背負う必要のない責任まで背負うことになりかねません。だから、貸主側がやるべきは、テナントの「社内の隙間」を埋めてあげるではなくて。“隙間があるかもしれない”前提で、テナントとの協議の事故の確率を下げるために、最初から、テナントとの境界線を引く。それだけです。 5-2.埋めにいける「隙間」と、埋めにいけない「隙間」を切り分ける テナント側の社内プロセスには介入できない。でも、判断材料と時間の条件なら貸主側でコントロールできます。貸主側が“埋めにいける”のは基本ここまで。近隣・競合も踏まえた賃料水準(レンジ)の提示設備仕様・更新履歴・制約条件などの客観情報いつまでに何を決める必要があるか(段取りと期限の言語化)ポイントはシンプルで、判断の土台は出す。でも判断そのものには踏み込まない。この線を崩さない。そのために、出し方は必ず「ファクト」と「提案」を分ける。混ぜると、テナント社内で誤解が発生しやすく、判断が歪みます。例:賃料改定の提示ファクト:成約賃料レンジ/需給/現行条件との乖離/前提(面積・階・設備・契約条件)提案:貸主としての新条件(賃料、FR、工事負担、契約年数など)「提案はする。でも決めるのはテナント」。ここは固定。あともう1つ。テナント事情を“読み過ぎない/斟酌しない”のも大事です。相手に寄せて条件を歪めると、関係が良くなるどころか、後で揉める火種になります。馴れ合いは結局、協議を壊します。 5-3.テナント側に問題がある場合でも、協議が壊れないインターフェースを作る テナント側が賃貸オフィス運用を軽視していたり、運用の仕様がなかったりすると、テナント側との協議や運用は“荒れる/壊れる”方向に行きがちです。相手の問題を上書きすることはできないので、貸主側としては、接点(インターフェース)の仕様を設定して、事故の発生確率を下げる他ないのです。①テナント側の決裁の“段差”を見つけ、決裁者を特定する窓口担当と意思決定者が違うのは普通です。更新・賃料改定・工事負担みたいな重い話ほど、淡々とこう聞く。「この件は、社内でどこまで決裁が必要ですか?」決裁権限がない担当者と延々と漫然と話していても、協議は進捗しません。②テナント側に提示する「前提条件」を文章で固定する(協議の土台を動かさない)条件・期限・対象範囲・比較前提は、毎回テキストで残す。メールで十分。協議の前提さえ固定されていれば、担当交代や社内の抜けがあっても、話の巻き戻しや漂流を防げます。③期限をこちらから提示する(相手都合任せにしない)協議においては、「いつまでに決める必要があるか」「この提案の有効期限」をセットで提示します。相手方を圧迫するのではなくて、協議が停滞することを防ぐこと。期限を設けない協議は、だいたい迷走します。④例外はあやふやな“判断”ではなく“ルール化”する例外対応は極力避ける。やむを得ずやるなら、その場での温情判断ではなく、ルール化(条件化)します。曖昧な優しさは、後々、双方を苦しめます。 終章:「そこにあるから借りてるだけ」を、言葉どおり受け取らない 「そこにあるから借りてるだけ」。この言い方は、テナント側の本音というより、考える手間を省くための便利な言い訳として使われている場面が多いのではないでしょうか。でも、賃貸オフィスはただの“箱”ではありません。立地・面積・賃料だけで完結する商品ではなく、建物・設備の整備、共用部の運用、保守、ルール整備、トラブル対応といった付帯サービスがあってはじめて成立します。そして、それぞれの仕様や条件設定については、テナント側でも本来は検討が必要です。本来、賃貸オフィスは工場や物流拠点と同じく、会社のビジネスを「止まらせない」ためのインフラです。だから運用には仕様が要ります。それでも現実には、賃貸オフィス関連の業務は社内の「隙間」に落ちやすい。賃料は等価交換として測りにくいので、いつの間にか単なる「場所代」に見えてしまう錯覚も起きやすい。結果として、貸主とテナントの協議が荒れやすくなる。ここまでが本稿で追ってきた流れです。では、貸主側が取るべき態度は何か。答えはシンプルです。テナントの言い分を、貸主の立場から無理に否定する必要はありません。代わりに、こちらの前提条件を明文化して、境界線を先に引く。そのうえで、ファクトと提案を分けて提示する(判断材料は出すが、判断には踏み込まない)。必要なら、協議の接点=インターフェースの仕様を固定する。これが一番効きます。「そこにあるから借りてるだけ」という言葉は残ります。たぶん消えません。でも、こちらがそれを言葉どおり受け取る必要はない。むしろ、その“省略”を前提にして対処したほうが、仕事として強い。貸主側の立場を一文で言うなら、こうです。「ここまではこちらの責任として整える。ここから先は、御社の判断です。」この線を、静かに引けるかどうか。そこに、ビル管理会社の実務の実力が出ます。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 飯野 仁 東京大学経済学部を卒業 日本興業銀行(現みずほ銀行)で市場・リスク・資産運用業務に携わり、外資系運用会社2社を経て、プライム上場企業で執行役員。 年金総合研究センター研究員も歴任。証券アナリスト協会検定会員。 2026年2月9日執筆2026年02月09日
皆さん、こんにちは。株式会社スペースライブラリの飯野です。この記事は「そこにあるから借りているだけ」というのは、ホントなの?──テナント企業は賃貸オフィスのことを、どこまで真面目に考えているのか」というタイトルで、2026年2月9日に執筆しています。少しでも、皆様に新たな気づきをもたらして、お役に立てる記事にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 目次序章:「そこにあるから借りてるだけ」なの?第1章:賃貸オフィスに関連する社内の意思決定は、なぜ“隙間”に落ちるのか第2章:テナント企業は、賃貸オフィスのどこで“マイナスになっている”のか第3章:賃貸オフィスの賃料を「ただの場所代」と見做す視線の根っこ第4章:賃貸オフィスをインフラとして扱うテナント企業と、雑務として扱うテナント企業の差第5章:貸主側が持てる視点:テナント側の運用に問題があることを前提に対処する終章:「そこにあるから借りてるだけ」を、言葉どおり受け取らない 序章:「そこにあるから借りてるだけ」なの? 賃貸オフィスビルの運営に携わっていると、ふと、不思議な感覚に襲われることがあります。テナント企業にとって、賃貸オフィスは「なくては困る」インフラです。明日から突然、その賃貸オフィスが使えなくなれば、営業も、バックオフィス事務も、採用も、会議も、ほとんどの業務が立ち行かなくなる。いわば、事業の基盤を支えている場所と言えます。けれども、賃貸オフィスの現場で耳にする言葉や、社内の意思決定のされ方を見ていると、どうも、その“インフラ”としての重要性と、テナントの社内での扱われ方のあいだに、微妙なギャップがあるようにも感じられます。「たまたま、そこに空いている物件があったから」「予算の範囲で、いちばん条件が良かったから」「社員から文句が出ていないので、今のところ大丈夫」どれも、現場でよく聞かれるフレーズです。もちろん、オフィス移転のたびに、経営方針を踏まえて、経営の哲学にまで立ち返った議論をしてほしい/しなくてはいけない、というつもりはありません。ただ、「なくては困るインフラ」にしては、あまりに“その場しのぎ”の言葉が並んでいるな、という違和感は拭えないのです。たとえば、製造業の会社において、工場のことであればどうでしょうか。どのエリアに建てるのか。どのくらいの投資をして、どのような製造ラインを組んで、どのように人と設備を配置するのか。その工場を、10年後、20年後にどのように使っていくのか。こうした問いは、経営のど真ん中で議論されるはずです。工場は、製造業の会社にとって、ビジネス上の競争力に直結するインフラだからです。そこに「たまたま空いていたから」「予算的にちょうど良かったから」で決めて良いことなど、あり得ません。しかし、賃貸オフィスになると、話は一気に軽くなっているように見受けられます。さすがに、オフィスの立地については、経営会議で一定の議論が行われるかもしれません。けれど、そのあとの賃貸条件の検討や、日々の運営、更新や解約の判断といった“インフラとしての運用”の部分は、多くの会社で「総務の仕事」として、一段下のレイヤーに落とされているのではないでしょうか。賃貸オフィスはテナント企業にとって、「止まったら困るインフラ」であるにもかかわらず、社内の位置づけとしては“雑務の延長線上”に置かれやすい。そのギャップが、現場でのコミュニケーションや交渉、ビル管理会社との関係性に、じわじわと影響を与えています。オフィスは「そこにあるから借りているだけ」なのか。それとも、本来は工場や物流拠点と同じように、もっと真面目に向き合うべきインフラなのか。このコラムでは、賃貸オフィスビルのビル管理会社という立場から、テナント企業が賃貸オフィスをどのように扱っているのか、その結果、どんな不都合が生まれる可能性があるのか、そして、その前提を踏まえたうえで、貸主側(ビル・オーナー・ビル管理会社側)はどこまで付き合い、どこで線を引くべきなのか――そんなことを、整理してみたいと思います。 第1章:賃貸オフィスに関連する社内の意思決定は、なぜ“隙間”に落ちるのか 序章で触れたとおり、賃貸オフィスは「止まったら困るインフラ」です。それなのに、実務の世界をのぞいてみると、その扱われ方はどう見ても“インフラ級”ではない。このギャップの正体を、まずは社内の意思決定プロセスから分解してみます。 1-1.賃貸オフィスの話には、本来いろんな部署が絡むはずなのに 賃貸オフィスについて、本当は誰が何を考えるべきなのか。ざっくり分解すると、こんな感じになります。経営陣事業ポートフォリオと拠点戦略中長期の人員計画・働き方の方向性固定費としての賃料水準・投資配分事業部門(現場)実際の働き方(来社頻度・会議のスタイル・来客の多さ)必要な席数・会議室数・倉庫スペース拠点ごとの役割分担(開発拠点なのか、営業拠点なのかなど)人事・労務採用・定着に効くロケーションやオフィス環境の水準ハイブリッドワークなど就業制度との整合性安全衛生・従業員のコンディション管理財務・経理キャッシュフローと賃料負担のバランス原価・販管費としての位置づけ長期の賃貸借契約がもつリスク総務・ファシリティビル側との窓口・日々の運用レイアウト変更・増員対応・修繕の取り回し契約更新や原状回復、移転プロジェクトの実務こうして並べてみると、賃貸オフィスの話って、本来は会社のほぼ全部門にまたがる「ど真ん中のテーマ」なんですよね。工場ほど露骨ではないにせよ、経営、事業、人、カネ、現場運用――全部が絡んでくる。……なんですが、現実の会社を見ていると、この全員がちゃんと集まって、腰を据えてオフィスを議論しているケースは、そこまで多くないのでは、ないのでしょうか。 1-2.プロジェクトのときだけ“総力戦”、ふだんは“総務預かり” 賃貸オフィスの話が社内で大きく扱われるタイミングは、だいたい決まっています。賃貸契約の更新が近づいて、「このビル、出るか・残るか」を決めるとき事業拡大や統合で、「増床・移転が必要だ」となったとき働き方改革やコロナ後対応で、「オフィスのあり方を見直そう」となったときこういう「一大イベント」のときには、経営陣も事業部門も人事も巻き込んで、プロジェクト・チームが立ち上がる。そこでは確かに、かなり真面目な議論が行われます。ただ、問題はその後です。移転・増床のプロジェクトが終わった瞬間、チームは解散されるその後の運営・細かな条件調整・更新の検討は、総務・ファシリティが単独で担う形に戻る「とりあえず今の条件からあまりブラさない範囲で更新しておいてください」というざっくりした指示だけ降りてくる結果として、オフィスに関する日々の意思決定は、どうしても「上でざっくり方向性を決める→具体的な判断は総務が現場で処理する」という構図に収まりがちです。ここで問題にしているのは、賃貸オフィス関連業務の扱いが結果的に“隙間業務”に落ちてしまう会社の仕組みであって、「総務がオフィスを真剣に考えていないから」というわけではありません。会社組織の業務分担とリソース配分の設計によって、賃貸オフィスの検討が会社組織の“隙間の仕事”に押し込まれてしまっているという点です。総務の仕事の現場を見てみると、株主総会・取締役会の準備社内規程・押印・契約書管理郵便・電話・来客対応備品・印章・社有車・携帯・PCの管理社内イベントや福利厚生の取り回し……といった、会社の裏側全般を抱えながら、その延長で「賃貸オフィスも見る」ことを求められているというようにも見受けられます。そこに突然、賃貸オフィス関連で、「年間◯億円レベルの固定費」を左右する賃貸条件の交渉10年スパンで効いてくるオフィスのレイアウトや仕様の判断ビル・オーナー、ビル管理会社との長期的な関係構築などが業務分掌のリストに追加されてのってくるわけなので、「雑に扱っている」というより、物理的・能力的に“抱えきれていない”って状況になってしまうんですよね。 1-3.「賃貸オフィスだけのことを考える人」が、社内にいない もう一つ、大きな会社の構造的な問題があるのではって思っています。それは、ほとんどの会社には「オフィスのことだけを、専門的に考えるポジション」が必ずしも置かれていない、という点です。IR担当は、投資家とどうコミュニケーションを取るか、で評価される人事担当は、採用・定着・評価制度などで評価される経営企画は、事業戦略・中期計画の実現度で評価されるじゃあ、「このオフィスが、事業と人にとってベストな状態かどうか」という点で評価されている人は、社内にいるか?と言われると、正直かなり怪しい。総務にしても、「トラブルなく回っているか」「コストが膨らんでいないか」「社員から大きな不満が出ていないか」といった、“マイナスを出さないこと”で評価されるケースが多い。プラスをどこまで取りに行くか、という視点でオフィスを設計する役割は、そもそも誰にも割り当てられていない。つまり、工場:「生産性」という、めちゃくちゃわかりやすいKPIがある物流拠点:配送リードタイムや在庫回転率など、測れる指標があるオフィス:生産性はチームや人によってバラバラ売上との因果関係も測りづらい「ここをこう変えたら〇%業績が上がる」とは言いきれないこうなってくると、賃貸オフィスの話は、どうしても「誰のKPIでもないから、誰も本気でその問題のオーナーシップを取りにいかない」という状態に陥りがちです。 1-4.重要だけど緊急じゃないものは、だいたい後回しになる さらに追い打ちをかけているのが、「緊急度と重要度」の問題です。いますぐ困るわけではないけど、じわじわ効いてくるコストいますぐクレームになるわけではないけど、じわじわ効いてくる使いにくさいますぐ採用難になるわけではないけど、じわじわ効いてくる立地や設備の見劣りオフィスに関する課題は、ほとんどが「重要だけど緊急じゃない」ゾーンに入ります。その一方で、会社には法改正対応システムトラブル大口顧客の対応組織再編・人事異動…などなど「重要かつ緊急」なタスクが、毎日のように降ってきます。その結果どうなるか。賃料の適正水準や、契約条件の見直しは「今度ちゃんと検討しよう」で棚上げレイアウトの最適化や、フロア構成の見直しは「増員したら考えよう」で先送り更新のタイミングになって、ようやくバタバタと協議が始まり、結局「現状維持」が一番通しやすい選択肢に見えてしまう貸主側(ビル・オーナー/ビル管理会社の側)から見ると、「このタイミングで、ちゃんと議論&検討のリストにのせて、関係者でテーブルを囲んで話せれば、結果的に、テナント側にもメリットが出るのに」という局面は、正直かなり多いです。でもテナントの会社内では、そういう中長期の調整に時間を割く余裕がない。ここにも、個人のやる気とか能力というより、会社の構造として“後回しになりやすいテーマ”に分類されてしまっているという事情があります。 1-5.「総務のせい」にしても、何も前に進まない ここまで整理してくると、賃貸オフィスの話は、本来ほぼ全社的なテーマでもプロジェクトのときを除けば、総務・ファシリティに集約されがちそもそも「オフィスの最適化」で評価される人が社内にいない重要だけど緊急じゃないので、構造的に後回しになりやすいという、ちょっと意地悪なパズルのような構図が見えてきます。この状態を前にして、「総務がちゃんとやっていないからだ」と結論づけてしまうのは、正直かなり乱暴だし、非生産的です。人も時間も足りないなかで、会社の“裏側全部”を担っている部署に、「オフィス戦略まで完璧に設計しておいてください」は、さすがに荷が重すぎる。むしろ、経営側が「オフィスをどう位置づけるか」をちゃんと決めているか事業側が「自分たちの仕事にとって、どんなオフィスが必要か」を言語化できているかその上で総務が、ビル管理会社との交渉や日々の運用を“実務として回せる状態”になっているかをセットで見ないと、現場の状況は変わっていきません。 第2章:テナント企業は、賃貸オフィスのどこで“マイナスになっている”のか 第1章では、賃貸オフィスに関連する意思決定が、会社の仕組み上、どうしても“隙間”に落ちやすいという話をしました。ここからは、その結果として、テナント企業側にどんな“マイナス”が生じ得るのかを、もう少し具体的に見ていきます。ここで言う「マイナス」は、いきなり、大きな損失が生じるというのではなくて、余計な費用負担もう少し楽に回せたはずの日常的な業務運用が、ジワジワとしんどくなってしまうという状況みたいな、「ジワジワ系のマイナス」がメイン・ストーリーです。複数の賃貸オフィスビルを横断してテナントの動きを見ていると、同じようなパターンが繰り返されているのがわかります。しかもそれは、「誰かがサボっているから」ではなく、テナント企業での社内の意思決定プロセスそのものがそういうマイナスを生みやすい設計になっている、という言い方のほうがしっくりきます。 2-1.賃料だけ見て「まあ妥当」という判断 わかりやすい例として、「賃料単価だけ見て、なんとなく“相場並みだからOK”になっているケース」です。よくある流れは、こんな感じです。立地と賃料は、仲介会社が持ってきた比較表で確認「この条件なら予算内なので大丈夫そう」ということを以て社内で意思決定表面上の立地を踏まえた賃料は“相場並み”でも、賃貸オフィスビルのグレード、床面積、設備、ビル管理の状況が、本当に見合っているのかについての確認、判断は複雑で難しいので、テナント企業自身が必ずしも重視していないポイントで余計な賃料プレミアムを負担しているというケースも珍しくなくて、そのことが見過ごされていたりもします。ここでのポイントは、社内の議論のテーブルに上がるのが、「立地を踏まえた賃料」と「床面積」に限定されがち賃貸契約の諸条件、賃貸オフィスビルのグレード等を細かく読み込んで、メリット、デメリット、将来コストを試算するだけの時間も、ツールも、役割も用意されていないという「テナント企業の社内の意思判断、組織設計の事情」にあります。個々の担当者の能力の問題ではなく、「賃料、床面積、立地」以外の論点が、そもそも議論に乗りにくい社内の意思決定の仕組みになっている、ということ。 2-2.「とりあえず今のまま」でという判断 次に多いのが、賃貸契約の更新局面で、本来なら検討すべきポイントを自分から見なかったことにしてしまうパターンです。判断としては「現状維持」なんだけど、実態は「現状維持しか選べない状態に自分で寄せていく」みたいな進み方になります。典型例はこうです。賃貸契約の更新が近づいても、社内検討がギリギリまで進まない更新時期が見えているのに、社内での議論が始まらない(始める担当も決まらない)。結果、ビル管理会社から「更新どうしますか?ちなみに適正賃料は○○なので、賃料を○○円上げたいです」という連絡が来て初めて、ようやく社内が“目覚める”。ビル管理会社との交渉での「落としどころ探し」だけになる社内で準備がない状態だと、できることが限られます。せいぜい、「とりあえず更新前提で、提示賃料と現状賃料の“真ん中あたり”を目安に交渉する」みたいな、反射的な対応になりやすい。これでは交渉の主導権は握れません。賃料の妥当性チェックが、近隣相場を踏まえて適正賃料を提示している管理会社の資料の妥当性の確認だけ。本来、テナント企業のビジネスにとっての、賃貸オフィスのロケーションの妥当性を踏まえて、賃料をどこまで負担できるのかということを社内で検討して、判断の上で、協議に臨むべきなのですが、そこまでの判断が下されているのでしょうか。本来、協議のテーブルに乗る前に、テナント側で最低限ここまで整っていると話は一気に前に進みます。社内で移転/残留のシナリオ比較がある程度できている「この条件なら残る」「ここまで上がるなら移転も検討せざるを得ない」というライン(判断基準)が、関係者の間で共有されているこの状態で話が始まれば、相場賃料との乖離があるのに「現状維持一点張り」で停滞し続ける、みたいな不毛なプロセスは避けられます。貸主側も、条件の根拠を出しやすいし、テナント側も“どこが争点か”を絞れる。つまり、お互いに時間を溶かさずに済む。でも現実は、そこまでたどり着かないケースがかなり多い。結局、更新期限ギリギリで「とりあえず継続」を前提に賃料の折り合いどころだけを探すこの形に落ちます。この進み方の問題は、単に交渉がお互いにとって非効率的であるだけじゃありません。立地、床面積、人員配置、運用のしやすさ、コスト負担――そういう要素を並べて、費用とメリットの両面から最適化する機会を、テナント自身が放棄している、とも言えます。更新は本来、そこを見直す“数少ない節目”のはずなので。ここでも原因は、個人のやる気の問題ではなく、ほぼ「社内の意思決定プロセスの設計」にあります。賃貸契約の更新検討に必要な時間が、社内スケジュールとして確保されていない「誰が」「どこまで決めるのか」という社内ルールが曖昧この2つが残っている限り、賃貸契約の更新のたびに同じことが起きます。だからこの節で言いたいのは、「賃貸契約の更新で揉める」のが問題なんじゃなくて、揉め方が毎回“準備不足の揉め方”になってしまう構造が問題、という点です。 2-3.人員増とレイアウト変更のたびに、じわじわと運用コストを払わされる テナント企業の組織改編、人員増を踏まえたとオフィス・レイアウト改変・調整の“ズレによるマイナス”も無視できません。よくあるのは、オフィスの移転、組織改編、人員増に対応した増床のタイミングで、レイアウトの基本設計をそこまで詰めないままスタートするそのときは「とりあえず目の前の人数が入ればOK」が最優先になるその後の組織改編、人員増を見越していないので、そのたびに、間に合わせで対応するので、オフィスで業務を進めるにあたって、やりにくさが露呈してくるというパターン。結果として、少し人が増えたり、組織をちょこっといじくるたびに、都度、レイアウト変更している会議室が足りなくなりがち文書保管のスペース等が後から足りなくなり、その調整に手間がかかるみたいな形で、「最初にちゃんと設計しておけば避けられたコスト」が、後からジワジワ出てきます。ここでも共通しているのは、レイアウト設計のときに、事業計画・人員計画とセットで検討されていない「どう増えるか」「どう縮むか」のシナリオを描ける人が、その場にいないという業務プロセス、組織の構造的なポイントです。「個人の担当者の判断が甘かったから」ではなく、オフィス計画と事業計画が別々のテーブルで進んでしまう組織設計になっているから、こうなりやすい、という見方のほうがしっくりきます。 2-4.賃料だけを重視して、賃貸オフィスビルのグレードを下げると、採用・従業員の定着で見えないマイナスが生じやすい もう1つ、数字には乗りにくいけれど無視できないのが、テナントの従業員側の“小さな我慢”の積み上げによるマイナスです。例えば、賃料をケチって、賃貸オフィスビルのグレードを下げると、どうしても、設備、ビル管理に皺寄せがいってしまって、エレベーター、トイレ・給湯室、空調等のキャパ不足、不調が起こりがちです。どれも1つ1つを取り出すと、「致命的な不具合」とまでは言いにくいものです。でも、毎日・毎週・毎月と積み重なっていくと、テナントの従業員、オフィスへの来訪者への印象に、普通にネガティブに効いてきます。例えば、ちょっとした不満が、「この会社で長く働きたいか?」の判断に影響する採用面接で来社した候補者が、辞退しがちお客様が来たときの印象が、営業のスタートラインに反映されるこういった影響は、KPIとして明示され難いのかもしれません。そのため社内ではどうしても「とりあえず現状維持で」で処理されがちです。ただ、複数のオフィス環境を見比べていると、“我慢の総量”が一定ラインを超えたあたりで、従業員の離職のタイミング、採用の手ごたえ、お客様からの「見られ方」に、ジワっと差が出てくるよな……という感覚は、どうしても拭えません。ここも結局、「従業員の小さな不満」を拾って、人事・総務・ビジネスの現場マネージャーの間で情報共有する場がなく、社内コミュニケーション・プロセスの設計不足が問題の背景にあります。 2-5.場当たり対応が、貸主側との関係性をじわじわ削っていく 最後に、少しセンシティブですが、貸主側(ビル・オーナー/ビル管理会社側)との関係性の“マイナス”の話です。例えば、テナントが:賃貸契約の更新の際、合理的な事由を示さずに「賃料は絶対に現状維持」とだけ主張し続ける社内の意思決定プロセスが外から見えず、「誰が何を決めているのか」が、まったくあやふや。こういったことが続くと、貸主側としては、「このテナントとは、中長期の前提を共有し難いな」「何か問題があっても、合理的に協議し検討するのは難しそうだ」と感じざるを得ない部分が出てきます。その結果として、テナントを重要なパートナーとして位置付けるが難しくなってしまい、入替え可能な相手先として扱わざるを得なくなりがちで、“一歩踏み込んだ提案・相談”をすること自体難しくなるという形のマイナスが出てきます。これも、「総務の対応が悪い」と切ってしまうと、ものすごく雑です。実際には、社内の意思決定に必要な時間が確保されていない誰が窓口で、どこまで権限を持つのかが曖昧「賃貸オフィスのことをちゃんと話す場」がそもそも用意されていないといった、テナント企業の会社としてのガバナンス設計・役割設計の問題として立ち上がってきます。 第3章:賃貸オフィスの賃料を「ただの場所代」と見做す視線の根っこ 賃貸オフィスがテナント社内で軽く扱われるのは、「隙間に落ちている」からだけでもありません。もう少し根っこのところに、オフィス賃貸で成り立つ収益不動産=そこにあるだけで賃料を生むものというイメージが、かなり強く影響しているのではないか――私はそこを疑っています。もちろん、収益不動産の仕組みや歴史をここで掘るつもりはありません。ここで押さえたいのは、テナント側の感覚として自然に立ち上がってくる“見え方”です。前提として、テナント側の頭のなかでは、だいたい次のような図式で整理されがちです。オーナーは、収益不動産を保有し、賃料を受け取る側テナントは、事業で稼いだ収益から、賃料という固定費を支払い続ける側事実と言えば事実です。問題は、この図式そのものではなく、この図式がどう受け止められるかです。実務では、交渉や連絡の相手は管理会社になります。するとテナントの目には、オーナーと管理会社がひとまとめに「同じ側」に見えやすい。ここで“見え方”が固定されます。さらに、賃料という支払いは、モノの納品や工事の完了のように、「これと引き換えに払った」と言い切れる対象が見えにくい。よく考えれば、建物・設備の整備、共用部の運用、保守、ルール整備、トラブル対応など、支払いの背景にはいろいろな実務がある。ただ、その内側を詳しく見ない限り、表面上は「箱に居られる権利にお金を払っている」ようにも見えてしまう。つまり賃料は、等価交換として測りにくい。測りにくい以上、比較軸が持ちにくい。比較軸が持てないと、人は納得のための物語を作ります。いちばん手っ取り早い物語が、「相手は持っているだけで入ってくる側」「こちらは稼いで払っている側」という整理です。そしていつの間にか、“払っている側が主導権を持つはずだ”という錯覚に寄っていく(※この「払った側が上」という感覚は、贈与と返礼の関係に近い構造として理解できる、という見方もあります。)この錯覚が定着してしまうと、振る舞いも変わってきます。本来、賃貸オフィスは、責任分界、連絡の経路、判断のタイミング、情報の粒度といった運用仕様を前提に回すインフラです。ところが“主導権の錯覚”が前提になると、そうした仕様の細かい話が細っていき、「結局いくらか」という一点に議論が寄っていく。隙間に落ちる以前に、テナント側に「賃貸オフィスの運用を見ないようにさせる装置」が内在している――私はむしろ、そう考えています。そして、その錯覚があるからこそ、結果として賃貸オフィスが「隙間に落ちている」とも言える。その結果、賃貸オフィスを巡る協議の経過も粗略に扱われやすくなる。「誰が何を言ったか」「どこまで決まっているか」「何が前提条件か」を社内で丁寧に共有しなくなる。ビル管理会社側にも前提が伝わらない。話が再現できない。だから同じ説明を何度も繰り返し、最後に揉める。さらに厄介なのはここから先です。この“主導権の錯覚”が強くなると、嘘や誇張への罪悪感が薄くなることがある。「相手はどうせ取っている側だ」「こちらは払っている側だ」という自己正当化が、雑なコミュニケーションを正当化してしまうからです。人間は、納得しづらい支払いに対して、後から理屈を作るのがうまい。賃料が等価交換として測りにくい以上、この手の“見え方”は、ある意味で自然に発生しがちです。この章の結論はシンプルです。“賃貸オフィスの賃料をただの場所代として扱う視線”が、テナント側との協議や運用を荒らしやすいのです。そしてその荒れは、結局、テナント側のコストとリスクにも跳ね返ってくる。次章では、その荒れ方がテナントごとにどのように分岐するのかを見ていきます。賃貸オフィスをインフラとして扱うテナント企業と、雑務として扱うテナント企業で、何が決定的に違い、どちらが長期でマイナスを積み増していくのか。そこを冷静に分解します。 第4章:賃貸オフィスをインフラとして扱うテナント企業と、雑務として扱うテナント企業の差 第3章では、「賃料が等価交換として測りにくいこと」が、テナント側の見え方を歪め、ビル側との協議や運用を荒らしやすい、その根っこを整理しました。ここからは、その荒れ方がテナント企業によってどう分岐しているのかを見ていきます。結論はシンプルで、差は「意識」ではなく、会社としてのプロセス設計(=運用の仕様)で決まります。 4-1.差は“やる気”や“意識の高さ”じゃない。運用の仕様の有無で決まる 賃貸オフィスは業務の基幹インフラです。止まったら業務が止まります。それなのに、賃貸オフィスだけが、製造工場や物流拠点のように「運用の仕様」が定められていないテナント企業が少なくないように見えます。ここで言っている「運用の仕様」というのは、立派な戦略のことではありません。もっと地味な話です。誰が最終判断するのか(決裁ライン)何を、いつ、どの粒度で共有するのか(情報のルール)例外が起きたとき、どう裁くのか(責任分界)ビル管理会社と、どの頻度で何を確認するのか(運用の型)こうしたポイントを押さえた運用の仕様の「型」があるテナント企業は、賃貸オフィス関連業務が、隙間に落ちにくい蓋然性を備えていると言えるかもしれません。逆に、そのような「型」がない会社は、賃貸オフィス関連業務が、いつまでも“雑務の延長”のまま片手間に処理されることになります。 4-2.運用の仕様が定まっていないテナントで起きている「いつものこと」 テナントごとに賃貸オフィスビル関連業務の運用の仕様はいろいろなカタチがあってもよいと思います。ただし、運用の仕様が定まっていない、または、実質的に機能していない場合、現象としては、だいたい同じような形で「いつものこと」が起きています。場合①スケジュール管理が回っていない担当者が気付いた時点で手遅れになりやすい。もっとも重要な賃貸契約の更新だけでなく、レイアウト変更工事の段取り、ビル側の設備更新工事、定期法定検査等のイベント管理等が後手に回って、結果として、社内外の関係者の業務の効率性を下げてしまいます。場合②社外の関係者に粛々と情報伝達ができない現場の不満、設備の不具合、使い勝手の問題。本来は「何が困っているか」を社内で整理すべきなのに、重要度・緊急度・個人の感想なのか会社としての要請なのか、そこすら整理されないまま外に転送される。ビル管理会社側も、何をどう優先して取り組んだらいいのか判断できなくなります。場合③ビル側とテナント側の協議の経過が残っていない「誰が何を言ったか」「どこまで決まったか」「前提条件は何か」が社内で共有されていない。その結果、テナント側の担当が変わるたびに話が巻き戻る。最後は、「言った・言わない」の水掛け論に帰結して、ビル側とテナント側の関係が荒れていきます。この3つの場合は、単なるテナントの担当者の不手際ではありません。賃貸オフィス関連業務の運用の仕様がないと、必然的に起きてしまう「いつものこと」なのです。 4-3.賃貸オフィスをインフラとして扱っているテナント企業は、何が違うのか 賃貸オフィスをインフラとして扱っているテナント企業は、別に、その会社の従業員の「意識が高い」わけではありません。やっていることはシンプルで、賃貸オフィスをインフラとして扱うための運用の仕様が定められ、社内で機能している、それだけです。賃貸オフィスを含めた業務拠点の位置付けについて、経営側の言葉で定義されている総務・ファシリティが、窓口だけでなく、権限と情報を持っているビル管理会社とのやり取りが、単発の交渉として処理されるのではなく、一連の運用の流れとして認識され、連続的に記録されている条件の変更や例外的な事態が発生したときのテナント側の判断基準が、最低限、共有されているこれだけで、賃貸契約の更新も、設備対応も、クレーム対応も、円滑に処理されて、ビル側との関係性も荒れにくくなります。ビル側と「揉めないテナント」は、だいたいこのような運用の仕様を備えています。 4-4.どっちが長期でマイナスを積み増すか:コストとリスクの話 運用の仕様を定めるか否かについては、それぞれのテナントが決めることです。ただし、長期で見ると差ははっきり出てくるものと思われます。運用の仕様の有無によって影響が出てきそうなポイントを、以下、あげておきます。①交渉・協議の長期化情報が整理されていない。経過が残っていない。決裁ラインが曖昧。だから毎回、説明、協議と合意形成をやり直すことになり、時間が溶ける。②事故処理コストの増加意思決定が遅れ、対応が後追いになる。結果として、余計な費用や無理なスケジュールが発生しやすい。③コストの硬直化競合案件との比較検討ができない。改善についての判断が下せない。すると運用を最適化する機会を失い、賃料負担を含めたコスト構造が硬直化していく。④ビル側との関係性の脆弱化ビル側から合理的に協議ができない相手として見られがち。長期の前提を共有しにくくなり、関係を安定させることが難しくなっていく。 4-5.ここまでの整理:差を生むのは「運用の仕様」、損を生むのは「曖昧さ」 第3章で見た“見え方の錯覚”があると、運用の仕様は細っていきます。そして運用の仕様が細っていくと、賃貸オフィス関連業務は、隙間に落ちる。隙間に落ちると、また錯覚が強まる。ここはループです。だから、第4章の結論はこれです。賃貸オフィスをインフラとして扱っている会社は、運用の仕様を持っている。運用の仕様がなくて、雑務として扱っている会社は、曖昧さのまま走り、マイナスを積み増していく。次章では、ここから貸主側(オーナー/PM/ビル管理会社)が持つべき視点に移ります。テナント側が賃貸オフィス関連業務をどのように扱っているのかを、そのままの「条件」として織り込み、どこまで付き合い、どこで線を引くべきか。実務として整理します。 第5章:貸主側が持てる視点:テナント側の運用に問題があることを前提に対処する 第4章で見たとおり、賃貸オフィスを“事業インフラ”として扱うテナント企業もあれば、総務の雑務として処理しているテナント企業もあります。ここで大事なのは、「テナントを変えよう」としないこと。無理です。変わりません。貸主側(オーナー/PM/管理会社)がやるべきは、テナントの進め方に是非をつけることではありません。「テナント側の運用に問題があって、社内の意思決定が円滑になされずに、起こり得るトラブルの発生」を前提に、貸主側が、どこまで関わり、どこから距離を取り、テナント側との協議や運用が“荒れる/壊れる”確率をどう下げるか。第5章はその話です。 5-1.テナント企業の「社内の仕組み」は書き換えられない まず前提。貸主側は、テナントの会社の仕組みを書き替えることはできません。事業戦略・人員計画・組織設計を踏まえた予算の設定社内意思決定の稟議決裁フロー実質的な決定者が誰かどこまでが担当者権限で、どこからが経営判断かこれらはテナント企業のガバナンス領域です。貸主側がここに踏み込むと、テナント側との関係が壊れてしまいがちですし、背負う必要のない責任まで背負うことになりかねません。だから、貸主側がやるべきは、テナントの「社内の隙間」を埋めてあげるではなくて。“隙間があるかもしれない”前提で、テナントとの協議の事故の確率を下げるために、最初から、テナントとの境界線を引く。それだけです。 5-2.埋めにいける「隙間」と、埋めにいけない「隙間」を切り分ける テナント側の社内プロセスには介入できない。でも、判断材料と時間の条件なら貸主側でコントロールできます。貸主側が“埋めにいける”のは基本ここまで。近隣・競合も踏まえた賃料水準(レンジ)の提示設備仕様・更新履歴・制約条件などの客観情報いつまでに何を決める必要があるか(段取りと期限の言語化)ポイントはシンプルで、判断の土台は出す。でも判断そのものには踏み込まない。この線を崩さない。そのために、出し方は必ず「ファクト」と「提案」を分ける。混ぜると、テナント社内で誤解が発生しやすく、判断が歪みます。例:賃料改定の提示ファクト:成約賃料レンジ/需給/現行条件との乖離/前提(面積・階・設備・契約条件)提案:貸主としての新条件(賃料、FR、工事負担、契約年数など)「提案はする。でも決めるのはテナント」。ここは固定。あともう1つ。テナント事情を“読み過ぎない/斟酌しない”のも大事です。相手に寄せて条件を歪めると、関係が良くなるどころか、後で揉める火種になります。馴れ合いは結局、協議を壊します。 5-3.テナント側に問題がある場合でも、協議が壊れないインターフェースを作る テナント側が賃貸オフィス運用を軽視していたり、運用の仕様がなかったりすると、テナント側との協議や運用は“荒れる/壊れる”方向に行きがちです。相手の問題を上書きすることはできないので、貸主側としては、接点(インターフェース)の仕様を設定して、事故の発生確率を下げる他ないのです。①テナント側の決裁の“段差”を見つけ、決裁者を特定する窓口担当と意思決定者が違うのは普通です。更新・賃料改定・工事負担みたいな重い話ほど、淡々とこう聞く。「この件は、社内でどこまで決裁が必要ですか?」決裁権限がない担当者と延々と漫然と話していても、協議は進捗しません。②テナント側に提示する「前提条件」を文章で固定する(協議の土台を動かさない)条件・期限・対象範囲・比較前提は、毎回テキストで残す。メールで十分。協議の前提さえ固定されていれば、担当交代や社内の抜けがあっても、話の巻き戻しや漂流を防げます。③期限をこちらから提示する(相手都合任せにしない)協議においては、「いつまでに決める必要があるか」「この提案の有効期限」をセットで提示します。相手方を圧迫するのではなくて、協議が停滞することを防ぐこと。期限を設けない協議は、だいたい迷走します。④例外はあやふやな“判断”ではなく“ルール化”する例外対応は極力避ける。やむを得ずやるなら、その場での温情判断ではなく、ルール化(条件化)します。曖昧な優しさは、後々、双方を苦しめます。 終章:「そこにあるから借りてるだけ」を、言葉どおり受け取らない 「そこにあるから借りてるだけ」。この言い方は、テナント側の本音というより、考える手間を省くための便利な言い訳として使われている場面が多いのではないでしょうか。でも、賃貸オフィスはただの“箱”ではありません。立地・面積・賃料だけで完結する商品ではなく、建物・設備の整備、共用部の運用、保守、ルール整備、トラブル対応といった付帯サービスがあってはじめて成立します。そして、それぞれの仕様や条件設定については、テナント側でも本来は検討が必要です。本来、賃貸オフィスは工場や物流拠点と同じく、会社のビジネスを「止まらせない」ためのインフラです。だから運用には仕様が要ります。それでも現実には、賃貸オフィス関連の業務は社内の「隙間」に落ちやすい。賃料は等価交換として測りにくいので、いつの間にか単なる「場所代」に見えてしまう錯覚も起きやすい。結果として、貸主とテナントの協議が荒れやすくなる。ここまでが本稿で追ってきた流れです。では、貸主側が取るべき態度は何か。答えはシンプルです。テナントの言い分を、貸主の立場から無理に否定する必要はありません。代わりに、こちらの前提条件を明文化して、境界線を先に引く。そのうえで、ファクトと提案を分けて提示する(判断材料は出すが、判断には踏み込まない)。必要なら、協議の接点=インターフェースの仕様を固定する。これが一番効きます。「そこにあるから借りてるだけ」という言葉は残ります。たぶん消えません。でも、こちらがそれを言葉どおり受け取る必要はない。むしろ、その“省略”を前提にして対処したほうが、仕事として強い。貸主側の立場を一文で言うなら、こうです。「ここまではこちらの責任として整える。ここから先は、御社の判断です。」この線を、静かに引けるかどうか。そこに、ビル管理会社の実務の実力が出ます。 執筆者紹介 株式会社スペースライブラリ プロパティマネジメントチーム 飯野 仁 東京大学経済学部を卒業 日本興業銀行(現みずほ銀行)で市場・リスク・資産運用業務に携わり、外資系運用会社2社を経て、プライム上場企業で執行役員。 年金総合研究センター研究員も歴任。証券アナリスト協会検定会員。 2026年2月9日執筆2026年02月09日
Our Business
事業概要
-
 Buildings and offices for rent
Buildings and offices for rent貸ビル・貸事務所
事業の成長に最適なオフィスを提案し、豊富な選択肢と専門的なサポートで理想のオフィス選びを実現します。移転計画から契約交渉、レイアウト工事の設計・施工まで一貫して対応します。 -
 Building Renovation
Building Renovationビルリノベーション
老朽化したビルの単なる修繕はリフォームと呼ばれますが、ある程度の広さを総合的に改修して建物の性能を向上させたり、価値を高めたりすることをリノベーションと呼びます。 -
 Property Management
Property Managementプロパティマネジメント
不動産オーナーやアセットマネージャーに代わって、不動産の管理や運営を行います。不動産の資産価値や収益を最大化することを目的としています。 -
 Building Maintenance
Building Maintenanceビルメンテナンス
建物を維持・管理し、ご利用の方が快適に過ごせる環境を保ちます。ビルメンテナンスがカバーする領域は幅広く、それぞれに専門的な知識・技術が要求されます。 有資格者のみができる業務も少なくありません。 -
 Building Development
Building Developmentビル開発
賃貸ビルは長期安定収益を目指した事業です。当社は賃貸オフィスビルと賃貸マンションの開発で多数の実績があり、オフィスでは80棟超・マンションでは東京建築賞(東京都建築士事務所協会主催)を3回受賞等数々の実績があります。当社はビル開発に伴う、全ての業務を行います。
Latest Articles